kurogenkokuです。
313冊目は
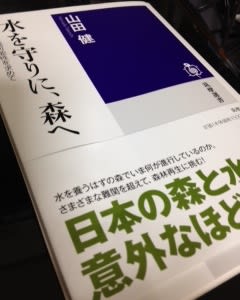
水を守りに、森へ: 地下水の持続可能性を求めて
山田 健 著 筑摩選書
これまでとはジャンルの違う本ですが、なぜこの本を読んだかといいますと。。。
kurogenkokuは荒川ダム水源地域ビジョン会議という会に属しています。水源地域の活性化に関する取り組みを旧商工会青年部が立ち上げたNPO法人の一員として行なっています。構成員それぞれに年間の活動計画が定められていて、進捗状況などを共有しながらコツコツ進めています。
ここで著者の紹介ですが、著者はサントリーエコ戦略部・部長シニアスペシャリスト。
サントリーの「天然水の森づくり」を推進している方で、東京大学秩父演習林との提携により荒川上流域の水源涵養に着手するようになったため、昨年度末より荒川ダム水源地域ビジョン会議のオブザーバーとして参加いただくようになりました。
当会の委員長でもある東京農業大学宮林教授が本書を絶賛しておられましたので、kurogenkokuも購入し拝読させていただいた次第です。
本書は「天然水の森づくり」の内容はもちろんのこと、その取り組みを行なう中で自然を守るために何をすべきか、著者の気づきを素人にもわかり易く解説しています。
まずサントリーの「天然水の森づくり」について。
社会貢献ではなく、事業としての水源涵養と位置づけているのが印象的です。多くの企業がCSR活動の一環として森づくり基金などを提供していますが、サントリーのそれは違います。
地下水に多くを依存している会社だからこそ、「工場でくみ上げている地下水以上の水を森で涵養しよう」そんな著者の提案で始まったプロジェクトです。自社のための取り組みが結果として環境保全につながる、だから継続できるんだと思います。
「自然を守る=何も手をかけずそのままにしておく」そう捉える方は多いのではないでしょうか。でも間伐などに手をかけなければ森は自ずと荒廃していきます。詳しくは本書を読んでいただければわかりますが、その労力は尋常ではありません。
「生物多様性」というキーワードが何度も登場します。
大自然の中では、単調な生物で構成されている集団よりも、複雑で多様な生物で構成されている集団の方が、強く、健康で、予期せぬ環境変化にしなやかに抵抗できるという考え方です。
そのためには人と自然が共生できる仕組みづくりが大切です。
経済や経営系の本もいいですが、間にこのような本を読むことで頭をリフレッシュすることができました。
【目次】
はじめに―その水は、持続可能な水ですか?
第1章 最初は、ほとんど無知でした
第2章 森があっても水は増えない?!
第3章 森づくりは道づくりから
第4章 森を脅かす思わぬ難敵
第5章 悪夢の連鎖
第6章 森から広がっていくつながり
あとがきに代えて―もっともっと、企業の力
<SCRIPT charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://ws.amazon.co.jp/widgets/q?rt=tf_mfw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=JP&ID=V20070822/JP/kurogenkoku-22/8001/aa3adf2e-b1b4-4701-9de4-fc29f677d0fe"> </SCRIPT>











