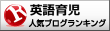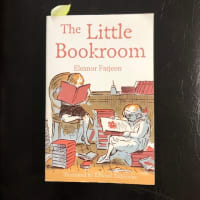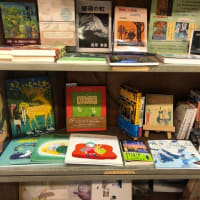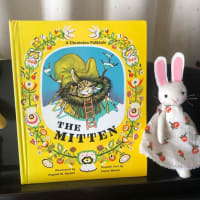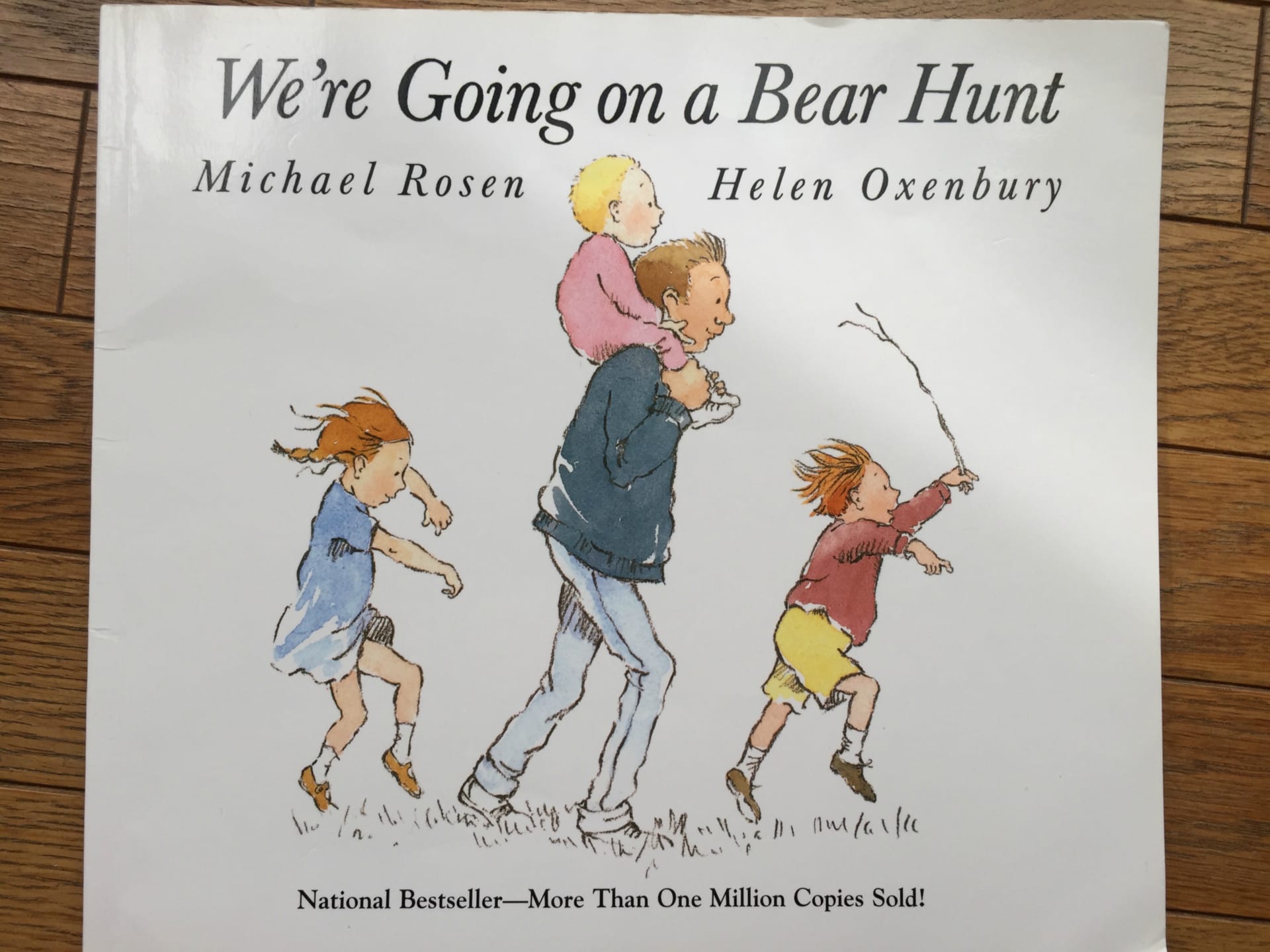
「きょうはみんなでクマがりだ」絵本は、繰り返しのフレーズがリズムよく、
自然にお話に合わせて体が動き出しちゃうような感覚をたのしめる。
何度も聞き、すきなように動いていると、
小さい子ほど、耳からの音をそのまま口に出して自由そのもの。
低学年、2年生もまだ幼児のその能力を残している。一つ一つの単語は不鮮明ながら
リエゾンするフレーズのリズム、イントネーション、アクセントはバッチリネイティブ音声に沿っていて
もう喃語は卒業なのだ。不完全なままで声を大きく出来る子は、大きい声を出している。
声の小さい子は、もっと自信を持って言いたいのだろうな。。。と思っていたら
ある子のママが、絵本のコピーにカナを振ってホチキス留めしてオリジナルテキストを作ってくれた。
母の愛は偉大。嬉しそうに子どもはその台本と首っ引きになって読んでいる。もちろん、私も一緒になって喜んだ。
…が、振ったカナは、カナであって、読み出した途端に、その子が聞いて話している英語ではなくなってしまう。
これはYちゃんが聞いた英語ではないよね。ママの耳と、Yちゃんのは違うからね。自分で聞いた音じゃないとね。
英語はカナでは書けないものだからね。
…と私は容赦なく言う。
すると、その子は、カナを直し始めたのだ。待って!止めて!とCDの音声をストップかけて。繰り返し。
これは大変な苦労なんだけれど、この子は頑張っています。
フリガナはあくまでも外国語獲得ごく初期の途中段階で、そのために向き合う英語の音との格闘が、もしかしたらその子を伸ばす。
無理してやるものではないけれど。
5年生くらいになると自然にこのくらいの英文を何となく読めてしまう子もいる。
4歳でも、アルファベットと英語の音がフッとマッチしたときに、聞こえた音を書く子もいる。
スペルは間違っていてもこの段階では関係ない。自分で気づいて自分から書くということがすばらしいのだ。
自然にお話に合わせて体が動き出しちゃうような感覚をたのしめる。
何度も聞き、すきなように動いていると、
小さい子ほど、耳からの音をそのまま口に出して自由そのもの。
低学年、2年生もまだ幼児のその能力を残している。一つ一つの単語は不鮮明ながら
リエゾンするフレーズのリズム、イントネーション、アクセントはバッチリネイティブ音声に沿っていて
もう喃語は卒業なのだ。不完全なままで声を大きく出来る子は、大きい声を出している。
声の小さい子は、もっと自信を持って言いたいのだろうな。。。と思っていたら
ある子のママが、絵本のコピーにカナを振ってホチキス留めしてオリジナルテキストを作ってくれた。
母の愛は偉大。嬉しそうに子どもはその台本と首っ引きになって読んでいる。もちろん、私も一緒になって喜んだ。
…が、振ったカナは、カナであって、読み出した途端に、その子が聞いて話している英語ではなくなってしまう。
これはYちゃんが聞いた英語ではないよね。ママの耳と、Yちゃんのは違うからね。自分で聞いた音じゃないとね。
英語はカナでは書けないものだからね。
…と私は容赦なく言う。
すると、その子は、カナを直し始めたのだ。待って!止めて!とCDの音声をストップかけて。繰り返し。
これは大変な苦労なんだけれど、この子は頑張っています。
フリガナはあくまでも外国語獲得ごく初期の途中段階で、そのために向き合う英語の音との格闘が、もしかしたらその子を伸ばす。
無理してやるものではないけれど。
5年生くらいになると自然にこのくらいの英文を何となく読めてしまう子もいる。
4歳でも、アルファベットと英語の音がフッとマッチしたときに、聞こえた音を書く子もいる。
スペルは間違っていてもこの段階では関係ない。自分で気づいて自分から書くということがすばらしいのだ。