 国土交通省は、2014年11月27日に公布され、2015年2月26日から一部施行されていた「空家等対策の推進に関する特別措置法」
国土交通省は、2014年11月27日に公布され、2015年2月26日から一部施行されていた「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が26日より全面施行されたことに伴い、適切な運用を図るためのガイドラインを発表した。
高齢化社会を背景に、近年では長期間、人が住んでいない空き家が各地で増えており、国土交通省が把握
している限りでも全国で約820万戸(平成25年現在)にも及ぶ。なかには、管理が行き届かず、倒壊の危険性があったり、
ゴミ捨て場のようになってしまい、防災面、防犯面、衛生面で地域住民の生活環境への深刻な影響を与えている
空き家も少なくない。場合によっては、所有者が明確でないような空き家もあり、自治体も対応に苦慮していた。
今回の法律施行に伴い発表されたガイドラインによれば、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる
おそれのある状態」、「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」、「適切な管理が行われて
いないことにより著しく景観を損なっている状態」、「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが
不適切である状態」の4つのいずれかに当てはまる状態の空き家を「特定空家等」と定義。
市町村長は「特定空家等」の所有者などに対して、適切な対策を行うように助言、指導、勧告、命令をすることができ、
それでも実行されない場合や、実行されても不十分な場合は、行政代執行法に基づいた適切な措置を講じることもできる。
措置に際して発生した費用は、所有者に対して請求可能。
また、これまでは空き家でも、建物があれば固定資産税等の特例が受けられたが、今回の法律施行に伴い、
固定資産税等の住宅用地特例から除外することもできる。運用形態としては、国が定めた法律のガイドラインをもとに、
各地域の実情に照らし合わせながら適切な措置を市町村長が行っていくという形になる。
法律の全面施行に合わせるように、不動産業者などによる空き家の見回り・管理サービスもすでに始まっており、
官民それぞれのアプローチでの空き家問題対策が進んでいる。
空き家「33年に2150万戸」…野村総研予測
06月22日 21:51読売新聞
野村総合研究所は22日、十分な空き家対策が行われなかった場合、2033年の空き家数は
13年比約2・6倍の約2150万戸に急増するとの予測を発表した。
同総研は、政府が中古住宅の流通市場の整備や、住宅以外への転用を進める必要があると指摘している。
同総研の予測によると、新設住宅着工戸数は14年度の88万戸が33年度には約50万戸まで減少するものの、
総住宅数は13年の6000万戸超が33年に約7100万戸まで増える。一方、総世帯数は20年以降、
急激に減少が進むため、総住宅数に占める「空き家率」は13年の13・5%が33年に30・2%まで
上昇するとしている。
全国で放置された空き家を巡っては、撤去や活用を進める「空家対策特別措置法」が今年5月、全面施行された。
これにより、自治体は倒壊する恐れがある空き家や店舗の所有者に解体を勧告し、撤去などの強制措置を
講じることができるようになった。今後は、利用価値のある空き家の有効活用も課題となる。














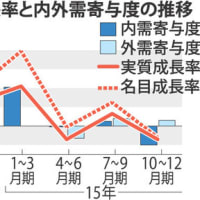





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます