今日は、先日目に留まった新聞記事についての感想を書くことにします。
日本でも報道されていたようですが、先週、ミズーリ州セントルイスにおいて、10年前に殺人罪で死刑を執行された男性が無実であった可能性が高まり検察が再捜査に乗り出した、という報道がありました(詳しくはこことここ)。
記事によれば、死刑になった男性は最後まで無実を主張していたそうですが、目撃証言が決め手となって最終的に死刑になってしまったそうです。しかし、今になって実はこの目撃証言が嘘だったかもしれないという疑いが出てきたというのです。
この記事を見たとき、正直なところ「あーあ、やっぱり起こったか。。」という諦めにも似た感覚をおぼえずにはおれませんでした。
無実の人間が誤判によって死刑に処せされるなどということは本来絶対にあってはならないことですが、そもそも裁判が人間という不完全な存在によって執り行われるものである以上、誤判が生じる可能性は決してゼロにはならないというのも事実です。
「1000人の罪人を逃すとも、1人の無辜を刑するなかれ」という精神は近代裁判の大きな柱です。
この大前提を踏み外さないために、近代における裁判制度では、行政権力に対するさまざまな“縛り”が設けられています。
この縛りは“デュー・プロセス・オブ・ロー(Due Process of Law)”と呼ばれます。
すなわち、検察側の手続きにミスがあったり、真実の証明が少しでも不完全ならば即、検察が負けて被告が勝つ。これが刑事裁判の原則なのです。
その際、鵜の目鷹の目で検察側に落ち度がないかどうかを調べ判断するのが裁判官の本来の仕事です。
「刑事裁判で裁かれるのは被告人ではなく、行政権力の代理人たる検察官である」と言われる所以はここにあります。
今日、“デュー・プロセス”の原則がもっとも徹底されていると言われている国が他ならぬアメリカです。しかし、あのO.J. シンプソンやマイケル・ジャクソンを無罪にしたこの国において、今回のような冤罪騒動が明るみに出たことはなんとも皮肉な話だと思います。
無論、アメリカは“地獄の沙汰も金次第”ですから、件のミズーリ事件の被告も、大金を払って腕利きの弁護士を雇うことができていたら結果は違っていたかもしれません。しかし、それはあくまで“たられば”の話です。今となっては死人を蘇らせて裁判をやり直すことは出来ません。
このように“誤判の可能性”の問題は、捜査技術の著しく進んだ現代の裁判制度においてですら避けて通ることは出来ません。
従って、死刑制度廃止を支持する人々の多くが唱えている「『無辜を刑してはならない』という目的を達成するためには死刑制度自体を廃止する以外にはないのだ」という主張にはそれなりの説得力があるように思われます(ここ参照)。
(死刑制度の存廃に関する論点を整理したい方はこちらを参照)
ところで、日本の裁判制度においては、告訴された被告の有罪率は実に99%に達します。
これはすなわち、逮捕された時点で容疑者の有罪はほとんど確定してしまっていることを意味します。この一点を見る限り、日本においてアメリカのような“デュー・プロセス”の原則が徹底されているとはとても言えないような気がします。
日本の裁判が“はじめに罪人ありき”であるとはよく言われることです。
殺人事件の容疑者が逮捕されると同時にマスコミをあげての一大報道合戦が繰り広げられ、その結果「どうせあいつがやったに違いない。死刑にしろ!」という世論が形成されていきます。そして、裁判官の判決も多くの場合世論の動向におもねったものになりがちです。
日本では、ここ20年の間に実に4人もの死刑確定者が再審で無罪になりました。
彼らは刑の執行を免れて再審のチャンスをものにすることが出来ましたが、すでに刑を執行されてしまった者の中に今回のミズーリにおけるケースのような冤罪事件が果たしてどのくらい含まれていたのか、、、もちろんこれも“たられば”の話ではありますが、その可能性について考えただけ背筋が凍るような思いがします。
私はここで死刑廃止論をぶとうなどと思っているわけではありません。
私のようなド素人がとやかく言えるほどこの問題が単純でないことはよく理解しているつもりです。
愛する家族を殺人者によって奪われた家族の怒りは想像を絶するものがあるに違いありません。その感情を慮れば、「死刑廃止論」など軽軽には発言すべきではないという意見がでるのも仕方のないことかもしれません。
国民の7割以上が死刑制度の存続に賛成している日本の現状に鑑みた時、
「1000人の罪人を刑するために、1人の無辜が刑されることは止むを得ないことなのだ」という論理が罷り通ることはもはや致し方のないことなのでしょうか?
日本でも報道されていたようですが、先週、ミズーリ州セントルイスにおいて、10年前に殺人罪で死刑を執行された男性が無実であった可能性が高まり検察が再捜査に乗り出した、という報道がありました(詳しくはこことここ)。
記事によれば、死刑になった男性は最後まで無実を主張していたそうですが、目撃証言が決め手となって最終的に死刑になってしまったそうです。しかし、今になって実はこの目撃証言が嘘だったかもしれないという疑いが出てきたというのです。
この記事を見たとき、正直なところ「あーあ、やっぱり起こったか。。」という諦めにも似た感覚をおぼえずにはおれませんでした。
無実の人間が誤判によって死刑に処せされるなどということは本来絶対にあってはならないことですが、そもそも裁判が人間という不完全な存在によって執り行われるものである以上、誤判が生じる可能性は決してゼロにはならないというのも事実です。
「1000人の罪人を逃すとも、1人の無辜を刑するなかれ」という精神は近代裁判の大きな柱です。
この大前提を踏み外さないために、近代における裁判制度では、行政権力に対するさまざまな“縛り”が設けられています。
この縛りは“デュー・プロセス・オブ・ロー(Due Process of Law)”と呼ばれます。
すなわち、検察側の手続きにミスがあったり、真実の証明が少しでも不完全ならば即、検察が負けて被告が勝つ。これが刑事裁判の原則なのです。
その際、鵜の目鷹の目で検察側に落ち度がないかどうかを調べ判断するのが裁判官の本来の仕事です。
「刑事裁判で裁かれるのは被告人ではなく、行政権力の代理人たる検察官である」と言われる所以はここにあります。
今日、“デュー・プロセス”の原則がもっとも徹底されていると言われている国が他ならぬアメリカです。しかし、あのO.J. シンプソンやマイケル・ジャクソンを無罪にしたこの国において、今回のような冤罪騒動が明るみに出たことはなんとも皮肉な話だと思います。
無論、アメリカは“地獄の沙汰も金次第”ですから、件のミズーリ事件の被告も、大金を払って腕利きの弁護士を雇うことができていたら結果は違っていたかもしれません。しかし、それはあくまで“たられば”の話です。今となっては死人を蘇らせて裁判をやり直すことは出来ません。
このように“誤判の可能性”の問題は、捜査技術の著しく進んだ現代の裁判制度においてですら避けて通ることは出来ません。
従って、死刑制度廃止を支持する人々の多くが唱えている「『無辜を刑してはならない』という目的を達成するためには死刑制度自体を廃止する以外にはないのだ」という主張にはそれなりの説得力があるように思われます(ここ参照)。
(死刑制度の存廃に関する論点を整理したい方はこちらを参照)
ところで、日本の裁判制度においては、告訴された被告の有罪率は実に99%に達します。
これはすなわち、逮捕された時点で容疑者の有罪はほとんど確定してしまっていることを意味します。この一点を見る限り、日本においてアメリカのような“デュー・プロセス”の原則が徹底されているとはとても言えないような気がします。
日本の裁判が“はじめに罪人ありき”であるとはよく言われることです。
殺人事件の容疑者が逮捕されると同時にマスコミをあげての一大報道合戦が繰り広げられ、その結果「どうせあいつがやったに違いない。死刑にしろ!」という世論が形成されていきます。そして、裁判官の判決も多くの場合世論の動向におもねったものになりがちです。
日本では、ここ20年の間に実に4人もの死刑確定者が再審で無罪になりました。
彼らは刑の執行を免れて再審のチャンスをものにすることが出来ましたが、すでに刑を執行されてしまった者の中に今回のミズーリにおけるケースのような冤罪事件が果たしてどのくらい含まれていたのか、、、もちろんこれも“たられば”の話ではありますが、その可能性について考えただけ背筋が凍るような思いがします。
私はここで死刑廃止論をぶとうなどと思っているわけではありません。
私のようなド素人がとやかく言えるほどこの問題が単純でないことはよく理解しているつもりです。
愛する家族を殺人者によって奪われた家族の怒りは想像を絶するものがあるに違いありません。その感情を慮れば、「死刑廃止論」など軽軽には発言すべきではないという意見がでるのも仕方のないことかもしれません。
国民の7割以上が死刑制度の存続に賛成している日本の現状に鑑みた時、
「1000人の罪人を刑するために、1人の無辜が刑されることは止むを得ないことなのだ」という論理が罷り通ることはもはや致し方のないことなのでしょうか?















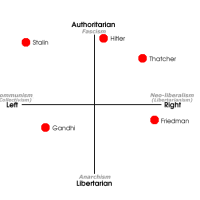
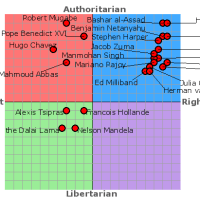
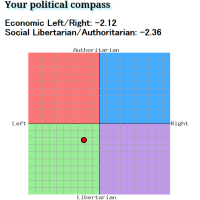
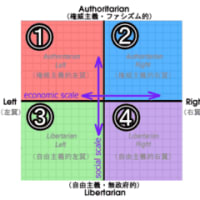






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます