内山節氏の「日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか」を読む。
筆者によると、1965年以前には、日本の各地に“キツネに莫迦される”人たちがいた。
どの村にも、“どこそこの誰々がキツネに莫迦された”的な話が普通に出回っていて、皆その話を“普通にあること”として疑わなかったという。
しかし、1965年を境に、その手の話は急速に姿を消してゆく。
それは何故なのか?
キツネに莫迦されるなんて、昔話の中だけだと思っていたが、ひと昔前までの日本では、それが十分にあり得る話として受け止められていたという事実にまず驚かされる。
日本人がキツネにだまされなくなった理由として、筆者はいくつかの仮説を提示する。
すなわち、科学の進歩、教育の充実、高度成長期の経済発展、情報・コミュニケーションの変化などである。
もちろん、これらの要素はそれぞれが、理由として十分にあり得るものだし、おそらくいずれも間違いではないだろう。
しかし、そこから哲学者である筆者は、この本の後半部分の多くを割いて、人間の歴史認識の変化について、非常に興味深い論考を展開する。
いわく、歴史には「見える歴史」と「見えない歴史」があるという。
現在の歴史学は、ヘーゲル的なそれであって、すなわち「歴史とは、歴史を動かす絶対的な意思、人間を超越した崇高な意思、その意味で神の意思の自己実現過程」の上に形成されるという。つまり、歴史はそれ自体が人類の進化の過程であり、ゆえに過去の歴史はあくまでも「現在から照射された過去」であり、未成熟であり、かつ未完成であるという前提の上に成り立っている。これは、言い換えれば、過去の歴史があくまで現代の問題意識を通してのみ規定、考察されるということを意味する。
そのような過程で、人間は“見たいものだけ”をみるようになっていき、現代の常識にそぐわないものは歴史学の本流から排除され“見えなく”なってゆく。
ショーペンハウエルやベルクソンはそのような歴史のとらえ方を批判した。
ショーペンハウエルは「世界は我が表象である」とし、「自然と人間が存在する世界の少なくとも半分は、客観的に時間の経過をとらえようとする歴史学では考察できない」と考えた。またベルクソンは「知性は生命のごく一部にすぎないとするなら、知性によってとらえられた歴史を歴史の全体にしてしまうことは、全く不当な試みだ」と考えた。
「現代の私たちは、知性によってとらえられたものを絶対視して生きている。その結果、知性を介するととらえられなくなってしまうものを、つかむのが苦手になった。人間がキツネにだまされた物語が生まれなくなっていくという変化もこのことの中で生じていたのである」。
筆者によると、1965年以前には、日本の各地に“キツネに莫迦される”人たちがいた。
どの村にも、“どこそこの誰々がキツネに莫迦された”的な話が普通に出回っていて、皆その話を“普通にあること”として疑わなかったという。
しかし、1965年を境に、その手の話は急速に姿を消してゆく。
それは何故なのか?
キツネに莫迦されるなんて、昔話の中だけだと思っていたが、ひと昔前までの日本では、それが十分にあり得る話として受け止められていたという事実にまず驚かされる。
日本人がキツネにだまされなくなった理由として、筆者はいくつかの仮説を提示する。
すなわち、科学の進歩、教育の充実、高度成長期の経済発展、情報・コミュニケーションの変化などである。
もちろん、これらの要素はそれぞれが、理由として十分にあり得るものだし、おそらくいずれも間違いではないだろう。
しかし、そこから哲学者である筆者は、この本の後半部分の多くを割いて、人間の歴史認識の変化について、非常に興味深い論考を展開する。
いわく、歴史には「見える歴史」と「見えない歴史」があるという。
現在の歴史学は、ヘーゲル的なそれであって、すなわち「歴史とは、歴史を動かす絶対的な意思、人間を超越した崇高な意思、その意味で神の意思の自己実現過程」の上に形成されるという。つまり、歴史はそれ自体が人類の進化の過程であり、ゆえに過去の歴史はあくまでも「現在から照射された過去」であり、未成熟であり、かつ未完成であるという前提の上に成り立っている。これは、言い換えれば、過去の歴史があくまで現代の問題意識を通してのみ規定、考察されるということを意味する。
そのような過程で、人間は“見たいものだけ”をみるようになっていき、現代の常識にそぐわないものは歴史学の本流から排除され“見えなく”なってゆく。
ショーペンハウエルやベルクソンはそのような歴史のとらえ方を批判した。
ショーペンハウエルは「世界は我が表象である」とし、「自然と人間が存在する世界の少なくとも半分は、客観的に時間の経過をとらえようとする歴史学では考察できない」と考えた。またベルクソンは「知性は生命のごく一部にすぎないとするなら、知性によってとらえられた歴史を歴史の全体にしてしまうことは、全く不当な試みだ」と考えた。
「現代の私たちは、知性によってとらえられたものを絶対視して生きている。その結果、知性を介するととらえられなくなってしまうものを、つかむのが苦手になった。人間がキツネにだまされた物語が生まれなくなっていくという変化もこのことの中で生じていたのである」。















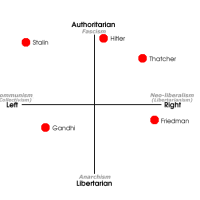
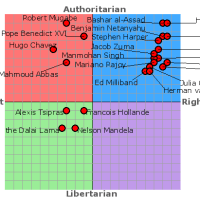
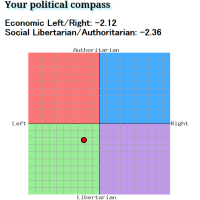
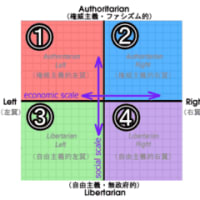






キツネにはだまされなくなったけど、信仰心や集合的個人的それぞれに特有の猜疑心は消えうることはなく、ただそれを覆す、絶大な信頼を科学は勝ち取っている感がある。とにかく、人間とは 「明らかな」証拠がないと安心できない。 まあ、私も右に同じです。