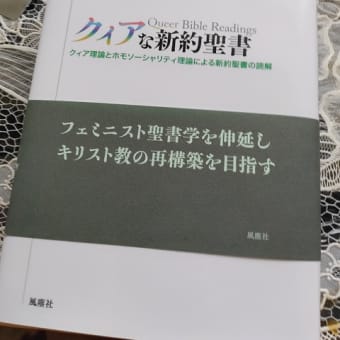多少メディアに詳しいと、リアリティショーの登場人物が作られたキャラクターであり、そのことを理解できない視聴者という対立構図を作り出す。
ところで、作られたキャラクターとは一体なんだろうか。番組制作側が「こういうキャラクターで演じて」と命令して、あるいは相談して、キャラクターを作るので、それは本来の自分ではないということになるのだろうか。
そうであるなら、あくまで演技として割り切ることができているということだ。演技であるなら、そこで表象されるキャラクターは自分とは関係ないのだから、悩む必要はない。仮に悪役的に演じ、憎悪を買っているとしたら、成功した演技である。罵詈雑言を浴びせられても、そのキャラクターを信じさせるほどの迫真の演技ができたとして、周りから賞賛を浴びるだろう。
だから、リアリティショーを単にやらせであるとして、突き放すことには無理がある。演技者として、理想の演技ができなかったとして苦悩を抱える役者はあるだろう。そこで自己の無能力に絶望することがないとはいえない。もちろん木村さんの話はそういうことではない。と考えれば、やらせを理解できない視聴者像には無理がある。そもそもリアリティショーは真実とやらせという二項対立的な図式では理解できないからだ。
ゆえにリアリティショーにはリアリティショーとしての独自の形式がある。そこを理解することの難しさをボードリヤールやメディア論者は認識する。歴史的に新しいメディアとパーソナリティの関係が生じたのだ。
新たなリアリティが生じた。この世界に映像というメディアがもたらせられて、映像の中に存在する人間のありようは、当初演劇するパーソナリティとして理解され、演劇以外では有名人というパーソナリティになってきた。
そして、今や映像の世界はそのまま演劇ではなく、リアルな人生を描き出し、人々に享受される。このリアルさはテレビに取り上げられることによって、テレビがなかった世界におけるリアリティとは差異があり、そこに臨場感空間が生じる。
オーディエンスは有名人との間に観念的な臨場感空間を作り出した。そして有名人ではなく素人、普通の人の最も個人的なこと、ここでは恋愛を取り上げることで、その臨場感空間の質に変化が起こった。普通の人の恋愛だが、テレビで企画された恋愛でありつつ、やはり普通の人の恋愛であると。有名人同士が週刊誌に撮られた恋愛という普通の人々とは差異のある恋愛ではなく、やはり普通の人の恋愛である。と同時にテレビに撮られているという点で普通の人の恋愛ではない・・・・こういう認識の循環運動、眩暈をもたらすリアリティが臨場感空間を作り出す。
確かに日本では、出演者の多くは芸能人の卵だったりする。しかしその無名さが普通の人ということで一般視聴者に親近感を与える。それでもなお、テレビに出演していることで有名性を身に纏い、普通であることと距離を作り出してはいる。
繰り返すが、ゆえにフィクションとは割り切れないのだ。このリアリティは巻き込まれながらも、既存のRealとFakeに回収することを拒否している。
そして、ネットやSNSという新たなメディアが新たなリアリティを作り出し、そこに現れる言説や映像に特別な地位が付与される。そこに臨場感空間が生み出されるのだ。僕たちはネットやSNSの書き込みや映像に高揚する。そして、その高揚感は依存的な性格を有している。
僕自身のことを振り返ると、パソコン通信の時代だが、フォーラムで誰かと繋がっている実感した時の高揚感を思い出す。パソコンという通信機器がもたらす高揚感である。メールが来たと言っては高揚し(メール受信の音が鳴る)、メールが来ないかと気にかけ、WWWにつながり、ネットで検索できたと高揚したものだ。
美学者の室井尚がネットのデータベースとのアクセスで次のように言う。
「電子的データベースを手にして知性が増幅されたと感じるのは、ちょうど巨大な図書館や書店に入った時に感じる高揚感であり、要するに巨大なシステムに融合しているという錯覚なのだ」(室井尚『哲学問題としてのテクノロジー』講談社2000年)
ネット、SNSも室井の言う「巨大なシステムに融合」の日常版である。自我の拡大を錯覚させ、臨場感空間を作るのである。
(つづく)