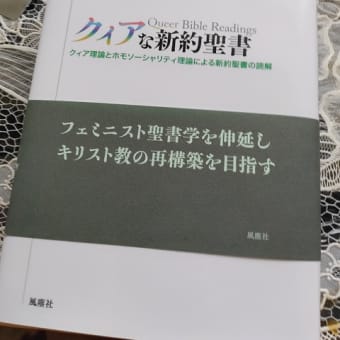このような道徳の強制性、その無意識性を自覚すれば、それらを信じることは難しい。相対主義的な態度になる。と同時に、現実的には行為遂行的に通俗化された、あるいは大衆化された道徳を実践もする。確かにこの道徳は大きな物語として、階級や民族などの社会的主体性を超えて広がっているというわけではない。この引き裂かれた状態が常態化しているのが現実でもある。
つまり本当は信じてはいないけれども、信じているかのような態度を取るのである。いや逆からいうことも出来る。信じているように行為するが、実は信じていないのだと。
ここに我われが取りうる姿勢が見出せる。道徳も真理もないと嘆くのではなく、仮の道徳や真理に過ぎないにしても、とりあえずは信じてみる。と同時に、常に仮の道徳や真理に懐疑を持っておくというバランス感覚に生きることである。これは相対主義にも陥らず、絶対主義や全体主義にも陥らない方法論になりうる。
最初に国家が道徳を規定するという話に触れたので、それを事例にしてみよう。国家が道徳を規定するという国家のありように関して、そのありように賛成反対どちらの立場もありうる。とりあえずはそういうことができる。
賛成とする人物は国家こそが道徳の起源であるとか、保守思想として必然であるとか、いくつかの理由を挙げるだろう。ただ先に触れてきた通り、我われの立場はニーチェに一旦立脚している。そうすると、国家が道徳を規定する立場というのは隠蔽が組み込まれている。ゆえに真理ではないが、一旦そのような立場になれば、とりあえず“あえて”信じるのだが、同時に懐疑の念をなくしてはならない。この懐疑が寛容の姿勢を作り出すことになるので、反対の意見と対話する基盤となる。
逆に国家が道徳を規定することは近代化という観点から、国民主権という立場から間違っていると断罪することができる。しかしながら、この立場もまた“あえて”信じるという姿勢にあり、同時に自ら信じることに懐疑を手放すことはない。そうすると、やはり寛容を持って対話する基盤を作れる。
このように考えると、愚かな立場とは信じているものに固執することになる。
(つづく)