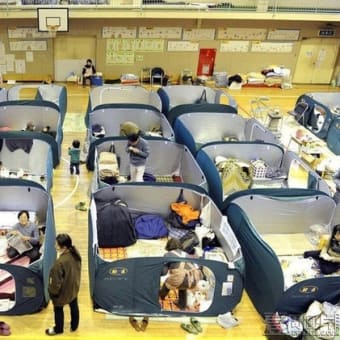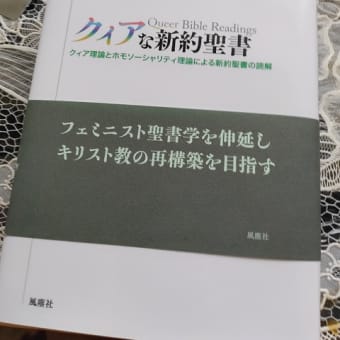芸人の中田敦彦さんが教育系のYouTube動画をあげて、その中にfakeがあったとして批判を受けている。
芸人として多彩な才能を発揮していた彼が教育系の動画を編集し提供している理由や動機はよく知らない。彼が誤った情報をあげてしまったことから、クリティカルシンキングという立場から分析している方もいるようだが、その中身についてもよく知らない。
そこで、僕なりに感じることを指摘しておきたい。ちなみにクリティカルシンキングも一つの方法論であるので、問題点もあろうかと思う。最近流行の思考方法ということだが、客観的に物事を判断し、情報を多角的に批評しつつ判断することができる、あるいはそういう方向に向かう思考方法とのことだ。ちなみに心理学のシステマティックな情報処理を方法論化したとみなすことができる。
システマティックな情報処理とは別にヒューリスティックな情報処理がある。それぞれ認知心理学者Chaikenの考え出した枠組みだが、後者は簡便な情報処理で、感情的な認知でとどまるとか、卑近な例を出せば、「有名人が言ってたんだから本当だ」とするような情報処理である。こういう見方からすれば芸能人で高学歴である彼が言うんだから間違いないとでも受容されるとすれば、fakeを鵜呑みにすることになるので問題だという指摘になるんだろう。
僕が指摘したいのはそういう水準ではない。近年の知のありようが短絡化していることを取り上げておきたい。人々の知識が受験的な様相になっていることである。
受験では教科書や参考書を理解し、その中にある知識を獲得する。獲得の度合いが高ければ優秀ということになる。しかしながら、このような知識はある問いがあった場合、何が答えになるのかが教科書に書いてあり、即確かめられるような性質の知識になっている。端的にいうと雑学である。もちろん多少の思考力が問われるものもあるが。
テレビで高学歴の芸能人であるとか、東大生などがクイズ番組に出ている。中には有名人となって、何万部もの本が売れているらしい。僕たちは彼らに教養があると考えるが、ここで分別しておこう。教養ではなく、雑学であると。
そのため、雑学を習得するような勉強に従事してきた人間が何かテーマを持って教育系の知識を披露するときの方法論は、既存の書籍やネットの情報からのコピペによって構成される。その整理の仕方は勉強ができるので上手に違いない。そして彼らはこれを教養だと誤解してしまう。特に学校の勉強が得意であった人間というのは、こういう雑学をプールする能力を「頭がいい」と自惚れてしまう。
2つだけ指摘しておこう。1つは真に教養を身につけている人間がいるとして(最近はそういう人物を想定しづらいような気もする)、例えば、西田幾多郎、日高六郎、小林秀雄、福田恒存のような知の巨人を想定してみよう。彼らがクイズ番組に出演して、勝てるかといえば、当然勝てない。しかしながら、彼らは随分と深い教養を身につけている。ここで明らかだろう。知が違うのである。
もう1点。社会科学を例にして、データを取り扱う時、生のデータ、それらを収集し分類したデータの集合、さらにそれらを分類し理論化の途上にある抽象化されたカテゴリーの水準を分析し分類し、抽象度の違いを整理し、他それらと同じ領域の二次資料や、カテゴリー、理論を総合する資料批判を訓練した上での知識のありようは先の雑学をコピペして並べた知識の有りようとは異なる。
このような作業を行なって知識を生産する知的労働に従事しているものが、書籍やネットの情報に当たるなら、当然のこと批評的に事に当たる姿勢をある程度身につけていることになる。やはり知のありようが違うのであり、こちらのほうこそ真に知識と言っていいか、それに近いことになる。
だから、中田敦彦さんの動画はそういう批評を組み込んでいるわけではないし、深遠な教養をもとに構成されているわけではない。YouTubeをメディアとした芸程度と位置付けておけばいいのではないか。そもそもケイシー高嶺の医療コント、ミスター梅介の法律コントがあったではないか。
ただ、“マジすぎる”という印象を持ってしまうのは、彼がボケていないのか、僕がボケと理解できないのか、そういうことなのかもしれない。ただ頭がいいとアピールしたいという程度であれば、それが有名性をもとにした収入を上げようという程度であるなら、なんと凡庸なことか。