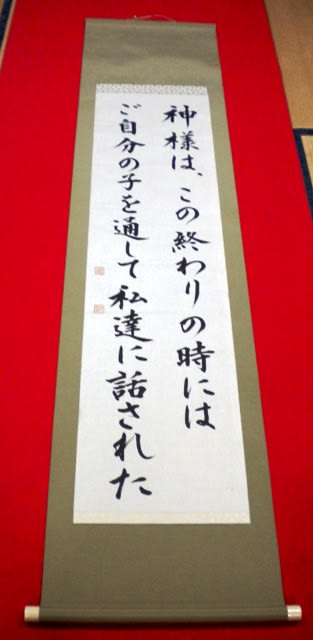B年 年間第二主日 2012・1・15
「聖書」(b)
旧約聖書は元来ユダヤ教の聖典です。新約聖書が「聖書」に言及するとき、それは旧約聖書と呼ばれています。その意味での聖書は【律法の書と預言者の書及び、その後に書かれたものです】。 まず、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記は、モーセ五書とも呼ばれ、「律法」の部分です。これらは主としてシナイでの神との契約になって、神の民の発生を主題としており、ユダヤ教の原点となるものです。
十戒を中心に神のおきてが集約されているため、もっとも重要な部分と見なされています。次に歴史書(ヨシュア記、土師記、ルツ記、サムエル記上下、列王記上下)と預言書(イザヤ書、エレミヤ書、エゼキエル書、以上大預言書、ホセア書、ヨエル書、アモス書、オバデヤ書、ヨナ書、ミカ書、ナホム書、ハバクク書、ゼファニヤ書、ハガイ書、ゼカリヤ書、マラキ書-以上十二の小預言書)は、「預言」と呼ばれています。歴史を通してイスラエル民族や正に神の意志を語る預言者の言動が中心になっているからです。詩編、蔵言、雅歌、哀歌、コヘレトの言葉などの祈りや詩歌と、ヨブ記、ルツ記、エステル記などの教訓物語、さらにダ二エル書、エズラ記、ネヘミヤ記、歴代誌上下など後期の歴史書などは、まとめて「諸書」と呼ばれています。これらの多くはユダヤ教でも比較的あとの時代に書かれたものです。なお、トビト記、ユディト記、マカバイ記一・二、知恵の書、シラ書(集会の書)、バルク書、ダニエル書のある部分は、新共同訳聖書では旧約聖書続編とされています。カトリックがこれらの書を聖書正典とし、プロテスタントは聖書外典と見なしているからです。これらの書は、さまざまな文体や文学類型を持っており、千年ほどの間に語り伝えられ、書き留められています。こうして、全体としてイエスの頃までのイスラエルの歴史の記録書を構成しています。しかし単なる歴史ではなく、一貫して神の民イスラエルに対する神の導きの歴史として語られています。ユダヤ教は紀元後一世紀末にこれらを正式に神のことばである聖書として最終的に確認しました。キリスト教は、さらに、イエス・キリストの前史でもあるこの聖書に、特別の神の啓示が見いだせるとして、旧約聖書(救い契約に基づいた聖書)として、キリスト教の正典の一部と見なすようになりました.
新約聖書は、キリストの言動を語る四つの福音書、初期の教会の歴史をペトロとパウロを軸として語る使徒言行録、十四のパウロ書簡、その他の七つの使徒的書簡、終末を描くヨハネの黙示録の二十七書から成立しています。これらの書の中でもっとも早く書かれたのは、パウロのテサロニケの信徒への手紙一・二、コリントの信徒への手紙一・二、ローマの信徒への手紙、ガラテヤの信徒への手紙、フィリピの信徒への手紙、フイレモンヘの手紙で、四〇年代末から五〇年代にかけて執筆されています。エフェソの信徒への手紙・コロサイの信徒への手紙は第ニパウロ書簡と呼ばれ、パウロないし彼に近い人の手によるものとされています。テモテヘの手紙一・二、テトスヘの手紙は牧会書簡とも呼ばれ、パウロの考えを受け継いだ後の世代の書です。なお、ヘブライ人への手紙はパウロのものではありません。その他の書簡(ヤコブの手紙、ペトロの手紙一・二、ヨハネの手紙一~三、ユダの手紙、場合によってヘブライ人への手紙)は、公同書簡と呼ばれています。これらの書の多くは、書簡形式を取っていますが、特定の教会に当てたものではなく、教会全体に対して教える意図で書かれています。その多くは、通常紀元一〇〇年前後に執筆されたとされています。
イエスのことばや行いは、教会に規範的なものとしてまずは口伝伝承として大切に伝えられてきましたが、それらを編集して福音潜を著したのがマルコです(六〇年代)。さらにルカによる福音書とマタイによる福音書が書かれ、最後にヨハネによる福音書が書かれました。
参考:カトリック教会の教え。 モヨリ神父
「聖書」(b)
旧約聖書は元来ユダヤ教の聖典です。新約聖書が「聖書」に言及するとき、それは旧約聖書と呼ばれています。その意味での聖書は【律法の書と預言者の書及び、その後に書かれたものです】。 まず、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記は、モーセ五書とも呼ばれ、「律法」の部分です。これらは主としてシナイでの神との契約になって、神の民の発生を主題としており、ユダヤ教の原点となるものです。
十戒を中心に神のおきてが集約されているため、もっとも重要な部分と見なされています。次に歴史書(ヨシュア記、土師記、ルツ記、サムエル記上下、列王記上下)と預言書(イザヤ書、エレミヤ書、エゼキエル書、以上大預言書、ホセア書、ヨエル書、アモス書、オバデヤ書、ヨナ書、ミカ書、ナホム書、ハバクク書、ゼファニヤ書、ハガイ書、ゼカリヤ書、マラキ書-以上十二の小預言書)は、「預言」と呼ばれています。歴史を通してイスラエル民族や正に神の意志を語る預言者の言動が中心になっているからです。詩編、蔵言、雅歌、哀歌、コヘレトの言葉などの祈りや詩歌と、ヨブ記、ルツ記、エステル記などの教訓物語、さらにダ二エル書、エズラ記、ネヘミヤ記、歴代誌上下など後期の歴史書などは、まとめて「諸書」と呼ばれています。これらの多くはユダヤ教でも比較的あとの時代に書かれたものです。なお、トビト記、ユディト記、マカバイ記一・二、知恵の書、シラ書(集会の書)、バルク書、ダニエル書のある部分は、新共同訳聖書では旧約聖書続編とされています。カトリックがこれらの書を聖書正典とし、プロテスタントは聖書外典と見なしているからです。これらの書は、さまざまな文体や文学類型を持っており、千年ほどの間に語り伝えられ、書き留められています。こうして、全体としてイエスの頃までのイスラエルの歴史の記録書を構成しています。しかし単なる歴史ではなく、一貫して神の民イスラエルに対する神の導きの歴史として語られています。ユダヤ教は紀元後一世紀末にこれらを正式に神のことばである聖書として最終的に確認しました。キリスト教は、さらに、イエス・キリストの前史でもあるこの聖書に、特別の神の啓示が見いだせるとして、旧約聖書(救い契約に基づいた聖書)として、キリスト教の正典の一部と見なすようになりました.
新約聖書は、キリストの言動を語る四つの福音書、初期の教会の歴史をペトロとパウロを軸として語る使徒言行録、十四のパウロ書簡、その他の七つの使徒的書簡、終末を描くヨハネの黙示録の二十七書から成立しています。これらの書の中でもっとも早く書かれたのは、パウロのテサロニケの信徒への手紙一・二、コリントの信徒への手紙一・二、ローマの信徒への手紙、ガラテヤの信徒への手紙、フィリピの信徒への手紙、フイレモンヘの手紙で、四〇年代末から五〇年代にかけて執筆されています。エフェソの信徒への手紙・コロサイの信徒への手紙は第ニパウロ書簡と呼ばれ、パウロないし彼に近い人の手によるものとされています。テモテヘの手紙一・二、テトスヘの手紙は牧会書簡とも呼ばれ、パウロの考えを受け継いだ後の世代の書です。なお、ヘブライ人への手紙はパウロのものではありません。その他の書簡(ヤコブの手紙、ペトロの手紙一・二、ヨハネの手紙一~三、ユダの手紙、場合によってヘブライ人への手紙)は、公同書簡と呼ばれています。これらの書の多くは、書簡形式を取っていますが、特定の教会に当てたものではなく、教会全体に対して教える意図で書かれています。その多くは、通常紀元一〇〇年前後に執筆されたとされています。
イエスのことばや行いは、教会に規範的なものとしてまずは口伝伝承として大切に伝えられてきましたが、それらを編集して福音潜を著したのがマルコです(六〇年代)。さらにルカによる福音書とマタイによる福音書が書かれ、最後にヨハネによる福音書が書かれました。
参考:カトリック教会の教え。 モヨリ神父