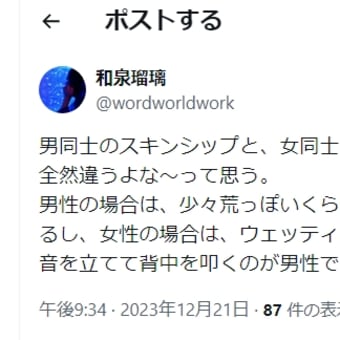各種『忠臣蔵』で描かれる話は以下のようなものだ。主な登場人物は以下の三名。
●浅野内匠頭(あさのたくみのかみ、1667~1701)=浅野長矩(~ながより)
●吉良上野介(きらかうづけのすけ→~こうずけ~、1641~1702)=吉良義央(~よしなか←ネットで「~よしひさ」もあり)
●大石内蔵助(おほいしくらのすけ→おおいし~、1659~1703)=大石良雄(おほいしよしを)
なお、生没年などは、陰暦と陽暦の違いなどにより、資料(史料)によって前後一年の違いがある。
例えば、吉良上野介義央の没年は1702年または1703年。
のちの平賀源内の没年は1779年または1780年。
西郷隆盛が生まれた年は1723年または1328年。
浅野内匠頭は殿中で無抵抗な吉良上野介に斬りつけた。
今も昔も法廷は嘘も真も区別なし
刃傷沙汰の直後、浅野内匠頭は目付の多門傳八郎(傳≠傅、おかどでんぱちらう→~ろう→「おおかど」でなく「おかど」らしい)から取調べを受けた。多門は「乱心ということにしておけば罰も少なくてすむ」という理由で、浅野に「乱心でござろうな」と確認したが、浅野内匠頭はその情けに感謝しながらも「乱心ではない」と主張。
これは今の裁判制度で、殺人犯の辯護(辯≠弁)をする辯護士が「精神が異常だったから責任能力がない」として罪を軽減しようとする工作に似ている。今の被告人は何でも辯護士の言いなりで、浅野内匠頭のように処刑覚悟で信念をはっきり言うものは少ない。それはオウムの麻原も同じだ。法廷というのは「人殺しをしてはいけない」という道徳も忘れ去られ、「責任能力」という詭辯と論点のすり替えで、殺人を正当化する茶番劇の舞台と化している。
裁判というものの奇妙さについては、ジョナサン・スイフト(Jonathan Swift、1667~1745)が『ガリヴァー旅行記(Gulliver's Travels)』(1726)で痛烈に指摘している。
当時の法にもとづいて、浅野は切腹処分となった。テレビでは徳川綱吉の判断での浅野切腹ということである。これに不満を持った大石内蔵助を初めとする赤穗浪士47人(46人との説も)が浅野切腹の次の年、深夜から明け方にかけて吉良邸に侵入、住民を多数、殺傷し、最後に無抵抗な吉良を引きずり出し、首を切断して、道を行進した。狂気の大量殺人事件である。
言わば、地方自治体の長・浅野長矩が、皇居(江戸城)で皇室を招くパーティの責任者となったが、職場で上司・吉良義央に刃物で切りつけたという殺人未遂事件である。そして、浅野長矩〝容疑者〟は死刑となり、浅野の部下・大石良雄以下47名がこの判定に不満を持ち、次の年の冬の夜間に吉良の自宅に侵入、住民を刃物で多数殺傷、最後は大石良雄のグループが吉良義央の首を切断して逃走したという事件である。
大石内蔵助は冬の夜中に人家の前で太鼓をたたき、騒動を起こしていた。これだけで今なら犯罪であろう。
吉良邸への討ち入りは「かたき討ち」ではない
江戸時代には「かたき討ち」、「仇(あだ)討ち」が認められていたが、赤穗浪士がやった吉良殺害事件は「仇討ち」にも入らない。仇討ちとは「加害者」が「被害者」を殺し、「被害者の縁者」が「加害者」の命を狙うものだ。この場合、「被害者の縁者」が大石内蔵助で、「加害者」が吉良上野介とすると、「被害者」は浅野内匠頭長矩になるが、吉良上野介は浅野内匠頭を殺してはいないので、吉良を「加害者」とする理由が存在しない。
殿中では浅野内匠頭が吉良上野介を斬殺しようとしたのであり、浅野は吉良の背中と額を斬って、吉良に傷を負わせ、浅野内匠頭は切腹処分になっている。松の廊下の殺人未遂事件では浅野内匠頭が「加害者」であり、吉良上野介が「被害者」である。そして、「討ち入り」は赤穗浪士が「加害者」で、再び、吉良上野介が「被害者」。
大石は綱吉を討ってこそ「仇討ち」
つまり、「忠臣蔵」とは浅野内匠頭と大石内蔵助という主從が、吉良上野介という同じ標的を殺傷しようとした、連続犯罪である。浅野内匠頭の切腹を「浅野が受けた被害」とすれば、浅野を「殺した」のは吉良上野介ではなく、浅野に切腹を命じた将軍・徳川綱吉である。直接的には浅野の切腹のときの介錯人だが、介錯人を恨む者はいないだろう。
したがって、もし、大石内蔵助らが「亡君・浅野内匠頭の仇討ち」を主張するのなら、徳川綱吉を討つべきであった。
また、浅野を「被害者」、吉良を「加害者」とした場合、浅野が吉良から受けた「被害」なるものは「陰湿ないじめ」だけである。「吉良邸討ち入り」は「刃傷松の廊下」と同様、浅野が受けた「いじめ」への報復である。
したがって、大石らが仇討ちの免状などもらえなかった(おそらく)のは当然で、仇討ちOKの江戸時代でも、赤穗浪士一味47人の所業はただの違法な殺人である。大石主從への切腹処分は当然であった。むしろ、吉良の縁者が大石内蔵助らを「かたき」として狙うことは、理論上、可能であった。「仇討ちの仇討ち」は認められなかったが、大石ら一味による吉良義央殺害事件は「仇討ち」ではないから、吉良の死後、吉良家の関係者が大石らを殺そうとしたら、それは立派な仇討ちであった。だが、結局、大石ら一味を処罰することは幕府によっておこなわれた。
討ち入りに参加する予定で、しなかった毛利小平太については、家族(毛利源左衛門か)から止められたとか、敵と戦って死んだとか、時代劇によっていろいろな解釋がある。
日本の一般庶民が大石らの犯罪行為に拍手を送るところを見ると、日本人はいじめられたと想ったら相手を殺す国民性を持っているのだろう。しかも、大石らは吉良の生首を袋に入れ、棒の先に結び付けて「凱旋」したのだから、日本人は野蛮な首狩り族だと想われても仕方があるまい。
日本で死刑を廃止したら仇討ち復活
呉智英(くれともふさ)氏は「死刑を廃止して仇討ちを復活させるべし」と言っている。光市母子殺害事件の被害者の遺族は、「犯人が死刑にならなかったら、私が復讐する」と述べている。つまり、死刑制度がなくなったら、形はどうあれ、仇討ち、報復が横行するだろう。この場合、仇討ちを合法化するかどうかは、重要ではない。赤穗浪士が吉良上野介を殺害した犯罪行為は違法であったが、日本の大衆はこれを強引に「仇討ち」にして讃美している。
つまり、日本人は「仇討ちなら人を殺していい」と考えている恐ろしい国民だということだ。国連總会が日本の死刑制度を批判しているが、国連とは連合国であり、そもそも、東京裁判で日本の軍人、幹部を処刑した勢力である。死刑制度廃止論者は、廃止したあとの報復の繰り返しを想定していない。日本のマスコミも光市の事件では死刑を求める遺族を好意的に取り上げ、死刑制度については死刑廃止論を好意的に扱う二枚舌が多いように見える。いわゆる「学級会民主主義」というものだろう。
霊媒師(スピリチュアル・カウンセラー?)の悪影響
また、是非はともかく、綱吉の時代は「生類憐みの令」(1685~1709)が出ていた時期である。今で言うスピリチュアル・カウンセラーのような僧侶が「上様に跡継ぎができないのは前世の殺生のせいだ」と言ったかららしい。
スピリチュアル・カウンセラーとは法に触れない限りの霊感商法である。
確か、TBSの『水戸黄門』では光圀が綱吉に犬の皮を多数献上して諭(さと)したように想うが、実際は「憐みの令」は綱吉の死まで、つまり、光圀の死後も九年ほど続いた。
人を犠牲にして犬の命を大事にしていたときに、日本人全体が赤穗の人殺し集団を英雄視していたのだから、「憐みの令」が言語道断だったか、当時の日本人がそこまで命を粗末にしていたか、どちらかだろう。
この風潮は、道連れ自殺を口実にした殺人を「無理心中」という異様なことばで正当化する日本人の国民性をもたらし、沖縄の集団自決も「無理心中」と認識されるに至った。
また、綱吉の時代から400年経過した今の日本でも、相変わらず、占い師や霊媒師が人気である。
犯罪者に対する非公式な処罰、非合法な復讐をもてはやす風土は、のちの「義賊」と称される盗賊、さらに町方同心が殺し屋グループに参加して復讐の代行業をするところに發展することになる。博打はご法度といわれながら、江戸時代中期以降は御三家の藩主、町奉行、さらに同心も賭場で博打をするようになる。
あの『四谷怪談』も元禄時代を舞台にしている(『忠臣蔵外伝・四谷怪談』)。歌舞伎狂言「東海道四谷怪談」の初演は1825年(文政8年)江戸中村座。
『刺客請負人』も吉良邸討ち入りのころの話。
前後一覧
2008年2/25 [1] [2](投稿順)
関連語句
忠臣蔵 赤穗
最新の画像もっと見る
最近の「延宝~貞享~元禄~宝永~正徳、綱吉前後」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- 当Blog内検索(索引)(13)
- 1970年代(59)
- 1980年代~90年代~20世紀末(78)
- 作品、ジャンル別(114)
- 書籍&網頁資料(40)
- 歴史全般、元号(150)
- 漢字論と言語学(39)
- T-Cup掲示板投稿LIST(6)
- SPORTS(51)
- 1960年代(23)
- 宣傳掲示板に書いた内容(9)
- 太古~未来(4)
- 平成史(10)
- 音楽(68)
- Ameba Livedoor Blogs(0)
- 自然科学(7)
- 皇室(3)
- 雑記、メモ、注目記事(6)
- 「終戦」~1950年代(33)
- まえがき、目次、あとがき(14)
- 太古~『西遊記』の時代(79)
- 奈良~平安(14)
- 鎌倉~室町~戦国~安土桃山(59)
- 江戸時代初期、家康~秀忠~家光~家綱(43)
- 延宝~貞享~元禄~宝永~正徳、綱吉前後(105)
- 享保~寛政の改革、エカテリーナIIとアントワネット(84)
- 21世紀~未来(582)
- 文化・文政(37)
- 天保~幕末前夜(59)
- 幕末(30)
- 明治(29)
- 大正(13)
- 昭和初期(55)
- 日記(2)
- 旅行(1)
- グルメ(0)
- 男女平等の限界(45)
バックナンバー
人気記事