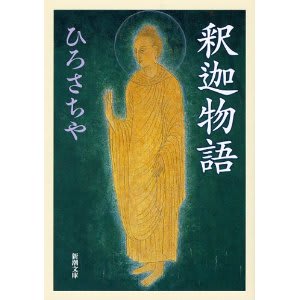
先日、『釈迦物語』(ひろさちや著、新潮文庫)を読了した。書名通り釈迦の生涯について書いたエッセイ集で、28章に亘っている。既に知っている話も多かったが、9章「伝道の旅に出よ」が私的には一番面白かったので、この章を中心に取り上げてみたい。文字通り9章では釈迦や弟子たちの伝道が書かれており、ある日釈尊は60人の弟子たちにこう命じた。
―比丘(びく)たちよ、あなたがたは伝道の旅に出よ。この世の中には真理を知ることによって、苦しみの共存から脱却できる人々が大勢いる。その人々のために、あなたがたは各地に赴き、真理を述べ伝えなければならない。
さらに釈迦は、「しかし、あなたがたは2人してひとつの道を行ってはならぬ」と付け加えている。2人でひとつの道を行くならば、それだけ人々が真理の言葉を耳にする機会が少なくなるからである。面白いことにそれから5百年後、イエスがパレスチナの地で12人の弟子たちに語った言葉は正反対なのだ。著者はイエスの言葉を引用して書く。
―わたしがお前たちを伝道に遣わすのは、狼の群れの中に羊を放り込むようなものだ(マタイ10:16)。お前たちは、ひとつの道を2人して行きなさい。
パレスチナの地でのイエスの伝道には大きな危険が伴っており、そんな状況では最低でも2人組になって行かねばならず、単独行は無理ということ。たった12人の弟子でありながらだ。当時からこの地は宗教には寛容ではなかったと言える。迫害される恐れのない現代日本でも、聖書の一節「また12弟子を呼び寄せ、2人ずつ遣わすことにして」(マルコ6:7)に従ってかクリスチャンは2人組で伝道しており、それを目撃しない日本人の方が稀ではないか?
一方、対照的にインドの地では古代も宗教的に寛容だった。伝道に危険はない。そのため釈迦は単独行を命じたのであり、60人の弟子が60の道を行けば、それだけ真理の教えを聞く人が増えるからだ。60人の弟子たちを伝道の旅に出した後、釈迦自身もまた伝道に赴く。もちろん1人で。向かう先はマガタ国(現代のビハール州辺り)のウルヴィルヴァー。ウルヴィルヴァーはナイランジャナー河(尼連禅河)のほとりにあり、かつて釈迦が苦行、悟りを開いた地である。
当時ウルヴィルヴァーには事火外道(じかげどう)の一大勢力があった。“外道”とは仏教から見た他宗教教団を指し、他宗教からすれば仏教こそ“外道”となるが、事火外道とは火を神聖視する宗教の信奉者を意味している。拝火教といえばゾロアスター教を連想される方が殆どだろうが、拝火信仰はゾロアスター教に限らない。
ウルヴィルヴァーの事火外道はインド神話の火神アグニを崇める教団であり、指導者はバラモンのカッサパ三兄弟(三迦葉)。この三兄弟が教団を指導・運営していた。ちなみにインドの大陸間弾道ミサイル・アグニVの名はこの火神から来ている。
長兄の大カッサパはナイランジャナー河の上流に本拠を構え、5百人の弟子を擁していた。次兄・中カッサパはナイランジャナー河の中流に住み3百人の弟子を、下流には三男の小カッサパと2百人の弟子がいた。釈迦は真っ先に大カッサパに挑戦する。
伝えによれば大カッサパは120歳で、釈迦は40歳前後と推定される。その名がマガタ国中に知れ渡った大宗教家の前者に対し、釈迦はまだ無名の人物なのだ。少なくともマガタ国では釈迦の名は知られてなかった。そんな若者がひょっこりやって来て、高名な宗教家に一夜の宿を貸して欲しいという有様。明らかに大カッサパに対する挑発であり挑戦だった。
「見知らぬ者を泊める処はここにはない」と、不遜な若者の要求に腹を立てた大カッサパは一旦断るが、聖火堂なら空いていると付け加えた。聖火堂には龍が住んでおり、自分以外の者には扱えない、だからお前はこの堂に泊まる訳にはいかないと言う。聖火堂は彼の教団の最高の聖所であり、そこに入り、無事に出てこられるのは大カッサパ以外に誰もいなかったのだ。
「心配には及ばない。龍が住んでいても結構だ。そこに泊めて頂こう」との釈迦の返答に応じた大カッサパだが、かくして両者の対決が始まる。
その二に続く
よろしかったら、クリックお願いします![]()
![]()




















どれもアーリア人文化の影響を受けているという共通項がありますね
後イグニスは、英語のイグニッションの語源とも
名は忘れましたが、ある欧米の知識人がインド人を讃え、偉大な世界宗教(仏教)と偉大な民族宗教(ヒンドゥー教)を生んだ唯一のアーリア人と言っていました。他のアーリア人は異民族が創生した宗教を拝んでいる…と悔しげな発言だったのを憶えています。