宮城県知事 会見 20070213
また、うんざりする異人の襲来である。
一部の人の利益の追求が、莫大な予算と時間を浪費させる。
朝日新聞のコメントで岩崎さんが言っているように、「根本的な解決策は、危険性がある生物輸入を阻止すること。国は検疫制度を充実させるべきだ」これしかない。
毎日新聞 ホヤ感染症 全国初確認 2007329
宮城のホヤ、一部禁漁へ 「軟化症」拡大防止へ強硬手段(朝日新聞) - goo ニュース
☆テキスト版
宮城のホヤ、一部禁漁へ 「軟化症」拡大防止へ強硬手段
2007年4月7日(土)20:29
* 朝日新聞
韓国から輸入した養殖用ホヤの「タネ」と一緒に侵入したとみられる疾病の拡大を防ぐため、宮城県はホヤの漁業権を一部停止して養殖を禁じる方針を決めた。農林水産省によると、疾病防止のための漁業権停止は全国で初めて。強硬手段の背景には、水産動物の大半が検疫の対象外となっている国の疾病防止策の緩さがあるとの指摘もある。
ホヤは殻に包まれたオレンジ色の肉が食用になり、宮城や岩手など三陸地方で根強い人気がある。韓国でも人気だが、同国では最近、殻が軟らかくなって死ぬ「軟化症」が流行して生産量が激減した。このため、三陸産ホヤの需要が急に増え、生産地ではタネの稚ホヤが慢性的に不足していた。
全国の養殖ホヤの8割を生産する宮城県は、感染防止のため韓国産稚ホヤを使わないよう指導していた。しかし、1月に一部地域で輸入していたことが判明。軟化症のホヤも次々と発見された。
拡大防止のため、県は軟化症が確認された北部沿岸で来年9月から5年間、ホヤ漁業権を停止することを決めた。感染したホヤを取り除き、海域の浄化を狙う。
国の検疫制度では、対象となっている水産動物は4種類だけで、大半が自由に輸入されている。日本ベントス(底生生物)学会で自然環境保全委員長を務める岩崎敬二・奈良大教授は「根本的な解決策は、危険性がある生物輸入を阻止すること。国は検疫制度を充実させるべきだ」と指摘する。
★テキスト版
ホヤ:全国初、身腐る感染症--養殖漁場6地点 /宮城
3月29日11時1分配信 毎日新聞
県は28日、ホヤの養殖漁場6地点で生産されたホヤから、殻が溶けて身が腐る感染症とみられる症状が全国で初めて確認された、と発表した。県は感染経路の解明を進めるとともに、6地点で養殖するホヤを順次撤去し、08年9月以降は5年間、養殖を中止する。
ホヤを養殖する県内15漁協のうち4漁協の組合員が、ホヤの大量死が発生している韓国から種苗を輸入していたことが発覚したため、県内全漁場35地点を調査していた。
その結果、南三陸町歌津末の崎周辺の6地点で、3年物以上のホヤに症状を確認。うち1地点は、04年に韓国産種苗を導入していたという。感染症は「被のう軟化症」と命名された。県漁港漁場整備課は「仮に食べたとしても健康に影響はない」と話している。
県内のホヤの生産量は年間6000~7000トンと全国1位。感染症が確認された漁場は県内有数の1500トン程度の水揚げがある。県漁連は「韓国との関連性の有無をしっかり調査して、風評被害が起こらないようにしてほしい」と話している。【石川貴教】
3月29日朝刊
最終更新:3月29日11時1分
毎日新聞
また、うんざりする異人の襲来である。
一部の人の利益の追求が、莫大な予算と時間を浪費させる。
朝日新聞のコメントで岩崎さんが言っているように、「根本的な解決策は、危険性がある生物輸入を阻止すること。国は検疫制度を充実させるべきだ」これしかない。
毎日新聞 ホヤ感染症 全国初確認 2007329
宮城のホヤ、一部禁漁へ 「軟化症」拡大防止へ強硬手段(朝日新聞) - goo ニュース
☆テキスト版
宮城のホヤ、一部禁漁へ 「軟化症」拡大防止へ強硬手段
2007年4月7日(土)20:29
* 朝日新聞
韓国から輸入した養殖用ホヤの「タネ」と一緒に侵入したとみられる疾病の拡大を防ぐため、宮城県はホヤの漁業権を一部停止して養殖を禁じる方針を決めた。農林水産省によると、疾病防止のための漁業権停止は全国で初めて。強硬手段の背景には、水産動物の大半が検疫の対象外となっている国の疾病防止策の緩さがあるとの指摘もある。
ホヤは殻に包まれたオレンジ色の肉が食用になり、宮城や岩手など三陸地方で根強い人気がある。韓国でも人気だが、同国では最近、殻が軟らかくなって死ぬ「軟化症」が流行して生産量が激減した。このため、三陸産ホヤの需要が急に増え、生産地ではタネの稚ホヤが慢性的に不足していた。
全国の養殖ホヤの8割を生産する宮城県は、感染防止のため韓国産稚ホヤを使わないよう指導していた。しかし、1月に一部地域で輸入していたことが判明。軟化症のホヤも次々と発見された。
拡大防止のため、県は軟化症が確認された北部沿岸で来年9月から5年間、ホヤ漁業権を停止することを決めた。感染したホヤを取り除き、海域の浄化を狙う。
国の検疫制度では、対象となっている水産動物は4種類だけで、大半が自由に輸入されている。日本ベントス(底生生物)学会で自然環境保全委員長を務める岩崎敬二・奈良大教授は「根本的な解決策は、危険性がある生物輸入を阻止すること。国は検疫制度を充実させるべきだ」と指摘する。
★テキスト版
ホヤ:全国初、身腐る感染症--養殖漁場6地点 /宮城
3月29日11時1分配信 毎日新聞
県は28日、ホヤの養殖漁場6地点で生産されたホヤから、殻が溶けて身が腐る感染症とみられる症状が全国で初めて確認された、と発表した。県は感染経路の解明を進めるとともに、6地点で養殖するホヤを順次撤去し、08年9月以降は5年間、養殖を中止する。
ホヤを養殖する県内15漁協のうち4漁協の組合員が、ホヤの大量死が発生している韓国から種苗を輸入していたことが発覚したため、県内全漁場35地点を調査していた。
その結果、南三陸町歌津末の崎周辺の6地点で、3年物以上のホヤに症状を確認。うち1地点は、04年に韓国産種苗を導入していたという。感染症は「被のう軟化症」と命名された。県漁港漁場整備課は「仮に食べたとしても健康に影響はない」と話している。
県内のホヤの生産量は年間6000~7000トンと全国1位。感染症が確認された漁場は県内有数の1500トン程度の水揚げがある。県漁連は「韓国との関連性の有無をしっかり調査して、風評被害が起こらないようにしてほしい」と話している。【石川貴教】
3月29日朝刊
最終更新:3月29日11時1分
毎日新聞











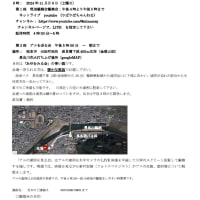














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます