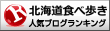逗子にて
逗子にて

私もいよいよ「アラフィフ」と言わねばならない年齢となりました。
どうして日本ってところは、こうも年齢にこだわるのだろうか。
私の頭は実年齢に追いついていけません。
40過ぎたら誕生日は2年に1回でいいと思う!
(心の叫び)
私が子供の頃、周りの大人たちはしょっちゅう「最近の歌はよく分からない。」と言って、
石原裕次郎や美空ひばりを聴いていました。
私も大人になったら「最近の歌はよく分からない。」と言うのだろうかと思いながら、
石原裕次郎や美空ひばりを聴いていました。
しかし、「アラフィフ」となっても最近の歌が分からないと思うことはありません。
むしろ、ますます好きな音楽のジャンルが広がって、
洋の東西を問わず色々な音楽が聴けることの喜びをかみしめています。
(いや、まだまだ私の知らない音楽はあるはずだ!)
なぜこのようなことが起こるのか、ちょこっと考えてみました。
そして思いついたことは、多分「音育」のお陰だったのではないか、ということです。
「食育」ならぬ「音育」。
子どもの頃から様々なジャンルの音楽を聴いてきたため、
音楽に対して好き嫌いがないのだと思います。
(若い時は苦手なジャンルもあったけどね。)
音楽については様々な好みや意見があることと思いますが、
私たちの生活に寄り添って潤いを与えてくれる音楽の種類がたくさんあるというのは、
とても幸せなことだと思います。
さて、先日訪れた高養寺(=浪子不動 神奈川県逗子市)。
そのお寺の前にちょっとした広場があり、「さくら貝の歌」の歌碑を見つけました。
 「さくら貝の歌」とは
「さくら貝の歌」とは
日本の唱歌。土屋花情・作詞、八洲秀章・作曲。
昭和18年(1943)には完成していたが、昭和24年(1949)に発表される。
2007年、文化庁と日本PTA全国協議会により「日本の歌百選」に選定される。
(コトバンクより)
作曲を担当した八洲が病で恋人を失った時に詠んだ和歌を元に、
八洲の友人であり、逗子町役場に勤めていた土屋花情が作詞した歌である。
(ミュージカル俳優 沢木順 公式HPより ※沢木順氏は八洲のご子息)
碑が建つ程の歌だというのに、残念ながら私、知りませんでした。
という訳で、聴いてみました。
(今は本当、便利よね。)
昭和24年に発表され、多くの女性の心をとらえたとあります。
その時代であれば、きっと戦争で大事な人を亡くした女性たちの心をとらえたのではないでしょうか。
歌の背景を知り、平和の尊さをかみしめることができました。
調べてみて良かったです。
この歌は多くの歌手によってカバーされているようですが、
声楽家の演唱の方がこの歌の芸術性がより強調されると思い、
鮫島有美子さんバージョンを選びました。
昭和20年代の歌というと、「リンゴの唄」や「東京キッド」、「青い山脈」、「岸壁の母」、「東京ブギウギ」、
「憧れのハワイ航路」、「お富さん」などなどありますが、この時代のものはメロディーが覚えやすいだけでなく、
短い歌詞であっても情景や心情をうまく表現しているものが多く、素晴らしい曲が多いと思います。
個人的には「リンゴの唄」は名曲だと思っています。
「さくら貝の歌」。
また良い音楽に出会えました。