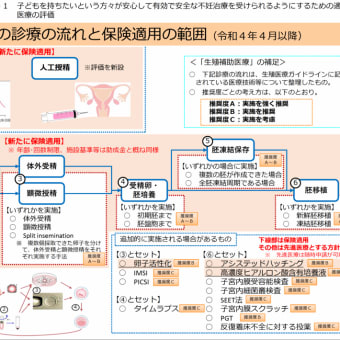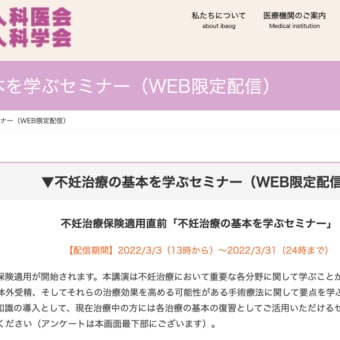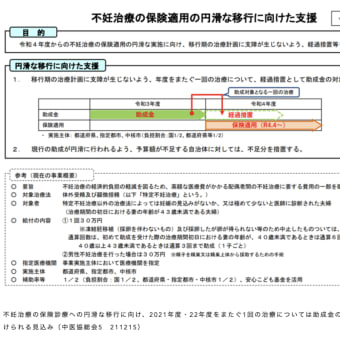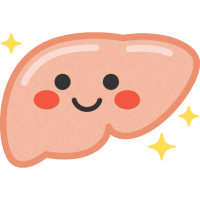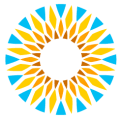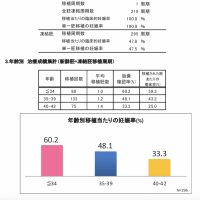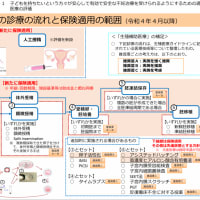東洋医学では体が持つ病気に抵抗する力を「正気」とよび、体の生命活動を妨げる要因を「邪気(邪)」といいます。
たとえ体が病因の影響を受けても、正気が邪気より強ければ病気にはなりません。正気は気・血・津液(水)や臓腑の働きが悪くなると弱くなり、体のバランスが崩れると邪気が体に侵入しやすくなります。
邪気が体に侵入すると正気は攻撃を開始し、それが症状として体に現れます。かぜを引いた時に熱が出たり悪寒がしたりするのは、かぜと正気が闘っているからです

また邪気には外からもたらされる「外邪」と、感情の変化など自分の体の中から発生する「内邪」とに分けられます。
外邪とは細菌やウイルスなど有害物質が体内に入ることも一つですが、季節の移り変わりによる気象の変化も、強くなると外邪となることがあり、これを「六淫(または六気)」と言います。
六淫(りくいん)
風邪・・・風が吹くように突然症状が現れ病状も次々と変わる。頭痛、発熱、悪寒など。
寒邪・・・冷えが気・血・水を停滞させ、停滞している部分が痛む。
暑邪・・・激しい暑さが体を消耗させる。熱と湿が混じった状態で汗を大量にかく。
湿邪・・・湿気が気・血・水を停滞させる。粘る性質があり長引きやすい。
燥邪・・・体が乾き水が不足する。呼吸器が影響を受けやすい。肌の乾燥、咳など。
火邪・・・暑以外の外熱か体の熱がさかんになりすぎたもの。
以上が外邪ですが、次にもう一つの病因、内邪について説明します。
自分の体の中から発生する病因を内因(内邪)と言い、精神的な面から病気になることを内傷と言います。喜・怒・憂・悲・思・恐・驚の7つの感情が度を超すと病気を起こすことがあり、これを「七情」と言います。過度の情動は気の動きに影響を与え、その結果、関係する臓腑の機能も乱れ内傷となるのです。
七情(しちじょう)
喜・・・喜びの感情が過剰になると心の不調が現れやすい。気の緩みや集中力の低下など
怒・・・気・血・水を滞りなく巡らせる役割の肝に影響を与えやすい。イライラなど。
憂(悲)・・・肺の変調につながりやすく呼吸器や風邪をひきやすくなる。
思・・・過剰に思い悩み続けると脾に影響する。食欲不振や腹痛、下痢など。
恐(驚)・・・極度に驚いたり恐怖を感じると腎の不調が現れやすい。水分代謝の悪化など
これらの感情がすぐに邪気になるわけではありませんが、とくに急激に感じたり、長期間に渡って感じ続けると病気につながると考えられています。
ストレスが病気に関わることは、よく言われていますが、東洋医学では、どの感情も偏りすぎると良くないと考えられています。病気にならないようにするには、自分の感情も上手にコントロールすることが大切です

その他にも飲食の不摂生や働きすぎによる疲労など、東洋医学の病因は、気候や感情、生活習慣を含めて様々な病因が複合的に関与しています。病気の治療は、外的要因の排除だけでなく、生活習慣の見直しや精神的なサポートも重要な治療の一環となります。
少し難しい話になりましたが、血の流れが悪くなって滞ったり、体が代謝した代謝産物が体の外に排出されず血が汚れると病気をひきおこしたりします。
調子が悪いな~と思ったら、鍼灸師にご相談頂ければ東洋医学的な視点でお体を診させていただくこともできますので、お気軽にご相談くださいね。