お友達に誘っていただいて、そして、
子どもも夜に私がいなくても大丈夫になってきたので、
高橋巌さんの講義に参加しました。
ここを覗きに来てくださる方は先刻ご承知のように、
シュタイナー関係の本を手に取ると、
半分くらいは高橋さん訳じゃない?というほど、
現在進行形で、膨大な翻訳仕事をされている方です。
講義テーマは「瞑想によるひとつの自己認識への道」。
テキストはご自分が訳している最中のもの。
私にとって、初リアル高橋巌さんは、
「大学の先生ってこんな感じだったな~」という印象。
一語一語をとてもゆっくり、かみしめながら読み上げ、
必要に応じて、淡々とコメントや解説を加えます。
しかし、その淡々とした解説の、
(私の理解力不足で)なんと意味不明で
(たまにわかるところの)なんと深いこと。
一言も聞き漏らしたくなくて、後でゆっくり考えたくて、
必死で書き留めます。
集中して書き留めているうちに、すぐ終わりました。
解説は、たとえば、
「わかる」ということは、
知識だけで手放すことにつながります。
シュタイナーは、読者に「わかった」と言わさないように、
あの手この手で、実際に瞑想させようと、誘っています。
…というような話。
シュタイナーが、体温を持つ身近な先生みたいに感じられて
かなりおもしろいです。
具体的なテキストの内容は、
知識として持ってても仕方ない種類の、瞑想の方法です。
「わかった」とは言えませんが、理解しなければ始められません。
そして、もちろん、1回では理解できません。
また時間をおいて読んで、やってみよう。
高橋さんの翻訳は、他の方と比べて
「~ねばならない」という表現がいっぱいあるんですが、
それは、ご自分がとてもきっちりした方っぽいので、
ごく自然にそう訳される言葉なんだな、と理解しました。
別にそれを読む私たちが
「そんなのできないよ~」とか「窮屈だわ」とか
勝手にひがむ必要はないんだ、と思いました。
自分の仕事に誠実に仕えるパワーを感じます。
とても、淡々とそして熱く、ご自身のするべきことを行い、
自分の思いこみの檻を厳しく外して自由に考え、
周囲に対しては、すべてを包み込むように目を注がれる。
テレビドラマも、哲学書も、歴史書も、
講義内容が難しくて付いていけてない私のような人も、
社会的に大丈夫??というくらい、変にハマってる人も、
色眼鏡で見られることなく、優劣付けられることなく、
同じ土俵の上で、きちんと尊重され包み込んでもらえる。
それって、すごい。
アントロポゾフィって、そういうところがすごい。
そういうところが自由だ。
余談ですが、高橋さん、
話すのも呼吸も物腰もゆっくりですが、
歩くのは早く飄々として、体重を感じさせませんでした。
休憩時間に廊下で話をしている横をすぅ~っと通られて、
「えっ、早っ!」と驚きました。
学んだことも少しはメモしておきましょう。
と言っても、理解できたのはたった2つ。
1
概念から表象へ。
表象とは、一般論を自分のこととしてとらえ直すことです。
表象することで、頭で理解したことを心でも、
場合によってはカラダでも理解できます。
たったそれだけの違いですが、そのとてつもない大切さ。
この集中講義で学んだ一番基本のとこです。
2
あとは「エーテル体験」への取り組み。
A(=石でも絵でも景色でも何でもいいけど)を見て、
「私がAを見ている」んじゃなくて、
「Aが私の中で存在している」という、主客の逆転。
自分が主語でなくなり、対象が主語になった時に、
自分の中に別の次元が生まれる、と。
(理解が浅くてうまくお伝えできません、ゴメンなさい)。
そういう話を聞いて3日後、
1時間くらい時間があったから、美術館に行って、
そういう心構えで、絵を見てきました。
「エーテル体験してみよう」と。
その話は、また今度。
その前に、講義の後の話に続きます。












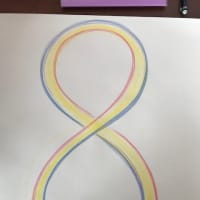







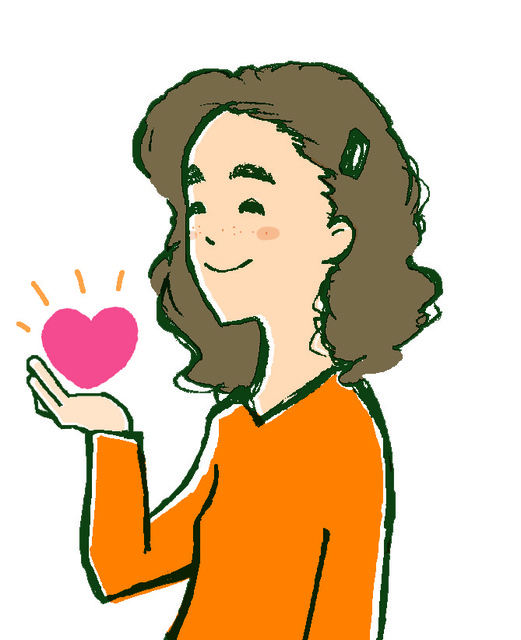

エーテル体験のところ、4章の問いにつながるのかもと思いました
観察対象がどのようにして意識に入り込むのか?という問いを、何で問うのよ?と違和感だったからヒントをいただいた気持ちです
いつもありがとうございます!
ありがとうございます。今頃のお返事でスミマセン。
4章、哲学用語満載で異常にややこしいですよね。
いつも思うのですが、私はとにかく書いてあることを理解しようとするけど、
hasutama様は、書いてあること自体を問いになさる、という、私から見るとミラクルな技を繰り出されますよね。
最近、ようやく反抗期になってきた娘が
「批判的精神や、対象に距離を置いて見ることが、自立への道だ」と、教えてくれています。
私もそのうち、この本を自立して読めるようになりたいなぁ。
今はまだ、従順な子羊状態。いつ大人になるんだろ(^^;)?
励みになります。ありがとうございます♪