東北の地震で日本中が慌て、
生きることについて考え直したり、
自分の力不足を嘆いたり、
誰かを責めたりしていた時、
普段通りに剣術の練習をしていた人の話を聞いた。
剣術と言えば、宮本武蔵。
宮本武蔵は、一生涯、無敗だった。
その著書『五輪の書』の水の巻に
「千日の稽古を鍛とし、
万日の稽古を錬とす」という有名な言葉がある。
原稿用紙1枚ちょっとの短い文章の最後の部分(後示)。
最初、これを読んだ時は、
無敗のオトコが、人を殺す方法を書いた、
生臭い書き物だと思った。
「この勤勉さを身につけたいな、
けど、私は戦うのキライだな」と思った。
でも、何かの縁があるらしく、
時間を置いてまた10回ほど読んだら、
「負けたら即、死」のギリギリの世界で生きている男が、
いかに(他人ではなく)自分に勝つか、強くなるか、
を書いた書物だと受け取り方が少し変わった。
さらに10回ほど読み重ねたら、今度は、
剣術を極めた男が、年を重ね、剣を越えて、
自分を鍛え、世に活かす「道」を弟子に伝える、
懐の深さを感じる暖かなまなざしを感じた。
「焦るな、迷うな」
「ただ為すべき事を一つずつ為せ」
「道を外れるな」って。
もちろん、剣は躰を使う術だから、
言葉で伝わらないもどかしさもあっただろうけど。
文章は自分の鏡なんだ、きっと。
それだけしか読み取れないのは、
自分がそれだけだからだ。
もっと読み続けたら、
もっと深い、別のメッセージが届くんだろうな。
もっと自分が成長したら、
もっと深い真理が開示されるのだ、きっと。
こういう読書は、娯楽ではない。
速読も、適さない。
それこそ「真剣」勝負。
この短い文章を、
何度も何度も声に出して味わいながら歩いていると、
フシギなことに、というか、何のフシギもないのだけれど、
行き交う人が、私も含めて、みんな、
「今、ほんの何十年かのひととき、
生きているんだなぁ…」と、
当たり前のことを改めて思い、愛おしくなった。
こっちがそういう、開いたモードだったせいか、
目が合った何人もの人が、挨拶を返してくれた。
ジョギング中の男性が「よ〜ッス!」、
犬の散歩をしている女性が「おはようございます」、
朝の早い道路工事の男性が、
わざわざ振り向いて「行ってらっしゃーい」、
…なんともフシギな朝だった。
宮本武蔵『五輪の書』水の巻より
慣れない言葉で読みにくいけど、こんなの↓。
あー、横書きだと全然イメージ違うなぁ。
兵法、太刀を取りて、人に勝つ所を覚ゆるは、
先ず五つのおもてを以て五方の構をしり、
太刀の道を覚へて惣躰自由になり、
心のきき出でて道の拍子をしり、
おのれと太刀も手さへて、
身も足も心の儘にほどけたる時に随ひ、
一人にかち、二人にかち、
兵法の善悪を知る程になり、
此一書の内を、一ヶ条一ヶ条と稽古して、
敵とたたかい、次第次第に道の利を得て、
不断心に懸け、いそぐ心なくして、
折々手にふれては徳を覚へ、
いづれの人とも打合ひ、其心をしつて、
千里の道もひと足宛はこぶなり。
緩々と思ひ、此法をおこなふ事、
武士のやくなりと心得て、
けふはきのふの我にかち、あすは下手にかち、
後は上手に勝つとおもひ、
此書物のごとくにして、
少しもわきの道へ心のゆかざるやうに思ふべし。
縦ひ何程の敵に打ちかちても、
ならいに背く事においては、
実の道にあるべからず。
此利心にうかびては、
一身を以て数十人にも勝つ心のわきまへあるべし。
然る上は、剣術の智力にて、
大分一分の兵法をも得道すべし。
千日の稽古を鍛とし、
万日の稽古を錬とす。
能々吟味有るべきもの也。
生きることについて考え直したり、
自分の力不足を嘆いたり、
誰かを責めたりしていた時、
普段通りに剣術の練習をしていた人の話を聞いた。
剣術と言えば、宮本武蔵。
宮本武蔵は、一生涯、無敗だった。
その著書『五輪の書』の水の巻に
「千日の稽古を鍛とし、
万日の稽古を錬とす」という有名な言葉がある。
原稿用紙1枚ちょっとの短い文章の最後の部分(後示)。
最初、これを読んだ時は、
無敗のオトコが、人を殺す方法を書いた、
生臭い書き物だと思った。
「この勤勉さを身につけたいな、
けど、私は戦うのキライだな」と思った。
でも、何かの縁があるらしく、
時間を置いてまた10回ほど読んだら、
「負けたら即、死」のギリギリの世界で生きている男が、
いかに(他人ではなく)自分に勝つか、強くなるか、
を書いた書物だと受け取り方が少し変わった。
さらに10回ほど読み重ねたら、今度は、
剣術を極めた男が、年を重ね、剣を越えて、
自分を鍛え、世に活かす「道」を弟子に伝える、
懐の深さを感じる暖かなまなざしを感じた。
「焦るな、迷うな」
「ただ為すべき事を一つずつ為せ」
「道を外れるな」って。
もちろん、剣は躰を使う術だから、
言葉で伝わらないもどかしさもあっただろうけど。
文章は自分の鏡なんだ、きっと。
それだけしか読み取れないのは、
自分がそれだけだからだ。
もっと読み続けたら、
もっと深い、別のメッセージが届くんだろうな。
もっと自分が成長したら、
もっと深い真理が開示されるのだ、きっと。
こういう読書は、娯楽ではない。
速読も、適さない。
それこそ「真剣」勝負。
この短い文章を、
何度も何度も声に出して味わいながら歩いていると、
フシギなことに、というか、何のフシギもないのだけれど、
行き交う人が、私も含めて、みんな、
「今、ほんの何十年かのひととき、
生きているんだなぁ…」と、
当たり前のことを改めて思い、愛おしくなった。
こっちがそういう、開いたモードだったせいか、
目が合った何人もの人が、挨拶を返してくれた。
ジョギング中の男性が「よ〜ッス!」、
犬の散歩をしている女性が「おはようございます」、
朝の早い道路工事の男性が、
わざわざ振り向いて「行ってらっしゃーい」、
…なんともフシギな朝だった。
宮本武蔵『五輪の書』水の巻より
慣れない言葉で読みにくいけど、こんなの↓。
あー、横書きだと全然イメージ違うなぁ。
兵法、太刀を取りて、人に勝つ所を覚ゆるは、
先ず五つのおもてを以て五方の構をしり、
太刀の道を覚へて惣躰自由になり、
心のきき出でて道の拍子をしり、
おのれと太刀も手さへて、
身も足も心の儘にほどけたる時に随ひ、
一人にかち、二人にかち、
兵法の善悪を知る程になり、
此一書の内を、一ヶ条一ヶ条と稽古して、
敵とたたかい、次第次第に道の利を得て、
不断心に懸け、いそぐ心なくして、
折々手にふれては徳を覚へ、
いづれの人とも打合ひ、其心をしつて、
千里の道もひと足宛はこぶなり。
緩々と思ひ、此法をおこなふ事、
武士のやくなりと心得て、
けふはきのふの我にかち、あすは下手にかち、
後は上手に勝つとおもひ、
此書物のごとくにして、
少しもわきの道へ心のゆかざるやうに思ふべし。
縦ひ何程の敵に打ちかちても、
ならいに背く事においては、
実の道にあるべからず。
此利心にうかびては、
一身を以て数十人にも勝つ心のわきまへあるべし。
然る上は、剣術の智力にて、
大分一分の兵法をも得道すべし。
千日の稽古を鍛とし、
万日の稽古を錬とす。
能々吟味有るべきもの也。












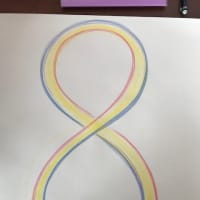







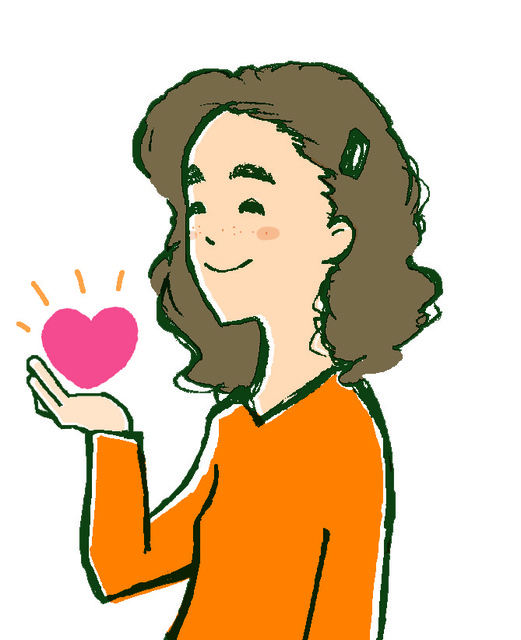

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます