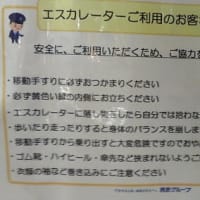11月8日(月)庄司紗矢香(Vn)/ジャンルカ・カシオーリ(Pf) デュオ・リサイタル
サントリーホール
【曲目】
1.ベートーヴェン/ヴァイオリン・ソナタ第2番イ長調Op.12-2
2.ベートーヴェン/ヴァイオリン・ソナタ第5番ヘ長調Op.24 「春」

3.ベートーヴェン/ヴァイオリン・ソナタ第9番イ長調Op.47 「クロイツェル」


【アンコール】
ベートーヴェン/ヴァイオリン・ソナタ第8番ト長調Op.30-3~第2楽章

大器にますます磨きをかけている庄司紗矢香が、気鋭の個性派ピアニスト、カシオーリとのデュオでやるベートーベン、どんな演奏になるか始まる前からワクワクする。
第2番のソナタの演奏からは、空気が澄み切った早朝、朝露が葉っぱの上を水玉になり、明るい光に反射しながら転がり落ち、下の池に心地よい雫の音を立てているシーンが、音と光も一緒に心に浮かんだ。汚れのない透明感、ハッとする刹那的な美しさ。庄司さんがプログラムで「特別」と語ったという第2楽章の静寂なカンタービレからは、蝶が羽化するような、命が生まれる瞬間に立ち合っている感じがした。
2番の演奏でも何か特別なものを感じたが、「スプリング・ソナタ」や「クロイツェル・ソナタ」では、よく知っているだけに、二人の演奏が聴き慣れた演奏とは異った、特別なものであることがよくわかる。庄司とカシオーリは、まずこれらの有名曲を、ばらせる最小のパーツにまでばらし、ひとつひとつのパーツの汚れや埃を落とし、丁寧に磨き、そして、当たり前のように出来上がっていた従来のこの曲のイメージを白紙状態にして再構築しているよう。
組み立てる際は、パーツ同士がどこでどんな風につながり、全体の中でどんな機能を果たすかを再検討して提示する。それが、現代曲の初演に立ち合っているような新鮮な発見と感動を呼び覚ます。いつもフォルテで聴き慣れているフレーズが弱音で奏でられ、いつもは聴こえてこないピアノの内声の動きが浮かび上がる。同じ形のフレーズが繰り返されるとき、2度目は姿を変えて奏される。この最後を例に取ってみると、一回目が外へ向けた気持ちだとすれば、2度目は内へと向かう気持ちという具合に、有機的につながっていて、これらの「変わり身」が、どれもが説得力を持って訴えてくる。それは、庄司とカシオーリの綿密な計算があればこそだろう。
二人は、荒々しく音の塊をぶつける「ベートーベンらしさ」の代わりに、全体的にテンポを落とし、敏感で、繊細なものを積み上げるやり方で、大きなものを作り上げて行く。二人は演奏する曲を研究し尽くしているに違いないが、ホールの響きとか、お客の雰囲気とか、二人の気分などの要素も加えて、再構築の作業に即興性も加えて、楽しんでいるようにも感じる。
庄司の研ぎ澄まされた美しいヴァイオリンと同時に、カシオーリのピアノが映えていた(美人の譜めくりスィニョリーナも気になる存在 )。ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタは、ピアノパートが重要であることはわかってはいるが、ヴァイオリンが伴奏型を受け持つときでもやっぱりヴァイオリンに耳が行ってしまう。それが、今夜は、ピアノが主役の部分はヴァイオリンが「さあ、今はピアノを聴いて下さい」とでも言っているように脇役に徹したり、或いは、スパイスの効いた味つけでピアノを引き立てる。
)。ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタは、ピアノパートが重要であることはわかってはいるが、ヴァイオリンが伴奏型を受け持つときでもやっぱりヴァイオリンに耳が行ってしまう。それが、今夜は、ピアノが主役の部分はヴァイオリンが「さあ、今はピアノを聴いて下さい」とでも言っているように脇役に徹したり、或いは、スパイスの効いた味つけでピアノを引き立てる。
同じ方向に向かい、ぴったりと意気投合しつつ作り上げられる、新鮮で、スリリングで、透徹したベートーヴェン像に、すっかり圧倒されてしまい、結局「すごい」という言葉しか出てこない。
最後のアンコールを聴いて思ったことは、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタにもし、ピアノ・ソナタや弦楽四重奏曲のような晩年の作品があれば、どんな演奏をしてくれるだろうか… ということ。二人の奏でるベートーヴェンはどこまでも深化していくように感じた。
サントリーホール
【曲目】
1.ベートーヴェン/ヴァイオリン・ソナタ第2番イ長調Op.12-2

2.ベートーヴェン/ヴァイオリン・ソナタ第5番ヘ長調Op.24 「春」


3.ベートーヴェン/ヴァイオリン・ソナタ第9番イ長調Op.47 「クロイツェル」



【アンコール】
ベートーヴェン/ヴァイオリン・ソナタ第8番ト長調Op.30-3~第2楽章


大器にますます磨きをかけている庄司紗矢香が、気鋭の個性派ピアニスト、カシオーリとのデュオでやるベートーベン、どんな演奏になるか始まる前からワクワクする。
第2番のソナタの演奏からは、空気が澄み切った早朝、朝露が葉っぱの上を水玉になり、明るい光に反射しながら転がり落ち、下の池に心地よい雫の音を立てているシーンが、音と光も一緒に心に浮かんだ。汚れのない透明感、ハッとする刹那的な美しさ。庄司さんがプログラムで「特別」と語ったという第2楽章の静寂なカンタービレからは、蝶が羽化するような、命が生まれる瞬間に立ち合っている感じがした。
2番の演奏でも何か特別なものを感じたが、「スプリング・ソナタ」や「クロイツェル・ソナタ」では、よく知っているだけに、二人の演奏が聴き慣れた演奏とは異った、特別なものであることがよくわかる。庄司とカシオーリは、まずこれらの有名曲を、ばらせる最小のパーツにまでばらし、ひとつひとつのパーツの汚れや埃を落とし、丁寧に磨き、そして、当たり前のように出来上がっていた従来のこの曲のイメージを白紙状態にして再構築しているよう。
組み立てる際は、パーツ同士がどこでどんな風につながり、全体の中でどんな機能を果たすかを再検討して提示する。それが、現代曲の初演に立ち合っているような新鮮な発見と感動を呼び覚ます。いつもフォルテで聴き慣れているフレーズが弱音で奏でられ、いつもは聴こえてこないピアノの内声の動きが浮かび上がる。同じ形のフレーズが繰り返されるとき、2度目は姿を変えて奏される。この最後を例に取ってみると、一回目が外へ向けた気持ちだとすれば、2度目は内へと向かう気持ちという具合に、有機的につながっていて、これらの「変わり身」が、どれもが説得力を持って訴えてくる。それは、庄司とカシオーリの綿密な計算があればこそだろう。
二人は、荒々しく音の塊をぶつける「ベートーベンらしさ」の代わりに、全体的にテンポを落とし、敏感で、繊細なものを積み上げるやり方で、大きなものを作り上げて行く。二人は演奏する曲を研究し尽くしているに違いないが、ホールの響きとか、お客の雰囲気とか、二人の気分などの要素も加えて、再構築の作業に即興性も加えて、楽しんでいるようにも感じる。
庄司の研ぎ澄まされた美しいヴァイオリンと同時に、カシオーリのピアノが映えていた(美人の譜めくりスィニョリーナも気になる存在
 )。ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタは、ピアノパートが重要であることはわかってはいるが、ヴァイオリンが伴奏型を受け持つときでもやっぱりヴァイオリンに耳が行ってしまう。それが、今夜は、ピアノが主役の部分はヴァイオリンが「さあ、今はピアノを聴いて下さい」とでも言っているように脇役に徹したり、或いは、スパイスの効いた味つけでピアノを引き立てる。
)。ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタは、ピアノパートが重要であることはわかってはいるが、ヴァイオリンが伴奏型を受け持つときでもやっぱりヴァイオリンに耳が行ってしまう。それが、今夜は、ピアノが主役の部分はヴァイオリンが「さあ、今はピアノを聴いて下さい」とでも言っているように脇役に徹したり、或いは、スパイスの効いた味つけでピアノを引き立てる。同じ方向に向かい、ぴったりと意気投合しつつ作り上げられる、新鮮で、スリリングで、透徹したベートーヴェン像に、すっかり圧倒されてしまい、結局「すごい」という言葉しか出てこない。
最後のアンコールを聴いて思ったことは、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタにもし、ピアノ・ソナタや弦楽四重奏曲のような晩年の作品があれば、どんな演奏をしてくれるだろうか… ということ。二人の奏でるベートーヴェンはどこまでも深化していくように感じた。