
2013年3月13日に自民党・公明党・日本維新の会は、インターネットによる選挙運動を解禁する公職選挙法改正案を衆議院に提出し、民主党・みんなの党もほぼ同様の法案を衆議院に提出しました。そして、両法案は3月22日、今国会で審議入りしました。予想とおり行けば、今夏の参議院選挙ではネットでの選挙運動が認められることになるでしょう。
ここで、「政治運動の自由」と「選挙活動の自由」の違いをおさらいしておきますと、これらは共に、憲法21条1項の定める表現の自由から保障される、極めて重要な基本的人権の行使です。
表現行為の中で、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。 ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なので、政治活動<選挙運動です。ただ、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
(1)選挙運動
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
(2)政治活動
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
ここで大切なことは、選挙では国民が自分たちと同質性のある代表者を選び(民主主義)、自分たちの人権を制約することもできる立法権を委ねるのですから(自由と人権の保障)、選挙権は民主主義の根幹をなす重大な権利であるということです。
これほど重要な選挙権が制約されるのは、「選挙の公正」が害され、国民の信の代表者を選ぶという選挙制度の目的そのものが揺らぐような、極めて限定的な場面でなければならないということです。
あとで見るように、今の公職選挙法は、選挙権が「公正」名目で過度に制限されているために、「べからず選挙」と揶揄されている始末なのです。
さて、ネット選挙に話を戻しますと、この法案の目的が、社会の情報インフラに成長したインターネットを選挙活動に活用し、政党と候補者の意見を広く有権者に届けること、また、効率的で費用負担の少ない選挙の実現であることに鑑み、私はこの法案には(一部条件はつきますが基本的に)大賛成です。まさに、国民の選挙活動の自由←政治活動の自由←表現の自由がより保障される制度と言えます。
与野党間で現時点で合意している部分だけでも、ネット選挙運動ができるようになると、冒頭の表のように
(1)候補者がブログやソーシャルメディアで、支持を訴える、(2)有権者がtwitterで、特定の候補者への投票を求める投稿をする、(3)演説をUstream中継する、(4)候補者や政党が投票を求めるメールを送信する、(5)政党がバナー広告を掲載する
ことなどが可能になります。
特に、ホームページ、ツイッターやミクシー・フェイスブックなどのソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を用いた選挙運動に関しては、国民の選挙への関心、政治への関与意識の高揚に大きな効果が期待できると考えます。
なぜ、全党一致できないのでしょうね。しょっちゅうツイッターで間違える橋下徹氏が代表する維新が、有権者からのメールを敬遠する理由はよくわかるのですが。。。
週刊朝日のことを間違えて「鬼畜」と言っちゃった橋下市長の謝り方

一方で、自公維と民・みで割れている「候補者・政党以外の第三者」による選挙運動はどう考えるべきでしょうか。
前者の与党案では、メールに限っては第三者の選挙運動を許さないというのですが、第三者って一般人、つまり、有権者を含む一般市民ですよね。選挙の主人公は誰ですか?それは選ばれる政党や候補者ではなくて、有権者のはずです。選挙とは有権者が国民主権原理に基づき主権を行使するほとんど唯一の機会です。これを制限するには極めて高度の合理的必要性がなければなりません。
とくに、ネット選挙運動解禁は、これまで選挙運動ができる日中に仕事や家事があって動けなかった一般市民も主体的に選挙運動ができる点にあるのに、そのメリットが台無しになってしまいます。
自公維があげる「合理的理由」とは、一般市民までメールをしたらなりすましやデマの拡散など「選挙の公正」を害する事態になる危険性が高いというものです。しかし、その危険性は政党や候補者がメールする場合もあり得ます。候補者がなりすまされる方が被害はずっと大きいでしょう。
それに、ぶっちゃけ、今までも公示前の政治活動でも、公示後の選挙運動でも、デマなんて無数にありました。それも、「怪文書」と言われる政党や候補者発信のものもあったではないですか。公示後の選挙運動だけ、メールだけ有権者を排除しても、なんら問題の解決にはなりません。つい最近、橋下維新の会代表のツイッターも乗っ取られました。このように今でも日常茶飯事のなりすましとか、巨大掲示板での誹謗などは、個別に対処すべきです。
なりすましの問題は、高度な情報通信技術である、ネットワーク技術、セキュリティ技術、大規模システム構築技術、情報技術運用のガバナンス技術、インターネット運用技術などの学術的、技術的側面で対処すべきです。
デマについては、構成要件を明確にしたうえで、選挙中・もしくは事後の厳しい取締で可及的に減らすしかないことです。
したがって、日本におけるネット選挙運動は、有権者にもメールを解放する民・み案を妥当であると考えます。全面解禁は、フェイスブックでネットウヨクから大人気!?の安倍首相も望むところでなんではないでしょうか。
なぜ安倍総理は辞めたのか、および、ネットウヨクによる安倍自民党総裁押しが気色悪い件

ただし、条件が3つあります。まず、第一は、候補者・政党に有権者からの質問に対する説明義務を課することです。
ネットではやり取りが双方向ですから、政党からのメッセージに対して、即座に有権者が疑問を投げかけることもできます。それらがのツイートが無視されないような第三者機関を起き、政党側が取捨選択しないことに留意すべきです。ネット選挙が一方的プロパガンダしか許されないのなら、その意味は半減以下となります。候補者や政党も、ツイッターやフェイスブックを使用するなら、一方的な宣伝の垂れ流しではなく、選挙民からの疑問・批判にこたえてこそ、充実した選挙になるはずです。
もちろん、膨大な質問や意義に全部答えることは不可能でしょうから、最初は質問を削除しない義務を課するだけでもいいかもしれません。堪えられないことが一目瞭然になるわけですから。そして、いずれは、自分の質問に答えてもらえない市民が「まともな質問だから答えるべきだ」と異議を申し出ることのできる第三者機関を設けるべきでしょう。
今まで公約だのマニフェストだのを垂れ流されてはうのみにせざるを得ず、騙され続けてきた我が国でこれができたら、まさに日本の民主主義に「革命」が起こります。
たとえば、マスコミの偏重に対抗すべく、市民やフリージャーナリストが作成する動画なんかは制限せずにどんどん流してほしいですね。消費税増税に命をかけるとまで言った野田前総理が、自民党の消費税増税に反対演説をぶったYouTubeなど抱腹絶倒で、かつ、非常に意義のあるものでした。
野田首相が消費税増税は「マニフェストに書いてないことはやらないのがルール」と熱弁←3年前の衆議院選挙
第2に、政党ネット選挙運動は制限すべきだということです。
ネット選挙の良さは、安価で一般市民が意見を発信しやすいところにあります。もし、たとえば何百億円も政党助成金を持っている自民党が金にあかして広告を打ちまくったら、ネット内はとても思想の自由市場とは言えなくなってしまいます。テレビ広告よりネット広告の方がはるかに安価ですから、政党によっては広告を出し放題になりますが、弱小政党はNHKの公開討論より悲惨なことになってしまいます。
これは大政党の選挙運動の自由に対する制限になりますが、最初にも述べたように、「選挙の公正」からはこの自由も制限しうるのです。
大政党が金をかけた自党の凄いホームページを作ることまでは制限できないでしょう。しかし、ネットサーフィンをしていたらある政党の宣伝ばかりというのではうんざりです。ここは、禁止とは言わないまでも各政党横並びで制限すべきです。
第3に、大企業などの巨大組織の選挙運動も制限すべきです。
企業の選挙運動はネットでも禁止すべきです。もとより、企業が政治献金をするなどの政治活動の自由は認めるべきですが、けた違いに金のある企業や団体が特定の政党をネット上でゴリ押ししたから、まるで選挙の公正が害されます。
まったく架空の例ですが、たとえば、「白戸家」が民主党を押しまくったり、三木谷社長が安倍さんを推しているからと言って、楽天で買い物しようとしたら全ページに安倍さんが出てきたりするべきではないです。企業・消費者団体・労働組合など巨大組織の場合は、金額制限などを設けるべきでしょう。
ところで、庶民にもなじみがある安価なネット選挙解禁で、日本が変わるという期待を抱かれる方も多いでしょうが、やはり世の中金と力です。オバマとロムニーのアメリカ大統領選挙を見ればわかりますが、安易な幻想は禁物です。
というわけで、以上3点の懸念はありつつも、わたしはネット選挙解禁は大いに賛成です。現に大統領候補がネットを使いまくるアメリカを筆頭に、主要先進国ではインターネットを用いた選挙運動を制限している先進国はほとんどなく、基本的には規制がなく自由に行うことができます。
ただし、日本の場合は!
選挙は、憲法違反の定数是正を完全に成し遂げてからにしてください。今度の参院選もまた1票の格差が5倍もある状態でする気ですか?それなら、ネット選挙解禁なんかやっている場合じゃありませんよ!!!>政治家様ALL
このシリーズの第3回は、いまの公職選挙法が「べからず選挙法」で、憲法違反であることについて書きます。ネット選挙解禁より先にすることがあるだろう!って感じです。
新聞やテレビよりはネットに賭けてみたい。
でも、結局、地道な普段の不断のリアルな努力が世の中を変えるのだと思ってます。
是非是非上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!
2013年3月21日17時51分 朝日新聞デジタル
衆院政治倫理確立・公職選挙法改正特別委員会(倫選特)は21日の理事会で、今夏の参院選からインターネットを使った選挙運動を解禁する公職選挙法改正案を、22日に審議入りさせることを決めた。自民と公明、日本維新の会の3党が提出した法案と、民主、みんな両党が出した法案の二つを審議する。
22日は2法案の提出者による趣旨説明にとどめ、質疑は来週から始まる見通し。倫選特の委員と与野党の実務者が、委員会審議と並行して修正協議に取り組む。各党は参院選からのネット解禁では一致しているが、審議入りが当初の予定より遅れたため法案成立は来月に持ち越されそうだ。
2法案はともにホームページやツイッターなどを利用した選挙運動を全面解禁する内容。電子メールによる選挙運動については、自公維案が政党と候補者に限定する一方、民み案は一般の有権者にも認めている。
ネット選挙 解禁へ妨害対処を万全に
夏の参院選からの導入に向け、与野党がインターネットによる選挙運動の解禁を目指している。今国会での公職選挙法改正を経て実現する可能性が高い。
国内のネット人口は9千万人を超え、パソコンや携帯などネットは情報伝達などに欠かせない手段だ。公選法がネットをビラやはがきと同じ「文書図画」とみなし、利用を認めないのは妥当性を欠く。解禁は当然だ。
課題となるのは、誹謗(ひぼう)中傷、なりすましなどネット特有の妨害行為をいかに封じるかである。
時間や場所の制約を受けずに情報を集め、発信できるのがネットの力だ。若者の政治への関心が高まる期待もある。その利点を生かすためにも、安全性や信頼性を確保する必要がある。
すでに自民、公明、日本維新の3党と民主、みんなの2党がそれぞれ共同で公選法改正案を提出しており、両案とも政党や候補者のホームページのほか、交流サイト「フェイスブック」や短文投稿サイト「ツイッター」の使用、電子メールの利用を認めている。
電子メールについては自民党などが政党と候補者に限定しているのに対し、民主党などは一般有権者を含む全面解禁としている。
メール制限の理由は、候補者になりすます行為の防止が難しいからとしている。メールマガジンの購読登録のように、あらかじめ受信者からメール送信について同意を得ることを条件とする。いずれもうなずける措置だ。
一方、この人だけには当選してほしくないという「落選運動」もアドレスや氏名などの表示を条件に事実上、容認する。政策的な批判と誹謗中傷の線引きは難しい。だれが、いかに判断するかを含め、問題があるのではないか。
権利侵害を受けた人を救済するため、プロバイダーの責任者に中傷記事を削除させる「プロバイダ責任制限法」の仕組みを採り入れるほか、なりすましなどメール送信者の表示義務違反には、禁錮1年、罰金30万円以下などの罰則を設ける。
これらも必要な措置といえるが、選挙戦最中に違法な権利侵害を受けた場合、直ちに名誉回復を図るのは難しく、課題である。
こうした問題を考えると、一部制限付きの解禁となるのはやむを得ない。施行後に実態を踏まえた再改正を行う必要がある。
アイレップ デジタルマーケティング レポート
有権者1,000人に聞いたネット選挙解禁に関する意識調査
ネット選挙解禁で、情報収集にネットを活用する有権者が8割に!
~SNSを活用して候補者・政党と関わっていきたい有権者は約3割
候補者・政党からのメールを受け取りたい有権者は約1割
検索エンジンによる検索結果上位20件が選挙に影響する可能性大~
プレスリリース
平成25年3月18日
株式会社アイレップ
JASDAQ(証券コード:2132)
広告主のマーケティングを最適化するデジタルマーケティングエージェンシーの株式会社アイレップ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:紺野俊 介、以下アイレップ)では、ネット選挙解禁が目前と迫った2013年2月末に、全国の有権者1,000人を対象としたネット選挙解禁に関する意識調査を実 施しました。この程、その調査結果がまとまりましたのでご報告いたします。
≪調査結果サマリー≫
- 50.2%の有権者がネット選挙解禁に賛成
- 38.1%が「ネット選挙解禁によって政策論争が深まると思う」と回答
- 56.7%が「ネット選挙解禁によって投票率が上がると思う」と回答
- 28.2%の有権者がネット選挙解禁によって自身の投票先選定に変化が生まれる可能性を示唆
■ネット選挙解禁でインターネットを積極的に活用する有権者は6割から8割に増加する見込み
- ネット選挙解禁前から、何らかのインターネットメディアを参考にしていた有権者は6割
今後、積極的にインターネットメディアを参考にしていきたい有権者は8割 - 「過去、選挙について活用したインターネット端末」と「今後の選挙で積極的に活用したいインターネット端末」を比較。PC、スマートフォン、タブレット端末それぞれにおいて、過去の選挙で既に活用していた有権者の約2倍の有権者が今後積極的に活用したいと回答
■解禁が見込まれるSNS・メールを活用して候補者・政党と関わっていきたい有権者は約3割
- SNS上で候補者・政党をフォローしたり、ファン登録・友達申請したい有権者は10.4%
- 候補者・政党の発言をTwitter上でリツイートしたりFacebook上のいいね!ボタンを押したりしたい有権者は8.4%
- 候補者・政党からのメールを受信したいと考える有権者は12.8%
■選挙に影響を与えるのは検索結果上位20件※ 半数以上は検索結果を3ページ以上閲覧せず
※検索結果が1ページ10件表示されると仮定
- 32.4%の有権者が、過去の選挙期間中に、選挙に関して何らかの「検索」を行った経験あり
- 選挙について検索した際、検索結果を1ページまたは2ページまでしか閲覧しない有権者は、
PC:56.7%、スマートフォン:77.0%、タブレット端末:69.7%、一般携帯電話:80.4% - 58%の有権者が、投票しようか迷っている候補者の検索結果でネガティブな情報ばかりが表示された場合、自身の投票先に影響が出るかもしれないと回答
■ネット選挙解禁で、デジタルマーケティングの専門家が選挙結果を左右する!?
- 60.3%の有権者が、「選挙参謀としてデジタルマーケティングのプロを雇うことが選挙結果に影響を及ぼすと思う」と回答
記事転載・引用等に関するお問い合わせ先
●株式会社アイレップ
TEL:03-3596-8050 FAX:03-3596-8145
【報道関係お問合せ先】広報担当 小泉 E-MAIL: pr@irep.co.jp
【弊社サービス内容に関するお問合せ先】 E-MAIL: contact@irep.co.jp
調査概要
- ■調査対象: 日本の有権者1,000人
- ■調査手法: インターネット調査
- ■調査期間: 2013年2月27日~2013年2月28日
- ■調査実施者:株式会社アイレップ
- ■回答者属性:20代・30代・40代・50代・60代以上の各世代の男性100人、女性100人ずつ
- ■調査目的:
ネット選挙解禁後に予想される有権者の意識・行動の変化を調査し、デジタルマーケティング領域におけるユーザーの意識・行動分析を行うことで、情報流通の最適化の発展に寄与し、ユーザーと商品・サービスのベストマッチングを追求する一助とする。
調査結果のハイライト
≪全体概要≫
・今回の調査によって、多くの有権者がネット選挙解禁に賛同・期待していることが浮き彫りとなりました。回答した有権者の約半数が、ネット選挙に賛成し、4割近くがネット選挙解禁によって政策論争が深まり、また5割強が投票率が上がることを期待しています。
・ネット選挙解禁後のインターネットを積極的に活用した情報収集意欲にも目を見張るものがあります。ネット選挙解禁後、何らかのインターネットメディアを参考にしたいと回答した有権者はおよそ8割で、過去の選挙で参考にしていた有権者6割から大幅に増加しています。
・また、PC、スマートフォン、タブレット端末に関して、ネット選挙解禁後、それぞれの端末を使って積極的に情報収集を行いたいと回答した有権者の数は、過去の選挙でそれらを活用していた有権者の約2倍近くとなっています。
・今回、解禁が見込まれているSNSやメールを使った選挙運動に関して、有権者の約3割が何らかの形で積極的に関わっていきたいと答えています。
・過去の選挙において有権者の約3割が、検索エンジンを使って情報収集をしたと回答。今後は、8割近くの有権者がインターネットを活用した情報収集を行うことものと予想されるため、検索エンジンを使った情報収集も今まで以上に活発になると思われます。
本調査では、半数以上の有権者は検索結果の2ページまでしか閲覧していないことも明らかになっており、検索結果の中でも、上位のおよそ20件の情報が有権 者へ影響を与えている可能性が高いものと推測されます。その他、有権者の6割が「選挙参謀としてデジタルマーケティングのプロを雇うことが選挙結果に影響 を及ぼすと思う」と回答しており、デジタルマーケティング業界の活躍の場が一層広がることが予想されます。
■ 選挙プランナー 三浦博史氏のコメント
今回の調査結果について、選挙プランナーの三浦博史氏は以下のようにコメントしています。
「この調査から、多くの有権者がネット選挙解禁に期待し、実際にネットを活用していきたいと考えていることがよくわかります。
今、ネット選挙というとSNSやメールの活用等が話題になりがちですが、それ以上に大切なことは、有権者がネットを使って候補者の詳しい情報を得ようと 思ったときに、そうした情報を、より早く、より簡単に得られるようにしておくことです。有権者が自分の選挙区の候補者に興味がわき、もっと詳しく知りたい と思って候補者の名前を検索した際に、求めている情報が見つけられなければ、興味を失ってしまうものです。現職議員の場合、公式サイトなどは比較的、検索 結果の上位に表示されますが、新人の候補者の場合、そうとは限りません。また、検索結果の上位にあがって来るものは何かというリスク管理、つまり、候補者 の悪い評判が書かれたブログが上位に表示された場合のことも想定しておかなければなりません。
FacebookやTwitterなどでの情報発信と同時に、検索エンジン経由のコミュニケーション対応をきちんと考えているかどうかも、ネット選挙解禁後の選挙戦を勝ち抜く重要なポイントとなるでしょう。」
≪ネット選挙解禁に関する有権者の意識≫
今回、解禁になるといわれているネット選挙について、賛成かどうかを有権者に聞いたところ、全体の約半数(50.2%)が賛成と回答しました。次いで多かったのが「どちらともいえない」40.5%、「反対」は9.3%でした。(図1)
ネット選挙が解禁されたら、政策論争が深まると思うかという質問では、全体の38.1%が「深まると思う」と回答。「深まらないと思う」が18.8%、「どちらともいえない」が43.1%でした。(図2)
また、ネット選挙が解禁されたら、投票率が上がると思うかを聞いたところ、全体の56.7%が「上がると思う」と回答。「下がると思う」は2.9%、「どちらともいえない」が40.4%でした。(図3)
ネット選挙が解禁となることで、有権者自身の投票先に変化が生まれる可能性については、39.9%の有権者が「変化はない」と回答した一方で、28.2%の有権者が「変化が生まれる可能性がある」と回答しています。(図4)
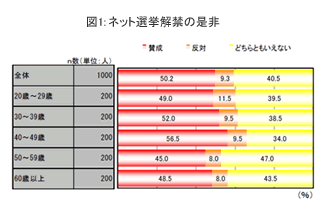
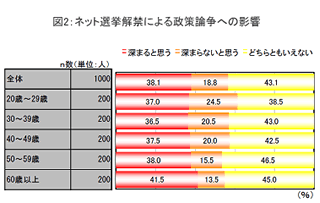
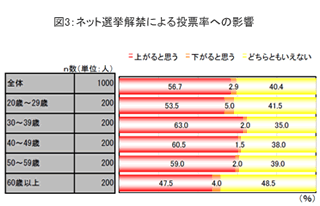
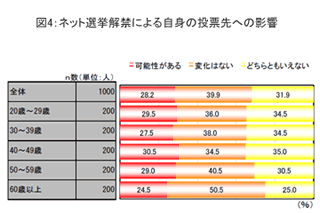
≪インターネット端末による選挙に関する情報収集≫
有権者に、過去の選挙において候補者選定のため情報源として何を参考にしているか聞いたところ、「テレビ」が最も高く(71.3%)、次いで「新 聞」(51.9%)でした。「インターネット」を情報源とした有権者は三番目に多い33.2%でした。世代別にみると、「テレビ」が各世代を通して最も情 報源とされています。「新聞」は世代が若くなるほど情報源とされておらず、20代になると「インターネット」を情報源とする有権者が45.5%と半数近く を占め、「新聞」を情報源とする有権者(36.5%)より多くなります。(図5)
過去の選挙の際、情報収集で参考にしたインターネットメディアと、ネット選挙解禁後に積極的に参考にしたいインターネットメディアをそれぞれ聞いたとこ ろ、過去の選挙で何らかのインターネットメディアを参考にしたことのある有権者56.6%で、ネット選挙解禁後に参考にしたいと回答した有権者は 76.1%でした。
また、インターネットメディア別にみると、過去に参考にしたメディアは、「ニュース・報道サイト」が最も多く(42.9%)、次いで「選挙関連情報をまと めたサイト」(17.5%)、「政党のHP・ブログ」(16.7%)、「候補者のHP・ブログ」(16.0%)となっており、SNSでは 「Twitter」(5.1%)、「Facebook」(2.3%)でした。一方で、今後参考にしたいメディアは、「ニュース・報道サイト」が最も多く (51.6%)、次いで「候補者のHP・ブログ」(44.1%)、「政党のHP・ブログ」(37.7%)、「選挙関連情報をまとめたサイト」 (28.1%)、となっており、SNSでは「Twitter」(6.1%)、「Facebook」(5.6%)とほぼ全てのメディアで増加傾向が見られま した。(図6)
インターネット端末別にみる選挙・政治に関する情報収集のための活用頻度を見ると、過去の選挙では、「よく活用した」・「たまに活用した」の合計は、 「PC」が最も多く(36.4%)、次いで「スマートフォン」(7.0%)、「タブレット端末」(2.0%)、「一般携帯電話」(2.4%)でした。
加えて、ネット選挙が解禁された場合、積極的に選挙・政治に関する情報収集をしていきたいインターネット端末別に聞いたところ、「PC」を活用したい回答 者が最も多く(70.8%)、次いで「スマートフォン」(13.0%)、「タブレット端末」(5.0%)、「一般携帯電話」(3.6%)でした。現在の各 端末の活用状況と比較すると、ネット選挙解禁後には、インターネット端末を活用する有権者は約2倍に増加することが予想されます。(図7)
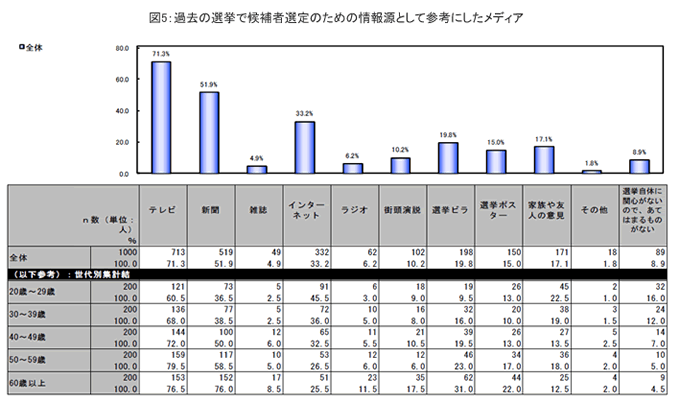
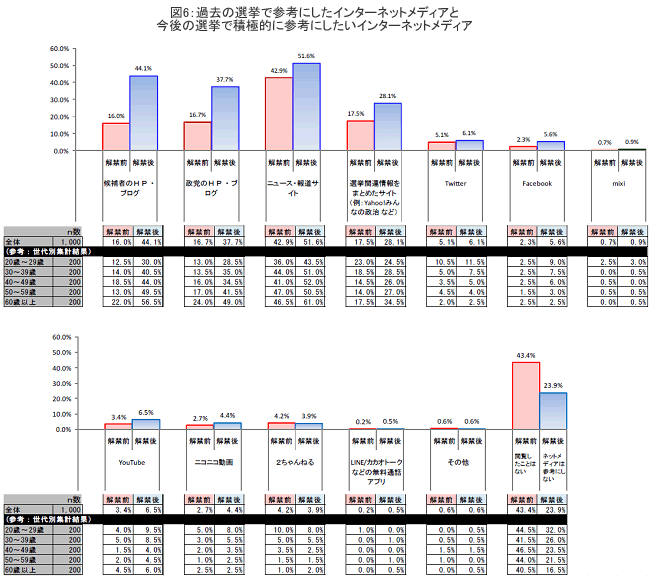
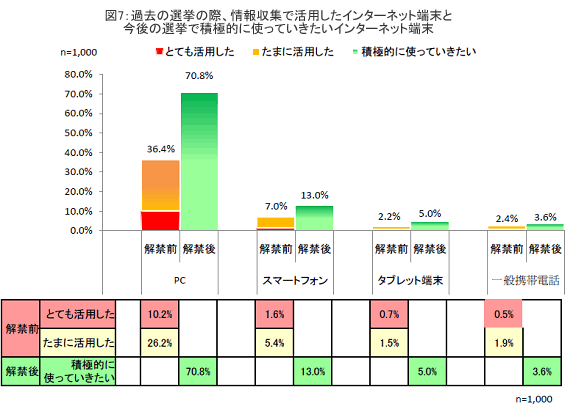
≪解禁が見込まれている選挙運動期間中のSNS/メールの活用≫
2013年7月の参議院議員選挙から解禁が見込まれているSNSの活用について、どのような形で候補者や政党と関わっていきたいか聞いたところ、 27.6%の有権者が何らかの形で関わっていくと回答しており、「自身のTwitter・Facebookなどソーシャルメディアのアカウントやブログな どを通した特定の政党・候補者の支持表明」が13.1%と最も多く、次いで「SNS上の候補者・政党などの公式アカウントをフォローしたり、ファン登録・ 友達申請するといった形で候補者と繋がる」(10.4%)、「ソーシャルメディア・候補者ブログなどを通した候補者との意見交換」(10.1%)、 「TwitterのリツイートやFacebookのいいね!ボタンなどを使った候補者・政党の情報拡散」(8.4%)でした。(図8)
また、SNSとともに解禁が見込まれている候補者・政党からのメール配信について、候補者・政党から配信されるメールを受け取りたいかを聞いたところ、 「受け取りたくない」回答者が半数以上を占めており(57.4%)、「受け取りたい」と回答した有権者は12.8%、「どちらともいえない」が29.8% でした。(図9)
世代別にみると、SNSの活用・メールの受信ともに、60歳以上が他の世代と比較して意欲的であることがうかがえます。
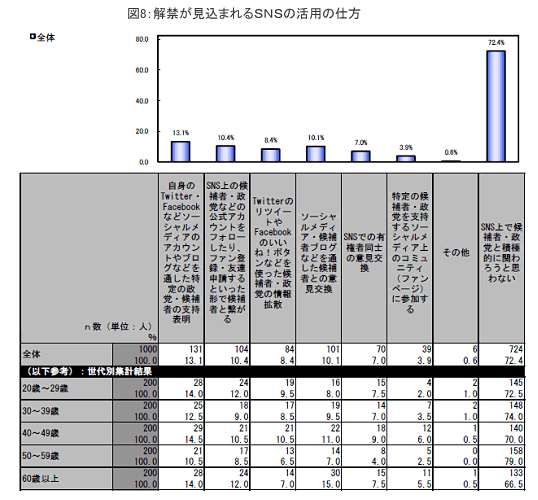
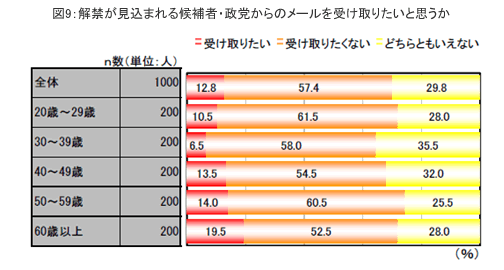
≪検索エンジンを使った選挙に関する情報収集≫
過去、選挙に関する情報を探すために、検索エンジンを使って検索をしたことがあるかを聞いたところ、「毎回、何らかの検索をしている」有権者が 8.3%、「何度か選挙で検索をしたことがある」有権者が24.1%で、合わせて約3割(32.4%)の有権者が、過去の選挙期間中に、何らかの検索を 行っています。(図10)
何らかの検索をしたことがある有権者に、どのようなキーワードで検索しているかどうかを聞いたところ、「その他」(22.7%)を除き、最も多かったのは 「政策・争点」(15.4%)、次いで、地元選挙区の候補者名(13.9%)、「政党名」(8.6%)でした。(図11)
自分が投票しようか迷っている候補者の名前を検索エンジンを使って調べる際に、検索結果が10件ずつ表示される場合、何ページ目まで情報を探すかインター ネット端末別に聞いたところ、1ページ目または2ページ目までと回答した有権者が全ての端末で半数以上を占めました。(図12)
また、候補者名での検索結果で、候補者にとってネガティブな情報ばかりが表示された場合、自身の投票先に影響が出るかもしれないと回答した有権者 は、「非常に思う」が全体の11.5%、「やや思う」が46.5%で、合わせて半数以上(57.5%)の有権者が投票先に影響が出るかもしれないと回答し ています。(図13)
以上のことから、検索上位の20件に入ることが、選挙に影響を与える可能性の高い検索結果であることが示唆されました。
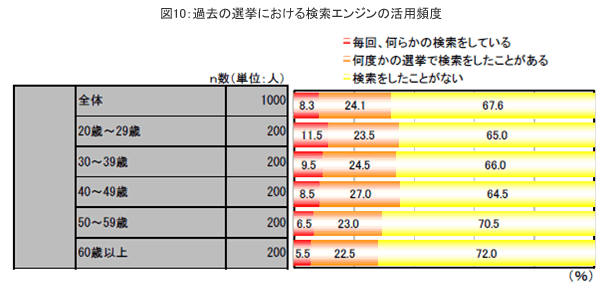
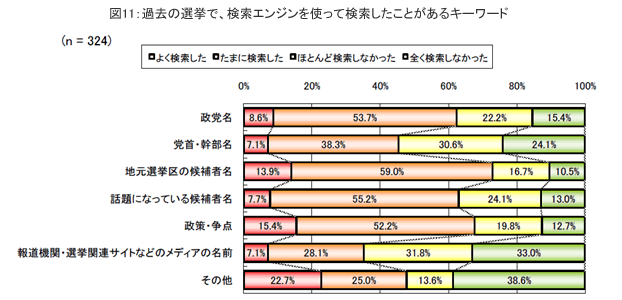
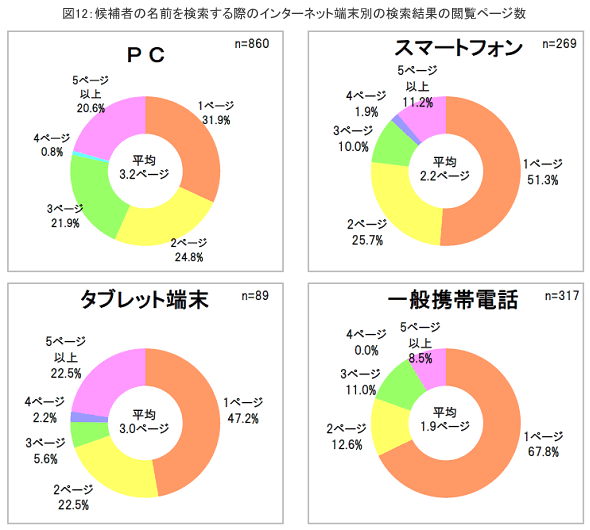
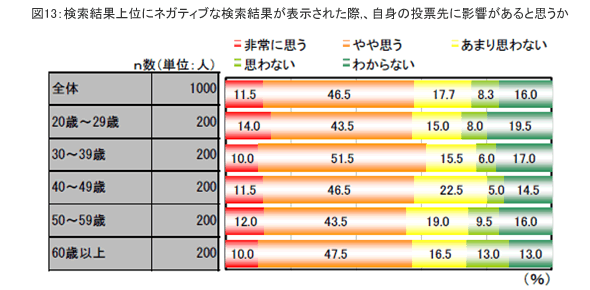
≪ネット選挙におけるデジタルマーケティングの専門家の影響≫
ネット選挙解禁後、選挙参謀として「デジタルマーケティングのプロ」を雇うことが選挙結果に影響を及ぼすと思うかどうかを聞いたところ、「大変な影 響を及ぼすと思う」が15.5%、「影響を及ぼすと思う」が44.8%で、合わせて6割(60.3%)の回答者が、投票結果に何らかの影響を及ぼすと考え ています。(図14)
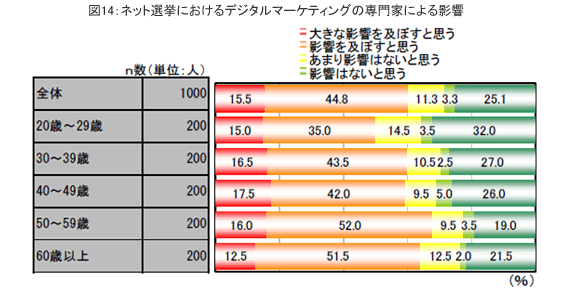
■ アイレップ 代表取締役社長 紺野俊介のコメント
今回の調査結果を受けて、今後、デジタルマーケティング業界に何が求められるのかについて、デジタルマーケティングエージェンシーである株式会社アイレップ 代表取締役社長 紺野俊介は、以下のようにコメントしています。
「今回の調査で、ネット選挙が解禁となった場合、選挙期間中の情報収集に関して、インターネット上の情報が、テレビや新聞の情報と同程度参考とされる可能 性が示されています。調査では、今までの選挙でもおよそ3割の有権者が検索エンジンを使って何らかの検索をしていることが明らかになりました。また、ネッ ト選挙解禁後はインターネットを活用しての情報収集が、PC・スマートフォン・タブレット端末経由のいずれも約2倍になる可能性があると数字が出ていま す。
有権者がインターネットを活用して情報収集をしていることは事実であり、政党・候補者は、間違いなく今まで以上にインターネットを通じた情報発信が必要に なってきます。有権者はインターネット上に選挙に関する情報があることを前提として情報収集をしているため、有権者による検索動向と、政党・候補者が発信 する情報がどうマッチするかが重要になります。
すでにアメリカではインターネットに精通した専門家を選挙対策本部に取り入れるなどの対策をしており、日本においても政党・候補者サイドのニーズも高まっ ていくと考えられ、アイレップとしても、より有権者と政党・候補者サイドをつなぐ必要性が高まってくると予測しております。」
以上





























