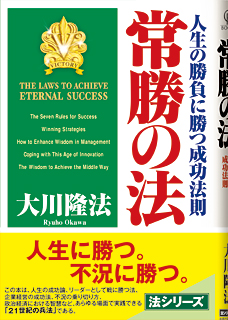本日も、幸福の科学高知なかまのぶろぐにお越しくださり、本当にありがとうございます。
まず、このサイトは、高知在住の幸福の科学信者による布教ブログですので、あまり火中の栗を拾うようなことはしたくはないのですが、あまりにも、テレビ等のニュースソースがうるさいので、個人的な見解ではありますが、一言二言書かせていただきたいと思いました。
と申しますのも、東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長発言云々の話題が大騒動になっており、森氏は五輪組織委員会会長職を辞任する意向だそうですが、私には、森氏の発言のどこが、男女平等の精神に反し、何が女性蔑視に当たるのか、さっぱり分からないのです。
ちなみに私は男性ですが、職業は、女性が圧倒的に主導権を握る看護師です。
そして私は、男尊女卑思想の持ち主でもありませんし、差別主義者でもありません。
先日職場のテレビで、森氏発言関連ニュースを見ていた同僚が、「そもそも、オリンピックなどのスポーツでは、男女を分けて競技をしちょいて、何が男女平等か!」と言っていましたが、目に見える形で、完全な男女平等を成し遂げるならば、スポーツ競技であれ、男女同じフィールドでするべきという議論があってよいはずです。
しかしそれは、女性にとって幸福な世界だとは、私にはどうしても思うことができません。
さて、森氏は、「理事会に女性が増えると、会議の時間が長くなる。」と話されたようですが、経験則から言って、この発言は恐らく正しいことを言っているとは思いますが、「会議の時間が長くなる」ということが、なぜ女性差別に当たるのでしょうか?
-w640.jpg)
たとえば、女性に会議の場で発言の自由がないとか、女性から発言された内容は、議論されずに即却下されるならば、女性差別であるとか、女性蔑視であると思われますが、森氏の発言は、むしろこの逆を想定しているはずです。
と申しますのも、「会議の時間が長くなる」ということは、女性らしい、細かいところまで目を配った議論がなされるということであり、「会議の時間が長くなる云々」という森氏の発言からは、「多くの女性理事の発言を、取り入れようとする意志がある。」という前提を伺うことができたのですね。
また、「会議の時間が長くなる」ということは、善でも悪でもありません。
まぁ議論される内容が、コストに見合わなければ、「時間の無駄」という悪に、転化してしまうものだと私は思います。
また森氏は、「私どもの組織委員会にも、女性は7人くらいおられますが、みんなわきまえておられます。」と言った中の「わきまえておられる」という文言に対して、カチンと来ている方がいらっしゃるようで、「私はわきまえない!」と書かれたプラカードを持ってデモをしている女性がテレビで放送されていました。
しかし「わきまえる」という言葉は、別に差別用語でもなんでもありません。
「わきまえる」とは、物事の違いを見分けることであり、公私の違いや、物事の道理、社会的な距離感などを心得ていることです。
また師弟関係や接客のお仕事などにおいては、教育的な言葉としての意味合いも含まれます。
ですので「わきまえよ!」という言葉には、ある意味での上から目線的な言霊も含まれていると思われ、カチンとくる人からすれば、この「上から目線的」なところが嫌な感じがするかと思いますが、大切なのは、森氏発言が、国民一般に対して述べているわけではなく、JOC臨時評議員会の中で、評議員に対して述べているわけです。
齢80歳を超える森氏は、当然組織委員会最高齢ですので、20~30歳、あるいはそれ以上年下であろう理事たちに対して「わきまえていらっしゃる。」と言っても、ある程度上から目線で当たり前でしょうし、この発言が差別でも何でもないわけです。
むしろ、たとえば、「私はわきまえない」というプラカードを持ってデモをしていた、恐らく40代くらいの女性が、元内閣総理大臣の80代の男性に対して「わきまえよ!」と言ったら、これは「あんたこそ、わきまえよ!」と言われても致し方なしです。
「私はわきまえない」というワードは、一見とてお新鮮なフレーズではありますが、くり返しますが「わきまえる」とは、物事の違いを見分けることであり、公私の違いや、物事の道理、社会的な距離感などを心得ていることですので、「私はわきまえない!」という言葉は、職場や社会的な人間関係から、反故にされても致し方ない言葉でもあることを「わきまえて」いただきたいものです。

この言論の自由のあるはずの国で、男性が女性に対して、気分を害する発言が、たとえ失言であっても許されないならば、それは男性に対する性差別であるし、もしも、「老害だ。年寄りは黙っちょれ!」というならば、高齢者差別です。
今後の日本は、どうやったって高齢化社会になるし、今は若い方であっても、いつかは年を取ります。
生老病死は人として逃れられないことは、釈尊が喝破した後、2500年が経過した今も真理ですので、いつか年を取るならば、お年寄りに優しい社会を築こうと努力する方が、「確実に未来は明るい」と私は考えます。
そしてこの森氏発言は、国会での質問でもなされていて、「森氏をオリンピック委員会会長職を辞めさせよ!」と菅総理に質問した野党議員がいましたが、森氏は元内閣総理大臣とは言え、今は国会議員を引退した「民間人」です。
となれば、会長職をどうするかはオリンピック委員会が決めることで、もしこれを菅総理が言って実現させるとすれば、それは専制政治であり独裁政治ですよね。
質問した野党議員は菅総理に対し、「あんた独裁者になれ!」と言っているのと同じであり、「日本は、この機に民主主義を捨てて、お隣の中国のような専制政治国家に向かうべきだ!」と言っているのと同じであるということで、もしそれを知らないなら、質問した議員は問題だし、知っていて行っているなら、深い謀略があるやも知れません。
そもそも、元内閣総理大臣ですが、これほど多くの時間を割いて報道するほどのことでもないし、膨大な国民の時間が奪われているので、世論は、そしてマスコミ各位のみなさまは、そろそろ落としどころを決めて、日本を取り巻く世界について、真摯な態度で情報を頂きたいと、切にお願い申し上げます。
と言うことで本日は、経典『常勝思考』(大川隆法著 幸福の科学出版)より、人生の挫折と徳の発生について、大川隆法幸福の科学グループ総裁が語った一節をご紹介いたします。
それでは、またのお越しを。
(ばく)
心の指針「思い残し」 天使のモーニングコール 第1532回(2021/2/6,7)
徳というものは、生まれつき与えられたものではないのです。徳は、この地上、三次元においては、人間が生きていく過程で生じてくるものであり、後天的なものなのです。
それでは、徳はいったいどこで生まれてくるのでしょうか。一つは挫折のさなかです。
まず、挫折のとき、失意のとき、逆境のときに、なぜ徳が生まれるのかを考えてみましょう。
逆境のときに不遇をかこつのは、普通の人間です。(中略)たいていの人は、失敗をすれば、「運が悪い」「これは環境が悪かった」などと言います。人のせいにしたり、いろいろなことのせいにしたりします。守護霊のせいにする人もいます。いずれにしても、逆境のときや挫折のときに、その重圧に耐えかねている人が大部分です。
また、これより少し心の程度が高い人がいます。単に逆境に打ちひしがれるのではなく、逆境を何とか認めよう、受け入れて耐えていこうとします。逆境を受け入れて、それに耐えようとする人は、平凡な人よりは上かもしれません。
その上には、逆境にあっても、楽天的に朗らかに生きていこうと努力する人もいるでしょう。こうした人は、もう少し上でしょう。上の下ぐらいまでは、いっているでしょう。
しかし、逆境において、ほんとうにいちばん偉い方というのは、この常勝思考を持っている方なのです。
逆境のなかにおいて、大きな天意、天の意志というものを読みとり、「この逆境が、この挫折が、自分に何を教えんとしているのか」を読みとるのです。いや、読みとらねばなりません。
この天意、天の心を読みとり、「自分にいま必要なものは何なのだろうか。いったい、この挫折や苦難は、自分に何を教えようとしているのか」――この部分を読みとって、その後の自己の人格形成、その後の行動の成功原理にもっていける、こうした体験のある人には、徳というものが生まれてきます。そこに非凡な力が、光が、輝いているからです。
苦難のとき、失意のときに耐えるということだけでも非凡ですが、ほんとうに非凡な人というのは、そのなかに天の意志を読みとって、自分をさらに生かしていく積極的な種を見出し、その種を育てていきます。それがほんとうの非凡であり、そこに徳が生まれます。これが一つです。
徳が生まれる過程のもう一つは、成功のときです。
世に名を遺す人は、やはりどこかで成功体験があります。
この花咲いたときの、花の咲かせ方がやはり大事なのです。そして、花を咲かせたときに、その果実を自分のものとしないという気持ちが大事だと思います。
大きな成功を自分のものだと思わないで、「自分は水を注いだかもしれないが、天の意がここに現われたのだ」という気持ちを持つことです。そして、自分の成功としない、成功を私物化しないという気持ちが、大きな徳を生みます。
『常勝思考』(大川隆法著 幸福の科学出版)P179~186
映画『美しき誘惑ー現代の画皮ー』公式サイト https://utsukushiki-yuwaku.jp/