明治政府の最高指導者、岩倉具視(1825~83年)にあてて西郷隆盛や大久保利通、伊藤博文ら明治の元勲が送った書簡、意見書など、新発見とみられる千数百点の文書が現存していることが7日、三沢純熊本大准教授、藤井譲治京大教授、佐々木克奈良大教授らの調査で分かった。明治新政府をめぐる文書類は出尽くしたとされており、新史料の大量発見は極めて珍しい。政権中枢にいた岩倉の元に各地から多様な情報が集まり、諸政策が決定された過程を裏付ける重要なもので、激動の幕末・明治史の空白を埋める新たな事実の確認が期待される。
文書は「海の見える杜美術館」(広島県廿日市市)が約20年前に購入し、未公開のまま所蔵。三沢准教授らが昨年から3年計画で調査を始めた。全部で約1700点あり、このうち約8割を新出史料と推定している。
書簡類は1868(慶応4、明治元)年から岩倉が死去する83年までに東京で受け取ったとみられる。詳細は未解読だが、新出とみられる伊藤の自筆が68通、岩倉の書簡草稿も128通、三条実美の書簡も429通あった。既に存在が知られている大久保の書簡の原本も191通見つかった。さらに「西郷吉之助」と署名された書簡も新出とみられ、西郷が戊辰戦争の指揮内容を報告しているのをはじめ、貨幣の不足を訴え「信州」で一揆が起こったとする報告書、追加鋳造を決めた政府文書など多岐にわたっている。
政権最高位の「太政大臣(三条実美)」あての書簡もあり、ナンバー2の右大臣だった岩倉が判断を委ねられ、保管していたとみられる。
文書の一部は大正時代に明治天皇紀編纂(へんさん)のため当時の宮内省が借り受けたほか、戦前に刊行された「大久保利通文書」に引用されている。
同美術館は京都市内の出版社から購入した。三沢准教授らは全史料の解読を進め、資料集として平成23年に刊行し、同美術館は調査終了後、一般公開する予定。
三沢純熊本大准教授らによると、官軍が幕府勢力を一掃した戊辰戦争(1868~69年)の緊迫した状況の中、西郷隆盛は鳥羽伏見の戦いで、幕府側の桑名藩の荷物を差し押さえ、また不審な蔵の荷物を検査した状況を報告。
宇都宮藩は68年、戊辰戦争での戦死者や重軽傷者の身分と名前などを報告、岩倉の元に届けられた。新政府側の薩摩藩と行動を共にして東北に北上した大垣藩は同年、幕府側の仙台藩と会津藩に「白川城」(白河城、福島県)を襲来されたが、山からの攻撃を防ぎ、追討した生々しい戦闘状況を報告していた。
旧福井藩主で大蔵卿などを務めた松平慶永は、新政府の正統性を民衆に示すために、暦は新政府がつくるべきだとする意見書を提出していた。
このほか、当時の貨幣「弐歩金(二分金)」が不足し、「信州上田」で一揆が起きた状況の報告書と同じ巻物に、吹き増し(増鋳)を承認する政府の文書があり、「(松平)慶永」「大久(保利通)」「副島(種臣)」などの決裁印が押されていた。通貨不足を知った政府高官たちが増鋳を決定したとみられる。
絵巻物の「明治維新事蹟画」には、「岩倉遣欧使節団」(71~73年)一行が和船で沖に停泊している大型船に乗り込む、これまで一般に知られていなかった構図の絵が収められていた。
◆新事実含む可能性大
佐々木克奈良大教授の話「岩倉具視のような明治政府の中心人物の史料は1960年代までに出尽くしたと考えられていた。これだけまとまって出現するのは50年ぶりの大発見だ。全体の調査が済んでいないので断定的なことは言えないが、内容が豊かで、情報が詰まっているものが多く、新事実が含まれている可能性がかなり高い。活字になった文献の原本が見つかった意義も大きい。丁寧に解読し、原本と対照することで、従来の文献の読み違いを修正できるだろう。歴史の再解釈につながるのではないか」
◆最多は三条実美の429通
「海の見える杜美術館」所蔵の岩倉具視関係文書から見つかった書簡や意見書を調査している三沢純熊本大准教授らによると、最も多くの書簡を送っていたのは明治政府の最高位にあった太政大臣三条実美で、429通だった。内容は岩倉との日程調整や事務連絡が多いという。
また、伊藤博文の書簡や意見書を集めた史料集はこれまで刊行されておらず、調
査中の68通は新出とみられる。木戸孝允の75通も新出史料の可能性があり、記述内容が注目される。
191通の大久保利通の書簡は既に「大久保利通文書」に収録されているが「明治維新の研究上極めて重要な書簡の原本が見つかった意義は大きい」(三沢准教授)という。
■海の見える杜美術館所蔵
「岩倉具視関係文書」の書簡類の主な差出人と数
三条実美 429通
大久保利通 191通
木戸孝允 75通
伊藤博文 68通
江藤新平 10通
井上 毅 8通
小松帯刀 4通
大村益次郎 4通
西郷隆盛 3通
勝 海舟 3通
【用語解説】岩倉具視
幕末・明治期の公家、政治家。京都の堀河家に生まれ、下級公家だった岩倉家の養子となる。1854年孝明天皇の侍従となり、58年日米修好通商条約勅許の阻止を図る。公武合体派として皇女和宮と将軍徳川家茂の婚姻を推進。尊皇攘夷(じょうい)派から非難され、身を潜めた。その後、討幕派の公家の中心として、大久保利通らと画策し王政復古を実現。明治新政府では事実上の首班として政権の中枢を担う。71年使節団を率いて欧米を視察した。岩倉に関係する文書は国立国会図書館、国立公文書館、対岳文庫(旧岩倉邸、京都市)の3カ所に現存し、今回の新史料は第4の文書群。
3/8 産業経済新聞社
よければ下記をクリックしてください。
人気ブログランキングへ
一日一回クリックしてもらえたらうれしいです。
文書は「海の見える杜美術館」(広島県廿日市市)が約20年前に購入し、未公開のまま所蔵。三沢准教授らが昨年から3年計画で調査を始めた。全部で約1700点あり、このうち約8割を新出史料と推定している。
書簡類は1868(慶応4、明治元)年から岩倉が死去する83年までに東京で受け取ったとみられる。詳細は未解読だが、新出とみられる伊藤の自筆が68通、岩倉の書簡草稿も128通、三条実美の書簡も429通あった。既に存在が知られている大久保の書簡の原本も191通見つかった。さらに「西郷吉之助」と署名された書簡も新出とみられ、西郷が戊辰戦争の指揮内容を報告しているのをはじめ、貨幣の不足を訴え「信州」で一揆が起こったとする報告書、追加鋳造を決めた政府文書など多岐にわたっている。
政権最高位の「太政大臣(三条実美)」あての書簡もあり、ナンバー2の右大臣だった岩倉が判断を委ねられ、保管していたとみられる。
文書の一部は大正時代に明治天皇紀編纂(へんさん)のため当時の宮内省が借り受けたほか、戦前に刊行された「大久保利通文書」に引用されている。
同美術館は京都市内の出版社から購入した。三沢准教授らは全史料の解読を進め、資料集として平成23年に刊行し、同美術館は調査終了後、一般公開する予定。
三沢純熊本大准教授らによると、官軍が幕府勢力を一掃した戊辰戦争(1868~69年)の緊迫した状況の中、西郷隆盛は鳥羽伏見の戦いで、幕府側の桑名藩の荷物を差し押さえ、また不審な蔵の荷物を検査した状況を報告。
宇都宮藩は68年、戊辰戦争での戦死者や重軽傷者の身分と名前などを報告、岩倉の元に届けられた。新政府側の薩摩藩と行動を共にして東北に北上した大垣藩は同年、幕府側の仙台藩と会津藩に「白川城」(白河城、福島県)を襲来されたが、山からの攻撃を防ぎ、追討した生々しい戦闘状況を報告していた。
旧福井藩主で大蔵卿などを務めた松平慶永は、新政府の正統性を民衆に示すために、暦は新政府がつくるべきだとする意見書を提出していた。
このほか、当時の貨幣「弐歩金(二分金)」が不足し、「信州上田」で一揆が起きた状況の報告書と同じ巻物に、吹き増し(増鋳)を承認する政府の文書があり、「(松平)慶永」「大久(保利通)」「副島(種臣)」などの決裁印が押されていた。通貨不足を知った政府高官たちが増鋳を決定したとみられる。
絵巻物の「明治維新事蹟画」には、「岩倉遣欧使節団」(71~73年)一行が和船で沖に停泊している大型船に乗り込む、これまで一般に知られていなかった構図の絵が収められていた。
◆新事実含む可能性大
佐々木克奈良大教授の話「岩倉具視のような明治政府の中心人物の史料は1960年代までに出尽くしたと考えられていた。これだけまとまって出現するのは50年ぶりの大発見だ。全体の調査が済んでいないので断定的なことは言えないが、内容が豊かで、情報が詰まっているものが多く、新事実が含まれている可能性がかなり高い。活字になった文献の原本が見つかった意義も大きい。丁寧に解読し、原本と対照することで、従来の文献の読み違いを修正できるだろう。歴史の再解釈につながるのではないか」
◆最多は三条実美の429通
「海の見える杜美術館」所蔵の岩倉具視関係文書から見つかった書簡や意見書を調査している三沢純熊本大准教授らによると、最も多くの書簡を送っていたのは明治政府の最高位にあった太政大臣三条実美で、429通だった。内容は岩倉との日程調整や事務連絡が多いという。
また、伊藤博文の書簡や意見書を集めた史料集はこれまで刊行されておらず、調
査中の68通は新出とみられる。木戸孝允の75通も新出史料の可能性があり、記述内容が注目される。
191通の大久保利通の書簡は既に「大久保利通文書」に収録されているが「明治維新の研究上極めて重要な書簡の原本が見つかった意義は大きい」(三沢准教授)という。
■海の見える杜美術館所蔵
「岩倉具視関係文書」の書簡類の主な差出人と数
三条実美 429通
大久保利通 191通
木戸孝允 75通
伊藤博文 68通
江藤新平 10通
井上 毅 8通
小松帯刀 4通
大村益次郎 4通
西郷隆盛 3通
勝 海舟 3通
【用語解説】岩倉具視
幕末・明治期の公家、政治家。京都の堀河家に生まれ、下級公家だった岩倉家の養子となる。1854年孝明天皇の侍従となり、58年日米修好通商条約勅許の阻止を図る。公武合体派として皇女和宮と将軍徳川家茂の婚姻を推進。尊皇攘夷(じょうい)派から非難され、身を潜めた。その後、討幕派の公家の中心として、大久保利通らと画策し王政復古を実現。明治新政府では事実上の首班として政権の中枢を担う。71年使節団を率いて欧米を視察した。岩倉に関係する文書は国立国会図書館、国立公文書館、対岳文庫(旧岩倉邸、京都市)の3カ所に現存し、今回の新史料は第4の文書群。
3/8 産業経済新聞社
よければ下記をクリックしてください。
人気ブログランキングへ
一日一回クリックしてもらえたらうれしいです。











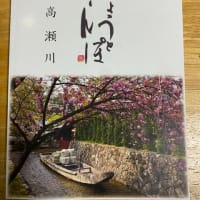

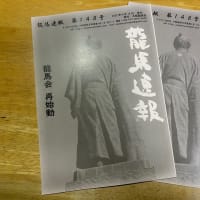

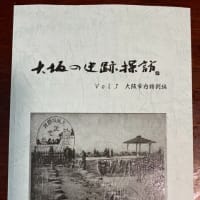


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます