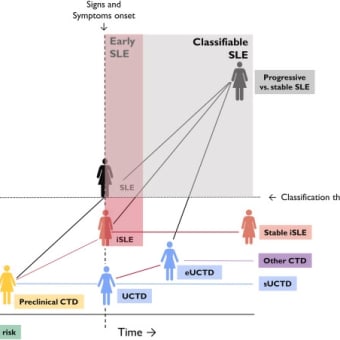C群およびG群レンサ球菌感染症についての総説
Microbiol Spectr 2019; 7: doi: 10.1128/micrcbiolspec.GPP3-0016-2018
C群および G群レンサ球菌、とりわけ Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (SDSE) はありふれたものから生命を脅かすものまでさまざまな病態の患者から培養されるようなってきている。
SDSE は微生物学的には Streptococcus pyogenes に似ている。これらのレンサ球菌はしばしば咽頭炎、皮膚·軟部組織感染症を起こす。さらに、血流感染によって播種され、心内膜炎などの深部感染症を起こすことがある。SDSE による重篤な感染症 (毒素性ショック症候群など) は、重度の基礎疾患がある患者に多く起こる。
ほとんどの場合で、ペニシリンで十分治療できるが、治療に失敗することもある。SDSE はテトラサイクリン、マクロライド、クリンダマイシンにも抵抗性であることがある。
C 群および G 群レンサ球菌感染症のほとんどはヒト-ヒト感染であるが、Streptococcus equi subsp. zooepidemicus (および稀に Streptococcus equi subsp.) の場合は人獣共通感染症 (zoonosis) である。これらの菌種は動物との接触または汚染された食物の摂取によって感染し、レンサ球菌感染後の糸球体腎炎を起こす。通常は Streptococcus viridans のグループに分類される Streptococcus anginosus グループはさまざまな化膿性感染症を起こす。
ランスフィールド分類の A 群 (S. pyogenes など) 、B 群 (S. agalactiae) とは対照的に、C 群および G 群レンサ球菌 (group C and G streptococci: GCGS) は生化学的反応、溶血性、感染しやすい生物種、臨床症状が多様である。GCGS は咽頭、皮膚に常在しており、時に女性の尿生殖路に定着しており、疫学的特徴や臨床所見はこれらの分布を反映している。
1. 歴史と分類
GCGS の分類は難しく、過去数十年で常に更新され続けている。GCGS 感染症の起炎菌ほとんどは S. anginosus group (SAG) か S. dysgalatiae subspecies equisimilis (SDSE) である。
2. 疫学
SAG は口腔内常在菌である。SDSE もヒトの常在菌である。いつくかの研究では、咽頭への SDSE の定着は他の病原体の感染を防ぐ可能性が示されている。SDSE が定着していると、咽頭炎の頻度が少ないからである。
一方で、SDSE による侵襲性感染症が世界中で増加している。SDSE は非A、非B β溶血性レンサ球菌による侵襲性感染症の原因の 80%以上を占めている。多くの国で、SDSE による菌血症の罹患率は 2-3倍に増加しており、S. pyogens による菌血症に迫っている。
GAS あるいは SDSE による侵襲性感染症は糖尿病患者、癌患者、免疫不全患者、静脈注射薬使用者、皮膚損傷患者に多い。
SDSE の伝播は起こるとすれば、ヒト-ヒト間でほとんどは散発的に起こる。共通の感染源からアウトブレイクが起こることは少ない。アウトブレイクが起こるとすれば、濃厚な身体接触があるか、環境が汚染されている場合である。
3. SAG 感染症
SAG は通常、Streptococcus viridans に分類される。S. viridans は肺、胸腔、脳、口腔、腹腔、皮膚軟部組織、尿生殖路に膿瘍を形成することが特徴である。菌血症をともなうことも、ともなわないこともある。他の S. viridans と異なり、S. anginosus は心内膜炎を起こすことがある。
4. 菌血症、心内膜炎、その他の侵襲性感染症
SDSE や S. equi subsp. zooepidemicus などの C、G 群レンサ球菌は菌血症を来すという報告が増えている。そのほとんどは皮膚軟部組織感染症に続発するものである。これらの菌種に感染している患者のうち最大 70%に基礎疾患 (悪性腫瘍、心血管疾患、糖尿病、免疫不全、アルコールまたは薬物依存症) がある。
SDSE による菌血症の 20%は原発性で、残りは局所感染症 (ほとんどは皮膚軟部組織感染症) に続発する。
Auckenthaler らは G群レンサ球菌菌血症 38例の症例集積研究を行った。メイヨークリニック傘下の病院で 10年間に陽性となった血液培養のうち、0.25%が G 群レンサ球菌だった。70%は市中感染だった。院内感染の場合は手術後の創部感染か経皮的な処置後だった。患者は高齢者が多く、ほとんどは 60-80歳台だった。多くの患者には静脈の障害やリンパ浮腫など慢性的な下肢の浮腫の原因があった。
Carmeli らはイスラエルにおける C群レンサ球菌菌血症 10例を報告し、他の症例集積研究をまとめた。この総説では、一部は原発性だったが、ほとんどは咽頭炎、喉頭蓋炎 (epiglottitis) 、心外内膜炎、肺炎、皮膚軟部組織感染症、心内膜炎、感染性動脈瘤に続発した。ボストン大学において 3年間で認めた G 群レンサ球菌菌血症についての症例集積研究では、年齢の中央値は 68歳で、半数は皮膚軟部組織感染症に続発していた。静脈注射薬を使用している患者における菌血症 6例についての報告では、侵入門戸は皮膚と考えられ、注射薬は少なくとも 10年以上使用していた。
複数の研究で、G 群レンサ球菌菌血症は再発率が高いと報告されている。イスラエルにおける 84症例の SDSE 菌血症のうち、6症例 (7%) で菌血症を再発した。再発した回数は 2-4回だった。シンガポールにおける研究では、再発率は 5.8%だった。
GCGS による心内膜炎も新興感染症である。他の感染症と同様に、心内膜炎は重度の基礎疾患を有する高齢者に多く、重症化、塞栓症、転移性感染症、死亡のリスクが高い。臨床的な所見は S. pyogenes による心内膜炎に似る。Oppegaard らは 1999-2013年のノルウェイにおける SDSE による心内膜炎 9症例についての症例集積研究を行った。年齢の中央値は 64歳で、2例を除いて基礎疾患があった。一般に急性の経過で発症し、重篤だった。発症から入院までの期間の中央値は 1日だった。感染していたのは僧房弁と動脈弁で同じくらいの頻度だった。9例のうち 4例で塞栓症症状を認め、7例で心合併症を認めた。9例中3例で弁置換術が必要だった。30日後の死亡率は 22%だった。G 群レンサ球菌による心内膜炎 40例についての総説では、平均年齢は 56歳で、死亡率は 36%だった。およそ半数の患者には基礎疾患があった。6例は悪性腫瘍、6例は糖尿病、4例はアルコール依存症、3例は注射製剤の使用者だった。さらに、半数の患者には既知の弁疾患があった。もっとも多い弁疾患は僧房弁逆流 (mitral regurgitation) だった。3例は人工弁 (prosthetic valve) 置換術後の患者だった。上記の総説に含まれない 7例についての症例集積研究では、平均年齢は 72歳で、1例のみ 60歳未満だった。ほとんどの症例が基礎疾患ありかつ/または弁疾患ありだった。
SDSE または S. equi subsp. zooepidemicus による菌血症の一部は多巣性の転移感染症 (髄膜炎、腹腔内膿瘍、心外膜炎、肺炎) を来す。
5. 治療
SDSE をはじめとする大きなコロニーを形成する C 群および G 群レンサ球菌はふつうはペニシリンに感受性であり、これらの菌種による感染症に対する治療薬としてまず考慮される。ペニシリン G に対する最小阻止濃度は 0.03-0.06 μg/mL である。βラクタム以外に、グリコペプチド、ダプトマイシンおよびリネゾリドに対しても試験管内では感受性である。
Lam と Bayer は菌の濃度が高い場合 (>10^8 colony forming unit/mL) にはペニシリンの殺菌活性が低下することを見出だしている。この現象は S. pyogenes でよく知られており、静止期にはペニシリン結合蛋白の産生が抑制されることによる (Eagle effect)。
他に感染性心内膜炎や化膿性関節炎、あるいは咽頭炎で治療に対する反応が遅いあるいは悪い場合がある。この原因については不明だが、細菌と宿主の両方に要因があるかもしれない。
細胞壁合成を阻害する抗菌薬にゲンタマイシンを追加すると、少なくとも試験管内では相乗効果を発揮する。そのため、アミノグリコシドが禁忌でなければ、重症の侵襲性 SDSE 感染症に対してアミノグリコシド併用を勧める意見もある。しかし、この推奨を裏付ける臨床データは現時点ではない。
最近、デンマークで疫学的に関連のある 3人の患者からペニシリン耐性株が分離された。4つの菌株は同じクローンで最小阻止濃度は 0.5-2 mg/L であり、複数のペニシリン結合蛋白 (penicillin binding proteins: PBPs) に変異を認めた。
テトラサイクリン、マクロライド、クリンダマイシン、フルオロキノロンに対する感受性はまちまちで、薬剤感受性試験を行わなければ分からない。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30977463/