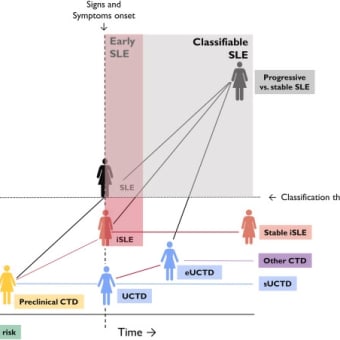感染性心内膜炎
Nat Rev Dis Primers 2016; 2: 16059
doi: 10.1038/nrdp.2016.59.
感染性心内膜炎(infectious endocarditis: IE)は、生命を脅かすまれな疾患であり、治癒した患者であってもその影響は長期にわたる。感染性心内膜炎は、基礎疾患として心臓の構造的疾患がある患者に多く発症し、特に血管内に人工物を留置している患者では、医療機関受診に関連することが多くなっている。
病原性細菌による菌血症の場合、侵入した細菌と宿主免疫系との複雑な相互作用の最終結果として、疣贅 (infected vegetation) が形成されることがある。一旦感染が成立すると、IE は体内のほとんど全ての臓器を侵す可能性がある。
IE の診断は困難であり、臨床的、微生物学的、および心エコー検査の結果を組み合わせた戦略が、修正デューク基準 (modified Duke criteria) として体系化されている。血液培養陰性の IE の場合、診断は特に困難であり、その存在を証明するための新しい微生物学的および画像診断技術が開発されている。
いったん IE と診断されれば、感染症、循環器内科、心臓外科の専門知識を有する集学的チームによって管理されるのが最善である。IE の予防のための抗菌薬投与については、まだ議論の余地がある。IE の原因となる一般的な細菌を標的としたワクチンを開発する努力が続けられているが、まだ市販されていない。
1. はじめに
IE は、心内膜表面の感染(通常は細菌感染)に起因する多臓器疾患である。数百年前から病態として認識され、19 世紀からは感染症として認識されている。1885 年の画期的な Gulstonian Lectures on malignant endocarditis において、ウィリアムオスラー (William Osler) 卿は、患者では弁に "真菌性 "の増殖を起こし、その後 "微生物が離れた部位に移行する "という統一理論を提示した。この 130 年の間に、IE に対する理解は飛躍的に深まるとともに、この疾患自体も根本的に変化した。医学の進歩、新たなリスク集団、そして抗菌薬耐性の出現は、IE の新たな臨床症状をもたらした。この入門書では、IE の疫学、病態生理、診断と治療の側面に関する現在の理解を概説し、IE とその管理における将来の発展を推測する。
2. 疫学
IE は比較的まれな疾患であるが、生命を脅かす疾患である。IE の世界的な負担に関するシステマティックレビューでは、粗発生率は 10 万人年あたり 1.5-11.6 例であり、10 カ国(ほとんどが高所得国)のみから質の高いデータが得られている。未治療の IE による死亡率は一様である。入手可能な最善の治療法を用いても、IE による現代の死亡率は約 25%である。
2-1. 統計
IE 患者の平均年齢は過去数十年で著しく上昇している。例えば、ジョンズ・ホプキンス病院 (Johns Hopkins Hospital) に受診したIE 患者の年齢の中央値は 1926 年には 30 歳未満であった。対照的に、現代の IE 患者の半数以上は 50 歳以上であり、症例の約 3 分の 2 は男性である。高所得国におけるこのような年齢分布の変化には複数の要因が関与している。第一に、多くの高所得国では、IE になりやすい心臓の危険因子が、主に若年成人に見られるリウマチ性心疾患から、主に高齢者に見られる弁膜症へと変化している。第二に、高齢化が着実に進行している。第三に、血管内カテーテル、高エネルギー輸液、心臓内デバイス、透析シャントなどの新しい治療法の導入に伴って、高齢者に多い医療関連 IE (healthcare-associated IE) という比較的新しい病態が出現したことである。
2-2. 危険因子
ほとんどすべてのタイプの心臓の構造的疾患が IE の素因となりうる。かつてはリウマチ性心疾患 (Rheumatic heart disease) が最も頻度の高い基礎疾患であり、僧帽弁が最もよく侵される部位であった。先進国では、リウマチ性心疾患に関連する症例の割合は過去 20 年間で 5%以下に減少している。しかし、発展途上国では、リウマチ性心疾患は依然として IE の最も一般的な素因となる心疾患である。
人工弁や心臓デバイス (永久ペースメーカーや除細動器) は IE の重要な危険因子である。これらの機器の植え込み率は過去数十年で劇的に増加した。その結果、人工弁や人工心臓が IE 症例に占める割合が増加している。例えば、25 カ国の成人 2,781 人の確定的な IE 患者を対象とした最近のコホートでは、5 分の 1 が人工弁を、7%が心臓器具を使用していた。
先天性心疾患も IE のリスクを高める。前述の研究では、明確な IE を発症した 2,781 人のうち 12%に先天性心疾患があった。しかし、このコホートは主に心臓手術プログラムを持つ紹介センターから集められたため、この割合はおそらく一般集団における先天性心疾患と IE の関連を過大評価している。僧帽弁逸脱は、発展途上国における先天性弁膜症の 7-30%を占める主要な素因となる構造異常であると報告されている。ある症例対照研究では、僧帽弁逸脱は IE とオッズ比 8.2 (95%信頼区間: 2.4-28.4) で関連していた。先進国では、弁膜症が知られていない IE 患者の 30%から 40%において、変性心病変 (degenerative cardiac lesion) が最も重要である。例えば、ある剖検シリーズでは、65 歳以上の IE 患者の 14%に僧帽弁輪石灰化が認められ、これは一般人口よりも高い割合であった。
IE の素因となる他の因子としては、注射薬の使用(injection drug use: IDU)、ヒト免疫不全ウイルス(human immunodeficiency virus: HIV)感染、医療機関の広範な利用が含まれる。特に医療関連 IE は、過去数十年間、特に先進国で増加している。例えば、最近の前向き多国籍コホートでは、自己弁 IE で IDU の既往のない 1,622 人の患者の 3 分の 1 が医療関連 IE であった。
3. 微生物学
患者の危険因子が変化すると、IE の微生物学も変化する。溶連菌 (streptococci) とブドウ球菌 (staphylococcus) は合わせて IE 症例の約 80%を占めているが、この二つの菌の割合は地域によって異なり(図 1)、時代とともに変化している。
図 1. 地球規模の感染性心内膜炎の起炎菌の疫学
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5240923/figure/F1/
医療関連 IE の出現により、黄色ブドウ球菌とコアグラーゼ陰性ブドウ球菌 (coagulase-negative staphylococci) の検出率が増加している。一方、緑色連鎖球菌(viridans group streptococci: VGS)による IE の割合は減少している。腸球菌は IE の第三の原因であり、医療機関受診に関連することが多くなっている。IE にグラム陰性菌や真菌が関与することはまれで、発症する場合は主に医療関連である。
IE 症例の約 10%では血液培養が陰性であるが、これは診断のためのワークアップの前に患者が抗菌薬を服用していたためである。真の培養陰性 IE は、従来の微生物学的手法では分離が困難な培養が難しい (fastidious) 微生物によって引き起こされる。血清学的検査や血液や弁の生検検体を用いたポリメラーゼ連鎖反応 (polymerase chain reaction: PCR) のような高度に専門化された検査法により、最終的にこのような症例の最大 60%で原因病原体を示唆することができる。真の培養陰性 IE の病因は地理的要因や疫学的要因によって異なるが、重要な原因としては Coxiella burnetii(Q 熱の原因菌)、Bartonella 属菌、Brucella 属菌、Tropheryma whipplei などが挙げられる。家畜や屠畜場との接触(Brucella 属および Coxiella 属)、ホームレスやアルコール中毒(Bartonella quintana 属)、中東や地中海への旅行や未殺菌乳製品の摂取(Brucella 属)、猫との接触(Bartonella henselae 属)、人工弁を持つ患者における医療機関の広範な利用や血液培養陰性(Aspergillus 属)などの特定の危険因子は、IE の可能性がある症例を評価する際に有用な手がかりとなる。
4. 病態生理
実験的には、正常な弁膜内皮は血管内への細菌投与による細菌のコロニー形成に対して抵抗性である。
したがって、IE を発症するためにはいくつかの独立した危険因子が同時に存在することが必要である。危険因子とは、1. 細菌の付着およびコロニー形成に適した心臓弁表面の変化、2. 弁組織に付着しコロニー形成することができる細菌による菌血症、3. 増殖した細菌がフィブリンなどの血清分子や血小板に「埋没」し、疣贅を形成することである(図 2)。
図 2. 感染性心内膜炎の病態生理
4-1. 非細菌性血栓性心内膜炎
上述したように、弁膜表面が障害されない限り、細菌の静脈注射で IE が起こることはまれである。ヒトの場合、弁膜表面への損傷は、特定の全身性疾患状態(リウマチ性心膜炎など)による一次的な弁膜損傷に関連した乱流血流 (turbulent blood flow)、カテーテルや電極による機械的損傷、IDU における固体粒子の反復注射に起因する損傷など、様々な要因から生じる可能性がある。
このような内皮の損傷は、間質浮腫の上にフィブリン-血小板沈着物の形成を促す。これは、1936 年に Gross と Friedberg によって初めて「非細菌性血栓性心内膜炎」(nonbacterial thrombotic endocarditis: NBTE)と呼ばれた病態生理学的実体 (pathophysiological entity) である。細菌を静脈内投与した実験動物の損傷した弁の連続走査型電子顕微鏡写真により、感染後 24 時間以内に NBTE 表面に細菌が付着していることが明らかになった。この付着の後、さらにマトリックス分子で細菌が覆われると、完全な疣贅が形成される。
4-2. 一過性の菌血症
血流感染は自己弁 IE 発症の必須条件であり、おそらく人工弁 IE 症例の大部分もそうであろう。しかし、IE を引き起こすのに必要な最小限の菌血症(1 mL あたりのコロニー形成単位(colony forming units: CFU)で測定)はわかっていない。
実験モデルでは通常、1 mL あたり 105-108 CFU の接種量 (inocula) をボーラス投与または長期にわたる持続静脈注射で使用している。低悪性度菌血症(10 CFU/ml 以上、104 CFU/ml 未満)は、歯科、胃腸、泌尿器、婦人科処置などの軽度の粘膜外傷後によく見られるようである。細菌血症は、歯科処置後や、歯磨きや咀嚼などの一般的な日常生活後、大多数の患者で容易に検出される。したがって、低レベルの菌血症はありふれたものではあるが、IE を引き起こすには通常不十分であると考えられる。
さらに、軽度の粘膜外傷の後に血液中に存在する細菌種の多くは、IE の症例ではあまり関与していない。例えば、補体を介する殺菌活性はグラム陰性病原体のほとんどを排除する。対照的に、従来から IE に関連している病原体(すなわち、黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌、緑色ブドウ球菌、腸球菌、緑膿菌)は、あまり一般的でない IE の原因である病原体よりも、in vitro でイヌの大動脈弁に付着しやすいことが示されている。同じ菌種であっても、IE を引き起こす傾向には違いがある。例えば、黄色ブドウ球菌特定のクローン複合体は IE のリスクの増加と関連している。同様に、S. mitis-oralis グループの一部は、緑色ブドウ球菌の多くの菌種の中で IE の原因として優勢である。
4-3. 微生物と NBTE の相互作用
IE を誘発する典型的な病原体による菌血症が成立した後の、次のステップは、NBTE のフィブリン-血小板マトリックスへの菌の付着である。このステップの重要性は、歯周炎 (periodontitis) ラットの抜歯 (dental extraction) に関する研究で証明された。この研究では、G 群連鎖球菌は菌血症の起炎菌としては少数にもかかわらず、IE エピソードの 83%に関与していた。In vitro のモデルでは、これらの菌は他の菌種と比較して、フィブリン-血小板マトリックスへの接着が増加していた。
NBTE への接着は、真菌 IE においても重要なステップである。カンジダ・クルセイ (Candida krusei) は付着性が低く、ヒトにおける IE の原因としては稀であるのに対し、カンジダ・アルビカンス (Candida albicans) は in vitro で NBTE に付着し、実験的 IE を容易に生じさせ、カンジダ属の中で IE の最多の原因である。
4-4. 細菌が心内膜に付着するメカニズム
病原菌が NBTE に結合することは IE の病態生理における共通のステップであるように思われるが、そのメカニズムはかなり異なる。一部の細菌は、フィブロネクチン、ラミニン、コラーゲンなど、損傷した内皮や NBTE の成分に結合するようである。その他の生物は、内皮細胞に直接結合したり、内皮細胞に取り込まれたりする。これは黄色ブドウ球菌が心臓弁に感染する重要なメカニズムであると思われる (図 3)。
図 3. 感染性心内膜炎の病態生理
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5240923/figure/F3/
このモデルでは、接着は、凝集因子やコアグラーゼのようなフィブリノーゲンと結合する黄色ブドウ球菌特異的表面タンパク質によって媒介される。黄色ブドウ球菌 IE の病態生理においては、フィブリノーゲンとフィブロネクチンが協働的な関係があるようである。 両者とも疣贅への最初の接着を仲介するが、フィブロネクチン結合は弁膜内皮部位における細菌の定着に重要であるようである。その後、α-トキシン (α-toxin) のような他の病原性因子 (vilurecnce factor) が、成熟した疣贅におけ維持と増殖を媒介する。
さらに、口腔内連鎖球菌の NBTE への接着における重要な因子は、細菌由来の細胞外多糖の複合体であるデキストラン (dextran) であると考えられている。その他、連鎖球菌の接着を媒介する病原因子として、口腔内で接着分子として機能する表面タンパク質である FimA、シアル酸結合性接着分子 Hsa、細菌、フィブリノーゲン、血小板の複雑な相互作用を媒介する phage-encoded bacterial adhesin などが提案されている。
4-5. 血小板凝集と疣贅の成長
細菌コロニー形成後、疣贅は血小板-フィブリン沈着と細菌増殖をくり返すことによって拡大する(図 2)。一部の細菌株は血小板凝集および血小板放出反応(すなわち脱顆粒 [degranulation])を強力に刺激する。一般に、IE の原因となるブドウ球菌や連鎖球菌の菌株は、IE の原因となりにくい他の細菌よりも、より活発に血小板を凝集させる。連鎖球菌は 2 つの細菌表面抗原を介して血小板凝集を促進する。黄色ブドウ球菌は 1. 血小板由来の von Willebrand 因子を介して、あるいは 2. von Willebrand 因子レセプターに直接に血小板を結合させることができるようである。
血小板は IE の病因における重要な構成要素であるが、疣贅における細菌増殖に対する宿主の防御においても極めて重要な役割を果たしている。例えば、血小板は血中のブドウ球菌を貪食し、α 顆粒 (α-granules) と融合する貪食液胞に取り込む。これらの α 顆粒は血小板由来マイクロパーティクル(platelet microbicidal proteins: PMP)と呼ばれる抗菌ペプチドを含んでいる。ブドウ球菌は PMPs に対する感受性により、1. 血小板内で死滅するか、2. 「トロイの木馬 (Trojan Horse)」機構を使って生き残り、播種する。血小板はまた、抗菌性 PMP を疣贅局所に放出することで、疣贅内での細菌増殖を阻止する。このように、黄色ブドウ球菌のなどの細菌の PMP に対する耐性が、IE における病原性の一因となっている。最後に、疣贅の奥深くに埋もれた細菌は、重要な栄養素を取り込むことができないため、代謝活性が低下した状態を示す可能性がある。この代謝状態の変化のために特定の抗菌薬に対して細菌が生き残りやすくなる。
侵入した微生物、内皮および単球は、IE の発症において複雑な相互作用をする。in vitro における内皮細胞に取り込まれた黄色ブドウ球菌のような微生物は、IL-6、IL-8、単球走化性ペプチド (monocyte chemotactic peptide) の発現を増加させ、強力な炎症性ケモカイン反応を引き起こす。単球は内皮細胞の微小環境 (microenvironment) に引き込まれ、そこで血中の細菌が単球表面に直接結合し、組織トロンボプラスチン (tissue thromboplastin)(組織因子 tissue factor)を放出させる。これにより凝固系カスケードが増幅し、疣贅形成が進行する。上述したように、凝固系カスケードは、疣贅マトリックス内の血小板による PMP 放出の抗菌効果も誘導する。
4-6. バイオフィルム形成
「バイオフィルム (biofilm)」形成の病理学的意義と IE の臨床転帰への影響については、意見が分かれている。心臓内デバイスに関連した IE がデバイス周囲のバイオフィルムを誘発することは明らかである。このような場合、バイオフィルム形成はデバイスに関連した疣贅形成に直接寄与する。
しかし、自己弁 IE に対するバイオフィルム形成の寄与については明らかでない。自己弁 IE におけるバイオフィルム形成の影響に関する最も説得力のあるデータは、黄色ブドウ球菌 IE における実験的研究から得られたものである。過去 10 年にわたる一連の研究により、in vitro でバイオフィルムを形成する黄色ブドウ球菌株の能力は、ヒトにおいて臨床的に「持続性」メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(methicillin-resistant S. aureus: MRSA)菌血症(バンコマイシン感受性分離株が存在し、適切なバンコマイシン治療レジメンが実施されているにもかかわらず、血液培養が 7 日以上陽性であると定義される)を引き起こす能力と関連があることが示されている。興味深いことに、持続性 MRSA 菌血症を来す細菌株は、一過性の MRSA 菌血症で分離された細菌株と比較して、in vitro で亜阻害濃度のバンコマイシンに曝露されると有意に多くのバイオフィルムを産生する。
4-7. クオラムセンシング (Quorum-sensing)
疣贅には多くの細菌が密集しているため、病原性因子のクオラムセンシングによる遺伝子制御(すなわち、細菌の細胞密度に基づく遺伝子発現制御)の役割が提起されてきた。
クオラムセンシング
https://bifidus-fund.jp/keyword/kw029.shtml#:~:text=%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%82%82%E3%82%88%E3%81%8F%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82
この点に関しても、ほとんどのデータは黄色ブドウ球菌から得られており、主にクオラムセンシングレギュロン agr(accessory gene regulator, アクセサリー遺伝子制御因子)についての知見である。興味深いことに、実験的に作り出した IE において、MRSA 株が増殖周期の初期に agr の活性化を引き起こす能力は、臨床的にも実験的 IE においても、バンコマイシン耐性持続性 IE を引き起こす能力と相関している。しかし、agr 遺伝子のノックアウトについての研究によると、agr の初期活性化は、病原性に直接結びつくといるとは結論できず、せいぜい持続性 IE 株のバイオマーカーに過ぎない。
4-8. 免疫病理学的要因
IE では、高ガンマグロブリン血症、脾腫、末梢血中のマクロファージを認めることから分かるように、体液性免疫と細胞性免疫の両方が刺激される。典型的な IE の特徴である持続的な菌血症に反応して、いくつかのクラスの抗体が産生される。オプソニック抗体 (opsonic aetibodies)、凝集抗体 (agglutinating antibodies)、補体固定抗体 (complement-fixing antibodies)、クリオグロブリン (cryoglobulins)、細菌のヒートショックタンパク質やマクログロブリンに対する抗体が、進行中の感染を制御するために宿主によって産生される。
4-9. IE における抗体反応の有効性
動物実験から、IE を予防する抗体反応の有効性は様々であることが示唆されている。例えば、熱で殺した S. sanguis とフロイトのアジュバント (Freut's adjuvant) で免疫したウサギは、大動脈弁を傷つけた後に S. sanguis を接種すると、免疫していないコントロールと比較して ID50(つまり、ウサギの 50%に感染を起こすのに必要な S. sanguis の量)が高かった。細胞表面成分に対する抗体は、in vitro では C. albicans のフィブリンや血小板への接着を減少させ、in vivo では IE の発生を減少させる。一方、S. epidermis と S. aureus の whole cell で誘導した抗体は、免疫動物において IE を予防しなかった。フィブリノゲン結合タンパク質であるクランピングファクター A(clumping factor A: ClfA)に特異的な抗体は、抗菌薬治療と併用した場合、疣贅からの細菌クリアランスを増加させた。さらに、最近のデータでは、ClfA に対するワクチン接種が IE 予防に有効である可能性が示唆されているが、ヒトでの研究では有効なワクチンは得られていない。
4-10. 病理学的抗体 (pathological antibodies)
リウマトイド因子(抗 IgG IgM 抗体)は、6 週間以上経過した IE 患者の約半数に発症し、抗菌薬治療により減少する。リウマトイド因子は、IgG のオプソニン活性を阻害したり、貪食を刺激したり、微小血管の損傷を促進したりすることにより、病態に関与している可能性があるが、IE に伴う免疫複合体糸球体腎炎に大きく関与しているようには見えない。抗核抗体も IE でみられ、筋骨格系の症状、発熱、胸膜痛に関与している可能性がある。
4-11. 免疫複合体
血中の免疫複合体はほとんど全ての IE 患者において高力価で検出されている。免疫複合体の沈着は IE に関連した糸球体腎炎に関与しており、オスラー結節 (Osler's node, IE の皮膚症状) やロス斑 (Roth spot, 網膜出血)のような IE の末梢症状も引き起こす可能性がある。病理学的には、これらの病変は、抗原抗体複合体が沈着して局所的な血管炎を引き起こす急性アルサス反応に似ているが、ある症例集積研究でオスラー結節からの吸引液の培養が陽性であったことから、これらは敗血症性塞栓現象である可能性が示唆されている。
アルサス反応
https://www.osmosis.org/answers/arthus-reaction#:~:text=An%20Arthus%20reaction%20refers%20to,an%20abnormal%20immune%20system%20response.
効果的な治療により、血中の免疫複合体は速やかに減少する。一方、治療が失敗した場合は、血中の免疫複合体価が上昇するのが特徴である。
4-11. 難培養細菌 (fastidious bacteria)
偏性細胞内病原体 (obligate intracellular pathogens) である C. burnetii やバルトネラ属 (Bartonella spp.) のような一部の細菌は、上記とは異なる病態生理学的メカニズムで IE を引き起こす。C. burnetii の場合、患者はマクロファージの活性化を欠くことで、菌の細胞内生存を促進し、Q 熱に伴う IE を示唆する泡沫細胞 (foamy macrophage) の病理組織学的所見をもたらす。また、特異的抗体が産生され、免疫複合体が形成される。罹患した弁には平滑な結節性の疣贅を伴う内皮下感染を認め、顕微鏡的には肉芽腫を伴わないフィブリン沈着、壊死、線維化が混在している。
5. 臓器特異的病態生理
IE は全身性の疾患であり、複数の臓器に特徴的な病理学的変化をもたらす(図 4)。
図 4. 感染性心内膜炎による臓器障害
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5240923/figure/F4/
疣贅の血小板-フィブリンマトリックスの一部は、感染した心臓弁から離れて動脈血とともに移動し、心臓外の血管を塞栓することがある。このような敗血症性塞栓は、体内のほとんどすべての臓器を巻き込む可能性があり、臨床的にはさまざまな形で現れる。
まず、塞栓が隣接する組織の酸素供給を絶つのに十分な大きさであれば、塞栓に起因する組織の梗塞が起こりうる。これが塞栓性脳卒中、心筋梗塞、腎臓、脾臓、腸間膜、皮膚の梗塞の病態である。第二に、塞栓子内の細菌が局所の組織に侵入し、膿瘍を形成することがある。最後に、免疫複合体の沈着や、菌血症によって細菌が播種されることによっても、心臓外症状が生じることがある。
5-1. 心症状
典型的には、疣贅は房室弁(atrioventricular valves 僧帽弁 [mitral valves] および三尖弁 [tricuspid valves])の心房表面または半月弁(semilunar vcalves 大動脈弁 [aortic valves] および肺動脈弁 [pulmonary valves])の心室表面の弁尖の閉鎖線に生じる。疣贅の大きさは様々で、直径数センチに達することもある。感染により弁尖の穿孔や腱索 (chordae tendineae)、心室中隔 (interventricular septum)、乳頭筋 (papillary muscle)の破裂を来すことがある。心筋や心嚢に瘻孔形成を伴う弁輪膿瘍 (valve ring abscess)が生じることもあり、特に S. aureus が原因であることが多い。心筋梗塞は IE の塞栓性合併症として、特に大動脈弁 IE の患者で起こることがある。
5-2. 腎症状
IE 患者では、腎臓は塞栓による梗塞、塞栓子による直接播種による膿瘍、免疫複合体糸球体腎炎を起こすことがある。活動性 IE 中に行われる腎生検は、臨床的に明らかな腎疾患がない場合でも一様に異常である。
5-3. 神経血管の症状
細菌性動脈瘤 (mycotic aneurysm) は、動脈壁の感染によって引き起こされる動脈の局所的な拡大であり、IE の急性期に発見される場合もあれば、治療が成功した数ヶ月から数年後に発見される場合もある。
細菌性動脈瘤をなぜ mycotic (真菌性) aneurysm と呼ぶのか
https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.11477/mf.1402216894#:~:text=%E8%B5%B7%E7%82%8E%E8%8F%8C%E3%81%AF%E3%81%BB%E3%81%A8%E3%82%93%E3%81%A9,%E3%81%AF%E7%94%A8%E3%81%84%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%EF%BC%8E
このような動脈瘤が発生する機序はいくつかある。すなわち、1. 動脈壁への直接的な細菌侵入とそれに続く膿瘍形成、2. vasa vasorum(太い血管の壁に血液を供給する細い血管)の閉塞、あるいは動脈壁の傷害の結果として生じる傷害を免疫複合体の沈着である。
細菌性動脈瘤は血管の分岐部で発生する傾向があり、最も多いのは脳血管であるが、ほとんどすべての血管床が侵される可能性がある。脳動脈瘤は、特に出血性合併症が生じた場合に症状を示すことがあるが、神経症状を伴わない患者に発見されることもある。例えば、ある前向き症例集積研究では、血管造影を伴う脳 MRI(磁気共鳴血管造影と呼ばれる手法)によるスクリーニングを受けた連続した IE 患者 130 人のうち 10 人に臨床的には無症状の脳動脈瘤が認められた。この研究では、磁気共鳴血管造影で検査した全患者の約 80%で、末梢の小さな脳血管に無症候性の「微小出血」を認めた。この微小出血が将来の症候性脳内出血のリスクを予測するかどうかは不明である。
IE の神経学的症状は脳塞栓から生じることが最も多い。症候性の脳塞栓症は IE 患者の約 20-30%で起こる。しかし、無症状の IE 患者に対してルーチンで MRI を撮像すると、大多数に脳血管合併症を認める。IE における脳卒中の発症率は、IE 発症後 1 週間で 4.82 例/1000人·日であり、抗菌薬の投与開始後は急速に低下する。
5-4. 脾臓の症状
脾梗塞は IE で死亡した患者の剖検時にしばしば発見されるが、臨床的には発見されないこともある。脾膿瘍は、疼痛、発熱、白血球増加を伴い、臨床的に明らかになる傾向がある。脾腫 (splenomegaly) は現代の先進工業国における IE 患者の約 10%にみられ、おそらく脾腫を来すためには免疫学的反応が長く続く必要があることから、急性例よりも慢性 IE(Q 熱や VGS によるものなど)でよく見つかる。
5-5. 肺の症状
血栓塞栓シャワー(thromboembolic shower, 小さな塞栓の「シャワー」が小血管を閉塞する現象)は、梗塞を伴うか伴わないかを問わず、敗血症性肺塞栓 (septic pulmonary emboli) の形成につながる可能性がある。この現象は、三尖弁 IE や、肺のすぐ「上流」に位置する中心静脈カテーテルなどの微小塞栓源によくみられる合併症である。肺炎、胸水、膿胸はしばしば敗血症性肺塞栓に伴う。敗血症性肺塞栓は、胸部 X 線写真上では、末梢の楔状の浸潤影として現れることが多いが、腫瘍のように見える丸みを帯びた「砲弾型 (cannonball)」病変が生じることもある。
5-6. 皮膚症状
IE における皮膚所見には、点状出血 (petechiae)、皮膚梗塞 (cutaneous infarcts)、オスラー結節 (Osler's node)、Janeway 疹 (Janeway lesion) がある。顕微鏡レベルでは、オスラー結節は静脈や毛細血管に進展した動脈管内膜増殖からなり、血栓症や壊死を伴うことがある。好中球および単球からなるびまん性の血管周囲浸潤が真皮血管を取り囲んでいる。病変内に免疫複合体がみられることもある。Janeway 疹は敗血症性塞栓によって引き起こされ、細菌、好中球、壊死および皮下出血の存在を特徴とする。
5-7. 眼症状
IE 患者は眼にロス斑 (Roth's spot) を認めることがある。ロス斑は免疫学的現象であり、眼底鏡検査で、中心が淡い網膜出血として現れる(図 4)。顕微鏡的には、網膜の神経線維層の浮腫と出血に囲まれたフィブリン-血小板栓またはリンパ球からなる。さらに、眼球に直接細菌が播種され、硝子体かつ/または房水に及ぶ眼内炎を引き起こすこともある。眼内炎は S. aureus IE で特に多くみられる。例えば、S. aureus 菌血症患者の前向きコホートでは、IE を発症した 23 人中 10 人(43%)が眼感染症も併発していた。
6. 診断、スクリーニング、予防
6-1. 診断
IE の診断には通常、臨床検査、微生物検査、心エコー検査の結果を組み合わせる必要がある。歴史的には、そしておそらく医療資源に乏しい環境では現在もそうであるように、IE は活動性の弁膜炎(心雑音など)、塞栓症状、免疫学的血管現象などの古典的な所見と血液培養陽性の組み合わせに基づいて臨床的に診断された。これらの症状は亜急性または慢性感染の特徴であり、多くの場合、リウマチ性心疾患の若年患者で認めた。
しかし、現代の先進国では、IE の多くは医療関連に変わり、しばしば黄色ブドウ球菌による急性発症例が見られるため、通常上記の特徴をほとんど認めない。発熱は最も一般的な症状であるが、非特異的である。 静注薬物常用者や血管内デバイスの存在など、危険因子の存在は、発熱患者における IE の臨床的疑いを強めるはずである。
このように臨床像が多様であるため、IE を早い段階で診断し、有効な抗菌薬の投与や心臓弁手術につなげることは容易ではない。また、不必要な抗菌薬の長期投与を避けるためにも、IE 以外の疾患の診断に集中するためにも、IE を確実に除外する能力は重要である。
6-2. 検査
血液培養は IE の診断において最も重要な検査である。菌血症は通常持続的であり、IE 患者の大部分は血液培養陽性である。血液培養を採取する前に抗菌薬治療が行われた場合、陽性率は低下する。最新の血液培養技術により、IE を引き起こすほとんどの病原体を分離できるようになった。このため、特定の血液培養瓶を使用したり、培養を 5 日以上延長したりするような、培養が難しい病原体の分離を容易にするために従来使用されてきた方法は、もはや一般的には推奨されていない。
培養陰性で IE が疑われる場合には、他の微生物学的検査法が有用である(表 1)。
表 1. 血液培養陰性の感染性心内膜炎の診断に有用な検査
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5240923/table/T1/
例えば、血清学的検査は Q 熱 (Q fever)、発疹熱 (murine typhus)、オウム病 (psittacosis) の診断に必要である。さらに、バルトネラ (Bartonella) は特殊な培養法で分離することができ、血清学的検査もこの病原体の同定に有用である。血液培養が陰性の場合、弁膜組織の培養から原因菌が見つかることがあり、培養が難しい病原体や細胞内病原体の顕微鏡検査も診断に役立つことがある。弁組織や血液・血清から特異的 DNA や 16S リボソームRNAを回収する分子技術は、特定の症例に有用である。その他の検査法も報告されているが (表 1)、広く利用できるものではない。
心エコー検査 (echocardiography) は診断の血液培養に次いで重要な検査であり、IE が疑われるすべての患者に実施すべきである。経胸壁心エコー(transthoracic echocardiography: TTE)により、多くの患者で植生の描出が可能である(図 5)。
図 5. 感染性心内膜炎の画像検査
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5240923/figure/F5/
TTE の感度はまちまちであり 、三尖弁と肺動脈弁が胸壁に近接しているため、右心系の IE の方が感度が高い。経食道心エコー検査 (Transoesophageal echocardiography: TOE) は、特に人工弁がある場合に、疣贅やその他の IE の心臓内病変の検出において、TTE よりも感度が高い。したがって、TTE と TOE は補完的な画像診断法と考えるのが最もよい。
2015 年の欧州心臓病学会 (European Society of Cardiology: ESC) と 2015 年の米国心臓協会 (American Heart Association: AHA) の両ガイドラインは、IE が疑われるすべての症例に対して心エコー検査を推奨し、TTE が陰性であっても IE の疑いが残る症例に対しては TOE を推奨している。これらのガイドラインは、TTE が陽性の患者における TOE に関しては異なっている。このような場合、ESC のガイドラインでは、膿瘍や瘻孔のような弁膜の局所合併症を検出するために、ほとんど全ての症例でその後の TOE を推奨している。対照的に、AHA ガイドラインでは、TTE が陽性の患者については、そのような合併症のリスクが高いと考えられる場合にのみ TOE を推奨している。肥満患者や人工弁を装着している患者など、画像診断が困難な患者には TOE が適切な初回検査となることもあるが、比較的簡便であるため、TTE が最初に実施されることが多い。
さらに、心エコー検査のタイミングも重要である。心エコー検査所見は経過の初期には陰性となることがある。従って、最初の心エコー検査が陰性であっても IE の疑いが強い患者には、数日後に心エコー検査を繰り返すことが推奨される。術中 TOE は局所合併症の同定に役立つので、手術を必要とする全ての IE 症例に推奨される。S.aureus 菌血症の患者は、IE の頻度が高いため、心エコー検査を受けるべきである。1. 永久的な心臓内デバイスを留置されておらず、2. 初回の血液培養後 4 日以内のフォローアップ血液培養で陰性が確認されており、3. 血液透析が行われておらず、4. 菌血症の院内感染があり、5. 二次的な感染病巣がなく、6. IE の臨床的徴候がない、注意深く選択された少数の患者においては疣贅の検索は TTE で十分である。IE のリスクが高い黄色ブドウ球菌菌血症患者と低い患者を区別するために、いくつかのスコアリングシステムが提案されているが、前向きに評価されたものはない。
他の画像診断法についても IE 診断の補助のために評価されている。たとえば、3D TEE、心臓 CT、心臓 MRI(図 5 および補足動画)、18F-フルオロデオキシグルコース PET-CT(図 5)などがある。複数の画像検査の併用は、相加的な利点が証明されれば、将来的に増加する可能性が高く、2015 年の ESC ガイドラインでは、これらの画像検査を人工弁 IE の診断アルゴリズムに組み込んでいる。
7. 診断基準
オリジナルの Duke 基準とその後修正された Duke 基準は、IE に対して感度と特異性の両方を持つ現在のゴールドスタンダードである。オリジナルの Duke 基準は、地理的、臨床的に多様な集団を対象とした複数の研究で評価され、その高い感度と特異性が確認された。
修正されたデューク基準は、IE が疑われる患者を、主要な基準および/またはマイナーな基準に基づいて、「確診」、「疑い」、「否定」の 3 つのカテゴリーに分類する (Box 1)。
Box 1. 修正 Duke 基準
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5240923/#BX1
微生物学的基準は主要な基準であり、典型的な IE を引き起こす病原体による菌血症が診断上重視される。IE との関連性が弱い細菌については、持続的に血液培養が陽性であることが必要である。第二の主要な基準は、心エコー検査や新しい弁逆流の所見によって示される心内膜の病変の証拠である。小基準としては、心臓の基礎疾患や注射薬の使用、発熱、血管現象、免疫学的現象、または大基準を満たさない微生物学的証拠がある。
従って、IE は単一の症状、徴候、検査に基づいて診断することはできない。むしろ、診断には臨床的に疑われることが重要であり、一般的には、危険因子を持つ患者の全身疾患によって疑い、その後、修正 Duke 基準に従って評価される。Duke 基準は元来、疫学的および臨床的研究を容易にするために開発されたものであり、臨床現場への適用は容易ではないことは覚えておく価値がある。患者の病像は多様であるため、基準の適用に加えて臨床的判断が必要となる。
新しい微生物学的手法や画像診断手法のエビデンスが得られれば、基準はさらに修正される可能性がある。2015 年の ESC 診断アルゴリズムでは、修正された Duke 基準によって人工弁 IE の「疑い」または「否定」とされたが、IE の疑いが高いという困難な状況に対して、追加的な画像検査(心臓 CT、PET-CT、白血球標識単一光子放射断層撮影 [leukocyte-labelled single-photon emission CT] など)が取り入れられている。
8. 予防
IE の死亡率が高いことから、リスクのある患者における IE の発生を予防する取り組みが行われてきた。VGS は正常な口腔内常在菌であり、IE 症例の約 20%を引き起こす。そのため、口腔衛生に焦点を当てる予防的対策が行われてきた。歯科治療が基礎心疾患を持つ患者の IE につながる可能性があるという仮定に基づき、AHA や他の主要な学会のガイドラインは以前、歯科治療を受けた基礎心疾患を持つ患者の IE を予防するために予防的抗菌薬投与を推奨していた。しかし、最近では、この推奨に疑問が呈されている。現在では、一過性の菌血症は歯磨き、歯間掃除、咀嚼などの通常の日常生活でよく見られるという十分な証拠があり、抗菌薬による予防の有効性は不明である。以前の指針とは異なり、2002 年のフランスの IE 予防ガイドラインは、歯科予防の適応を劇的に減少させた最初のものであった。2007 年の AHA ガイドラインでは、歯科予防が妥当であると推奨される心臓疾患の範囲を、人工弁または人工弁材料を有する患者、IE 既往患者、先天性心疾患を有する患者、および心臓弁膜症を発症した心臓移植レシピエントの 4 つの臨床的シチュエーションに限定した。消化管や泌尿生殖器の治療に対する予防はもはや推奨されていない。ESC のガイドラインでも同様に、IE の発症リスクが最も高い人にのみ歯科予防薬の使用が推奨されている。2008 年に発表された英国国立医療技術評価機構 (British National Institute for Health and Clinical Excellence: NICE) の勧告はさらに厳しく、歯科、消化器、泌尿生殖器、呼吸器治療に対して IE 予防を行わないことを推奨している。
2008 年の NICE ガイドライン以降、英国では歯科治療前の抗菌薬予防投与が 78.6%減少した。ガイドライン発表後 2 年間のフォローアップデータでは、IE 症例や死亡の有意な増加は見られなかった。改訂された AHA とフランスのガイドラインの導入後にも、同様に信頼できるデータが報告されている。しかし、AHA ガイドラインの遵守率が低いため、米国におけるこれらの結果の解釈は複雑である。
近年、追跡調査期間が延長されたことに伴い、懸念が高まっている。イングランドで 2013 年まで追跡調査期間を延長したところ、IE 症例数は予測された過去の傾向よりも大幅に増加したようであり、以前の予防投与率が継続した場合に予想された症例数よりも、1 ヶ月あたり 35 症例増加したと推定された。この増加は、AHA と ESC のガイドラインで定義されている全てのリスクカテゴリーの患者で見られた。しかし、この研究には細菌別のデータが含まれていなかったため、この増加が VGS によるものなのか(歯科予防によって予防できた可能性がある)、それとも黄色ブドウ球菌のような他の病原体によるものなのかを判断することはできなかった。その後、米国では、NIS(Nationwide Inpatient Sample)データベースに登録された 457,052 件のIE に関連した入院を後ろ向きに検討した結果、新ガイドラインの発表後、IE による入院率が全体的に、また「溶連菌」に分類された菌による入院率も増加し、英国と同様の傾向があることが示唆された。しかし、連鎖球菌のカテゴリーには腸球菌も含まれており、連鎖球菌性 IE の明らかな増加は、腸球菌性 IE 率の上昇によるものかもしれないと指摘されている。
現在までに、少なくとも 9 件の集団ベースの研究で、ガイドライン変更前後の IE 発生率が調べられている(表 2)。
表 2. ガイドライン変更前後の感染性心内膜炎の罹患率を検討した疫学研究
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5240923/table/T2/
これらのデータを総合すると、抗菌薬の予防には有効性とリスク(抗菌薬に関連した有害事象)の両方があることが示唆される。重要なことは、入手可能なエビデンスはすべて観察コホートから得られたものであり、微生物学的データは不正確であるということである。さらに、たとえ IE 発生率がガイドラインの変更後に増加したとしても、因果関係を立証することはできない。予防の有効性を評価する前向き無作為化比較試験は、少なくとも過去 25 年間実施されていない。2015 年に行われた 2008 年以前のガイドラインの見直しにおいて、NICE は以前の勧告を何ら変更せず、予防薬と予防薬なしを比較する無作為化試験の必要性を改めて強調した。
歯科予防に加え、血管内カテーテル関連菌血症の予防に努めることも、医療関連 IE の発生率を低下させる可能性がある。手指衛生の徹底、中心静脈カテーテル挿入時のフルバリアプレコーション (full barrier precaution) の適用、クロルヘキシジンによる皮膚の洗浄、可能であれば鼠径部からの中心静脈カテーテル挿入を避ける、不要なカテーテルの抜去などからなるケアバンドル (care bundle) やチェックリストなどの質改善介入によって、細菌血症発生率は低下する。しかし、これらの介入が IE 発生率に与える影響についての確証データは得られていない。
9. 治療
現代では、IE の治療には通常、少なくとも感染症専門医、循環器専門医、心臓外科医を含む集学的チームが必要である。すべての患者は抗菌薬治療を受けるべきであり、一部の患者には心臓血管外科的治療が有効である。
9-1. 抗菌薬療法の一般原則
抗菌薬療法の第一の目的は感染を根絶することである。疣贅には、1. 細菌密度が高い(「接種効果 [inoculum effect]」とも呼ばれる)、2. バイオフィルムにおける細菌の増殖速度が遅い、3. 微生物の代謝活性が低いなど、問題となるいくつかの特徴がある。その結果、殺菌性(または殺真菌性)薬剤による非経口療法の長期コースが一般的に必要となる。
9-3. 治療期間
治療期間は、疣贅内の微生物を完全に根絶するのに十分でなければならない。疣贅内への抗菌薬の浸透性が悪く、一般的に使用される薬剤(バンコマイシンなど)の殺菌作用が緩徐であるため、通常、抗菌薬の長期投与が必要となる。殺菌作用が急速な場合は、より短期間の投与が可能である。例えば、ペニシリンまたはセフトリアキソンとアミノグリコシドとの併用療法は、VGS 関連 IE に対して相乗効果を発揮し、感受性株に対して 2 週間という短期間の投与が可能である。右心系の疣贅では細菌密度が低い傾向があり、より短期間の治療が可能である。
抗菌薬療法の期間は、一般に血液培養が陰性となった最初の日から計算される。血液培養は、血流感染が消失したことが証明されるまで、24-72 時間ごとに行うべきである。手術弁組織培養が陽性の場合は、抗菌薬投与期間は心臓血管外科手術をした日を最初の日として決めるべきである。
9-3. 適切な抗菌薬の選択
治療は、血液培養または血清学的検査で同定された細菌を対象とすべきである。微生物学的結果を待つ間、疫学的および患者背景に基づいて経験的治療を行う。ほとんどの IE 症例はグラム陽性菌が原因であるため、バンコマイシンはしばしば適切な選択となる。しかし、地域の微生物学と感受性パターンによっては、他の経験的治療薬も適切な場合がある。特定の病原体に対する抗菌薬治療の詳細な推奨は、最近の治療ガイドラインで包括的に扱われている。主なポイントを表 3 にまとめた。
表 3. 感染性心内膜炎の病原体特異的治療
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5240923/table/T3/
9-4. 人工弁および植え込み型心臓デバイスがある場合の考え方
人工弁感染性心内膜炎(native valve infective endocarditis: NVIE)の治療期間は 2 週間から 6 週間であるのに対し、人工弁感染性心内膜炎(prosthetic valve infective endocarditis: PVIE)の治療期間は通常 6 週間である。NVIE と PVIE に対する抗菌薬は通常同じであるが、ブドウ球菌性 PVIE に対してはリファンピン (rifampin) とゲンタマイシン (gentamicin) の追加が推奨される。
心臓植込み型電子機器(ペースメーカーや除細動器など)の感染は、弁膜の IE を伴う場合と伴わない場合がある。感染が、デバイスのリードのみ(これは「リード心内膜炎」と呼ばれることもある)、弁のみ、またはその両方に関与していると思われるかにかかわらず、デバイスとリードの完全な除去が推奨される。心臓デバイス感染に対する最適な抗菌薬治療期間を示す臨床データは限られており、リード心内膜炎に対しては弁膜症 IE と同じ抗菌薬を用いて少なくとも 4-6 週間が推奨される。
元論文
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5240923/