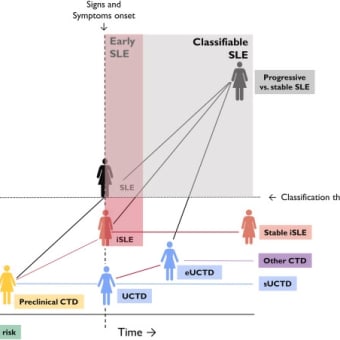パーキンソン病
N Engl J Med 2024; 391: 442-452
パーキンソン病 (Parkinson's disease) の世界的な負担は、高齢者の数と割合の増加に伴い、今後数十年で増加すると予測されている。この総説では、本疾患が最後に本誌に掲載された 1998 年以降の研究の進展を取り上げ、臨床実践に関連する最近導入された概念も紹介する。2 世紀にわたり、パーキンソン病は、安静時振戦 (resting tremor) 、固縮 (rigidity)、姿勢反射障害 (postural reflex impairment) を伴う寡動 (bradykinesia) という特徴的な運動症候群に基づいて臨床的に診断されてきたが、これらはすべて主に黒質系 (nigrostriatal system) におけるドーパミン作動性機能障害 (dopaminergic dysfunction) の結果である。本総説では、パーキンソン病の臨床的定義を用いる。
キーポイント
·パーキンソン病は老年期にみられる進行性の神経疾患であり、臨床的には運動障害(非対称性の寡動、固縮、振戦、平衡障害 [imbalance])により定義され、病理学的にはドーパミン作動性脳幹ニューロンを含む中枢および末梢神経系の特定領域における神経細胞の変性および神経細胞内のミスフォールディング α-シヌクレイン(α-synuclein, レビー小体 [Lewy bodies])により定義される。
·しばしば気分、睡眠、感覚、認知、自律神経機能の障害を認め、多くの場合、運動徴候に数年先行し(前駆期パーキンソン病 [prodromal Parkinson's disease])、罹病期間とともに増加する。
·約 20%の症例で遺伝子変異が原因である。リスクを増加させる非遺伝的危険因子(毒物や頭部外傷)に加え、寄与の小さい一般的な遺伝的バリエーションが、おそらくほとんどの症例の原因である。運動はリスクを減少させる可能性がある。
·進行を遅らせる治療法は証明されていない。ドパミン作動性療法は運動機能を改善するが、効果の減弱と副作用が多い。脳深部刺激手術 (deep-brain stimulation surgery) は運動機能の変動に有効である。
·非運動症状はかなり頻度が高いが、治療に関するエビデンスは乏しい。一般的に適応外の薬物が使用されている。包括的な集学的治療が有用である。
·バイオマーカー研究から、パーキンソン病の生物学的定義が可能であることが示唆されている。
疫学
パーキンソン病の罹患率および有病率は年齢とともに増加し、男女比は約 2:1 である。さまざまな研究において、罹患率は 45 歳以上の人口 10 万人あたり 47-77 例、65 歳以上の人口 10 万人あたり 108-212 例である。パーキンソン病の罹患率は、一般的に白人では黒人やアジア人よりも高いが、後述するパーキンソン病の特徴である剖検時に検出されるレビー小体の頻度は、黒人でも白人でも同程度である。年齢と性別で調整した死亡率は約 60%と推定されており、一般集団の死亡率よりも高い。米国におけるパーキンソン病の経済的負担は、2017 年の 520 億ドルから 2037 年には 790 億ドルに増加すると予測されている。
パーキンソン病の診断
依然として、ドパミン作動性ニューロンの喪失に起因するパーキンソン病の運動障害が診断の基礎ではあるが、パーキンソン病は多系統の神経疾患である。非運動症状としては、睡眠障害、認知障害、気分や感情の変化、自律神経機能障害(便秘、泌尿生殖器障害、起立性低血圧)、感覚症状(嗅覚障害 [hyposmia]、疼痛)などがある。非運動症状、特に嗅覚障害と急速眼球運動(rapid-eye-movement: REM)睡眠行動障害 (REM 睡眠中の正常なアトニー (atony, 筋弛緩) の消失と、走ったり暴れたりするような四肢運動を特徴とする) は、運動症状の発現より何年も前に発症することが多く、このことはこのような症状が前駆症状である可能性を示唆している。
国際パーキンソン病・運動障害学会 (the International Perkinson and Movement Disorder Society) は、パーキンソン病の臨床診断基準および前駆期パーキンソン病の研究診断基準を発表している。どの画像技術もパーキンソン病の診断を確定することはできないが、線条体ドパミン系の可視化(主に 123I-ioflupane 単光子放出コンピュータ断層撮影法[single-photon-emission computed tomography: SPECT]または 18F 標識フルオロドパ陽電子放出断層撮影法 [18F-labeled fluorodopa positron-emission tomography] を使用)によって、パーキンソン病と本態性振戦などの疾患を鑑別することができる。123I-ioflupaneSPECT 画像の感度と特異度は 90%以上であり、システマティックレビューでは、これらの技術の使用により、研究参加者の 31%で診断が変更され、54%で管理が変更されたことが示されている。
脳の磁気共鳴画像法(magnetic resonance imaging: MRI)は、パーキンソン症状を伴う他の神経変性疾患(進行性核上性麻痺 [progressive supranuclear palsy] や多系統萎縮症 [multiple-system atrophy] など)に特徴的であるが、パーキンソン病とは異なる大脳基底核 (basal ganglia) や脳底構造 (infratentorial structures) の変化を同定することができる。
剖検では、臨床的に診断されたパーキンソン病症例の最大 90%に、ミスフォールディングした α-シヌクレインタンパク質の神経細胞内蓄積(レビー小体およびレビー神経突起 [Lewy neurites]、総称して「レビー病理 (Lewy pathology)」)が認められる、 脳幹核 (brain-stem nuclei)(迷走神経背側運動核 [dorsal motor nucleus of the vagus]、青斑核 [locus coeruleus]、黒質)、末梢自律神経領域 (periferal autonomic region(腸管神経叢 [myenteric plexus]、交感神経節 [sympathetic ganglia]、皮膚自律神経系 [skin autonomic nervous system])、大脳辺縁系 (limbic system) および新皮質領域 (neocortical region) に選択的に影響を及ぼす。 色素性ニューロン (pigmented neuron)、特にドーパミンを産生する黒質ニューロンの消失も、この疾患の非常に特徴的な特徴であると考えられている。
臨床診断基準は依然として有用であるが、限界もある。あるコホートでは、臨床診断と剖検所見との一致率は、初診時にはわずか 28%であったが、罹病期間が長くなるにつれて 89%まで上昇した。診断と死後所見の一致は、運動障害の専門家による診断であった場合に最も可能性が高い。
原因
パーキンソン病は、遺伝的因子と非遺伝的因子の両方から生じる複数の原因があると考えられている。パーキンソン病患者の約 20%(monogenic Parkinson's disease, 単一遺伝子変異によるパーキンソン病 )において、大きなエフェクトサイズを有する遺伝子変異が同定されている。不完全浸透性の常染色体優性パーキンソン病には、LRRK2 の変異(全症例の約 1-2%、家族性症例の最大 40%に存在する)、グルコセレブロシダーゼ (glucocerebrosidase) をコードする GBA1 の変異(症例の 5-15%に存在し、アシュケナージ系ユダヤ人または北アフリカの祖先を持つ集団に最も多い)、さらに少ない VPS35 および SNCA の変異(症例の 1%未満に存在する)が含まれる。
グルコセレブロシダーゼ変異はゴーシェ病の原因
https://www.shouman.jp/disease/details/08_06_090/
アシュケナージ系ユダヤ人
https://www.natureasia.com/ja-jp/research/highlight/9440
劣性遺伝性のパーキンソン病のバリアントには、PRKN、PINK1、DJ1 があり、若年で発症する症例のほとんどを占めている。いずれのバリアントも頻度は低いが、集団によっては最も一般的な遺伝的原因となっている。異常 α シヌクレインは、SNCA または GBA1 に関連するパーキンソン病、および LRRK2 に関連する症例の約半数に認められるが、劣性変異に関連するパーキンソン病ではまれである。
ゲノムワイド関連研究 (genomewide association study) では、独立効果 (independent effect) の小さい 90 以上の遺伝的リスク座位 (genetic risk loci) が同定されており、その多くは上記の原因遺伝子の近くに位置している。世界的な取り組みが拡大するにつれ、新たな遺伝的関連が同定されるかもしれない。例えば、アフリカ系祖先のパーキンソン病症例の 39%を占める GBA1 の新規変異が報告されている。
パーキンソン病の強力な遺伝的危険因子がない場合、遺伝率は 20-30%と推定される。リスク因子の同定は、特定の集団における観察に限られており、いくつかの種類のバイアスの影響を受ける。遺伝的リスクに関する研究とは対照的に、ほとんどの疫学研究ではいくつかの危険因子しか調査されていない。一般的に人は生涯を通じて多くの潜在的な暴露を受けており、現在知られていることから判断すると、単一の因子ではなく、複数の非遺伝的因子への曝露と遺伝的感受性の組み合わせがリスクを決定していると考えられる。さらに、環境や生活習慣に関連するリスクの多くは、容易に測定することができない。この分野の研究はほとんどすべて、ヨーロッパと北米の集団を対象としている。
農薬(パラコート [paraquat]、ロテノン [rotenone]、2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 [2, 4-dichlorophenoxyacetic acid] 、いくつかの有機塩素および有機リン酸塩など)や塩素系溶剤(トリクロロエチレン [trichloroethylene]、パークロロエチレン [perchloroethylene] など)への家庭内または職業上の曝露は、ほとんどの研究で、用量依存的な 40%以上のパーキンソン病リスクと関連している。基礎研究では、これらの毒性物質は、例えばミトコンドリア機能を阻害することにより、選択的なドーパミン作動性ニューロンの損失、運動機能障害、その他の変化を引き起こすなど、パーキンソン病の実験的類似症状を引き起こす可能性がある。あるプロスペクティブ・コホート研究では、乳製品の多量摂取は、パーキンソン病の臨床的または病理学的診断リスクの上昇、および有機塩素系農薬であるヘプタクロル (heptachlor) の脳内濃度の上昇と関連しており、これはおそらく牛乳中のこの化合物の生体濃縮に起因している。
すべての研究ではないが、軽度から中等度の頭部外傷と、数十年後のパーキンソン病またはレム睡眠行動障害の発症との関連を示した研究もあり、疾患リスクは 31%から 400%以上増加した。喫煙、カフェイン摂取、身体活動の増加はパーキンソン病のリスク低下と関連している。遺伝子変異に関連するメカニズムの研究や有害物質曝露の実験により、炎症、免疫調節障害、酸化ストレス、ミトコンドリア機能障害、タンパク質凝集、オートファジー障害、エンドライソゾームシステムの機能障害など、遺伝性疾患や散発性疾患に共通する異常が同定されている。
自然経過および臨床経過
運動緩慢および振戦の症状は非対称的である傾向がある。最終的には、両側性の寡動、硬直、振戦、歩行障害、平衡障害により、機能障害や自立の喪失に至るが、多くの場合、運動機能と認知機能の低下、転倒、骨折が複合的に影響する。進行の時間的経過は非常に多様である。起立性低血圧、消化管運動障害、排尿障害、勃起障害、体温調節障害などの自律神経異常は早期に発症し、進行することが多い。
視空間障害や遂行機能障害などの認知機能の変化は、時に運動症状に先行する自覚症状であることがあり、パーキンソン病の進行に伴って神経心理学的検査によって同定することができる。レビー小体型認知症は、主に認知機能と幻覚などを精神医学的特徴とし、パーキンソニズムも認める。臨床的にパーキンソン病と診断された症例の約 38%、レビー小体型認知症の症例の 89%がアルツハイマー病に関連した病理学的特徴を有している。
疾患進行の特徴的なパターンを有する臨床的サブタイプを同定することについては、集団間で再現性が得られていない。臨床的パーキンソン病のサブグループを生物学的特徴付けられれば、個々の予後予測や患者カウンセリングを改善できると期待される。例えば、認知機能の低下は、GBA1 の変異を有する患者では一般的であるが、PRKN の変異を有する患者ではまれである。
治療
定期的な運動、健康的な食事、質の高い睡眠、および有害な曝露の回避は、死亡率の低下と関連しており、どのような段階のパーキンソン病患者にも勧められるアドバイスである。例えば、モノアミン酸化酵素 B(monoamine oxydase B: MAO-B)阻害薬の初期試験は有望であると考えられたが、その後の研究では、症状に対する効果とは独立した保護効果は示されなかった。パーキンソン病と診断された後に登録された、疾患の進行を遅らせる治療法の試験は、疾患の初期段階でも黒質ドーパミン作動性ニューロンの 75%までが機能を失っているため、失敗した可能性がある。α-シヌクレイン凝集体を除去するメカニズムに焦点を当てた臨床試験は結果は一致していない。GBA1 または LRRK2 の病原性変異体を有する遺伝的に定義された亜集団を対象とした臨床試験でも同様に結果は一致していない。
パーキンソン病は人によって症状や経過が異なるため、最良の結果を得るためには症状管理を個別に行う必要がある。患者の意見を聞き、神経科医、精神保健専門家、神経外科医、理学療法士、作業療法士、言語療法士などを含むチームによる集学的アプローチを早期に導入することが理想的である。患者、家族、介護者のニーズは、アドバンス・ケア・プランニングや、重症例ではホスピスへの紹介も含めて、定期的に再評価されるべきである。
薬物療法
運動症状
レボドパの経口製剤は運動症状に対する主な治療法である(表 1)。
表 1. パーキンソン病の運動障害に対する薬物治療
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra2401857?logout=true#t1
レボドパ投与後の効果持続時間(「オン」時間)は、通常数時間であるが、平均して 4 年後に短縮し始める。"オン "時間には症状軽減効果が減弱する時間("オフ "時間)が散在する。この薬効変動は、おそらくレボドパの半減期の短さ、消化管吸収の不安定さ、ドパミン作動性ニューロンの進行性変性によるものであろう。このような変動に対処するために、総投与量の増加、投与頻度の増加、徐放性製剤の追加や切り替えなどの戦略がしばしば用いられる。一般的な用量依存性の副作用には、ジスキネジー (dyskinesia)(hyperkinetic involuntary movements, 運動亢進性不随意運動)、幻覚や行動異常の発現または悪化、起立性低血圧、嘔気などがある。
運動症状やその変動を改善する他の戦略としては、レボドパよりも半減期が長いという利点があるドパミンアゴニストを単剤またはレボドパと併用する方法がある。ドパミンアゴニストは副作用の特性が好ましくないため、現在では以前ほど使用されていない。副作用には用量依存性の嘔気、傾眠、睡眠発作、衝動制御障害、末梢浮腫などがある。レボドパの効果は、シナプスのドパミン代謝を阻害するカテコール-O-メチルトランスフェラーゼ(catechol-O-methyltransferase: COMT)阻害薬や MAO-B 阻害薬を追加することで増強することができる。アマンタジンやイストラデフィリンなどの非ドパミン作用薬も、併用療法として用いると、運動変動を改善し、ジスキネジアを軽減することがある。振戦を標的とする抗コリン薬は、高齢者では認知機能の悪化を引き起こす可能性があるため、以前よりも使用されることが少なくなっている。
重度または頻度の高い「オフ」エピソードに対するドパミン作動性療法のオンデマンド戦略としては、アポモルヒネ (apomorphine) の皮下注射や舌下投与、レボドパの吸入などがある。
アポモルヒネ
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/series/drug/update/201206/525192.html
レボドパの持続経腸投与(空腸内ポンプ)、アポモルヒネの皮下投与、レボドパの皮下投与(皮下ポンプ)もパーキンソン病の進行例で用いられている。
非運動症状
前述したように非運動症状はパーキンソン病の負担に大きく寄与しているが、治療の指針となるエビデンスに基づいた研究は不足しており、適応外の薬剤の使用が一般的である(表 2)。
表 2. 非運動症状の治療
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra2401857?logout=true#t2
非運動症状の多くは、疾患の進行やドパミン作動薬治療により悪化する。パーキンソン病に関連した認知症は、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬やメマンチンによる治療で緩やかに減少する可能性があるが、国際パーキンソン病・運動障害学会が行ったエビデンスに基づくレビューによると、臨床的に有用と分類されているのはリバスチグミン (rivastigmine) だけである。うつ病と不安症は、薬物相互作用とセロトニン症候群の発症の可能性に注意しながら、選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (selective serotonin reuptake inhibitor)、選択的セロトニン・ノルエピネフリン再取り込み阻害薬 (selective serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor)、またはあまり一般的ではないがドパミン作動薬 (dopamine agonist) で治療できる。幻覚や妄想などの精神症状は、ピマバンセリン (pimavanserin) や非定型抗精神病薬(クロザピン [clozapine] またはクエチアピン [quetiapine])で治療できる。
精神症状を有するパーキンソン病患者にピマゼンセリンは有用
https://www.carenet.com/news/journal/carenet/36684
その他のドパミン D2 受容体遮断作用のある抗精神病薬は、パーキンソニズムを悪化させる可能性があるため使用しない。認知行動療法とカウンセリングは、精神症状の管理に有用な非薬物療法である。
起立性低血圧を含む自律神経症状には、水分摂取量の増加、食塩摂取、弾性ストッキング、およびフルドロコルチゾン (fludrocortisone)、ミドドリン(midodrine)、ドロキシドパ (droxidopa) などの血圧上昇薬で対処できる。便秘は、食物繊維の増量、便軟化剤、または下剤で管理する。睡眠障害またはレム睡眠行動障害は、認知行動療法、メラトニン (melatonin)、または低用量クロナゼパム (clonazepam) で改善できる。
手術療法
脳深部刺激療法(deep-brain stimulation: DBS)では、通常は視床下核 (subthalamic nucleus) または淡蒼球 (globus pallidus) に細いリード線(片側または両側)を頭蓋内に留置し、延長リード線を介して鎖骨下の皮下に留置した神経刺激装置に接続する。効果の機序は不明であるが、疾患の主な運動機能の原因となる大脳基底核回路の機能異常の遮断が一因と考えられている。DBS の適応の決定、システムの植え込み、継続的な患者ケアと装置管理は、通常、専門施設で行われる。DBS 療法を受ける患者のほとんどは、薬物療法ではコントロールが不十分な運動変動があるため、この手技を行うことが正当化される。
DBS は QOL を改善し、運動機能の変動(「オン」時間の平均増加、1 日 3-4 時間)や薬物療法を行わない場合に生じる症状(薬物療法を行わない場合の UPDRS III [Unified Parkinson's Disease Rating Scale, part III] スコアの平均改善、30-50%)を緩和する。また、特に視床下核を標的とする場合は、刺激パラメータのプログラミングが患者の症状に最もよく対応するように最適化された後、薬物療法を減らすことができる(平均投与量 50%減)。最新の手技による手技リスク(脳卒中や感染など)の低さ、およびその有効性を考慮すると、DBS は運動変動が始まった時点で使用することが承認されている。運動器の有益性は最長 15 年間持続する可能性がある。
現在の DBS 神経刺激装置には、非充電式バッテリ(バッテリ寿命 3-5 年)または充電式バッテリ(バッテリ寿命 15 年以上)を備えたシングルチャネルおよびデュアルチャネルシステムがある。一部の DBS システムには、画像ベースのソフトウェアが搭載されており、標的とする脳構造に対するリードの位置関係を視覚化したり、組織活性化量をシミュレーションしたりして、プログラミングを容易にすることができる。DBS リードからの局所電位を測定できるセンシングシステムもプログラミングに役立ち、近い将来、神経細胞のフィードバック信号に基づいて刺激強度を調整する適応刺激が可能になるかもしれない。パーキンソン病の非運動症状(認知障害、気分変化、無気力、自律神経症状)と運動症状(平衡障害、すくみ足 [freezing gait])のほとんどは DBS を使用しても改善しないのが一般的であるが、将来的には神経活動のフィードバックによる刺激調節によってこれらの症状に対処できるようになるかもしれない。DBS の潜在的合併症には、ジスキネジア、言語、歩行、平衡障害の悪化などがある。まれに、標的外の刺激が気分、認知、行動の変化を引き起こすことがあるが、通常は DBS のプログラム変更で修正可能である。
加熱プローブによって直接病変に侵襲を加える古い手技(片側視床切開術または淡蒼球切開術)は、現在ではまれな症例にのみ用いられている。片側の視床腹側中間核をターゲットとした MRI ガイド下高周波集束超音波検査などの無切開病変アプローチは、パーキンソン病患者の振戦の治療に使用されるようになってきているが、このアプローチは時間の経過とともに効果が限られてくる可能性があり、パーキンソン病の他の症状を治療するものではない。また、視床下核や淡蒼球をターゲットにした治療も超音波検査で検討されている。
これまでに行われ、現在も進行中の遺伝子治療としては、神経栄養因子(グリア由来神経栄養因子 [glial-derived neurotrophic factor] とノイトリン [neurturin])の産生を高めるために、遺伝子を介したウイルスベクターを視床下部や黒質に定位注入する方法、運動回路を修正するために γ-アミノ酪酸を視床下核に投与する方法、ドーパミンの合成を増加させるために芳香族 l-アミノ酸脱炭酸酵素を視床下部に投与する方法などがある。これまでのところ、これらの治療法はいずれも規制当局の承認を得ていない。ドーパミンを産生する細胞を被核 (putamen) に移植する以前の試みは期待外れの結果に終わったが、ヒト人工多能性幹細胞 (human induced pluripotent stem cells) 、同種細胞 (allogeneic cells)、ヒト胚性幹細胞 (human embrionic stem cells) 由来の移植株を用いた新しいアプローチは現在も開発中である。これらのアプローチは、1 回きりの外科手術によって運動症状を改善し、薬物治療の負担を軽減することに重点を置いているが、安全性、実現可能性、有効性が証明されていないという課題に直面している。
今後の方向性
パーキンソン病の予防は、依然として研究の重要な焦点である。性別、人種、民族、経済状態、地理的な場所などによる既存の格差に対処する試みと、環境毒物への曝露を減らし、生活習慣を改善するための世界的な取り組みが必要である。特に研究が十分でない集団における遺伝子変異の同定は、新たな洞察をもたらすであろう。遠隔医療を含む技術の進歩は、医療へのアクセスを改善することができ、人工知能、デジタル評価、ウェアラブルデバイス、バーチャルリアリティによって、スクリーニング、モニタリング、治療が改善される日が来るかもしれない。異常 α シヌクレインのバイオマーカーは、臨床的に診断されたパーキンソン病、レビー小体型認知症、レム睡眠行動障害の患者を、健常対照者や他の神経疾患の患者と高い感度と特異度で区別できる。α-シヌクレインの検査により、神経細胞性 α-シヌクレイン疾患の早期発見が可能になる可能性があり、早期介入への道筋を示し、精密医療の基礎となるであろう。
結論
パーキンソン病は、進行性の運動症状および非運動症状を引き起こす。過去 20 年間における、本疾患のリスクと異なる表現型および病理学的提示をもたらす遺伝子変異の同定、バイオマーカーの特性化、内科的および外科的治療の洗練、ならびにライフスタイルの見直しの進歩により、本疾患患者の治療を個別化し、症状を軽減し、QOL を改善する枠組みが可能となった。
元論文
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra2401857