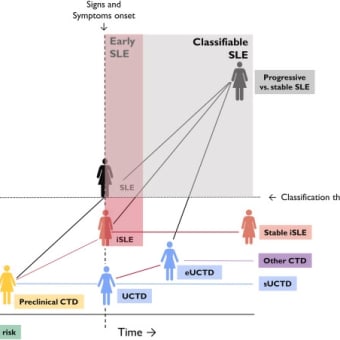脳卒中後の症候性てんかん
Drugs Aging 2021; 38: 285-299
脳卒中は高齢者におけるてんかん発作の主な原因である。大脳皮質に及ぶ脳卒中の範囲が大きく、重症であり、年齢が若く、急性期の症候性発作と脳内出血を有する患者では、脳卒中後のてんかん発症リスクが高い。SeLECT スコアや CAVE スコアなどの予後予測モデルは、てんかん発症リスクを評価するのに役立つ。初期の脳波や血液検査のバイオマーカーは、脳卒中後てんかんの臨床的危険因子に追加の情報を提供する。脳卒中後の急性発作と慢性期の症候性発作の管理は著しく異なる。理想的な抗てんかん薬の選択は、有効性だけでなく、副作用、高齢者における薬物動態の変化、基礎疾患である血管合併症への影響も考慮する必要がある。薬物間相互作用、特に抗てんかん薬と抗凝固薬や抗血小板薬との相互作用も治療決定に影響を及ぼす。本総説では、脳梗塞または脳出血後のてんかん発作の疫学、危険因子、バイオマーカー、管理について述べる。患者の年齢、併存疾患、併用薬、脆弱性に起因する脳卒中後の症候性てんかんの治療に必要な特別な配慮について述べる。
キーポイント
·脳卒中後のてんかん発作のリスクを評価するために、臨床的特徴、画像所見、脳波所見、血液バイオマーカーを予後予測モデルに統合することが考えられる。
·脳卒中後てんかんの治療は、年齢、併存疾患、併用薬による薬物動態の変化を考慮し、個別化する必要がある。
·高齢者は抗てんかん薬による副作用を受けやすい可能性があるため、発作のない人では抗てんかん薬の減量または中止を考慮すべきである。
はじめに
脳卒中は、高齢者におけるてんかん発作の原因として最多である。脳卒中後のてんかんは、年間 300-600 万人の脳卒中患者の約 6%に発症する。
脳卒中直後の発作は、代謝ストレスの増大と細胞死を引き起こし、梗塞サイズの増大、死亡率の上昇、機能的転帰の悪化を引き起こすことがある。
発作の再発は、外傷の原因となり、認知や労働・自動車運転能力に影響を及ぼし、生活の質を低下させることがある。
脳卒中後の発作をいつ、どのように治療するかを決定する際には、年齢、併存疾患、併用薬、脳卒中生存者の一般的脆弱性を考慮しなければならない。
ここでは、脳梗塞または脳出血後の発作の疫学、危険因子、バイオマーカー、管理について概説する。
脳卒中後の発作は、急性 (acute) 発作と遠隔症候性(remote symptomatic) 発作に二分される。
急性症候性発作(「早期 (early)」発作とも呼ばれる)は、梗塞後 7 日以内に起こり、脳卒中の毒性(? toxic) または代謝作用によって誘発されると考えられている。
遠隔症候性発作(「晩期 (late)」発作とも呼ばれる)は、脳卒中後 1 週間以上経過してから起こる誘因のない発作である。
急性症候性発作の後に誘発のない発作が起こるリスクは約 30%であり、急性症候性発作は再発リスクが高くないことからてんかんとはみなされない。対照的に、脳卒中後の遠隔症候性発作は その後の非誘発性発作のリスクは 60%以上であり、てんかんと診断するには十分である。
疫学
脳卒中の大部分は 45 歳以上の成人に起こる。脳卒中の最大 90%は脳梗塞で、残りは脳出血である。脳卒中は、高所得国における後天性てんかんの最も多い病因である。
脳卒中後のてんかんのリスク推定は広く研究されており、研究方法によって異なる。一般集団では、大規模コホートの前向き追跡調査や登録ベースの研究が最も代表的な推定値を提供している。脳卒中後のてんかん発症率は 6.4%であり、ロンドン(英国)の集団ベースの研究でも、スウェーデンの全国規模の登録研究でも認められた。
一般的に若年患者やより重症の脳卒中を治療している大学病院の単一施設研究では、その後のてんかんの累積発生率は、特に血栓溶解療法を受けた重症患者では 15%を超えることがある。
脳出血後のてんかん発症率は 12%強である。
脳卒中後てんかんのリスクは、脳卒中後数年で最も高くなる。てんかんを発症した患者の約 85%が、脳卒中後 2 年以内に最初の遠隔症候性発作を経験している。
急性期の症候性発作の疫学はあまりよく分かっていない。急性発作は脳梗塞患者の 1-4%で観察されるが、脳出血患者では最大 16%まで観察される。
危険因子、画像診断、予後予測モデル
脳卒中後てんかんの危険因子として一貫して同定されているのは、急性症候性発作、皮質病変、脳卒中の重症度と病因、若年、脳卒中のタイプ(出血性か虚血性か)である。同様に、メタアナリシスでは、脳卒中後のてんかんリスクを増加させる要因として、急性症候性発作、皮質病変、出血が明らかにされた。
脳卒中後のてんかん発作リスクに影響を及ぼす併存疾患に関するエビデンスは一貫していない。糖尿病、脂質異常症、高血圧、末梢感染症、うつ病、認知症を有する患者では、血管てんかん (vascular epilepsy) のリスクが増加することを支持する結果もある。
脳梗塞後の再灌流療法 (reperfusion therapy) と急性および遠隔期の症候性発作との関係は、現在のところ不明である。いくつかの研究では、再灌流療法を受けた患者では痙攣発作のリスクが高いことが示唆されているが、関連性を認めなかった研究もある。大血管閉塞による脳卒中が重症であるほど再灌流治療を受ける可能性が高く、発作のリスクも高いため、これらの研究では治療選択による交絡の可能性がある。
脳卒中後のてんかん発症の画像バイオマーカーについては、ほとんど知られていない。これまでのところ、ヒトのてんかん発症を予測するのに役立つと証明された特定の画像所見はない。脳卒中後のてんかん発症リスクに関するいくつかの手がかりは、磁気共鳴画像やコンピュータ断層撮影(computed tomography: CT)スキャンから得ることができる。
脳卒中発症リスクの手がかりとなる画像所見
·大脳皮質の病変は、その後のてんかん発作と高い関連性がある。
·皮質下脳卒中は脳卒中後てんかんのリスクを増加させない。
·発作は、梗塞または出血が前方循環、特に中大脳動脈 (medial cerebral artery) 領域に及ぶ場合に最もよくみられる。
·脳梗塞が脳底構造のみを侵す場合は発作はまれである。
·病変の大きさが 70 mL 以上であれば、発作を起こす確率は 4 倍になる。
これらの危険因子の多くはルーチンの検査で入手可能であり、これらを組み合わせることで、脳卒中後のてんかん発症の全体的なリスクを予測することができる。SeLECT(図 1)と呼ばれる予後予測モデルは、虚血性脳卒中後のてんかん発症リスクを正確かつ確実に予測できることが示されている。このモデルには 5 つのパラメータが含まれる: 脳卒中の重症度、大動脈アテローム性動脈硬化の病因、初期のてんかん発作、皮質病変、中大脳動脈病変の領域である。SeLECT スコアが最高(9 点)の場合、脳卒中後 5 年以内のてんかんリスクは 80%を超える(図 1)。このモデルは「SeLECT score」アプリとしてApple AppStoreおよびGoogle Play Storeで入手可能である。
図 1. SeLECT スコアを用いた脳卒中後の遠隔症候性発作の予測
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8007525/#Fig1
CAVE スコア(図 2)は、脳内出血後の発作リスクを予測するために開発されたもので、病変が皮質に及んでいるか、年齢、血腫量、急性症候性発作の因子を含んでいる。CAVE スコアが最高(4 点)の場合、後に発作が起こる危険性は 46%である。
図 2. CAVE スコアを用いた脳出血後の遠隔症候性発作の予測
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8007525/#Fig2
これらのスコアは、脳卒中生存者を脳卒中後てんかん発症の低リスク群と高リスク群に層別化し、目標に沿ったフォローアップを行う上で有用である。これまでのところ、脳卒中後てんかんの一次予防に有効であると証明された治療法はない。これらのスコアは、一次予防治療の指針となるものではないが、抗てんかん薬の前向き研究のリクルートツールとして使用することができる。
後天性てんかんの動物モデルにおいて、抗てんかん薬(antiseizure medications: ASM)であるレベチラセタム (levetiracetam)、ブリバラセタム (brivaracetam)、エスリカルバゼピン (eslicarbazepine)、トピラマート (topiramate)、ガバペンチン (gabapentine)、プレガバリン (pregabaline)、ビガバトリン (vigabatrin) など、多様な適応で臨床使用されている多くの薬剤が抗てんかん作用を有することが報告されている。心的外傷後てんかんに対するレベチラセタムを除いて、これらの薬剤はいずれも臨床試験への応用を視野に入れた体系的な研究が行われていない。このことが、前臨床研究プロジェクトのほとんどが臨床応用に至っていないということの一因となっている。抗てんかん薬の臨床試験が行われていない主な理由の一つは、非選択的脳卒中コホートにおける脳卒中後てんかんのリスクが比較的低い(6%)ことであり、脳卒中後の妥当な観察期間(18-24 ヵ月)中に中等度の治療効果(50%減少)を示すためには、多数の患者(N = 1500)が必要となる。SeLECT スコアのようなツールは、脳卒中後の遠隔発作のリスクが少なくとも 20%以上あり、抗てんかん薬投与試験の対象となりえる集団を同定するために必要である(N = 400)。
脳卒中後の脳波
脳波(electroencephalogram: EEG)は時間分解能が高く、脳機能をリアルタイムで評価する上で重要であり、さまざまなてんかんやけいれんの原因を同定するためのゴールドスタンダードである。システマティックレビューとメタアナリシスでは、脳卒中後の脳波において、発作時てんかん性活動と発作間欠期てんかん性活動がそれぞれ 7%(95%信頼区間 [confidece interval: CI] 3-12)と 8%(95%CI: 4-13)の患者に認められた。長期脳波モニタリングが導入されれば、これらの値はさらに高くなる可能性がある。
集中治療室の環境では、発作が「非痙攣性」であることが多く、臨床的に発見できないことがある。このような環境での脳波モニタリングは、発作やてんかん状態の診断と治療に不可欠である。脳波モニタリングを受けている急性脳卒中患者のうち、てんかん活動は 17%の症例で検出される。脳梗塞では、11%に発作がみられ 、9%はもっぱら非けいれん性発作であり、7%は非けいれん性てんかん重積状態の基準を満たした。非けいれん性てんかん状態は、不良な転帰と死亡率の増加と関連している。ある前向き研究では、脳梗塞患者の 4%に非けいれん性てんかん状態を認めた。一方、臨床医は、脳波で非けいれん性てんかん状態を認めた症例の 40%において、てんかん活動を疑わなかった。このように、脳波の長期モニタリングは、発作が継続している典型的な臨床徴候のない患者でもてんかん重積状態を検出するのに役立つ可能性がある。
脳卒中病棟における脳波の有用性に関するデータは少ない。脳卒中病棟で発作を起こした患者の 5 分の 1 以上は、脳波上発作 (electrographic seizures) のみであった。前方循環の脳梗塞患者における急性期の症候性発作の 22.7%は、短時間の脳波検査により、脳波上発作のみであり、それ以外の方法では認識できなかった。一方、追跡脳波検査は、脳卒中後 1 年経過した患者の 1.7%に認められた部分てんかんの同定にも役立つ可能性がある。
脳卒中後てんかんの予測における早期脳波の有用性の検討は、臨床的な重要であるが、まだ十分に検討されていない。ある前向き研究では、脳卒中後 1 年後のてんかんの独立した予測因子として、脳卒中後早期の視覚的脳波 (visual EEG features) の特徴が同定された。脳波上の主な危険因子は、発作間欠期てんかん様活動を早期に認めることであった(図 3)。
図 3. 脳卒中後の患者の脳波所見
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8007525/#Fig3
著者らはまた、脳卒中後早期の脳波における周期性放電 (periodic discharges) の存在と、CT スキャンにおける梗塞内に保存された皮質の島の存在が、脳卒中ユニットにおいてより広範な、あるいは反復的な神経生理学的評価を必要とする患者の同定に役立つ可能性があることを提唱した。
特に画像診断で梗塞が認められない場合、早期脳波はてんかん発作と一過性脳虚血発作の鑑別診断にも役立つことがある。脳波がてんかん発作の臨床診断を支持することがあるのは、てんかん発作が疑われる症例の半数以下である。一過性脳虚血発作患者の 90%は脳波が正常であったのに対して、痙攣発作患者では特異的または非特異的な脳波異常を示すことがある。
血液バイオマーカーと遺伝子バイオマーカー
バイオマーカーとは、正常または病的な生物学的プロセスの特徴を客観的に測定したものと定義される。てんかん発症のバイオマーカーは、脳卒中後のてんかん発症の予測に役立つ可能性がある。
脳卒中による急性神経細胞障害(低酸素、代謝機能障害、脳全体の低灌流、グルタミン酸興奮毒性、イオンチャネル機能障害、血液脳関門 [blood-brain barrier: BBB] の破綻)は、神経炎症カスケードを誘発する。その結果、脳の損傷を修復するために複数の炎症メディエーターが放出される(損傷関連分子パターン [damage-associated molecular patterns: DAMPs]、サイトカイン、ケモカイン、補体、プロスタグランジン、成長因子)。神経炎症が長期間持続すると、神経細胞やアストログリアの機能障害を引き起こし、その結果、シナプス伝達の変化、興奮性亢進、神経細胞喪失、グリオーシス、異常な神経新生を引き起こす。したがって、これらすべてのメカニズムがてんかん発症の過程に関与している可能性がある。
脳梗塞後に放出される炎症性分子の一部は、出血性変化や肺炎など、いくつかの脳卒中合併症のバイオマーカーとして評価されている。しかし、脳卒中後のてんかんの予測におけるこれらのバイオマーカーの有用性は不明である。
急性症候性発作(図 4a)は、脳卒中発症後 6 時間の血中神経細胞接着分子(neural cell adhesion molecule: NCAM)濃度の上昇と腫瘍壊死因子受容体 1(tumor necrosis factor receptor 1: TNF-R1)濃度の低下と関連していた。
図 4. 急性発作および遠隔発作の血液検査によるバイオマーカー
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8007525/#Fig4
NCAM は細胞接着に関与している可能性があり、急性発作においてシナプス可塑性が高いことを示唆している可能性がある。TNF-R1 は炎症性サイトカインであり、痙攣促進作用を示す可能性がある 。急性症候性発作患者の血中 TNF-R1 濃度が低いことは、脳卒中誘発性神経炎症において、TNFα に対するこれらの受容体の結合が増加していることを示唆している可能性がある。
脳卒中後てんかん(図 4b)は、脳卒中発症後 6 時間以内の血中 S100 カルシウム結合蛋白 B(S100 calcium binding protein B: S100B)と熱ショック 70 kDa 蛋白-8(heat shock 70 kDa protein-8: Hsc70)の低値、エンドスタチンの高値と関連していた。脳卒中後のてんかん発症率は、3 つのバイオマーカーすべてに異常が認められた症例では 17%であったのに対し、バイオマーカーに異常が認められなかった症例では 1%未満であった。別のグループは、脳卒中後てんかんを発症した 4 人の被験者において、脳損傷の血中バイオマーカー(S100B、ニューロフィラメント軽鎖 [neurofilament light]、タウ [tau]、グリア線維性酸性蛋白質 [glial fibrillary acidic protein]、神経特異的エノラーゼ [neuron-specific enolase])レベルの上昇を観察した。S100B と Hsc70 は、脳卒中後の神経炎症期に放出される DAMPs ファミリーに属するタンパク質である。後にてんかんを発症した患者におけるこれらのタンパク質のレベルの低下は、直感に反するように思われるが、S100B と Hsc70 は BBB の機能的完全性の維持に関係しており、これらの濃度が低いことは BBB の障害を悪化させる可能性がある。エンドスタチンは血管新生の阻害剤であり、神経新生と細胞増殖の仲介に寄与している。脳損傷後には一過性の血管新生反応が観察される。したがって、エンドスタチンのアップレギュレーションは細胞の修復を損なう可能性がある。
急性発作と遠隔症候性発作の患者で異なるバイオマーカーが観察されたことは、これらの発作タイプの背景にあるメカニズムが異なるという考えを支持するものである。いずれの場合も、血液バイオマーカーは、後に急性発作や遠隔症候性発作を起こす患者の予測を改善する可能性があり、臨床的要因や画像的要因とともに有用である。
脳卒中後てんかんにおける遺伝的要因とその役割については、ほとんど知られていない。第一度近親者にてんかん患者がいる場合に脳卒中後てんかん発作のリスクが高いことから示唆されるように、血管てんかんの発症には家族性素因がある可能性があるが、リスクの増加は小さい。脳卒中患者におけるてんかん発症に対する遺伝子変異の寄与を評価した研究が 3 件ある 。Yang らは、ミトコンドリアのアルデヒドデヒドロゲナーゼ 2 (aldehyde dehydrogenase 2) をコードする遺伝子の rs671 多型の対立遺伝子 A が脳卒中後のてんかんと関連し、アルデヒドデヒドロゲナーゼ 2 の基質である 4-ヒドロジノメナール (4-hydrozynomenal) の血漿中濃度を上昇させると報告した。Zhang らは、Cluster of Differentiation(CD)-40-1C/T 多型が脳卒中後てんかんと関連している可能性を報告した。彼らは、考えられる機序として、炎症反応に関与する sCD40L の血漿中濃度の上昇を示唆した。Fu らは、TRPM6 の多型(rs2274924)が脳梗塞後のてんかん感受性と関連している可能性を報告している。さらに、この多型を持つ脳卒中後のてんかん患者では、血清中の Mg2+ 濃度が有意に低下していたことから、TRPM6 の多型もこれらの患者の血清中の Mg2+ 濃度に影響を及ぼす可能性があることが示された。
急性症候性発作の管理
脳卒中後の急性期(7 日以下)と遠隔期(7 日以上)の症候性発作の時間的な切り分けは、根本的に異なる病因メカニズムを仮定して設定されている。初期の痙攣発作は、低酸素症、脳灌流シフト、神経細胞代謝障害、興奮毒性、BBB 障害など、脳卒中後の急性期に起こりうる一過性のプロセスによって引き起こされると想定されている。発作が起こる頻度は低いが、死亡率の上昇と関連しており、てんかん発症の危険因子である。脳卒中後に急性症候性発作を起こした患者の 10 年後の非誘発性発作再発リスクは33%である。したがって、急性の症候性発作だけではてんかんと診断するには不十分である。対照的に、遠隔症候性発作の 10 年以内の再発率は 72%である。このように再発リスクが高いため、遠隔の非誘発性発作が 1 回でもあれば、てんかんと診断できる。
脳卒中後の急性症候性発作の管理については多くの議論がある。急性症候性発作の再発リスクが低いことを考慮すると、抗てんかん薬の開始は通常推奨されない。しかし、ガイドラインの推奨と一般的なベッドサイドでの実践との間には乖離がある。抗てんかん薬の適応外投与は、急性症候性発作の後にしばしば開始される。このような治療は通常、脳卒中発症後数週間から数カ月に限定される。多くの臨床医は、さらなる発作を回避し、臨床転帰への潜在的な悪影響を防ぐために、このようなアプローチをとっている。急性症候性発作の予防や治療に関しても、十分な検出力を有する対照試験は実施されていない。
急性症候性発作後の再発リスクは比較的低いにもかかわらず、そのような発作が完全に良性であるとは限らない。脳波上の発作パターンや周期性放電
(periodic discharge) は、脳卒中後の神経学的悪化と関連している。発作や周期性放電は代謝需要の増加と関連しており、代謝クリーゼを引き起こす可能性がある。したがって、脳灌流が低下している状況では、早期の発作や脳波上のてんかん活動の治療が重要である。このような状況としては、血行動態に関連する狭窄を伴う脳梗塞、脳浮腫、くも膜下出血後の血管痙攣などがある。また、急性発作を繰り返すと悪化する可能性のある手術後間もない状態や外傷も含まれる。このような状況では、抗てんかん薬による短期治療が正当化されることがある。その他のほとんどの症例では、孤立性急性症候性発作の治療は必要なく、推奨されない。
早期治療のもう一つの側面は、てんかん発生を阻害する可能性である。このような一次予防的治療を支持するエビデンスはほとんどない。抗てんかん薬はてんかん発作を抑制するが、抗てんかん作用は報告されていない。現在利用可能な予後予測モデルやバイオマーカーは、一次予防治療を正当化するのに十分な確実性をもって、脳卒中後のてんかん発症を予測することはできない。抗てんかん治療に関する実験的知見は有望であるが、ヒトでは再現されていない。
抗てんかん薬治療の試験は、ほとんどが外傷性脳損傷または脳腫瘍後のてんかんの一次予防に焦点を当てており、結果は否定的であった。脳卒中後てんかんの一次予防としてレベチラセタムをプラセボと比較した 1 件のランダム化比較試験は、確定的な結論を出すのに十分な参加者数を含んでいなかった。
最近、抗てんかん薬としてエスリカルバゼピン酢酸塩 (eslicarbazepine acetate) とセレン酸ナトリウム (sodium selenate) が注目されている。いくつかの観察研究では、スタチン (statin) を処方された患者では急性症候性発作の発生率が低下することが明らかにされている。また、ある研究では、シンバスタチン (simvastatin) の投与を開始した患者では、脳卒中後 1 年以内のてんかんのリスクが低いことが明らかにされている。このような観察分析は、交絡の可能性や治療選択バイアスによって制限されるため、結果の解釈には注意が必要である。これらの観察結果は、より大規模な前向き対照試験で再現される必要がある。
脳卒中後てんかんの管理
抗てんかん薬の使用は、てんかん発作の再発リスクを軽減することを目的としている。通常、抗てんかん薬は急性症候性発作とは異なり、再発リスクが高い誘発性のない遠隔症候性発作の治療に用いられる。しかし、1 回の非誘発性脳卒中後発作の後に抗てんかん薬治療を開始するかどうかは、常に患者の総合的な評価に依存すべきである。例えば、常時監視下にある患者、歩行が困難で発作関連傷害のリスクが低い患者、発作が非常に軽度な患者などでは、治療の延期や全く治療を行わないことを正当化する理由がある場合もある。
非誘発性発作後の予防的治療が適切または必要である場合、抗てんかん薬の選択は、文献で入手可能な最良のエビデンスに依拠し、いくつかの臨床的・薬理学的問題を考慮すべきである。現実的なアプローチとしては、「ゆっくり始めて低用量を目指す」ことである。これにより、副作用の強さとリスクを軽減し、最低用量で治療することができる。脳卒中後てんかん患者の多くは、低用量治療にもよく反応する。通常、多剤併用療法よりも単剤併用療法が望ましい。用量設定は、腎機能、肝機能、体重を考慮する必要がある。可溶性薬剤の使用は、嚥下障害のある脳卒中生存者に有用であろう。ほとんどの研究は脳梗塞における抗てんかん薬を評価したものであり、脳出血における抗てんかん薬の使用に関するデータはほとんどない。とはいえ、脳梗塞と脳出血における治療の原則は類似しており、治療法は主に患者の年齢、併存疾患、併用薬に基づいて決められる。
特定の抗てんかん薬の使用を支持する証拠は限られており、質も低い。2 件の無作為化非盲検試験が、放出制御型カルバマゼピン (carbamazepine) とラモトリギン (lamotrigine) またはレベチラセタムを比較している。これらの試験は少数の患者を対象に実施されたため、12 ヵ月間の発作消失率(放出制御型カルバマゼピンは 44%と 85%、ラモトリギンとレベチラセタムは 72%と 94%)における薬剤間の統計学的に有意かつ臨床的に関連性のある差を明らかにするにはパワー不足であった。しかし、両試験において、放出制御型カルバマゼピンはラモトリギンおよびレベチラセタムよりも忍容性が低く、この所見は様々な病因のてんかんを有する高齢者を対象とした他の試験と一致していた。これらの研究はいずれもオープンラベルであり、選択バイアス、割り付け隠蔽、パフォーマンスバイアス、検出バイアスのリスクが不明確または高い、質の低いものであった 。これら 2 つの試験のネットワークメタ解析を伴う最近の系統的レビューでは、レベチラセタムとラモトリギンの間に発作の自由度に関する差は認められなかった(オッズ比 [odds ratio: OR] 0.86;95%CI 0.15-4.89)が、これは潜在的に差を検出する統計的検出力が不足しているためである。しかし、レベチラセタムはラモトリギンよりも有害事象の発生が多かった(OR 6.87;95%CI 1.15-41.1)。
エスリカルバゼピン酢酸塩、ガバペンチン、レベチラセタム、バルプロ酸、その他の新しい抗てんかん薬の有効性と忍容性を示す非対照試験もいくつかあるが、これらの研究の妥当性は、バイアス、プラセボ効果、平均への回帰、その他の交絡因子のために限定的である。
脳卒中後てんかんの治療に特定の抗てんかん薬を使用することを支持する質の高いエビデンスがないことから、薬剤の選択は、様々な病因の焦点性てんかんを有する高齢者を対象に実施されたランダム化比較試験の結果にほとんど依存することになる。これらの研究では、ガバペンチン、ラコサミド、ラモトリギン、レベチラセタム、バルプロ酸の有効性と忍容性が、即時型または放出制御型カルバマゼピンにと比較されている。その結果、新しい抗てんかん薬はカルバマゼピンよりも忍容性プロファイルが優れていることが一貫して示されたが、発作制御に有意な差はなく、時には発作の持続率が高いこともあった。最近、新規発症てんかんを有する高齢者における抗てんかん薬の有効性と安全性の比較を推定したネットワークメタ解析が行われた。ラコサミド、ラモトリギン、レベチラセタムは、発作の消失を達成する確率が最も高く、最高ランクであったが、有効性に有意差は認められなかった。一方、即時型および放出制御型カルバマゼピンは、レベチラセタムやバルプロ酸よりも離脱率が高く、あまり好ましくない忍容性プロファイルを示した。しかし、高齢者を対象とした試験の結果、特に有効性に関する結果は、各試験に含まれる脳卒中後てんかん患者の割合が異なるため、脳卒中後てんかん患者集団に一般化するには注意が必要である。ラコサミドと放出制御型カルバマゼピンとの比較試験の最近の探索的事後解析では、ラコサミドは脳卒中後てんかん患者において一般的に忍容性が高いことが示された。ラコサミドを投与された患者では、放出制御型カルバマゼピンを投与された患者よりも、6 ヵ月間(82 対 59%)および 12 ヵ月間(67 対 50%)、最終評価用量において発作を起こすことなく治療を完了した患者が多かったが、正式な統計解析は不可能であった。ラコサミドもまた、高齢者における非けいれん性てんかん状態に対する安全な潜在的治療薬として報告されているが、その有効性を決定するためには、前向きの比較試験が必要である。
副作用と相互作用
高齢者における薬剤選択は、薬剤の有効性だけでなく、薬力学の変化や副作用・相互作用の可能性を考慮した適切な投与量を個別に検討する必要がある。定義から脳卒中後発作の患者はすべて、血管合併症を有している。また、他の薬剤(抗血小板薬や抗凝固薬、スタチン、降圧薬など)を服用しており、65 歳以上で神経障害が残存している可能性が高い。したがって、理想的な抗てんかん薬は、基礎疾患である血管疾患に対する有害な影響を最小限または全く及ぼさないものでなければならず、例えば、心・脳血管障害のリスク上昇に関連する代用マーカー(例えば、低比重コレステロール、リポ蛋白、C 反応性蛋白、ホモシステイン、頸動脈内膜中膜厚など)に影響を及ぼさないものでなければならない。さらに、関連する薬物相互作用がなく、有効で忍容性が高く、腎不全や肝不全のある患者にも安全に投与できるものでなければならない。
したがって、カルバマゼピン、フェニトイン、フェノバルビタール、プリミドンなどの酵素誘導性抗てんかん薬は、脂質や血管疾患の他の生化学的マーカーの血清値を上昇させる可能性があるため、可能な限り避けるべきである。さらに、これらの薬剤はいくつかの併用薬の肝代謝を増加させる可能性があり、そのうちのいくつか(例えば、ワルファリン)は脳卒中後の患者に使用されている。最近、欧州心臓リズム協会 (European Heart Rhythm Association) は、抗凝固効果を低下させる潜在的なリスクがあるとして、いくつかの抗てんかん薬と非ビタミン K 拮抗経口抗凝固薬との併用に反対するよう勧告した。すなわち、カルバマゼピン、 レベチラセタム、フェノバルビタール、フェニトイン、およびバルプロ酸は P-glycoprotein を誘導することにより、またカルバマゼピン、オクスカルバゼピン、フェニトイン、フェノバルビタール、およびトピラマートは P450 3A4 の活性を誘導することにより、抗凝固効果を低下させる危険性がある。しかし、これらの推奨は、製品特性と専門家の意見に基づいており、これまでのところ、根拠としてはヒトにおける散発的な症例報告しか存在しない。したがって、これらの薬物相互作用の臨床的妥当性を評価するためには、さらなる臨床研究が必要である。それまでは、新規経口抗凝固薬と特定の抗てんかん薬を併用する際には注意が必要である。
高齢者では薬物動態が変化する可能性がある。腎機能は加齢とともに確実に低下する。さらに、肝代謝、蛋白結合、酵素誘導が低下する可能性がある。薬力学に対する加齢の影響、恒常性維持機構および神経伝達における変化は、高齢者における副作用のリスクを増大させる可能性がある。高齢者は、一般的に眠気、疲労、めまい、目のかすみ、集中力または記憶力の低下、運動失調などの薬の用量に関連した副作用に対してより脆弱である。
認知機能の低下は高齢者で多く認められる。抗てんかん薬、特に多剤併用療法で投与される抗てんかん薬の鎮静および抗コリン作用は、認知を悪化させる可能性がある。認知に対する悪影響は、特に「古い」抗てんかん薬、すなわち 1990 年以前に開発された抗てんかん薬で認められ、フェノバルビタール、カルバマゼピン、フェニトイン、バルプロ酸塩について報告されている 。認知に対する最も顕著な影響は、フェノバルビタールで認められた。新しい抗てんかん薬の中では、トピラマート (特に 75 mg/日を超える用量で使用した場合) で言語機能に影響を及ぼす用量依存性の認知障害が副作用として報告されている。ガバペンチン、ラモトリギン、レベチラセタムなどの他の新しい抗てんかん薬は、カルバマゼピンよりも認知機能への悪影響が少なかった。
精神医学的および行動学的副作用は、精神疾患の既往歴のある患者、難治性発作、二次性全般化発作、欠神発作において特に多い。レベチラセタム(22%)とゾニサミド(zonisamide 10%)は、特に行動の副作用を誘発しやすかった。対照的に、カルバマゼピン、オクスカルバゼピン (oxcarbazepine)、ガバペンチン、ラモトリギン (lamotrigine)、フェニトイン (phenytoin)、クロバザム (clozabam)、バルプロ酸 (valproate) は、より良好な行動学的忍容性と関連していた。薬物-薬物相互作用はまた、同時に服用する向精神薬の血漿中濃度の低下を招き、抗うつ薬の効力の低下をもたらすことがある。
骨の健康は高齢者に関連する問題である。フェノバルビタール (phenobarbital)、フェニトイン、カルバマゼピン、プリミドン (primidone) などの酵素誘導性抗てんかん薬や酵素阻害薬のバルプロ酸は、骨折のリスクを高める可能性がある。酵素誘導によりビタミン D の代謝が促進され、骨のターンオーバーが増加する可能性がある。バルプロ酸塩の場合、骨芽細胞の機能を阻害することにより、骨破壊作用が生じる。抗てんかん薬療法の期間は、骨密度の低下と骨折のリスクにとって重要な因子である。骨粗鬆症の既往歴のある高齢女性にこれらの抗てんかん薬を使用する場合は、特に注意が必要である。
カルバマゼピン、オクスカルバゼピン、エスリカルバゼピン酢酸塩がサイアザイド系薬剤または他の利尿薬で治療を受けている患者に処方された場合、薬力学的相互作用により低ナトリウム血症が起こることがある。オクスカルバゼピンは、低ナトリウム血症を引き起こす傾向が最も高い。低ナトリウム血症は一般に軽度で、ゆっくりと発症するが、脳卒中の既往がある人では発作のコントロールを悪化させ、錯乱やせん妄を引き起こすことがある。
抗痙攣薬の休薬
抗てんかん薬を継続すべきかどうかは定期的に評価すべきである。特に、発作のない期間が長い場合や発作が非常に軽度で頻度が少ない場合には、休薬も選択肢の一つである。高齢者では、休薬によって副作用が軽減され、抗凝固薬、脂質低下薬、または高齢者によく処方される他の薬物との相互作用が防止されるため、有益な場合がある。さらに、抗てんかん薬療法は運動機能の回復や骨密度に悪影響を及ぼし、医療費増加、脂質異常、体重変化、不整脈のリスクを増加させる可能性がある。症候性てんかん患者における抗てんかん薬離脱後の再発リスクを評価した研究では、離脱を試みると発作再発のリスクが増加することが示されている。
離脱開始の決定は、患者の臨床的特徴、併用薬、脳卒中のタイプ/形態、併存疾患、個人の嗜好に基づいて個別に行うべきである。少なくとも 2 年間発作のない状態が続いた後に休薬すると、早期に休薬した場合に比べて再発のリスクが低下する可能性がある。脳卒中後てんかん患者の 3 分の 2 以上が抗てんかん薬で発作が消失しており、これは他の病因のてんかんと同様である。
最近の研究で、発作のない患者における抗てんかん薬離脱の指針となる予後モデルが開発されたが、このモデルは脳卒中後てんかんに特化したものではない(図 5)。
図 5. 抗てんかん薬中止後の再発の予測
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8007525/#Fig5
良好な転帰を予測する因子として、寛解までのてんかん罹病期間が短いこと、離脱までの無発作間隔が長いこと、てんかん発症年齢が若いこと、熱性発作の既往がないこと、自然終息性てんかん症候群 (self-limited epilepsy syndrome) であること、発達遅滞がないこと、離脱前の脳波が正常であることが挙げられる。このモデルには画像異常は含まれておらず、脳卒中生存者では検証されていない。脳梗塞や脳出血の後に病変があると、薬物療法を中止した後に発作が起こらない可能性が低くなる。発作の再発は死亡リスクを増加させ 、神経機能を悪化させる可能性があるため、脳卒中生存者における抗てんかん薬の休薬は、個々の患者に合わせたアプローチを用いて慎重に行う必要がある。脳卒中後てんかんにおける抗てんかん薬離脱後の再発リスクについては、さらなる研究が必要である。
急性症候性発作後に抗てんかん薬療法を開始した患者に対しては、急性症候性発作は再発リスクが低いため、脳卒中後早期に休薬することが一般的に勧められる。急性症候性発作後早期に抗てんかん薬を中止するまでの最適な「観察期間」は不明であり、臨床での実践はかなり異なる。本論文の著者らは、急性症候性発作後に抗てんかん薬を開始した場合、抗てんかん薬離脱を開始する前に通常 1 週間から 3 ヵ月待つ。病態生理学的な観点からは、誘因のない
遠隔症候性発作のリスクが非常に高いと考えられる場合を除き、急性症候性発作に対する抗てんかん薬治療を急性期以降も継続する理由はほとんどない。ある観察研究では、脳卒中後最初の発作直後に抗てんかん薬を投与された患者は、最初の 2 年間に抗てんかん薬を投与されなかった患者と、休薬後の再発リスクが同じであったと結論づけている。さらに、現在使用可能な抗てんかん薬のうち、てんかんの発生を予防したり、長期予後や死亡率を改善したりするものはない。
結論
脳卒中後てんかんに関する今後の研究課題はいくつかある。てんかん発症のバイオマーカーの精緻化と開発は、脳卒中生存者が後にどのようなてんかん発作を起こすかを予測するために重要である。このような知見は、抗てんかん薬治療の臨床試験の募集にも役立つであろう。脳卒中は、てんかんの原因となる病変がよく分かっていることが多く、梗塞発症からてんかん発作発症までの期間から介入のための時間の判定に役立つことから、このような試験の優れたモデルである。
抗てんかん薬の効果、忍容性、相互作用については、脳卒中生存者集団において特に研究する必要がある。抗てんかん薬と非ビタミン K 拮抗経口抗凝固薬との相互作用についても早急に研究する必要がある。最後に、抗てんかん薬の休薬が有効な患者を予測するためには、てんかん活動の継続を示すより優れたバイオマーカーが必要である。
元論文
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33619704/