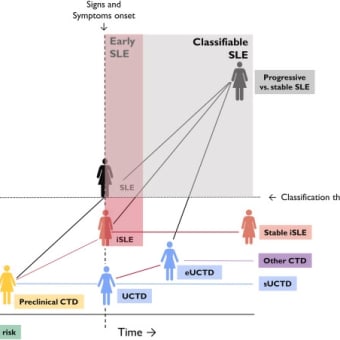下垂体卒中についての総説
Endocr Rev 2015; 36: 622-645
下垂体卒中は下垂体腺腫の 2-12% に合併する。主な症状は突然起こる激しい頭痛であり、時に視野障害や眼球運動障害をともなう。髄膜刺激症状や意識障害をともなう場合は診断が難しくなる。
頭蓋内圧亢進、高血圧、大手術、抗凝固療法、負荷試験が下垂体卒中の誘因となることがある。
下垂体性副腎皮質機能低下症を合併した場合、治療が遅れると生命に関わる。
CT または MRI で出血かつまたは壊死組織をともなう下垂体腫瘍を確認することで診断は確定される。
かつては下垂体卒中は脳神経外科の緊急疾患と考えられ、全例で手術が行われていた。最近では、症例によっては保存的に加療されることが増えてきている。後ろ向きの観察研究によると、保存的に加療した場合も眼球運動障害、下垂体機能、腫瘍の増大については手術と大差ない。
1. 疫学
下垂体卒中の有病率は 6.2/10万人、罹患率は 0.17 /10万人・年だと報告されている。
下垂体腺腫の 2-12%で下垂体卒中を経験し、下垂体卒中発症後に下垂体腺腫が発見されるケースは 3/4 以上である。2件のメタ分析によると、非機能性下垂体腫瘍を保存的に診ていく場合、年率 0.2-0.6%で下垂体卒中を起こす。
下垂体卒中は全ての年齢層で発症し得るが、特に 50-60歳台で多い。
無症候性の下垂体卒中は症候性の下垂体卒中よりもはるかに多い。実際、下垂体腫瘍の最大 25%で出血や壊死組織を認める。
2. 誘因
下垂体卒中の 10-40%で誘因を認める。血管内操作、特に脳血管造影は下垂体卒中と関連すると報告されている。血管内操作の数分後に発症する場合もあるし、7時間後に発症した場合もある。血圧の変動や血管攣縮が原因になると言われている。
手術の中では、整形外科と心臓血管外科の手術は消化器や呼吸器、甲状腺の手術と比較して下垂体卒中を合併しやすいようである。整形外科の手術では膝よりも肩や股関節の手術で発症しやすく、手術中あるいは術後 24-48時間に発症することが多い。術中・術後の低血圧、抗凝固、微小血栓が下垂体梗塞の原因になるのではないかと言われている。
心臓血管外科の手術は血圧変動が大きく、抗凝固療法を行うので、下垂体卒中のリスクになることが昔から知られている。特に人工心肺装置 (cardiopulmonary bypass) を使用すると血圧変動が大きくなるので、下垂体腺腫があることが分かっている場合は off-pump で手術を行った方が良いのではないかと言う専門家もいる。
頭部外傷も下垂体卒中の原因になり得る。
また、負荷試験も下垂体卒中のリスクである。多くの場合は負荷後数分以内に発症する。インスリン、TRH、GnRH や GHRH と比べると CRH 負荷は下垂体卒中のリスクは小さい。また複数のホルモンで同時に刺激すると下垂体卒中のリスクが高くなる。近年は負荷試験後に下垂体卒中を発症するケースは少なくなっている。おそらく多くの内分泌代謝内科医が下垂体卒中のリスクが高い症例で、TRH や GnRH の負荷を避けるようになったからだと考えられる。著者らはトルコ鞍の上方に伸展する大きな腺腫 (macroadenoma) では術前は ACTH 分泌能評価目的の CRH (またはインスリン) 負荷以外の負荷試験は行わない方が良いと考えている。前立腺癌の治療に用いられる GnRH アゴニスト (リュープリン、ゾラデックスなど) も下垂体卒中発症と関連すると報告されている。投与後数分で発症する場合もあるし、徐放製剤の場合は投与から 10日経った後に発症した場合もある。
下垂体卒中は抗凝固療法と関連するようである。抗凝固療法開始直後に発症する場合もあるし、もっと時間が経ってから発症することもある。抗凝固療法以外の原因で出血傾向がある患者についても下垂体卒中との関連が報告されている。しかし、これらは症例報告であり、前向きの観察研究はない。したがって、既知の下垂体腺腫の患者で抗凝固療法を行うことの是非については現在のところ不明である。
ドーパミンアゴニストと下垂体卒中との関連が言われているが、はっきりしない。
ほとんどの場合、下垂体卒中は大きな下垂体腺腫で起こる。そのためか下垂体卒中を起こした下垂体腫瘍の多くは非機能性である。非機能性の腺腫は発見が遅くなるため、機能性の腺腫よりも大きいことが多い。非機能性腺腫に次いで多いのはプロラクチノーマと成長ホルモン分泌腫瘍である。
3. 病態生理
下垂体卒中の病態生理は不明だが、下垂体卒中のほとんどは大きな腺腫で起こることは重要である。
下垂体は 1. 下垂体門脈系および 2. 上・下下垂体動脈から直接血流を受けている。上下垂体動脈は下垂体茎に沿って走行し、下垂体前葉に血流を送る。下下垂体動脈は下垂体後葉に血流を送る。さらに、上下垂体動脈と下下垂体動脈は吻合している。静脈血は下垂体静脈から隣接する静脈洞を経て、頚静脈に流れる。
下垂体腺腫では、正常下垂体と比較して、門脈系よりも動脈系にほとんどの血流を依存している。また腺腫は正常下垂体に比べて血流が乏しい。
正常下垂体の毛細血管は有窓の内皮からなるが、プロラクチノーマにおいては平滑筋層をともなう通常の動脈や有窓の内皮に平滑筋層をともなう異常な血管を認める。
下垂体腺腫は脆弱な血液供給に見合わない増殖のために虚血や出血を来しやすい可能性がある。あるいは腺腫によって、漏斗や上下垂体動脈が鞍隔膜に押しつけられることによって虚血になる可能性もある。
4. 臨床症状
頭痛は下垂体卒中の最も頻度の高い症状であり、80%の症例で認める。下垂体卒中の頭痛は最初の症状であることが一般的であり、晴天の霹靂のような (like a thunderclap in a clear sky) と形容される突然の激しい頭痛である。しかし、亜急性の経過で出現することもある。疼痛の部位は眼の奥であることが多いが、両側頭部や頭部全体であることもある。嘔気や嘔吐をともなうことも多く、偏頭痛や髄膜炎と間違われることもある。
視覚障害は下垂体卒中の半数以上で認める。血腫による腫瘍の増大で視交叉や視神経が圧迫されることが原因である。視野障害の程度は症例により様々だが、両耳側半盲が最も頻度が多い。視力障害や失明も起こり得るが、稀である。眼球運動障害も頻度の高い症状で 52%の患者で認める。海綿静脈洞内の圧力が上昇すると、海綿静脈洞内を走行する第 III, IV, VI 脳神経が障害される。特に障害されやすいのは第 III 脳神経 (動眼神経) であり、半数を占める。第 III 脳神経の障害は、眼瞼下垂、内転障害、散瞳が特徴である。
下垂体卒中の患者では、嘔気・嘔吐 (57%)、羞明 (40%)、髄膜刺激症状 (25%)、発熱 (16%) を認め、髄膜炎と間違えることがある。髄液検査では、リンパ球高値を認めることがある。無気力、混迷、昏睡などの意識障害を認めることもある。
内頚動脈が前床突起に押しつけられたり、能動脈の攣縮したりすると脳虚血のために片麻痺や嚥下障害などの巣床状を認めることがある。
頻度は低いが嗅覚障害 (嗅神経の圧迫による) 、鼻血・髄液漏 (トルコ鞍の侵食による)、顔面痛 (三叉神経の圧迫による) もあり得る。
下垂体卒中に続発する下垂体性副腎皮質機能低下によりショックになると心筋梗塞と間違われる可能性がある。
5. 内分泌学的異常
下垂体卒中の発症時点では 1つ以上の前葉ホルモンの分泌が低下している。後ろ向きの検討では、下垂体卒中を発症する前から性的な問題、月経不順、乳汁分泌、倦怠感などの内分泌学的異常と関連する症状を認めた。これらの症状は下垂体腫瘍による正常下垂体の圧排によって起こると考えられる。
ACTH (corticotropin) の分泌低下は下垂体卒中の患者で最も頻度の高いホルモン分泌低下であり、50-80%の患者で認める。ACTH が欠損するとショックや低ナトリウム血症を起こし、命に関わる。下垂体卒中では、二次性副腎皮質機能低下症を高率に合併するので、下垂体卒中と診断したら、ACTH と血清コルチゾールを提出し、副腎皮質機能低下の診断確定を待たずに直ちに糖質コルチコイドを経静脈的に投与する。
副腎皮質機能低下によるショックはカテコラミンに反応しない。下垂体卒中急性期では、重度の低ナトリウム血症を認めることがある。これは糖質コルチコイドの分泌低下が原因である。糖質コルチコイドの分泌が低下すると、1. 抗利尿ホルモンの分泌抑制がかからなくなり、2. 糖質コルチコイド欠損自体が腎からの水排泄を抑制する。
下垂体卒中では、視床下部の機能障害のために ADH 不適合分泌症候群 (syndrome of inappropriate antidiuretics: SIADH) を合併することもある。下垂体卒中後に低ナトリウム血症を認めた場合は、血清の重炭酸イオンを確認すると良い。副腎皮質機能低下症では、重炭酸イオン濃度が低下しており、SIADH との鑑別に役立つ。
TSH (thyrotropin) 欠損による甲状腺機能低下症も低ナトリウム血症の原因になり得る。嘔気・嘔吐、低血糖 (いずれも ACTH/コルチゾール、成長ホルモン/IGF-1 欠損と関連する) も非浸透圧性の抗利尿ホルモンの分泌刺激となる。
重篤な患者では、下垂体-副腎皮質軸の反応が正常であれば血漿コルチゾールの濃度は上昇している。ICU に入室した患者では、入院 2日目の血清コルチゾールの平均値は 20 μg/dL でその後 1週間以上高値 (平均 16.8±7.8 μg/dL) が続くと報告されている。ちなみに、コルチゾールの濃度が高値になるのはコルチゾール分解の低下に依るところが大きく、コルチゾール産生増加の寄与は小さい。
重篤な患者でコルチゾール濃度が 15 μg/dL 未満である場合、副腎皮質機能低下症を疑う。多くの文献と著者らの経験によれば、下垂体卒中に続発する二次性副腎皮質機能低下症では、コルチゾール濃度は非常に低く、診断に迷うことはまずない。それでも、下垂体卒中では全例で糖質コルチコイドを経静脈的に投与するべきである。
下垂体卒中では、TSH は 30-70%、ゴナドトロピンは 40-75% で分泌低下すると報告されている。成長ホルモンはほとんど全例で分泌低下しているが、診断時には検査されていないことが多い。プロラクチン分泌低下は 10-40%で認める。
尿崩症が下垂体卒中に合併することは稀で、頻度は 5%未満である。尿崩症は副腎不全 (あるいは甲状腺機能低下症) によってマスクされることがあり、糖質コルチコイド(あるいは甲状腺ホルモン) 補充後に尿崩症が顕在化することがある。
下垂体卒中に下垂体ホルモン分泌亢進がともなうこともある。特に、プロラクチノーマは出血しやすい性質があるので、下垂体卒中を合併しやすい。
6. 鑑別
下垂体卒中の主な鑑別疾患はくも膜下出血と細菌性髄膜炎である。他には海綿静脈洞血栓症、中脳梗塞も鑑別に挙がる。髄液検査は下垂体卒中とくも膜下出血、細菌性髄膜炎の鑑別にはあまり役に立たない。下垂体卒中では、特に髄膜刺激徴候を認める場合は、髄液中の赤血球高値、キサントクロミー、髄液細胞増加、蛋白質高値を認めるからである。しかし、髄液培養で細菌性髄膜炎は除外できる。
下垂体卒中の診断に最も有用なのは、CT と MRI である。下垂体腫瘍を認めれば、出血や壊死所見を認めなくても下垂体卒中だと考える。たとえば、突然の頭痛と視覚障害を訴える患者に下垂体腫瘍を認めれば、下垂体卒中だと診断して良い。
CT はくも膜下出血の除外に有用である。下垂体卒中の 80%の症例では下垂体腫瘍を認める。このうち 20-30%では腫瘍内部に出血を認める。数日すると出血は検出できなくなる。造影すると、不均一な造影効果を認める。
MRI は出血と壊死の検出に優れ、下垂体と周辺の構造 (視交叉、海綿静脈洞、視床下部) を詳細に観察することができる。下垂体卒中急性期に蝶形骨洞の粘膜、特にトルコ鞍直下の粘膜の肥厚は神経学的および内分泌学的予後不良と関連する。蝶形骨洞の粘膜肥厚はトルコ鞍内圧の上昇と海綿静脈洞のうっ血を反映していると考えられている。
7. 臨床経過
下垂体卒中の臨床経過は症例によりさまざまである。梗塞よりも出血性梗塞あるいは出血の方が予後不良である。
軽症の場合は頭痛、視覚障害、下垂体機能障害は緩徐に出現し、数日から数週間持続する。最重症の場合は、数時間の経過で目が見えなくなったり、昏睡したり、神経学的な異常が現れたり、循環動態が不安定になったりする。この場合、直ちに診断し、除圧と糖質コルチコイド投与を開始しないと、副腎不全または神経学的な合併症のために死亡することもあり得る。ほとんどのケースは前二者の中間で、数日の経過で頭痛と視覚障害が出現することが多い。
神経学的異常、視覚異常、内分泌異常の回復についても、症例によりさまざまである。手術によって除圧すると意識障害は改善する。視野障害や視力障害も下垂体卒中後に出現したものであれば手術後に改善する可能性がある。しかし、視神経が萎縮してしまっている場合には手術しても改善しない可能性が高い。眼筋麻痺も多くの場合改善するが、改善には数週間がかかる。内分泌障害は多少変化はあるが、しばしば永続する。
8. 治療
下垂体卒中では多くの場合、ACTH 分泌低下をともなうので、手術を行う場合でも保存的に治療する場合でも、下垂体卒中診断後直ちに糖質コルチコイドを経静脈的に投与するべきである。具体的には、ヒドロコルチゾン 50 mg を 6時間毎か、初回に 100-200 mg、以後 50-100 mg を 6時間毎に静脈注射 (または筋肉注射) する。あるいは 2-4 mg/時で持続静脈注射しても良い。ショックになっている患者では低血糖を予防するために生理食塩水に 5%ブドウ糖を混合注射して投与する。
手術を選択する場合は、ほとんど全ての症例で経蝶骨アプローチが推奨される。理由としては除圧に優れ、術後の合併症と死亡率が少ないからである。経蝶骨下垂体手術はかつては上口唇下粘膜を切開する sublabial transseptal approach が行われたが、現在は鼻中隔粘膜を切開する nasal septal displacement が主流である。手術顕微鏡 (operating microscope) を使用するか、内視鏡を使用するかは脳外科医の好みによる。特に熟練した脳外科医では手術にともなう合併症は稀だが、髄液漏と尿崩症は起こり得る。
下垂体卒中後に下垂体腫瘍が自然に収縮し、症状が改善することがあると報告されている。そのため、症例によっては保存的に治療するのが妥当ではないかと言われている。
下垂体ホルモン分泌低下と下垂体腫瘍の再増大の頻度については手術しても保存的に治療しても変わらない。また保存的に治療した場合でも眼筋麻痺は 75-100%で完全に回復する。ただし、回復には数週間~数ヵ月がかかる。
手術と保存的治療を比較した前向き研究はないが、後ろ向きの検討では早期に手術を行った方が保存的治療よりも下垂体卒中の重症度スコア (Pituitary Apoplexy Score: PAS) が低かったと報告されている。
手術を行った場合、視力障害の 50%で正常化、 6-36%で部分的な改善を認める。視野障害は 30-60%で正常化、50%で部分的な改善を認める。失明している場合は、50%で改善を認める。
視力障害および視野障害については、保存的に治療しても手術と同様に改善する。保存的に治療した場合、視力障害は 60-100%で正常化し、25%で部分的に改善する。視野障害は 50-100%で正常化し、25%で部分的に改善する。失明している場合は、50%で改善を認める。
保存的に治療した方が視覚障害の予後が良さそうに見えるのは、重症な患者では手術を選択されることが多いからだろうと考えられている。
内分泌障害については、手術を行うと 50%以上で完全または部分的な改善を認める。しかし、保存的に治療した場合でも手術と同程度の割合で改善を認めたとも報告されている。
手術を行った場合、下垂体腫瘍を除去することができる。しかし、保存的に治療した場合でも、腫瘍はしばしば縮小し、腫瘍を認めなくなることも多い。
手術後平均 6.6年の時点での評価では、11.1%で腫瘍の再増大を認めた。腫瘍の再増大については、手術をしても保存的に治療しても同程度の頻度で認める。いずれの治療方法を選択したとしても、腫瘍の再増大は起こり得るので、長期間のフォローアップはした方が良い。
最近上梓された英国の下垂体卒中の治療についてのガイドラインでは、神経障害および視覚障害が顕著または意識レベルが低下している場合には手術を推奨している。手術を選択する場合はいつ手術するかは重要な問題である。視覚障害については、3日以内に手術しても、1週間以内に手術しても予後は変わらなかった。しかし、1週間以上経過してから手術した場合は改善に乏しかった (8日以内 86%で改善、9-34日 46%で改善)。
元論文
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26414232/