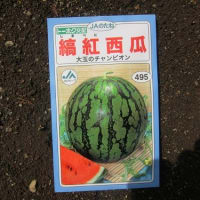2022年度玉ねぎ成長記録のスタートです。
成長する過程を節目毎に追記していきます。
今回は、「第8回保存編」です😁
今後の節目予定は
1⃣9/8種まき編・・・済み
2⃣9/25追肥、土寄せ編・・・済み
3⃣10/8害虫対策・・・済み
4⃣⃣11/19苗の定植・・・済み
5⃣2/5追肥・・・済み
6⃣3/12追肥・・・済み
7⃣4/29収穫・・・済み
8⃣6/4保存・・・今回報告
玉ねぎは坪収穫単価(一坪で収穫出来る野菜の売上高が高い)が非常に高い野菜だと思っています。また、料理でも使用頻度が高い野菜なので……
更に良いことは、手間が掛からない野菜だと思っています。(鳥獣対策は不要、除草作業も冬場なので)
それでは、
【第8回6/4保存編】
本日の作業工程
①収穫する
②保存作業
作業ポイントの説明
作業1:収穫する
早生は、鎌で葉を取ってからマルチを剥がして収穫です。マルチを剥がした状態が下記写真となります。
中生は、保存のために葉を残して収穫します。(葉が枯れてしまわないうちに収穫します。)

作業2:保存作業
風通しの良い日陰に吊して保存するので、下記要領で行います。
①作業を行う玉ねぎの葉が、下記写真の状態になったところを見計らって作業を行います。(水分が抜けて、しなやかになった状態:葉がパサパサに乾燥していたら切れて作業不可能となリます。逆に、青々しすぎていたら編むことができません)
下記写真は、少し枯れすぎですね!もう少し早いほうが良い!

②3個の玉ねぎを三つ編みにします。下の写真が、三つ編みにした状態です。

③上の写真の三つ編みした物同士を、こぶ結びします。

④つる下げて終了です。

吊り下げてから7日目

以上で、本日の作業は終了です。
この保存方法は、父親から伝授された物です。三つ編みするときのタイミングで作業性の合否が決まります。
【第7回4/29収穫編】
今年は暖かく生長が早かったように思われたので「薹だち」が多いのではと心配していましたが、全体の4%程度が薹だちしました。
肝心の出来具合は「上出来」と言ったところです。4月中頃から薹だちしている株から収穫して食べていました。玉ねぎ専業農家さんからの薹だち株の扱い方は……
・芯から腐るので優先して食べること(長期保存に向いていない)
・味は変わらない
以上、頭に入れて扱いましょう!
注:ここで記している「薹だち」とは、花芽が付いた株のことを指します。花芽があるので玉ねぎの中心に芯が出来てそこの部分から腐敗が進みます。
本日の作業工程
①収穫
早生品種の収穫が本格的になりました。個人の感想ですが、玉ねぎは倒れ始めから完全に倒れた状態までの期間が玉ねぎの実が一段と生長すると思います。
一番美味しき時期ですね!!!

セコイ話ですが、玉ねぎの使用済みのマルチをさつまいもに使用しています。上の写真のように玉ねぎを引き抜くとマルチに大きな穴が開いてしまいます。そのため、茎を切断してからマルチを剥がして玉ねぎを収穫しています。勿論、端から順番に収穫して順次マルチを剥がしていきます。
私の場合は、茎の太さ分しかマルチに穴が開いていないので再利用可能で、さつまいもの根張り防止ぐらいなら使えるのでやっています。(軒下に保存する「茎付き玉ねぎ」を収穫したマルチは使用できません)
以上で本日の作業は終了です。
以下は前回の記事参考
【第6回3/12追肥編】
本日の作業工程
①追肥
玉ねぎが伸び盛りの状態なので2回目の追肥を行いました。今年は成長が早いかも知れません。薹(とう)がたってしまうかな……
化成肥料をマルチの上からパラパラとまきます。マルチ穴が小さいので明日の雨で化成肥料が溶けてマルチ内に入ることを期待していますが?
下記写真のように玉ねぎの茎でマルチ穴は塞がれており肥料が入り込むか疑問です?(白い粒が化成肥料です)
マルチ穴の開け方、肥料のやり方は玉ねぎ農家さんからの伝授なので大丈夫だと思いますが…… 雨で流れてしまいそうですね!

以上で本日の作業は終了です。
以下は、前回の記事で参考まで
【第5回2/5追肥編】
本日の作業工程
①追肥
春めいて成長し始めたので追肥を行いました。
化成肥料をマルチの上からパラパラとまきます。マルチ穴が小さいので明日の雨で化成肥料が溶けてマルチ内に入ることを期待しています。

以上で本日の作業は終了です
【第4回11/19苗の定植編】
本日の作業工程
①畝造り作業
②マルチに穴開け作業
③苗の下準備
④苗の定植作業
⑤水やり
苗も30cm程の大きさになり定植時期になりました。

《作業ポイントの説明》
本日の作業(治具)は、概ね玉ねぎ農家さんから教わった方法です。
①畝造り作業
1m幅の畝を造ります。牛糞と腐葉土をまいて、両脇の土で盛り上げます。
手前1列目が土を盛る前の状態で、2列目、3列目は土を盛った状態で畝が完成されています。マルチを張るので畝の表面は出来るだけ平たくします。

②マルチに穴開け作業
マルチの穴開け作業には手製の治具を使います。写真は治具の裏から撮った写真です。24個の丸い木材が刺さっています。これによってマルチに穴が開きます。

下の写真のように使います。
これで24個の穴が出来ます。

作業完了後の写真です。15cm格子状に穴が開いています。

治具の詳しい情報は、後日報告とします。
③苗の下準備
苗は軽く鍬で持ち上げて、手で抜き取ります。抜き取り後、根が25mm前後残る位で根の先を手でカットします。(10本位まとめてカットしています)カットする理由は、根をカットしないでマルチ穴に入れると根が飛び出してしまうためです。(現状はカットしても飛び出している苗がありますが問題なく生育します。玉ねぎは生命力が強いです)
成長が飛び抜けいる苗は、葉先を適当にカットします。とう立ちを防ぐためです。(今年は生育が良かったので、1/3位の苗で葉先を手で25cm位になるようにカットしました)
写真は根をカットする前の写真です。

④苗の定植作業
苗をマルチの穴に1本筒入れて、マルチ上から苗を挟み込むように押さえ込んで終了です。たまに入らない苗があるので、「1本穴開け棒治具」を利用して穴を開け直します。全部で1000本植え付けました。
マルチが風で浮かないように、両脇に鉄の棒の重しをしています。(苗が大きくなるまで)

⑤水やり
水を上からまいて終了です。
以上で本日の作業は終了です。
以下は、前回の記事で参考まで
【第3回10/8害虫対策編】
本日の作業工程
①除草作業
②害虫対策
良い感じで育っているなと横目で見ていましたが……
害虫除けネット越しによく見ると……
葉先が食害にあっており、慌て駆除することとしました。

《作業ポイントの説明》
①除草作業
お決まりの作業です。大きくなる前に処理します。
②害虫対策
苗に居る害虫は非常に小さいので探す気で見ないと発見できません。写真の害虫は大きく成長していますが、1mm位の虫が沢山居たので……
奥の手を使ってしまいました。(液体農薬散布)
苗を指ではじくと、糸にぶるさがった1mm程の虫が現れます。徹底抗戦しました。
以下の写真は、分かりやすくするために一番大きな虫を撮りました

本日の作業は終了です。
以下は、前回の記事で参考まで
【第2回9/25追肥・土寄せ編】
本日の作業工程
①除草作業
②追肥
③土寄せ作業
オケラによる土盛り上げ被害の影響がどの程度出るか心配でした。また、雨台風によって種が流されてしまうのではと…… はらはら・ドキドキでしたが、無事に発芽していました。
こんな感じです。

土が盛り上がっている部分がありますがモグラの跡です。腐葉土を入れているのでミミズが繁殖しています。それを食べに来ます。
手前の発芽していない部分は、オケラの通過した部分です。思ったほど被害は軽傷で済みました。
《作業ポイントの説明》
①除草作業
除草作業を行いながら土の表面全体を道具(草削り)を使用して柔らかくします。
条と条の間(中央)は、少し深めに道具(草削り)でさらいます(草削りの先の尖った部分を使って、線を引くように深くさらいます。深さは20mm位かな)中央部に深く線を引くのは、苗の根を傷めないようにするためです。また、線を引く理由は、土寄せをする土を確保するためです。
②追肥
上から全体に化成肥料をパラパラとまきます。
③土寄せ作業
草削りで土の表面は柔らかくなっています。更に、中央部は20mm程深く柔らかくなっていますので、指を使って発芽した苗の根元に土を寄せます。
写真は、土寄せ後の状態です。

以上で本日の作業は終了です。
しばらくは、発芽した芽の先端を食する害虫が発生するのでチェックが必要です。同色でピタッとくっついているので判りずらいです。それと、ネキリムシですね!新芽が倒れていたら、その周辺をほじくりかえしましょう。黒い虫が現れます。
それでは、次回!
以下は、前回の記事で参考まで
【第1回9/8種まき編】
本日の作業工程
①種をまくための「苗床」を耕す
②苗床に腐葉土を加える
③土を盛り上げる
④種まき用の溝を造る
⑤種をまく
⑥土を被せ、水をまく
⑦乾燥防止のため「よしず」を被せる
⑧9/11オケラ対策
作業ポイントの説明
本日用意した玉ねぎの種は、早生と中生(2袋)です。内容量は同じでしたが、種の大きさが触感で判るほど違いがありました。早生の方が種が小さい分、種の数が多かったようです。
毎年9/15前後に種まきをしていますので、今年は天気予報の関係で少し早めの種まきとなりました。

①種をまくための「苗床」を耕す
除草作業後に耕運機で耕しています。苦土石灰は、冬季に1回/年、散布しています。
②苗床に腐葉土を加える
腐葉土・牛糞は下記写真のように一様に散布します。

③土を盛り上げる
両脇の土を盛り上げて幅1mの苗床を造り表面を平らにします。
④種まき用の溝を造る
5条の種を蒔く形になります。種を蒔く溝は、家庭菜園用のポールを使って写真のように造ります。ポールを上から両手(両指)で深さ1cmほど押さえ込めば溝は出来ます。

⑤種をまく
溝が完成したら種まきです。5mm間隔ぐらいで蒔けば間引きが不要の間隔です。
2種類の種を同じ苗床に蒔いているので、境目が判るように目印(棒を立てるとか)を忘れずに!

⑥土を被せ、水をまく
親指と人差し指とで溝を挟むようにして土を被せます(最後に蒔いた部分を軽く手のひらでたたいて下さい)
水をまいて終了です。
⑦乾燥防止のため「よしず」を被せる
乾燥を防ぐために「よしず」を被せます(他の方法でも全然問題ありません。不織布とか……)
発芽したら、よしずを外して虫除けネットを被せます。

以上で、本日の作業は終了です。
臨時作業:9/11「オケラ対策」発生
9/11玉ねぎの苗床が以下の写真のような状態になっていました。
土が盛り上がっている所が、オケラが穴を掘って進んだ奇跡です。掘り返されているので該当箇所は発芽しないようです。(オケラは、モグラの昆虫判のような物ですね!)

人参でも被害が発生しましたので、今回は農薬「オルトラン」を苗床全体にパラパラとまきました。農薬袋の裏面ですが、たまねぎの部分に「けら」と書かれています。

掘った軌跡を叩いてもしょうが無いのでそのままで様子を見ることにしました。どの程度の影響があるやら……
次回は、発芽後の追肥、土寄せを紹介する予定です。