遺族に代わって墓参し、墓を清掃する“墓参り代行サービス”が、人気を集めている。依頼者は、高齢者や故郷から離れて暮らす人が多い。葬祭業者やハウスクリーニング業者らの新規参入が相次ぎ、インターネット上には、墓参り代行業者を検索できる専用サイトも登場している。
代行サービスは、石材店や農協、生花店などが十数年ほど前から手がけるようになった。葬祭場「家族葬のファミーユ」を全国展開するエポック・ジャパン(東京)は今年2月、創業地の宮崎市でサービスを開始。これまでに、同市から5件の依頼があった。同社が葬儀を請け負った遺族や、運転免許を持たない高齢者らだった。
社員は、まず墓石に向かって合掌。約20~30分かけて、草むしりをし、墓石のコケを取り除き、線香立てを洗い、再び合掌する。料金は5250円。同社ケアチームマネジャーの藤田直喜さん(44)は「葬儀以来、スタッフが遺族の心の支えになってきたので安心して墓参りを頼んでくれている」と話す。
山口県周南市の「お墓参りと墓石クリーニングの優美」は2007年6月、内田雄二さん(53)が開業した。内田さんは佐賀県出身で、墓参りになかなか行けない自身の境遇から、「ふる里を離れた団塊の世代は多く、需要はある」と見込んだ。大阪、東京在住者などから年間数十件の依頼を受け、山口県内の墓を訪れ、清掃している。
ハウスクリーニング業大手の長谷川興産・おそうじ本舗(東京)は07年3月から墓参代行を全国展開。同社九州支店(福岡市博多区)によると、九州では鹿児島県内からの依頼が多く、同支店の寺北大悟さん(32)は「墓参りを大事にする県民性があるためでは」と話している。
九州大文学部の関一敏教授(比較宗教学)は「故郷と離れた場所で仕事をする人が増えていることに加え、墓参を頼むことができる親族や近所づきあいをする人とのネットワークがなくなっていることが要因だろう。寂しいことだが、お金を払い、他人に頼んででも、墓をきれいにしておきたい心がけは立派なものではないか」と話している。
(2009年10月24日 読売新聞)

たしかに、お墓参りに行きたくても行けない人には便利だけど、
それでいいの?と思ってしまいます。
上記「九州大文学部の関一敏教授」のいうように、現代の様々な事情もあって、行きたくても行けない人もいるでしょうが、
「お金を払い、他人に頼んででも、墓をきれいにしておきたい心がけは立派なものではないか」
そうかな?
他人にお墓をきれいにしてもらえれば、とりあえず満足っていうのが、ちょっと違うと思ってしまいます。
こんなことを感じることじたい矛盾?
毎日のように仏壇にローソクと線香を上げ、手を合わせ、時には語りかけ、それでもお盆やお彼岸にはお墓参りに行く。
死者はどこにいるというのだろうか?
仏教的には、死者は極楽浄土にいる。
だから、仏壇ではご本尊が一番高いところにいる。
一般的に、仏壇の中の何に手を合わせ、語りかける?
厳格な住職は、仏壇の中に故人の写真を置くものではないと言う。
ご本尊に向かって手を合わせるのであって、故人に対してお経を唱えているわけではないと言う。
仏壇の中に死者がいるわけではないし、お骨のある場所に死者がいるわけでもない。
それとも、風になっている?
代行サービスは、石材店や農協、生花店などが十数年ほど前から手がけるようになった。葬祭場「家族葬のファミーユ」を全国展開するエポック・ジャパン(東京)は今年2月、創業地の宮崎市でサービスを開始。これまでに、同市から5件の依頼があった。同社が葬儀を請け負った遺族や、運転免許を持たない高齢者らだった。
社員は、まず墓石に向かって合掌。約20~30分かけて、草むしりをし、墓石のコケを取り除き、線香立てを洗い、再び合掌する。料金は5250円。同社ケアチームマネジャーの藤田直喜さん(44)は「葬儀以来、スタッフが遺族の心の支えになってきたので安心して墓参りを頼んでくれている」と話す。
山口県周南市の「お墓参りと墓石クリーニングの優美」は2007年6月、内田雄二さん(53)が開業した。内田さんは佐賀県出身で、墓参りになかなか行けない自身の境遇から、「ふる里を離れた団塊の世代は多く、需要はある」と見込んだ。大阪、東京在住者などから年間数十件の依頼を受け、山口県内の墓を訪れ、清掃している。
ハウスクリーニング業大手の長谷川興産・おそうじ本舗(東京)は07年3月から墓参代行を全国展開。同社九州支店(福岡市博多区)によると、九州では鹿児島県内からの依頼が多く、同支店の寺北大悟さん(32)は「墓参りを大事にする県民性があるためでは」と話している。
九州大文学部の関一敏教授(比較宗教学)は「故郷と離れた場所で仕事をする人が増えていることに加え、墓参を頼むことができる親族や近所づきあいをする人とのネットワークがなくなっていることが要因だろう。寂しいことだが、お金を払い、他人に頼んででも、墓をきれいにしておきたい心がけは立派なものではないか」と話している。
(2009年10月24日 読売新聞)

たしかに、お墓参りに行きたくても行けない人には便利だけど、
それでいいの?と思ってしまいます。
上記「九州大文学部の関一敏教授」のいうように、現代の様々な事情もあって、行きたくても行けない人もいるでしょうが、
「お金を払い、他人に頼んででも、墓をきれいにしておきたい心がけは立派なものではないか」
そうかな?
他人にお墓をきれいにしてもらえれば、とりあえず満足っていうのが、ちょっと違うと思ってしまいます。
こんなことを感じることじたい矛盾?
毎日のように仏壇にローソクと線香を上げ、手を合わせ、時には語りかけ、それでもお盆やお彼岸にはお墓参りに行く。
死者はどこにいるというのだろうか?
仏教的には、死者は極楽浄土にいる。
だから、仏壇ではご本尊が一番高いところにいる。
一般的に、仏壇の中の何に手を合わせ、語りかける?
厳格な住職は、仏壇の中に故人の写真を置くものではないと言う。
ご本尊に向かって手を合わせるのであって、故人に対してお経を唱えているわけではないと言う。
仏壇の中に死者がいるわけではないし、お骨のある場所に死者がいるわけでもない。
それとも、風になっている?














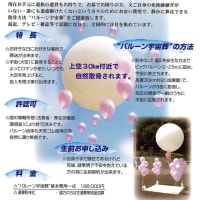
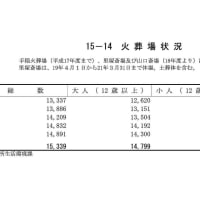




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます