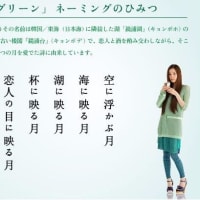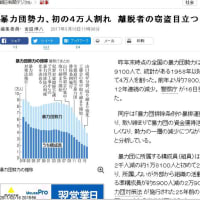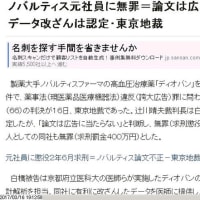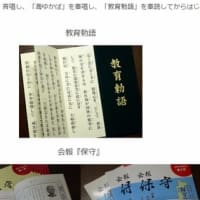1033年初頭 (長元5年末) 噴火
1083年 (永保三年) 噴火
1435年または1436初頭 (永享7年) 噴火
1511年 (永正8年) 噴火
1704年 (元禄16年末~17年初頭) 鳴動
1707?
12月16日(宝永4年)旧暦 11月23日 宝永大噴火
詳細は「宝永大噴火」を参照
大量のスコリアと火山灰を噴出。この噴火は日本最大級の地震である宝永地震の49日後に始まり、江戸市中まで大量の火山灰を降下させる等特徴的な噴火であった。
1708年 (宝永5年) 鳴動
1923年 (大正12年) あらたな噴気
1987年 (昭和62年) 山頂のみで有感地震
宝永地震
宝永地震(宝永東海・南海地震)
本震
発生日 1707年10月28日
発生時刻 13-14時(日本標準時)
震央 日本 東海道・南海道沖
北緯33度20分0秒
東経135度54分0秒座標: 北緯33度20分0秒 東経135度54分0秒
規模 ML8.4-MW8.7
最大震度 震度7: 遠江袋井、三河野田、河内布施、土佐室津・宿毛大島
地震の種類 海溝型地震
逆断層型
余震
回数 強震17回(記録にあるもの)[1]
被害
死傷者数 死者 2万人(4900人)
宝永地震(ほうえいじしん)は江戸時代の宝永年間に起こった、東海・南海・東南海連動型地震である。2011年に東北地方太平洋沖地震が起こるまでは、記録に残る日本最大級の地震とされてきた[2][3]。地震の49日後に起きた宝永大噴火と共に亥の大変(いのたいへん)と呼ばれる。
江戸時代には南海トラフ沿いを震源とする巨大地震として、この他に慶長9年(1605年)に起こった慶長地震、および嘉永7年(1854年)の安政東海地震および安政南海地震の記録がある。またこの地震の4年前(1703年)には元号を「宝永」へと改元するに至らしめた関東地震の一つである元禄地震があった。
(wikiのデータより)