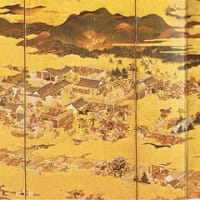九月に入り、少しは涼しくなった。風が秋らしくなった。温暖化や環境破壊など騒がれるようにはなったけれど、季節の流れの根本まで崩れたわけではない。
風に秋の到来を感じる。この感性は日本人にはなじみのもので、万葉集や古今和歌集に見られるように、奈良や平安の昔からのものである。
土佐日記の作者で、古今和歌集の編者でもあった紀貫之は、その昔の立秋の日に、貴族の若者たちの伴をして賀茂川の河原を散策したおり、秋を感じて詠んだ歌を残している。
河風の すずしくもあるか うちよする
浪とともにや 秋は立つらむ
川風が涼しいね。秋風に打ち立てられるようにして寄せくる浪が、いよいよ秋の到来を感じさせるよ。
古今和歌集に収められたこの歌が、いつ詠まれたのかは正確にはわからない。しかし、紀貫之は9世紀に生まれた人だから、すでに千年以上も昔の出来事である。詞書によれば、五条か六条あたりに貴族の屋敷が多かったから、貴族の青年たちと五条川原あたりを散策したときの歌かもしれない。賀茂川はもちろん今も流れている。けれども今は、京阪電車が走ったり、川沿いの道路を自動車が走るなど、その面影はすっかり変っている。私たちは、観念の中で往時を追憶できるだけである。
「土佐日記」のなかには紀貫之が大阪から京にいたるまで桂川を遡ったことが記録されている。桂川はその堤防の上はよく走る。もちろん今の桂川を舟でさかのぼることはできない。コンクリートで堰が造られたりして、舟のみならず魚すらも遡ることがむずかしい。
もし、行政の施策が行き届いていれば、紀貫之が生きた当時の美しい景観を保つことも可能なのだろうが、そうなってはいない。桂川で舟遊びができればどんなに楽しいだろうと思う。現代の市民が平安の貴族たちのように、その河原で散策を楽しめるようになるのは、まだ遠い先のことかも知れない。
JRの駅から自宅に至るまでには、まだかなりの稲田が残っている。やや色づき始めた稲田の間のあぜ道を風に吹かれて歩く。用水路に白い羽のセキレイが見える。
いつ南国に帰るのか、ツバメの夫婦も少し色づきはじめた稲穂の上をまだ飛び交っている。農家の人が作った小さな垣に白や紫の小さな朝顔がまとわりついている。朝顔を植えるのを忘れていたことを思い出す。来年は植えようと思う。もう夏の名残になってしまったけれど、露を帯びた朝顔の花を早朝に眺めるはすがすがしい。
オシロイバナも目に付くようになった。そのほとんどは赤か白の花である。近くを通りかかると、この花特有の香りが漂う。赤と白の縞模様をもった突然変異に交配した花を見るときもある。たまに見る黄色のオシロイバナがとても美しい。