
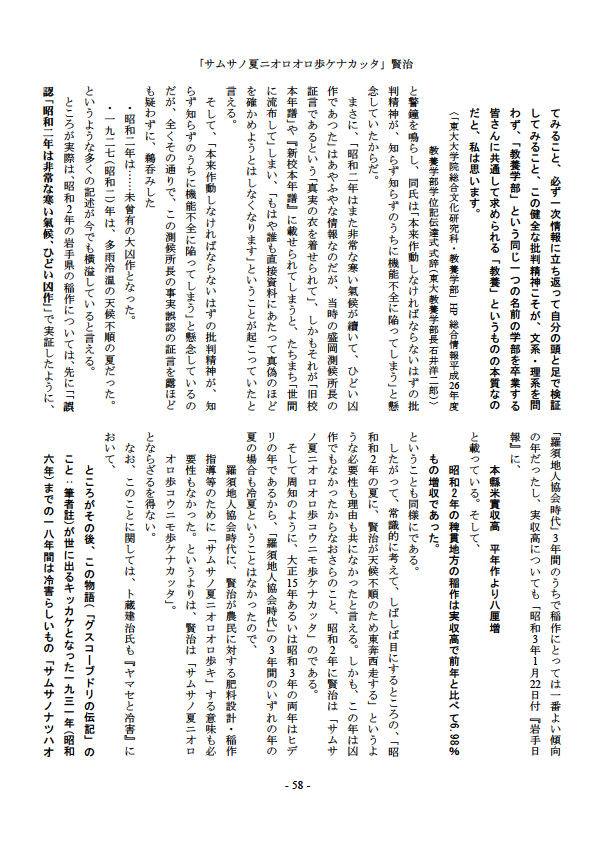



 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 ”『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ移る。
”『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ移る。 ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。
”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。*****************************なお、以下はテキスト形式版である。****************************
「サムサノ夏ニオロオロ歩ケナカッタ」賢治
かつての私は、「羅須地人協会時代」における昭和2年の賢治は農民たちのために、
氣候不順に依る稻作の不良を心痛し、風雨の中を東奔西走し、サムサノナツハオロオロアルキ……○☆
していたとばかり認識していた。
それはまず、同年2月1日付『岩手日報』に「農村文化の創造に努む」という見出しの記事が報道されたことによって、爾後の賢治の活動は肥料設計を中心とした稲作指導に収斂していった(〈註一〉)と理解していたからだ。
そして先に「誤認「昭和二年は非常な寒い氣候、ひどい凶作」の項で考察したように、昭和2年の賢治に関しては、当時盛岡測候所長であった福井規矩三の「昭和二年は非常な寒い気候が続いて、ひどい凶作であった」を始めとして多くの人達がこれと似たようなことを、例えば「一九二七年は冷温多雨の夏」だったとか「未曾有の大凶作」だったということを述べていることを知っていたからだ。
そこで私は、この『岩手日報』の報道を境としてかつてのような羅須地人協会の活動ができなくなってしまった昭和2年の賢治は、それを穴埋めするかの如くに、〝○☆〟しながら、肥料設計を中心とした稲作指導ために専ら献身していたであろうと素直に信じ込み、そして流石賢治!と感心していた。
しかも忘れてはならないことがもう一つある。それは、前年大正15年の紫波郡の大旱害、稗貫郡の不作の際に何ら救援活動をしなかったばかりでなくて無関心でいたことを賢治は悔い、昭和2年の場合に賢治は、多雨冷温による「稻作の不良を心痛し、風雨の中を徹宵東奔西走し」、さぞかし「サムサノナツハオロオロアル」いたりしていたであろうことをである。、そしてそれだけでなく、「大凶作」によって苦悶している農民たちを救わんとして救援活動をしたであろうこともである。
ところがその後、先の福井規矩三の「昭和二年は非常な寒い気候が続いて、ひどい凶作であった」という証言は実は全くの事実誤認であるということを私は実証できた(「誤認「昭和二年は非常な寒い氣候、ひどい凶作」」の項を参照)ので、先の私の認識は悲しいことにどうやら誤解であったということを覚った。そしてそれどころか、
稗貫郡の昭和2年の稲作は天候にも恵まれ、周りの郡とは違っては稲熱病による被害もそれほどではなく、その作柄はほぼ平年作であった(〈註二〉)。
と言えることを知った。
こんな時に思い出すのが、平成27年3月のある大学の教養学部卒業式における式辞だ。同学部長であった石井洋二郎氏はその式辞の中で、
あやふやな情報がいったん真実の衣を着せられて世間に流布してしまうと、もはや誰も直接資料にあたって真偽のほどを確かめようとはしなくなります。
情報が何重にも媒介されていくにつれて、最初の事実からは加速度的に遠ざかっていき、誰もがそれを鵜呑みにしてしまう。そしてその結果、本来作動しなければならないはずの批判精神が、知らず知らずのうちに機能不全に陥ってしまう。
しかし、こうした悪弊は断ち切らなければなりません。あらゆることを疑い、あらゆる情報の真偽を自分の目で確認してみること、必ず一次情報に立ち返って自分の頭と足で検証してみること、この健全な批判精神こそが、文系・理系を問わず、「教養学部」という同じ一つの名前の学部を卒業する皆さんに共通して求められる「教養」というものの本質なのだと、私は思います。
〈「東大大学院総合文化研究科・教養学部」HP総合情報平成26年度教養学部学位記伝達式式辞(東大教養学部長石井洋二郎)〉
と警鐘を鳴らし、同氏は「本来作動しなければならないはずの批判精神が、知らず知らずのうちに機能不全に陥ってしまう」と懸念していたからだ。
まさに、「昭和二年はまた非常な寒い氣候が續いて、ひどい凶作であつた」はあやふやな情報なのだが、当時の盛岡測候所長の証言であるという「真実の衣を着せられて」、しかもそれが「旧校本年譜」や『新校本年譜』に載せられてしまうと、たちまち「世間に流布して」しまい、「もはや誰も直接資料にあたって真偽のほどを確かめようとはしなくなります」ということが起こっていたと言える。
そして、「本来作動しなければならないはずの批判精神が、知らず知らずのうちに機能不全に陥ってしまう」と懸念しているのだが、全くその通りで、この測候所長の事実誤認の証言を露ほども疑わずに、鵜呑みした
・昭和二年は……未曾有の大凶作となった。
・一九二七(昭和二)年は、多雨冷温の天候不順の夏だった。
というような多くの記述が今でも横溢していると言える。
ところが実際は、昭和2年の岩手県の稲作については、先に「「誤認「昭和二年は非常な寒い氣候、ひどい凶作」」で実証したように、「羅須地人協会時代」3年間のうちで稲作にとっては一番よい傾向の年だったし、実収高についても「昭和3年1月22日付『岩手日報』に、
本縣米實収高 平年作より八厘増
と載っている。そして、
昭和2年の稗貫地方の稲作は実収高で前年と比べて6.98%もの増収であった。
ということも同様にである。
したがって、常識的に考えて、しばしば目にするところの、「昭和和2年の夏に、賢治が天候不順のため東奔西走する」というような必要性も理由も共になかったと言える。しかも、この年は凶作でもなかったからなおさらのこと、昭和2年に賢治は「サムサノ夏ニオロオロ歩コウニモ歩ケナカッタ」のである。
そして周知のように、大正15年あるいは昭和3年の両年はヒデリの年であるから、「羅須地人協会時代」の3年間のいずれの年の夏の場合も冷夏ということはなかったので、
羅須地人協会時代に、賢治が農民に対する肥料設計・稲作指導等のために「サムサノ夏ニオロオロ歩キ」する意味も必要性もなかった。というよりは、賢治は「サムサノ夏ニオロオロ歩コウニモ歩ケナカッタ」。
とならざるを得ない。
なお、このことに関しては、ト蔵建治氏も『ヤマセと冷害』において、
ところがその後、この物語(「グスコーブドリの伝記」のこと:筆者註)が世に出るキッカケとなった一九三一年(昭和六年)までの一八年間は冷害らしいもの「サムサノナツハオロオロアルキ」はなく気温の面ではかなり安定していた。むしろ暑い夏で「ヒドリノトキハナミダヲナガシ」=晴天続きで雨が少なく田圃に水がなくなり枯れてゆく水稲を見て、無念さから思わず涙する農民の姿=旱魃が多く発生している(図2・3)。この物語にも挙げたように冷害年の天候の描写が何度かでてくるが、彼が体験した一八九〇年代後半から一九一三年までの冷害頻発期(図2・2)のものや江戸時代からの言い伝えなどを文章にしたものだろう。
<『ヤマセと冷害』(ト蔵建治著、成山堂書店)、15p>
と述べているように、
賢治が生きていた時代の冷害による凶作年としては、盛岡中学を卒業する大正3年までの間には明治35年(賢治6歳)、同39年(10歳)、大正2年(17歳)の3回があるにはあったが、賢治18歳~没年までの間は冷害はただ一度の昭和6年しかなかった。
となるだろう。しかも、多くの方が誤認していると思うのだが、実はこの年昭和6年は確かに岩手県は冷害で凶作だったのだが、稗貫もそうだったというわけではなく、先に掲げた《図1 当時の米の反当収量》から明らかなように平年作以上だった(〈註三〉)。
つまるところ、大正15年の大旱害の時に賢治は一切救援活動をしなかったどころか、全く無関心であったと言わざるを得ないから、残念ながらその時に賢治は「ヒデリノトキハナミダヲナガシ」ていたわけではなかったし、昭和3年の夏には40日をも超える「ヒデリ」が続いたが旱害はなかったのでこの年は「ナミダヲナガシ」たりする必要がなかったから、結局、「羅須地人協会時代」の賢治は「ヒデリノトキハナミダヲナガシ」たとは言えない。一方で、前述したように、「羅須地人協会時代」に冷害はなかったから、賢治は同時代に「サムサノナツハオロオロアルキ」したわけでもない。したがって、折角貧しい農民たちのために献身しようと思って移り住んだはずの下根子桜だったようだが、賢治の実態はこのようなことだったから、これらの無為は後々賢治を苛むものとなっていったことは必然であろう。
そして昭和6年の11月3日、「羅須地人協会時代」のしかるべき時にしかるべきことを為さなかった賢治は己を恥じ、せめてこれからはそのような場合には、
ヒデリノトキハナミダヲナガシ
サムサノナツハオロオロアルキ
するような人間になりたいとうことで、
サウイフモノニワタシハナリタイ
と締め括って懺悔したのではなかろうか。簡潔に言い換えれば、ヒデリノトキに「涙ヲ流サナカッタ」ことの悔いが、賢治をして〔雨ニモマケズ〕を書かせしめた、という一つの見方も充分に成り立ち得る。
それにしても不思議に思うことは、この大正15年の紫波郡赤石村等の大旱害に賢治がどう対応したかは、「羅須地人協会時代」の本質が問われ、かつその在り方の是非が判定できる貴重な試金石だと私は思うのだが、賢治研究家の誰一人としてこの対応についての論考等を一切著していないどころか、言及さえもしていないということだ。一体なぜなのだろうか?
<註一> たとえば、
・羅須地人協会の活動が『岩手日報』によって批判的に報道されたために、昭和二年にははやくも挫折せざるを得なかった。
<『評伝 宮澤賢治』(境忠一著、桜楓社)、289p>
・賢治はこの新聞記事を契機として、たったひとりではじめた農民芸術学校の運動から、思想性の問われない肥料設計の仕事に移行していったように思われる。
<『評伝 宮澤賢治』(境忠一著、桜楓社)、281p>
・(この記事)は充分に好意的な記事であったが、文中の表現(《青年三十余名と共に羅須地人協会を組織し》など)が治安当局の目にとまり、また、前年十二月一日に発足した労農党稗貫支部に賢治が内々に協力したこともあって、花巻警察の取調べを受けるという事態になり、協会の集会活動は以後極めて表立たない形に変わる。
<『新潮日本文学アルバム宮沢賢治』(天沢退二郎編、
新潮社)、73p>
・残された道は徹底した奉仕活動だった。羅須地人協会開設当初の、…(筆者略)…多彩な活動は、思想問題にうるさくなった当時の情勢からしだいに不活発となり、肥料設計を中心にした農事相談に収斂していく。
<『宮沢賢治・第六号』(洋々社)、77p>
・協会員伊藤克己によると、賢治は「其の晩新聞を見せて重い口調で誤解を招いては済まない」と言いオーケストラを一時解散し、集会も不定期になったという。
<『新校本宮澤賢治全集第十六巻(下)年譜篇』(筑摩書房)、343p>
ということであり、断定・推定の多少のニュアンスのちがいはあるものの、爾後の賢治の活動は「肥料設計を中心にした農事相談」であったというのが大方の見方だからだ。
<註二> 当時の『岩手日報』の報道を基にして昭和2年の岩手県の稲作事情をまとめてみれば、
・5月半ばにも降霜があったりと、天候不順ではあったが下旬頃からは天候が回復し月末頃からは田植えが始まった。
・6月、入梅の季節になっても降雨がなく田植えが出来ない田圃が多かったが、6月末に降雨があり殆どの田圃の植え付けは完了した。
・7月~8月、植え付け後の天候にもまずまず恵まれ、活着、分蘖、伸長共に良好であった。やや徒長軟弱な傾向はあるものの、土用入りと同時に相當雨量あり良い天気も続き生育は順調、豊作が見込まれていた。
・9月に入っても、稲は近年稀に見る良い発育をなし登熟も順調に進み平年作をかなり上回る増収を予想されていた。ところが、県全体としては9月下旬に至り多少の風雨の害をうけて倒伏あるいは稲熱病に罹ったために当初の予想を裏切る。
・11月12日、岩手県の第二回豫想収穫高が百六幡五十二石(平年作に比し七厘四毛増収)と発表された。
・明けて昭和3年1月22日に、本縣米實収高 平年作より八厘増という報道がなされた。
となるから、昭和2年の岩手県の水稲の作柄は平年を多少上回るものであったことがわかる。したがって、もちろん、
一九二七(昭和二)年は、多雨冷温天候不順の夏だった。
ということでもないし、
昭和二年はまた非常な寒い氣候が續いて、ひどい凶作であつた。
ということでもなかった、ということが当時の『岩手日報』の新聞報道からは導かれる。
さらには、少なくとも稗貫の場合は前年より実収高で6.98%もの増収だし、周りの郡とは違っては稲熱病による被害もそれほどではなかったということが知られているから、これらと『阿部晁の家政日誌』に記載されている花巻の天気も併せて考えれば、
稗貫郡の昭和2年の水稲は天候にも恵まれ、周りの郡とは違っては稲熱病による被害もそれほどではなく、その作柄はほぼ平年作と言える。
と判断できる。
<註三> 「雨ニモマケズ」が書かれたのが昭和6年11月だからなおさらに、羅須地人協会から撤退はしていたものの東北砕石工場のセールスマンとして働いていた昭和6年ということもあり、病臥中の賢治はさぞかし「サムサノ夏ニオロオロ歩キ」たかったであろうとかつての私は忖度していたが、先に揚げたように、《図1 当時の米の反当収量》によれば、この年は確かに岩手県は冷害だったが稗貫がそうだったわけでもないし、それどころか平年作以上であったから、昭和6年に賢治が地元の農民たちのために「サムサノ夏ニオロオロ歩」く必要性は実はほぼなかった、と言える。したがって、
実は「羅須地人協会時代」のみならず、賢治は中学卒業以降冷害の経験が全くできなかったので、賢治は「サムサノ夏ニオロオロ歩コウニモ歩ケナカッタ」。
ということになりそうだ。
***************************** 以上 ****************************
《鈴木 守著作案内》
◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。
本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。
あるいは、次の方法でもご購入いただけます。
まず、葉書か電話にて下記にその旨をご連絡していただければ最初に本書を郵送いたします。到着後、その代金として500円、送料180円、計680円分の郵便切手をお送り下さい。
〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木 守 電話 0198-24-9813☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)
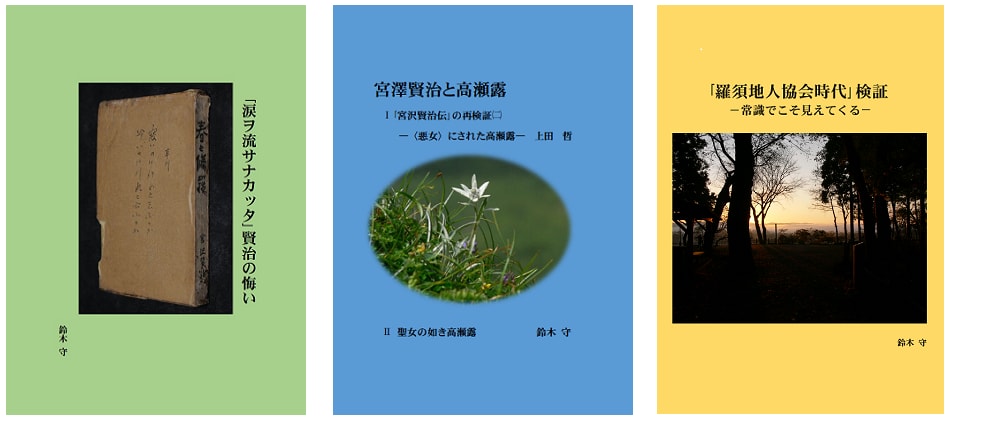
なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。
☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和2年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』
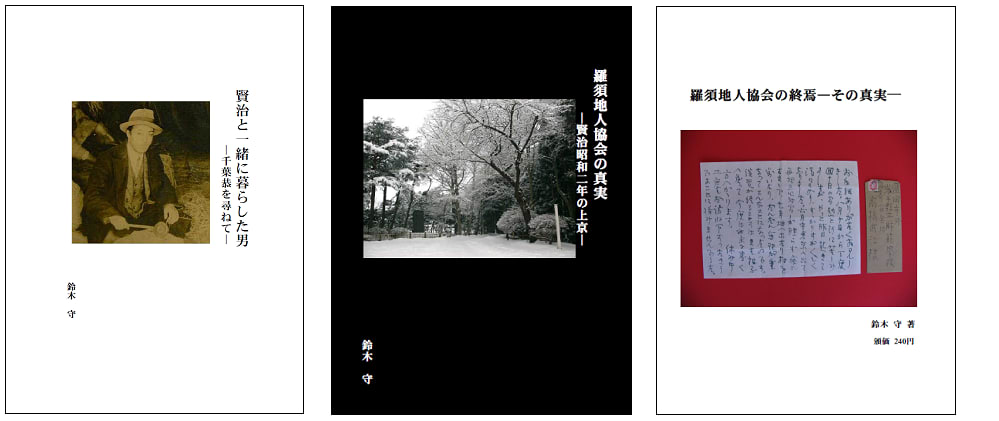


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます