《創られた賢治から愛される賢治に》
青江舜二郎著『宮沢賢治 修羅に生きる』というのは、『宮沢賢治 修羅に生きる』の中に
「2――真実とごまかし」
という節があり、その中で例えば
賢治は羅須地人協会時代において、まぎれもなく労農派のシンパであり協会はその運動実践のためのものだった――この立場に立つとき、賢治が農学校の教師をやめて、この協会を足場に新しい生活にとびこむまでの期間を記した、これまでの伝記に痛感される歯切れの悪いもやもやがたちまちにして消え、いっさいがはっきりしてくる。
<『宮沢賢治』(青江舜二郎著、講談社現代新書)152pより>と青江は言い切っているからである。
しかし今までの私は、青江の主張するところの〝賢治と労農党〟関連についてはなんとなく敬して遠ざけてきた。主張していることには頷けることも少なからずあるとは思いつつも、どうも抵抗感があったからだ。先に挙げた例にしても、そこまで断定的に言い切って良いのだろうかと訝っていたからかもしれない。
ところがこの度、父政次郎が賢治は労農党支部のシンパであったということをあの小倉豊文に対して証言していたことを知って、いつまでも青江の主張や見方を見て見ぬふりをしていることはもう止めようと私は決意した。この状態が続くということは、「目の前に見えているのにそんなことはあり得ないと決めつけて、見なかったことに」することがこれからも続いてしまうことになる。そして、それでは真実を見誤ってしまう危険性があるということを懼れたからだ。
だから、青江は前掲書の中で、
賢治が労農派のシンパであることを、極力秘密にしておこうとしたことを、当時の教え子たちが私に話してくれたとき…
<『宮沢賢治』(青江舜二郎著、講談社現代新書)163pより>と紹介しているが、この教え子たちのとってきたその態度が歴史的事実であったであろうことが十分にあり得ると思えるようになった。そして、教え子たちがそうせなばならなかった理由もある程度頷ける気がしてきた。なぜならば次のような可能性が少なからずあったと考えられるからである。
第二次世界大戦中に戦意高揚のために利用されていた賢治のイメージと、労農党のシンパであった現実の賢治とでは全く真逆であり、賢治が当時「アカ」であると周りから見られていたということが知られることは不都合だった。
 『賢治昭和三年の自宅蟄居』の仮「目次」へ
『賢治昭和三年の自宅蟄居』の仮「目次」へ 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。
”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。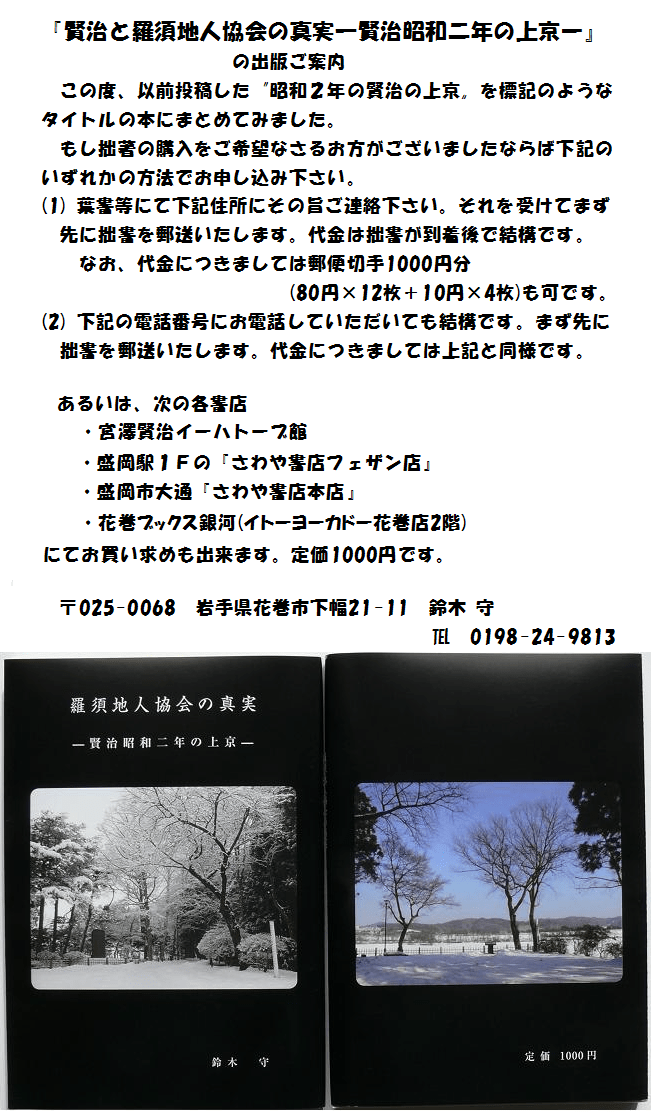
なお、その一部につきましてはそれぞれ以下のとおりです。
「目次」
「第一章 改竄された『宮澤賢治物語』(6p~11p)」
「おわり」
クリックすれば見られます。


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます