私はやっぱりこういうのに反応しちゃう(お祭り系;)ブロガーなんだな、と再認識。でも、マジで時間ごとの情報波及測定やブログサービスごとの記事数比較とかやってみたいですー。反応者のさくっとしたプロフィールも知りたい。今、ブログやSNSがユーザーの中でどういう位置づけになってるのか、指標化できるチャンスかも。・・・なんてことを妄想しつつ。
「mixi日記、無断書籍化はしない」――規約改定の意図をミクシィが説明
ミクシィの広報担当者はこれに対し、「ユーザーの日記などの権利は従来通りユーザー自身が持ち、書籍化も、ユーザーの事前了承なしには進めない」と釈明。その上で、新条項を追加した意図について、
(1)投稿された日記データなどをサーバに格納する際、データ形式や容量が改変される(ユーザーの著作者人格権《同一性保持権》を侵害する)可能性がある
(2)アクセス数が多い日記などは、データを複製して複数のサーバに格納する(ユーザーの複製権を侵害する)可能性がある
(3)日記などが他ユーザーに閲覧される場合、データが他ユーザーに送信される(ユーザーの公衆送信権を侵害する)可能性がある
――など、厳密に著作権法を適用した場合に、ユーザーに無断で行うと法に抵触しかねないデータの複製や改変について、規約で改めて規定した、と意図を説明した。
うーん、ユーザーの反応を見た上での後付け弁解にすぎない、という印象。
そしてそう言われても仕方がないかな、と。
「ユーザーが日記などを投稿する場合、ユーザーはミクシィに対して、その情報を国内外で無償・非独占的に使用する(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行う)権利を許諾するものとする」「ユーザーはミクシィに対し、著作者人格権を行使しない」
という文言が変わらないなら、現時点でユーザーへの説得力はないのでは。
規約というからには、言葉で釈明するのではなく文言化すべきで、上記の3つの場合を重視してるというのなら、そこにきちんと言及した記載にすべきかな、と。
こういう、どうとでも取れる内容を改訂文として提示する根性が、情報を生業とする企業として信じられません。(って、企業サイドのみに有利な文面を、こそっと小さくさりげなく、はデフォではありますが;;)。
※追記:はてなでも2004年もめてるんですね。ライブドアでも過去事例あり。そのあたりきちんとふまえて対策化しなかったのは何故だろう???
やー、なんだかひさびさの大型な祭り、という感じですが、減少するPVを食止めるための話題作りかなぁ、とすら思うほど。
私自身は最初は憤って&純粋に疑問を感じて
個人的に質問書を送ろうと思ってたのですが
少し様子見に切替えて、経過情報を収集していきたいと思いまーす。
最終的にどういう形に落ち着くかが楽しみです。<オイオイ
関連:
mixi利用規約
ミクシイはあなたの日記をあなたに無断で商品化します
インパクトありました。ブロガーへの意識喚起力高いなぁ、と
別の意味で勉強させていただきました。
こういうのを見ると、「うおー、これは伝えなくちゃ」と思いますもんね。
自らの行動がなにより人を動かし説得する、いい事例であり、
ネット力学(コミュニケーション・エネルギー伝達法則)の基本だなぁ、と。
mixi、4月1日より利用規約を改定--日記などについて著作者人格権の行使を禁止
他サービスでの「著作者人格権行使の禁止」関係事例を比較しています。
こういう情報はものすごくありがたいっす。
mixiの利用規約改定に関する重要なお知らせについてひとこと言っておくか
2004年にはてなで同様のトラブルがあったことをふまえた解釈。
わかりやすいです。
mixiも、まともな事業体なら類似事例や前例を調べておけよ、と思いますが。
※今回、視点が逆ですが、参考として。
「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授
作者、権利者、ユーザー、流用者の関係をいろんな方向から
把握しておく必要があるかなぁ、と。
「mixi日記、無断書籍化はしない」――規約改定の意図をミクシィが説明
ミクシィの広報担当者はこれに対し、「ユーザーの日記などの権利は従来通りユーザー自身が持ち、書籍化も、ユーザーの事前了承なしには進めない」と釈明。その上で、新条項を追加した意図について、
(1)投稿された日記データなどをサーバに格納する際、データ形式や容量が改変される(ユーザーの著作者人格権《同一性保持権》を侵害する)可能性がある
(2)アクセス数が多い日記などは、データを複製して複数のサーバに格納する(ユーザーの複製権を侵害する)可能性がある
(3)日記などが他ユーザーに閲覧される場合、データが他ユーザーに送信される(ユーザーの公衆送信権を侵害する)可能性がある
――など、厳密に著作権法を適用した場合に、ユーザーに無断で行うと法に抵触しかねないデータの複製や改変について、規約で改めて規定した、と意図を説明した。
うーん、ユーザーの反応を見た上での後付け弁解にすぎない、という印象。
そしてそう言われても仕方がないかな、と。
「ユーザーが日記などを投稿する場合、ユーザーはミクシィに対して、その情報を国内外で無償・非独占的に使用する(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行う)権利を許諾するものとする」「ユーザーはミクシィに対し、著作者人格権を行使しない」
という文言が変わらないなら、現時点でユーザーへの説得力はないのでは。
規約というからには、言葉で釈明するのではなく文言化すべきで、上記の3つの場合を重視してるというのなら、そこにきちんと言及した記載にすべきかな、と。
こういう、どうとでも取れる内容を改訂文として提示する根性が、情報を生業とする企業として信じられません。(って、企業サイドのみに有利な文面を、こそっと小さくさりげなく、はデフォではありますが;;)。
※追記:はてなでも2004年もめてるんですね。ライブドアでも過去事例あり。そのあたりきちんとふまえて対策化しなかったのは何故だろう???
やー、なんだかひさびさの大型な祭り、という感じですが、減少するPVを食止めるための話題作りかなぁ、とすら思うほど。
私自身は最初は憤って&純粋に疑問を感じて
個人的に質問書を送ろうと思ってたのですが
少し様子見に切替えて、経過情報を収集していきたいと思いまーす。
最終的にどういう形に落ち着くかが楽しみです。<オイオイ
関連:
mixi利用規約
ミクシイはあなたの日記をあなたに無断で商品化します
インパクトありました。ブロガーへの意識喚起力高いなぁ、と
別の意味で勉強させていただきました。
こういうのを見ると、「うおー、これは伝えなくちゃ」と思いますもんね。
自らの行動がなにより人を動かし説得する、いい事例であり、
ネット力学(コミュニケーション・エネルギー伝達法則)の基本だなぁ、と。
mixi、4月1日より利用規約を改定--日記などについて著作者人格権の行使を禁止
他サービスでの「著作者人格権行使の禁止」関係事例を比較しています。
こういう情報はものすごくありがたいっす。
mixiの利用規約改定に関する重要なお知らせについてひとこと言っておくか
2004年にはてなで同様のトラブルがあったことをふまえた解釈。
わかりやすいです。
mixiも、まともな事業体なら類似事例や前例を調べておけよ、と思いますが。
※今回、視点が逆ですが、参考として。
「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授
作者、権利者、ユーザー、流用者の関係をいろんな方向から
把握しておく必要があるかなぁ、と。











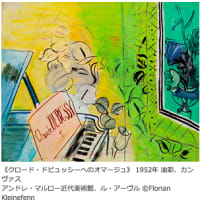
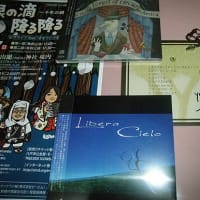













言葉足らずでしたが、推測してくださった通りです。
お手数おかけしました!
ようするに、mixiが実際に日記本をユーザーに無断で発売するというような事態にならない限りは、その可能性がある規約を設定されても、侵害にはならないということですよね。なるほど。
>その規定が存在することそれ自体が,直ちに権利侵害になるとはいえません。
なんだかちょっと不思議な気もしますが
「コロすぞ」「氏ね!」と言ったからといって即罪に問われることはない、に近いのかなぁ(めっちゃ乱暴でゴメンナサイ;)と。
このあたり、ユーザーの危機意識を煽ってしまったことで社会的信用を(一時的であるにしろ)失ったことのほうが、現時点では影響が大きいかもしれないですね。試行錯誤にしては大きな代償だったかも。SNSの成り立ちからして、ユーザー不在はありえないので。
いろいろなブログで、他のサービスとの規約比較が
出ていてなかなか興味深いです。
今回はやはり「mixiであったこと」「後発行為であったこと」「ブログメディア市場が活性化してユーザーサイドの著作権意識が高まってきていること」が大きい気がします。
説明レスをありがとうございました!
やや,質問の趣旨が分かりずらいのですが,規約改定によって,不法行為責任が発生するかという意味なら,それは無いと思います。
まず,一般論ですが,ある規定が法律に違反しており無効であったとしても,その規定が存在することそれ自体が,直ちに権利侵害になるとはいえません。
権利侵害というためには,(おおざっぱにいえば)なにかしらの損害がなくてはいけないわけなので,実害が現実に生じていない以上「権利侵害」とはなりません。(厳密には,権利侵害と損害は別個に観念されるので,以上の説明は,正確さを欠いています。現在は,どちらかといえば「損害」有無のほうが重要な要件だと言われています。損害がないため,不法行為は成立しない,というのが正確かもしれません。ただ,このへんは,わかりにくいので,質問に合わせて,権利侵害にならないと説明しました。)
次に,今回の規定ですが,部分的に無効になる可能性はありますが,この規定があることによって,直接的に何かしらの損害が直ちに生じるわけではないので,不法行為でいうところの権利侵害(損害)は無いと思います。
また,著作権侵害罪(著作権法119条)になるかといえば,同じくならない思います。
昨日、この件でじっぱ様に質問しに伺おうかな、と思っておりました。
私もあれこれアップされている事例を読んで、確かにユーザーに逆手に取られるケースもあるだろうし、シリアスなトラブル(犯罪性の高いものやつながりそうなもの)の芽を積むためには必要な部分もあるかな、とは思うものの、責任に関しては全面的にユーザーの個人責任であり、権利部分はmixiに一任、という部分が前面に出てる感じで、ユーザー感覚で言えばこのままでは到底飲めない条件だなぁ、と思います。
ネットでの著作権問題が全般的に揺れている時に、美味しい部分だけ先に確保、と見られてもしかたない表現かな、と思うのですが。
>ちなみに,ミクシィの広報担当者の発言は,規約の文言に書かれていなくても法的な意味は十分にあります。
メディアに開示された時点で企業としての責任・拘束力を持つのですね?
こういう(私にとっては)専門情報はとてもありがたいです。
>また,例え,著作者人格権の行使を制限する規約を定めたとしても,113条6項との関係では,無効なんじゃないかと思います(私見)
『6 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。』
著作権法はより上位ですよね。mixiはこのあたりを個人の意志で放棄させたいのでしょうね。今回のmixiの規約改定は、もしこのまま規約改訂されたとして、著作権侵害には抵触しないのでしょうか?
今のままでは、やはりどうとでも解釈できる文面だと感じるのですが。
いや、この記事を書きながら、今まではネットでの既得権者の著作物流用(you tube等)への制限に反対していたのに、立場が変わると著作権を奪われる(便宜上この表現で)のは絶対許せないな、と思う自分に矛盾を感じつつ。(汗;
ただ、これって「のまねこ騒動」に近い感じというか、個人と企業の違いかなぁ、と。もしくは趣味とビジネスというべきか。やはりmixiだったということも大きい気がします。
そのあたり自分でももっと整理が必要だな、と感じました。
ネットの著作権の新しい辞書&ルールブックが早急に必要だなぁと感じます。
(個人ユーザー優先で<オイ)
著作者人格権というのは,結構幅が広く(著作権法18条,19条,20条,113条6項など),著作物の利用者側からすると,リスク要素なので。
で,「著作者人格権を行使しない」というのは,実は結構,面白い規定のしかだなあと…
そもそも,著作人格権は譲渡も相続もできない権利で(著作権法59条),放棄が可能か?という点についても争いがあるので「行使しない」という形にしているんだろうなと。(ここは想像)
この辺は,中山信弘の「著作権法」という本に詳しいです。(普通の人には難しい内容ですが,ネット関係に対応した体系書としては結構良い本です。著作者人格権の問題点についても詳しいので。)
ちなみに,ミクシィの広報担当者の発言は,規約の文言に書かれていなくても法的な意味は十分にあります。
特に,こういった規約に関して企業側が説明したことは,例え口頭であったとしても規約の解釈において意味をもってきます。
また,例え,著作者人格権の行使を制限する規約を定めたとしても,113条6項との関係では,無効なんじゃないかと思います(私見)