
二本杉峠(旧天城峠)
山の仲間がラインで「河津側の二本杉歩道は少しづつ整備されそうですね。」と情報を届けてくれた。
こちらにリンク↓
吉田松陰も通った古道“通行禁止の道”復活へ一歩【河津・二本杉歩道】
(『テレしずWasabee』2024年6月15日)

峠の名の由来となった二本杉
歴史的な街道である旧下田街道を今に伝える二本杉峠の河津側は、大雨被害によって10年余に亘り「閉鎖」されたままであったが、歩道の復活に向けて地元の有志たちが登山道整備を始めたとのことだった。二本杉歩道の荒廃は河津側だけでなく、北側の伊豆市(湯ヶ島)側も同様で、先日の伊豆山稜線歩道山行の際にも感じられたことだった。「天城遊々の森(旧大川端野営場)」の上部にあたるが、歩道の管理者すらおらず勝手に手が付けられない状況のようで、こうした歩道の保全には行政の問題もあって難しい面がある。
また、旧下田街道という歴史的遺産の側面を重視するのか、あるいは単なる自然歩道として整備するのかによっても、補修方法や管理方法が変わってくることだろうと思う。その意味で、「目標は下草やササが茂る環境になり、その中に人が歩ける最小限の道があることです。」という施工者の方向性には少し考える処があるが(馬も、駕篭も、荷車も通ったのが“街道”であるのだから)、ともあれ手が付けられ始めたのは良いことだった。


二本杉峠下(河津側)に佇む地蔵仏
二本杉歩道について以前、私は所属会の会報に次のような文を寄せていた。
* *
来年度定例山行候補地としてTAKさんより提案の「二本杉歩道」を、一緒に歩かせていただいた。二本杉峠は、三島から下田まで伊豆半島を縦断する旧下田街道(現国道414号)が天城山稜線を越える核心部である。河津町の資料には次のように記されている。
天城峠を越えて南(賀茂)と北(田方)の交通の始まったのは、いつの頃か定かではないが、いくつかの古道や旧道が残っている。その内の一つ、二本杉峠(旧天城峠)越えのルートは文政2年(1819)に開通し、幕末開国を巡って、数多くの歴史上の人物が往来した街道である。(中略)明治38年(1905)に旧天城トンネルが開通するまで、この街道は伊豆の南北を結ぶ幹線道路で、文化交流や日本歴史に多大な影響をもたらしたため、日本の歴史の道百選に選ばれている。
TAKさんの要請は、この峠道は近年の大雨で荒れ、河津側の宗太郎園地~二本杉林道間が閉鎖されているようだが、歩行が可能かどうか踏査してみるということ。この道は観光地である河津七滝の延長上であって、「閉鎖」はおそらく観光客に向けての処置だろうと推測した。案の定、登山者にとっては「少々荒れ気味」位で普通に歩ける状態だった。長い歳月踏まれてきた道は、易々とは失われない。ただ、気になることもあった。
二本杉歩道は「踊子歩道」(旧天城トンネル越え)などと共に、前記文のとおり行政もその価値を認めているのだが、歩いてみると保存意欲が後退しているのではないかと感じられた。これは河津側だけでなく湯ヶ島側も同様。倒木の伐採除去や木橋の補修、付け替え、道標の明確化といったことが、近年行われた様子が見られない。無論、それは登山者にとってはさほど大きな問題ではないが、一方で「歩道」と銘打ち歴史的遺産として位置付けている割には中途半端な対応ではないかと思う(ひょっとすると放棄、永遠の閉鎖ではないかとさえ思える)。道は歩かれることによって維持されるのだから、「通行止め」ではなく、この峠道を歩いてみようと思う人たちに開かれることが大事なことだと言えよう。現代の下田街道=伊豆縦貫道の早期開通と同等に、過去の下田街道の「開通」も意義があることだろう。
(2015年7月記)
* *

二本杉歩道の壊れた橋(2016年12月)
河津七滝宗太郎園地より北西に上がり伊豆山稜線を越える二本杉歩道(旧下田街道)については、既に昨年6月踏査を行った(『やまびこ』№220)。その後のルート状態と冬季となる定例山行での問題点を確認するため下見を行った。
今回再訪し、宗太郎園地~二本杉林道間の状態は前回同様、沢内が歩きにくいものの登山者にとって特に危険な箇所があるものではないが、宗太郎園地分岐の橋渡り口には進入禁止ロープが前よりもしっかりと張られ、また二本杉峠北側には通行止め告知の指導標が目立って設置されていた。もとより2013年夏より「当面の間」ということで閉鎖され三年余が経つが、一向に修復に着手した形跡はないのだから、道は荒れるに任せたままというわけだ。定例山行という性格上、また冬季という条件上、通行止めルートを使い万が一参加者にケガがあった場合には問題があると判断、天城峠から二本杉峠への縦走に変更を提案し、企画者のTAKさんの了解を戴いた。道の駅に下る本隊と別れ、同ルートを逆に歩いた。葉を落した山稜線歩道からは富士山がきれいに眺められ、展望のない二本杉歩道より気持ち良く歩けるかなと感じた。
前回の報告にも記載したことだが、行政の保存意欲の後退と「閉鎖」という安直な方法が、歴史的な街道を埋もれさせてしまうのではないかと危惧する。道は人に歩かれることで保たれるのだから。
(2016年12月記)

涸れ沢状で踏み跡は判然としない(2016年12月)














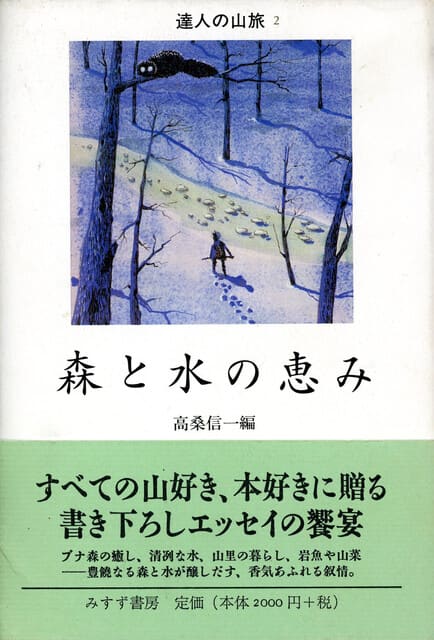





 アジサイ
アジサイ ムラサキカタバミ
ムラサキカタバミ ノアザミ
ノアザミ
 マツヨイグサ
マツヨイグサ ホタルブクロ
ホタルブクロ