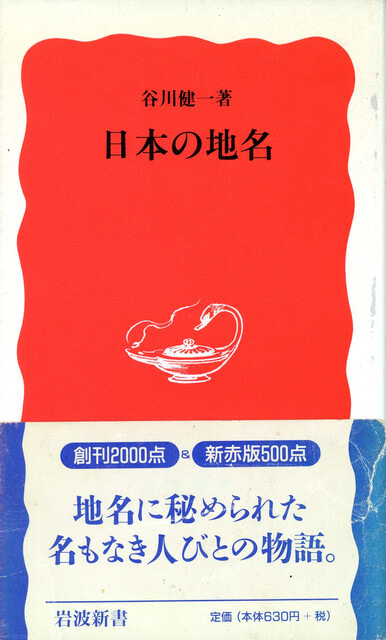一面に花が咲いたソバ畑=静岡市葵区小河内
(2014年)9月22日付静岡新聞に〝焼き畑復活3年目 静岡・井川の「在来ソバ」根付く〟という記事が掲載されていた。
静岡市葵区井川地域で伝統の焼き畑農業を復活させ、在来ソバのブランド化を目指す取り組みが3年目を迎えた。ことしは近隣の民家を改装し、そば打ち体験など交流拠点としての活用も始まった。県外からの移住者も受入れ、集落に活気が生まれ始めている。
として、2012年、井川小河内で約50年ぶりに焼き畑を実施し、井川地区の村起こしの一つとなりつつあることが紹介されていた。
井川において焼畑が行われていたのは、遠い昔のことではない。戦後しばらく、場所によっては昭和50年代まで続けられ、山間(やまあい)の集落という地理的条件に即した農法であり、生活の基盤であった。井川の昭和28年の主要農作物の作付面積は、水稲がわずか13.2反に対し、焼畑作物である稗(193.4反)、粟(69反)、大豆(70.6反)、小豆(70.2反)、甘藷(181反)の割合が高く、主要な作物であったことがわかる。また、井川における焼畑農法では、3、4年を基本とするローテーションで作物を植え、20~30年かけて雑木林を復活させるという循環的な方法が用いられ、山の自然のリズムと恵みに頼る暮しを、長い伝統として保持してきた。

近世における焼畑のローテーションの想定図

焼畑の居小屋と井川湖
(共に静岡市立登呂博物館『祖父母から孫に伝えたい焼畑の暮らし』より)
米が日本人の生活を支え、稲作が日本文化生成の基盤になったことはまぎれもない事実である。しかし一方、焼畑農業が山に住む人々の生活を力強く支え、そこに独自な文化を育んできたのも事実である。(中略)
焼畑農業を基盤として生まれた伝説、民謡、芸能、家屋、食物、酒、祭り、儀礼、葬送などを総合的、有機的にとらえた時に、真の「焼畑文化論」が成り立ち、それがまた日本文化解明の鍵にもなる。(野本寛一『大井川 ―その風土と文化―』)
日本の〈原風景〉として語られる田園と里山というものとは異なるもの、これは井川に限ったことではなく、例えば一昨年合宿の檜枝岐や遠山郷・下栗の里などを格別に上げずとも、山の行き帰りに山間の集落に目をやれば幾つでも気付く風景だ。「豊葦原千五百秋瑞穂国」(とよあしはらのちいおあきのみずほのくに)この記紀来の「瑞穂の国」(某首相が「美しい国、日本」の同義としてよく使う)のみが、古代から現在に至るまで、「日本」の隅々に亘るもので無かったことは確かであって、言うなればヤマトとしての理想郷〈幻風景〉だったのではないか。「瑞穂の国」を前提とした伝統、文化、地域は、野本寛一氏の述べるように「日本」のある個別の一面に過ぎず、列島には南北や山間の地域によって様々な伝統、文化が存在し、多種多様な「日本」があったはずだ。それは今日の「東北」や「沖縄」の問題、位相にも繋がっているのだと思う。
井川の歴史は古い。割田原遺跡は縄文時代中期の遺跡であり、この頃から既に人の住み着きがあったことが示されている。また、井川田代では「先祖が遠山から来た」と伝えられ、山を越えた伊那側でも滝浪姓の家に「井川から来た」「井川へ行った」という伝承があったという。人だけではなく文化の根源となる信仰(神)もまた奥山の峠を越え、信濃俣、沼平、田代と入ってきたことは、田代諏訪神社の伝えから明らかで、南アルプスそして諏訪へと連なる三住ヶ岳(大無間山)が聖地として崇拝されてきたことを示している。そうした「瑞穂の国」以前の、あるいは外の、今日にまで連なる様々な「日本」の姿を垣間見ることも、私にとって山歩きの一つである。
(2014年10月記)