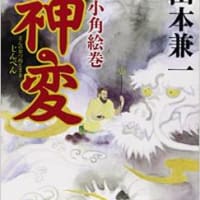ご多分にもれず、Facebookに入っていて、時折気が触れたようにコメントを書いていたりする。
フォローしている中に共産党のシンパである、あるいは党員であると思われる人がいて、新聞「赤旗」の記事などを紹介してくれる。本日紹介された記事が、アフリカモザンビークの農地を日本の資本が買い占めているという話だ。
モザンピークといえば、サイマル出版会が出していたモザンビークの嵐という書籍を大昔に読んで、その成立などの激動の時代を知識として少し保持している。
ここには日本のODAの問題が焦点として存在しているのではないかと思うのだ。
日本のODAの多くは、東南アジアに供与されていった。フィリピンやインドネシアなどの森林資源は、山がまるごとハゲ山になるほどに、枯渇し始めていて、その森林から伐採された木材の多くが、日本向けになる。工業化も進めているのだが、多くの発展途上国がそうであるかのように、工業廃棄物などの問題が生じている。
自然環境と共生してきた社会は、例えば廃棄物も自然の力で分解し、再生するという自然の処理サイクルの中で社会が構成されている。そこに、工業化と消費の世界が入り込む。廃棄物をゴミとして処理する方法や、生産が環境に与える方法、それまでの豊かな自然環境を保全する方法を、すべて「コスト」として扱い、いわゆる「公害」を世界に撒き散らす役割を、残念ながら一面で果たしているのが、ODAの問題でもある。
木は自然に生えてくるものだ、という感覚が、それまでの「発展途上」な生活の中では信じられていた地域で、当然、そうした木が自然に生えてくる程度のサイクルでしか木材が消費されなかった社会に、いわゆる「近代化」を持ち込み「消費社会」を持ち込む。しかし、他方では、山林の保全には放置しておくと駄目で、場合によっては植林が必要だ、という自明の事を知らせない。
多くの発展の影には、その歪とも言えるものがある。光だけを強調するあまり、その影について触れないままに、幻想の未来を振りまくような「外交」が罷り通る。その根底には、常に強い側の経済的利益の優位性だけがあるのだが、弱い側の持つ資源、それを回収するために生じる弊害については触れない。
例えば金の精錬に多くの場合用いられている水銀は、水俣病などを産んだ。しかし、多くの途上国での金産出には、未だに水銀が使われている。すでに、知見があることに対して、ほとんど無関心でありつづけたままの「経済」である。それは人を生かす事を考えないという事である。
不具合を示しながらも、それでも交渉の中で、不具合を減らすための手法も含め知らせるという姿が無いと、相手国の人々の信頼は得られない。やらずぶったくりでは、この国の国際的な立場そのものが脆弱化するのだ。
ODAの問題点は、大規模な援助にこそ問題が生じる。巨大なプロジェクトへの政府援助は、実は日本企業の受注ばかりが目だつ。紐付き援助と言われる所以であり、政府が供与した援助の金が、実態として相手国に回らずに、プロジェクト受注という形で日本企業に還流しているということだ。
そして、問題点は、例えば公害に対する考え方予防のための設備、公害が起きる仕組みと防止するための方法などが、相手国に全く伝わらず、世界に公害が広がっている点だ。
工業化、経済成長などは、光の側面だが、公害やごみ処理問題などは影の側面でもある。これらを併せての援助でなければ、それは歪に発達してきた日本の公害問題やゴミ問題なども併せて外に押し付けるだけのものとなる。
善意に基づく青年海外協力隊などが、そうした影の部分を補う役割を果たしているのだろうが、いかんせん数がすくなく、現地での発言力も確保されているとは言えない。時として日本の資本の尖兵として活動するようにも見える。個々の協力隊員は善意なのだが、その強力システムそのものが、国益の名の下、相手国への経済的侵略となってしまう。これでいいのか?