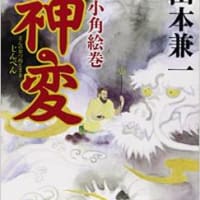後藤政志より 2013年を振り返って 原子力の問題
この動画の中で後藤さんが示す問題点は、現実に「どう対応するか」という問題がある。山積みとなっている問題の、有効な「解」が見つかっていないという話にしか見えない。福島第一事故以外にも核関連問題は存在続けているし、些細と思われる事故も起きている。それが些細な段階で今後も留まるかどうかは、誰も確約できない。
世界の叡智を結集しなくてはならない。が、それでも「解」が見つかるとは言えない。
少なくとも「解」が無いものを「実用」することの危険性は、福島第一原発事故で十分に解ったはずだ。いや、本当はスリーマイル島の事故でも、チェルノブイリ事故でも、事故が「自分の事」として考えねばならなかったのに、対岸の火事のように扱ってしまった。
事故は起きないというのは、単なる過信でしかなかった。自動車の運転だって誰も事故を起こそうとは考えない。考えないのだが事故は起きる。十分に注意しても、他者の不注意での事故は起きる。精密な機器ならば、部品のひとつが規格外の状態で、正しく備え付けられないだけでも、全体的な故障の発生に繋がる。
基本的に技術というものはトライ&エラーで向上する。そうしたエラーの繰り返しによって、故障の程度を減らすための部品同士の設置方法、距離などがわかり、取り扱い方法も分かる。ところが、原発はエラーが許されない技術である。エラーが放射能という極めて危険な害毒の汚染に直結するからだ。したがって、エラーが生じない前提の既存の安定した技術が基本となって作られる。しかし、原発の発するエネルギーは、人間がかって使ったことの無いほどのレベルのものだ。部材の劣化などについても、シミュレーションでしか確認できない。
シミュレーションは、与えられたパラメーターによって結果が変わる。自然界が実際に表す状況は、時としてシミュレーションの範囲を超えた「力」を生じさせる。東日本大震災の起きた姿は、多くの地震学者の想定範囲を超えたものだった。
つまり、我々の知見などは、たかが知れていて、そのたかが知れた知見に基づくシミュレーションは、実際に起きる事象の範囲を大きく変えている。そうした知への謙虚さが失われている事そのものが、我々自身に振りかかる災厄を生み出す。