知られざる30年の開発史_特集 mRNAワクチン_日経サイエンス2021年11月号 出村政彬 日経サイエンス社

ウイルスのゲノム情報が報告されてからわずか2日後(20200113)にモデルナのワクチンの基本設計が
分かったなんてこともあり、COVID-19に対するワクチンまでの流れがとんとん拍子に見えたかもしれない。
しかし、mRNAワクチンには過去30年にわたる研究開発の歴史があったりもするわけで・・・・・・
頼りないメッセンジャー
mRNA分子の単離は1961年には成功していたがDNAの遺伝子工学が1970年代から盛んになったのに対し、mRNAが全身の細胞に含まれるごくありふれた紐状の分子でメモ、付箋的な役割が終われば速やかに分解される壊れやすい特徴により研究は低調。それでも1990年にマウスの筋肉にmRNAを注射し、体内でタンパク質を合成させる実験に成功(米ウィスコンシン大学)。
体に拒絶された外来RNA
壊れにくく扱いやすいDNAワクチンの研究は1990年代半ばにHIV向けのワクチンの臨床試験が行われたり。
一方、リポソームで包んだmRNAを細胞に届ける試み(1993)は追試の動物実験で炎症が続出、これは投与されたmRNAが危険な侵入者と見なされ、過剰な免疫反応が起こったから。外来mRNAに対する免疫反応を抑える方法がなかなか見つからないまま21世紀に入り、1年、2年、・・・
免疫の目をかいくぐれ
2005年、カリコとワイスマンら(米ペンシルベニア大)は体細胞が死んだ後に放出される自分のRNAをあまり
攻撃しないことに注目し、外来RNAにはない「目印」を見つけた(この論文を査読した研究者らも化学修飾されたRNAでは免疫反応が弱まることを半年ほど前に報告)。RNA中の塩基Uを似た構造の塩基シュードウリジンの人工的に置き換える改変でmRNAの発現効率を高めた。外来RNAがすぐに分解されなければ、コードされたタンパク質が細胞内で作られ、医薬品としての目的を果たすことも叶いそうに。
ワクチンにうってつけ
カリコらの示した塩基の置き換えはRNAへの免疫反応が程よく抑えられているなど、さじ加減が絶妙で(治療薬には必要なタンパク質の量に達する前にmRNAが分解される傾向であっても)ワクチンにうってつけ(なことに当人らが気付くまで幾何の時間を要したらしい)。免疫を抑制することへの苦心が免疫を誘導するワクチンには嵌った形。
ワクチンにmRNAを用いる場合、免疫系の訓練※に必要な抗原タンパク質が一時的に作られ、後は速やかに分解されることになる。
(※体細胞から急に異質な抗原タンパク質が出てくるから本物のウイルス感染みたいな状況)
当たり始めた光
2010年ごろから様々な学会で分解されて消えるmRNAは安全性を担保し易いなど医薬として使えるムードが高まり、特にがんワクチンの臨床試験が多く実施された。2013年にカリコを引き抜いたドイツのビオンテックもがんのmRNAワクチンを精力的に開発。
運び屋にも一工夫
血液中をはじめ、体内の至るところにRNAを分解する酵素があるため、mRNAを細胞に届ける薬物送達技術DDSの確立も欠かせない。脂質やタンパク質のカプセルで保護し、細胞内に到着したらカプセルは速やかに壊れて中身のmRNAを放出されるといった工夫が考えられる。
現在のmRNAワクチンに使われている技術は巧妙。外側の膜の中にいくつもの袋状の膜があり、mRNAはこの袋に閉じ込められている。粒子全体の径はウイルス程度な100nmほどで、外側の膜は主に水にも油に馴染む脂質ポリエチレングリコールで細胞近くに到達させる。細胞が異物を細胞膜ごとのみ込み小胞に閉じ込めるエンドサイトーシスを起こすので取り込まれたワクチン粒子の外側の膜が外れることになる。内側にあったmRNAを直接包んでいる袋状の膜には酸性下で正の電荷を帯びるカチオニック脂質が含まれている。細胞は小胞内を酸性化にして異物を処理をしようとうするので負に帯電している小胞の膜とカチオニック脂質がくっつき、小胞の外側である細胞内にmRNAが放出されることになる。また、流動性を高めて細胞内でmRNAを放出しやすくするヘルパー脂質や安定化させるコレステロールも脂質膜に含まれる。
(r575"77")うそ寒の体内巡るワクチンや、"脂質"の"カプセル"によるmRNAワクチンの"デリバリー"の"妙"は大学入試問題(化学)にしてほしいぞ
パンデミックならmRNA
毎年開かれるようになった国際mRNAヘルスカンファレンスでは感染症のパンデミックが起こればmRNAが必要になるという考えも囁かれ、2018年にビオンテックはファイザーと共同でインフルエンザ向けのmRNAワクチンの開発を開始、2019年までにモデルナやビオンテックを筆頭に複数の製薬企業がジカ熱やチクングニア熱、ヒトパピローマウイルス感染症に対するワクチンの臨床試験を開始。病原体のゲノム情報を解読する(2005年前後に生まれた次世代)シーケンシングの技術が中国で見つかった未知のウイルスのゲノム情報を数週間で突き止められるレベルに発達。2002年のSARS、2012年のMERSの経験からコロナウイルスのワクチンにはスパイクを使うと良いという知見がCOVID-19のmRNAワクチンに活かされる。これらに多額の資金が開発現場に投入され、大規模な臨床試験の実施機会を得たことが最後の一押しになったと現実を知るある研究者が評するのも頷ける。
20世紀末からRNA利用の技術について相当いい加減な情報収集を忘れた頃に思い出したようにしたことによる生半可に齧った状態だったので昨今の新聞やテレビなどのワンポイント的な解説では十分な修正ができないでいたごちゃごちゃをようやく整理しつつ未熟者でも少しは理解を深めた気持ちを得る機会を与えてくれた記事!
どうでもいいことだが小さい頃、ウイルスってビールスという表記がされていたことも思い出したり(で読む側のごちゃごちゃ30?年史でもあったりしたかも)。
"→♂♀←"「オススメ」のインデックスへ

ウイルスのゲノム情報が報告されてからわずか2日後(20200113)にモデルナのワクチンの基本設計が
分かったなんてこともあり、COVID-19に対するワクチンまでの流れがとんとん拍子に見えたかもしれない。
しかし、mRNAワクチンには過去30年にわたる研究開発の歴史があったりもするわけで・・・・・・
頼りないメッセンジャー
mRNA分子の単離は1961年には成功していたがDNAの遺伝子工学が1970年代から盛んになったのに対し、mRNAが全身の細胞に含まれるごくありふれた紐状の分子でメモ、付箋的な役割が終われば速やかに分解される壊れやすい特徴により研究は低調。それでも1990年にマウスの筋肉にmRNAを注射し、体内でタンパク質を合成させる実験に成功(米ウィスコンシン大学)。
体に拒絶された外来RNA
壊れにくく扱いやすいDNAワクチンの研究は1990年代半ばにHIV向けのワクチンの臨床試験が行われたり。
一方、リポソームで包んだmRNAを細胞に届ける試み(1993)は追試の動物実験で炎症が続出、これは投与されたmRNAが危険な侵入者と見なされ、過剰な免疫反応が起こったから。外来mRNAに対する免疫反応を抑える方法がなかなか見つからないまま21世紀に入り、1年、2年、・・・
免疫の目をかいくぐれ
2005年、カリコとワイスマンら(米ペンシルベニア大)は体細胞が死んだ後に放出される自分のRNAをあまり
攻撃しないことに注目し、外来RNAにはない「目印」を見つけた(この論文を査読した研究者らも化学修飾されたRNAでは免疫反応が弱まることを半年ほど前に報告)。RNA中の塩基Uを似た構造の塩基シュードウリジンの人工的に置き換える改変でmRNAの発現効率を高めた。外来RNAがすぐに分解されなければ、コードされたタンパク質が細胞内で作られ、医薬品としての目的を果たすことも叶いそうに。
ワクチンにうってつけ
カリコらの示した塩基の置き換えはRNAへの免疫反応が程よく抑えられているなど、さじ加減が絶妙で(治療薬には必要なタンパク質の量に達する前にmRNAが分解される傾向であっても)ワクチンにうってつけ(なことに当人らが気付くまで幾何の時間を要したらしい)。免疫を抑制することへの苦心が免疫を誘導するワクチンには嵌った形。
ワクチンにmRNAを用いる場合、免疫系の訓練※に必要な抗原タンパク質が一時的に作られ、後は速やかに分解されることになる。
(※体細胞から急に異質な抗原タンパク質が出てくるから本物のウイルス感染みたいな状況)
当たり始めた光
2010年ごろから様々な学会で分解されて消えるmRNAは安全性を担保し易いなど医薬として使えるムードが高まり、特にがんワクチンの臨床試験が多く実施された。2013年にカリコを引き抜いたドイツのビオンテックもがんのmRNAワクチンを精力的に開発。
運び屋にも一工夫
血液中をはじめ、体内の至るところにRNAを分解する酵素があるため、mRNAを細胞に届ける薬物送達技術DDSの確立も欠かせない。脂質やタンパク質のカプセルで保護し、細胞内に到着したらカプセルは速やかに壊れて中身のmRNAを放出されるといった工夫が考えられる。
現在のmRNAワクチンに使われている技術は巧妙。外側の膜の中にいくつもの袋状の膜があり、mRNAはこの袋に閉じ込められている。粒子全体の径はウイルス程度な100nmほどで、外側の膜は主に水にも油に馴染む脂質ポリエチレングリコールで細胞近くに到達させる。細胞が異物を細胞膜ごとのみ込み小胞に閉じ込めるエンドサイトーシスを起こすので取り込まれたワクチン粒子の外側の膜が外れることになる。内側にあったmRNAを直接包んでいる袋状の膜には酸性下で正の電荷を帯びるカチオニック脂質が含まれている。細胞は小胞内を酸性化にして異物を処理をしようとうするので負に帯電している小胞の膜とカチオニック脂質がくっつき、小胞の外側である細胞内にmRNAが放出されることになる。また、流動性を高めて細胞内でmRNAを放出しやすくするヘルパー脂質や安定化させるコレステロールも脂質膜に含まれる。
(r575"77")うそ寒の体内巡るワクチンや、"脂質"の"カプセル"によるmRNAワクチンの"デリバリー"の"妙"は大学入試問題(化学)にしてほしいぞ
パンデミックならmRNA
毎年開かれるようになった国際mRNAヘルスカンファレンスでは感染症のパンデミックが起こればmRNAが必要になるという考えも囁かれ、2018年にビオンテックはファイザーと共同でインフルエンザ向けのmRNAワクチンの開発を開始、2019年までにモデルナやビオンテックを筆頭に複数の製薬企業がジカ熱やチクングニア熱、ヒトパピローマウイルス感染症に対するワクチンの臨床試験を開始。病原体のゲノム情報を解読する(2005年前後に生まれた次世代)シーケンシングの技術が中国で見つかった未知のウイルスのゲノム情報を数週間で突き止められるレベルに発達。2002年のSARS、2012年のMERSの経験からコロナウイルスのワクチンにはスパイクを使うと良いという知見がCOVID-19のmRNAワクチンに活かされる。これらに多額の資金が開発現場に投入され、大規模な臨床試験の実施機会を得たことが最後の一押しになったと現実を知るある研究者が評するのも頷ける。
20世紀末からRNA利用の技術について相当いい加減な情報収集を忘れた頃に思い出したようにしたことによる生半可に齧った状態だったので昨今の新聞やテレビなどのワンポイント的な解説では十分な修正ができないでいたごちゃごちゃをようやく整理しつつ未熟者でも少しは理解を深めた気持ちを得る機会を与えてくれた記事!
どうでもいいことだが小さい頃、ウイルスってビールスという表記がされていたことも思い出したり(で読む側のごちゃごちゃ30?年史でもあったりしたかも)。
"→♂♀←"「オススメ」のインデックスへ












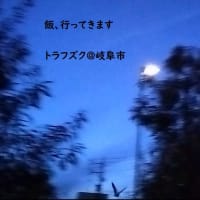

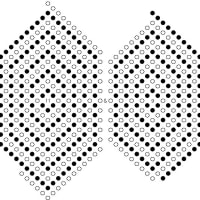

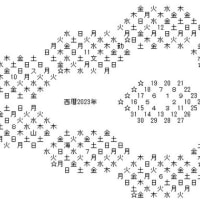









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます