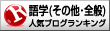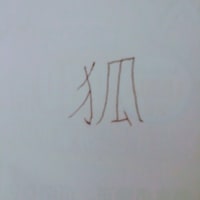化学分野では「フォ」は用いず、原音の「フォ」は「ホ」に置き換えることになっているようだ(ホルマリン、ホルムアルデヒド、スルホン酸など)。カリフォルニアに由来する金属元素も「カリホルニウム」だ。ピーホス、ピーホアもそれにならったのだろう。化学分野でも「ファ、フィ、フェ」は用いるが(例:フェルミウム)「フォ」は用いず「ホ」に置き換える。また、「ティ」「ディ」も用いずそれぞれ「チ」「ジ」に置き換える。
ちなみにウィキペディアの当該ページではピーフォス、ピーフォアと書かれていた。
文系(語学、歴史、社会、文化、文学)では、外来語(特に固有名詞)を原音に忠実に表記する傾向が強いが、それに対して理系では外来語を原音に忠実に表記することはそれほど求められていないことがうかがえる。
「ハ、へ、ホ」の子音が[h]なのに対し「フ」の子音は[φ]であり、フの子音[φ]を母音「ウ」以外の4母音と組んだのが「ファ、フィ、フェ、フォ」である。母音「オ」は口をあまり大きくあけずに発音する「ウ」から近い音ということもあって、「ファ、フィ、フェ」と比べて「フォ」は不安定で発音しづらい、「ホ」との区別が付きづらいという人もいるだろう。そのためか、化学分野に限らず、「フォ」の代わりに「ホ」で書かれることもよくある(テレフォン/テレホン、ユニフォーム/ユニホームなど)。「スマートフォン」も略さずに言う時は「スマートフォン」、略すと「スマホ」と言うことが多い(新聞でも「スマートフォン/スマホ」という表記を採用)。
逆に、本当は「ホ」なのに「フォ」で書かれているのもたまに見る(過剰修正?)。
沖縄県内にあるビルの名前で「ホーク○○」(現地の看板にもそう書かれている。おそらくホークはhawk=タカのこと)というのが「フォーク○○」と誤記されているのも見た(求人誌で)。また、ディアマンテスの曲に『Bajo el Sol(邦題:バッフォ・エル・ソル)』があるが、実際のスペイン語の発音は「バホ・エル・ソル」に近く、「フォ」で書くのは適当ではない。
最新の画像もっと見る
最近の「言語・語学」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事