これはたしか、映画のタイトルとしてよく見たと思うが、小説も有名だよね?
wikiで見た所、アメリカで“数年に渡り大ベストセラー”だってよ。
まあわたしはこういうの全然ダメですけれども。
村上春樹も大江健三郎もヴォネガットも嫌いだ。
現代アメリカ人は一体何を考えて……と思ったが、1978年発行ということは、
もう全然現代じゃないですね。すでに歴史上の作品ですね。
ベストセラーになる小説というのは、構造的に名作の割合は少ないと思う。
というのは、普段本を読まない、買わないという層がこぞって買うからこその大売れなわけで、
読みやすいというのは確実なところだけれども、それと内容の優劣は別の話。
これは劣とは言わないけれども、もともと好きなタイプの小説じゃないんだ。
だいぶグロテスク。上巻はそうでもないけど、下巻は途中で止めようかと思ったグロさ。
裏表紙の新潮文庫のあらすじには「現代をコミカルに描く」と書いてあるが、
これはコミカルじゃない。これをコミカルと言われたらわたしは怒る。
新潮文庫のこの部分は、ほんとにいつもヒドイですね。ひどすぎますね。
社内で問題にならないんですかね?
これ自伝?
わたしはアーヴィングのことは欠片も知らないが、主人公が作家ってだけでそう思う。
実際、人生としてはどうか知らないが、作家としての姿はけっこう重なるようだ。
ここらへんも、どうかねえと思う所以だ。いさぎよく自伝的小説ならそれでいいんだけどもね、
あんまり書き手の姿が二重写しになってしまう小説は嫌なんだよね。
ガープの「人生は二流のメロドラマだ」という台詞があるが、
二流のメロドラマをわざわざ読みたくはない。
ドタバタ・グロテスク・ナンセンスな感じ。ページターナーではあるが、
(矛盾しているが)読み終わるのは苦労だった。
しかし考えてみれば「精霊たちの家」と、大雑把な枠では似てるんだよね。
家庭小説。ドタバタ的。不幸と不安にうっすらとまぶされた幸せ。
なぜ「精霊たちの家」は面白くて、「ガープの世界」は嫌なのか。
何が一番違うのかというと、……土着性があるか否かというところかと思うが、どうだろう。
わたしが“アメリカ文学ってどうしてこんなにザリザリした砂を噛むような味気無さ?”
という疑問から、30冊くらい年代順に読んでみた結果、
土地の精霊に守られてるかどうか、というところに根があるのではないかという考えを持った。
不安定感。不安感。いつも足元が危うい、いつも背後がうすら寒い。
それは創成神話を持たない、地霊を持たない人々だからではないんだろうか。
はるか昔に、「なぜハリウッド映画はアメリカが攻撃されるものばかりなのか?」というお題に、
(当時、ハリウッドはパニック物が多かったんですよ。「宇宙人が攻めてくる!」とか)
「侵略者の子孫で、その後攻め込まれた経験もないのでそれがコンプレックスになっている」と
答えがついていたものがあって、それは長い間わたしを納得させてきたのだが、
それはそれとして、その背後にはやはり土着性のない不安感があるのではないか。
寄って立つものがない。
アメリカ文学にも、例えば中上健次的なものもあるんだろうけどなあ。
「風と共に去りぬ」なんかは最終的には土地が支えてくれて終わるよね。
あれはアイルランドの土地の記憶を、アメリカに移植出来た幸せな例なんだろう。
まあどっちかいうとメロドラマなので、単純に比較するのはちょっと違うのかもしれないが。
wikiで見た所、アメリカで“数年に渡り大ベストセラー”だってよ。
まあわたしはこういうの全然ダメですけれども。
村上春樹も大江健三郎もヴォネガットも嫌いだ。
現代アメリカ人は一体何を考えて……と思ったが、1978年発行ということは、
もう全然現代じゃないですね。すでに歴史上の作品ですね。
ベストセラーになる小説というのは、構造的に名作の割合は少ないと思う。
というのは、普段本を読まない、買わないという層がこぞって買うからこその大売れなわけで、
読みやすいというのは確実なところだけれども、それと内容の優劣は別の話。
これは劣とは言わないけれども、もともと好きなタイプの小説じゃないんだ。
だいぶグロテスク。上巻はそうでもないけど、下巻は途中で止めようかと思ったグロさ。
裏表紙の新潮文庫のあらすじには「現代をコミカルに描く」と書いてあるが、
これはコミカルじゃない。これをコミカルと言われたらわたしは怒る。
新潮文庫のこの部分は、ほんとにいつもヒドイですね。ひどすぎますね。
社内で問題にならないんですかね?
これ自伝?
わたしはアーヴィングのことは欠片も知らないが、主人公が作家ってだけでそう思う。
実際、人生としてはどうか知らないが、作家としての姿はけっこう重なるようだ。
ここらへんも、どうかねえと思う所以だ。いさぎよく自伝的小説ならそれでいいんだけどもね、
あんまり書き手の姿が二重写しになってしまう小説は嫌なんだよね。
ガープの「人生は二流のメロドラマだ」という台詞があるが、
二流のメロドラマをわざわざ読みたくはない。
ドタバタ・グロテスク・ナンセンスな感じ。ページターナーではあるが、
(矛盾しているが)読み終わるのは苦労だった。
しかし考えてみれば「精霊たちの家」と、大雑把な枠では似てるんだよね。
家庭小説。ドタバタ的。不幸と不安にうっすらとまぶされた幸せ。
なぜ「精霊たちの家」は面白くて、「ガープの世界」は嫌なのか。
何が一番違うのかというと、……土着性があるか否かというところかと思うが、どうだろう。
わたしが“アメリカ文学ってどうしてこんなにザリザリした砂を噛むような味気無さ?”
という疑問から、30冊くらい年代順に読んでみた結果、
土地の精霊に守られてるかどうか、というところに根があるのではないかという考えを持った。
不安定感。不安感。いつも足元が危うい、いつも背後がうすら寒い。
それは創成神話を持たない、地霊を持たない人々だからではないんだろうか。
はるか昔に、「なぜハリウッド映画はアメリカが攻撃されるものばかりなのか?」というお題に、
(当時、ハリウッドはパニック物が多かったんですよ。「宇宙人が攻めてくる!」とか)
「侵略者の子孫で、その後攻め込まれた経験もないのでそれがコンプレックスになっている」と
答えがついていたものがあって、それは長い間わたしを納得させてきたのだが、
それはそれとして、その背後にはやはり土着性のない不安感があるのではないか。
寄って立つものがない。
アメリカ文学にも、例えば中上健次的なものもあるんだろうけどなあ。
「風と共に去りぬ」なんかは最終的には土地が支えてくれて終わるよね。
あれはアイルランドの土地の記憶を、アメリカに移植出来た幸せな例なんだろう。
まあどっちかいうとメロドラマなので、単純に比較するのはちょっと違うのかもしれないが。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1144c174.4eab29b7.1144c175.4b3387f5/?me_id=1213310&item_id=10227272&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3012%2F9784102273012.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3012%2F9784102273012.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext) ガープの世界(上巻) (新潮文庫) [ ジョン・アーヴィング ] |










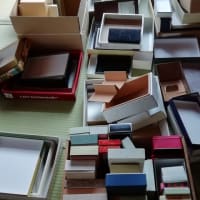














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます