法隆寺は、前に来た時は梅原猛の著作を読んでからそれほど年月も経っておらず、そういう目でどうしても見た。
今回はわりと虚心坦懐に。淡々と。
天下の法隆寺だというのに、8時半の段階でほぼ人っ子一人いない。あの広大な空間を一人占め。
贅沢な話です。冬の奈良は寒いけどそういうことが出来るからお薦め。
南大門から入って、そこから見える真正面の中門と五重の塔の風景は、寺の姿として屈指だと思う。
塔と中門のバランスが美。ズームで撮って吉。
中門両側の松があった方がいいのかどうかは要検討。
塔を半分隠すのはいいと思うが、右側の松で金堂がすっぽり隠れるのはどうなのか。
しかしここで金堂が見えたら、中門の美しさは薄れるか。
金堂は近くで斜め横から見て、やはり美しい建造物だと感じる。
万字崩しの勾欄が華やかなアクセントで、その他の部分で質実。
「顔」と「胴体」のある、人体的な建物だと思う。
その中にあるのは釈迦三尊像。
何の気なしに入って、そこにそれがあったので、「おお、ここにあったか」とびっくりした。
てっきり博物館にでも入っている気がしていた。
印刷された写真で見る分には――
飛鳥時代の仏像らしい仏像。前に垂れ下がる衣紋はすでに流麗すぎるほどだけど、
肉体部分はまだまだ生硬。顔は面長で、平安時代の円満な仏像を見ている目には、少々異様。
が、実見すると、生硬さも異様さもあまり感じない。
金網の向こうの遠いところにあるし、そもそも金堂が暗くてよく見えない、という点もあるが。
ただほんのりとした、最初の仏教に対する憧れが香る。
まだ手探りで仏像を彫っていた時代。そこにあるのは無知なるものの純粋さ。
その純粋さがほのかな手肌の温度となって仏像を守っているように想像する。
近くから見れば厳しい顔つきなのかもしれないが、全体を見るとふんわりした優しさがある。
細部は暗くて遠くて見えない!金堂再現壁画も金網の隙間を狙って、ああ、何か描いてあるとわかるだけ。
あの古い金網、味と言えば味だけど、何となく自分が虫になったような気分になるので、
何とかしてもらえませんか。遠いんだよなー。
五重の塔は、地中から生えた建築。薬師寺東塔はフェノロサに「凍れる音楽」と称えられたそうだが、
わたしは法隆寺五重の塔を「大樹の塔」と名付ける。大木が一本、自らの地に安住して、天へと伸びる。
塔の真上にある空が本当の天。大地と空を結ぶ宇宙樹のイメージ。
ストゥーパが塔に変化していくのは、NHKのドキュメンタリーとかでやっていそうなテーマだが
やってないかね?ストゥーパに高さが加わって行く過程なんかをもし探せたら、相当面白い番組が出来そうだ。
金堂と五重の塔を囲む回廊も美しいもの。
敷地も定かならぬただっぴろい場所に金堂・講堂・五重塔・中門があってもいまいち統一性を感じない。
特に金堂と塔は、いわば非対称だからね。
回廊でまとめることでその建築群が一つになると思う。
夢殿は逆に、回廊があまりにも小さくあることで残念な結果になっている。
あの建物はもう少し遠くから見たい。回廊をもっと大きくとってくれたら良かったのに。
前に来た時はなかった大宝蔵院。仏像がいろいろ集められている。有名どころのみ印象に残った。
小品もそれなりに良かったけれどね。たしか十二神将とかあって、なかなか良かったけれど。
ここは、何と言っても「百済観音」。
以前は若干荒れ果てたような、温湿度管理もしてないような建物だったと記憶する。
でも今の建物もガラスケースもなく、直接見られるようになっていて(だよね?)大変ありがたい。
だが百済観音は彩色がまだらになっていて、顔の表情があまりわからないんだよなー。
表情を見るには照明が少し暗い。……と思ったら、同じく仏像をみていた観仏人が、こっそり光を当てた。
当然これはマナー違反だし、小さいけれども強いその光が塵も積もって仏像を傷めるのだから、
絶対にやるべきではないと思うが、しかしそのおかげで見たいと思っていたものを見られたので、
アリガタイと思ったことも否めない。懺悔合掌。
飛鳥仏なのに飛鳥仏の造型をしていない。その独自な雰囲気を考えると、どこか工房で修業をした人ではなく、
そして自分の工房も残さなかった人であることを想像する。
海を越えて来た渡来人が見知らぬ異国で、その異国になじむ前にたった一体彫った仏像。
薄い笑みははるか高みにいるよりは、むしろ身近な存在として感じさせる。
翻った天衣(?)が剣の印象になるほど薄くて鋭い。
横から見たなで肩の優しいライン。
優しいのか、実は醒めているのか、どちらとも取れるまなざし。
その細身すぎるほどの体は、仏像の円満ではなく、むしろ霊魂の姿を表したものというように思える。
衆生を救うための造型ではなく、後に残すものとして、形見としての像。
「橘夫人念持仏」
これは可愛い。いかにも女性が日々眺めて愛玩(ではないが)しそうなブツ。装飾性が高い。
尚、厨子は三尊の両側も吹き抜けになっている。普通は両脇はふさぐ気がする。
横からも眺めて楽しんだということか?
「玉虫厨子」
現在東京に出品中のため模刻品の展示。
玉虫厨子は前に地元の博物館に来た時にじっくり見たことがあって、それなりに強い印象があった気がするが、
それは造型としてよりも、「写真師来ず」……もとい、「捨身飼虎図」のテーマに打たれたせいかもしれない。
玉虫厨子は玉虫の羽を貼りつけていることによってそう呼ばれるわけだが、
……その制作のために何千匹の玉虫の殺生をしたのかを考えると、いいのか仏教のスタンス的に。
造型的にはだいぶ塗りがはげており、何が描いてあるのかわからない。
※※※※※※※※※※※※
中宮寺の「如意輪観音」は大好きな仏。広隆寺の弥勒菩薩と姉妹。
……前に来た時は堪能した記憶があったんだがなあ。
本堂の建物は当時からコンクリート作りだったし、それ自体は変わってないと思うのだが、
内陣の大きさを変えたりしたのかなあ。
満足のいく距離で見ることが出来ない。
これも光が奥まで届かなくて、ちゃんと表情が見られない。
そもそも黒い像だから、陰になっていると溶け込んでしまって……
頭の上のかわいいミヅラ?さえよく見えない。
存在として感じることは出来るけど、細部まで見られない。
気配を感じるだけでも、嬉しいことは嬉しいけれどもね。
でもせっかく行ったら、ちゃんと見ることが出来るとアリガタイ。
季節や時間や天気によって光の量は違うだろうから、見える時もあるのかもしれないが。
もう少し近くて見せてくれないか。
だが、ここは非常に鳥の声が多かった。
仏に正対するより、仏と同じ方角を向き、ここで鳥の声に耳を傾け、池の水面の揺らぎを見つめる日々は
どんなだろう、と想像することの方が楽しかった。それはそれで収穫。
※※※※※※※※※※※※
意外なところで、全く期待をしていなかった斑鳩文化財センターでいいものを見た。
すぐそばの藤ノ木古墳から出土したものを展示している。といっても、主要展示物は模作らしい。
が、こんな小さな円墳から、こんなにすごいものが出てきたの!?と思う金製品のすごさ。
正直言ってどんなんかは忘れたけど、鞍だの馬具だのアクセサリーだの、デザイン性の高い、相当なもの。
しかも金ですから見栄えがする。
模作だったらもしかして写真撮影出来たかな。今さくっとネット上を漁っても出土品の画像がないので少し惜しい。
せっかくですから斑鳩文化財センターはホームページを作って、写真を挙げて置いて欲しい。
検索で出てくるけっこう後の方で、歴史倶楽部というところのサイトでいくつか収蔵品の写真が見られる。
被葬者の結論は出ておらず、穴穂部皇子・宅部皇子・崇峻天皇などの名前が挙がっているそうだが、
暗殺されたような皇子たちにすらこんな副葬品があるのなら、天皇の墓には一体どんなお宝が、と驚いた。
わたしの大和時代の認識はもっとずっと貧相な(……)感じだった。
※※※※※※※※※※※※
最後に法輪寺と法起寺にさくっと行って斑鳩散策は終り。
法起寺なんて、いい季節に行けばいつまででものんびりしたいようないいところなのに、
……何しろ寒かった。
春の斑鳩なんてのはいいでしょうねえ。
この二つのお寺の三重塔は双子のようにそっくり。
意図してではなかったが、写真を2つの塔を続けて撮ることになったので、
自分で後で見返すと「あ!こっちは法輪寺の方か!」「あ!こっちは法起寺か!」と驚いた。
どっちにも仏像もちょこちょこあったけど、こちらの印象は散漫。
幸せな斑鳩でした。
今回はわりと虚心坦懐に。淡々と。
天下の法隆寺だというのに、8時半の段階でほぼ人っ子一人いない。あの広大な空間を一人占め。
贅沢な話です。冬の奈良は寒いけどそういうことが出来るからお薦め。
南大門から入って、そこから見える真正面の中門と五重の塔の風景は、寺の姿として屈指だと思う。
塔と中門のバランスが美。ズームで撮って吉。
中門両側の松があった方がいいのかどうかは要検討。
塔を半分隠すのはいいと思うが、右側の松で金堂がすっぽり隠れるのはどうなのか。
しかしここで金堂が見えたら、中門の美しさは薄れるか。
金堂は近くで斜め横から見て、やはり美しい建造物だと感じる。
万字崩しの勾欄が華やかなアクセントで、その他の部分で質実。
「顔」と「胴体」のある、人体的な建物だと思う。
その中にあるのは釈迦三尊像。
何の気なしに入って、そこにそれがあったので、「おお、ここにあったか」とびっくりした。
てっきり博物館にでも入っている気がしていた。
印刷された写真で見る分には――
飛鳥時代の仏像らしい仏像。前に垂れ下がる衣紋はすでに流麗すぎるほどだけど、
肉体部分はまだまだ生硬。顔は面長で、平安時代の円満な仏像を見ている目には、少々異様。
が、実見すると、生硬さも異様さもあまり感じない。
金網の向こうの遠いところにあるし、そもそも金堂が暗くてよく見えない、という点もあるが。
ただほんのりとした、最初の仏教に対する憧れが香る。
まだ手探りで仏像を彫っていた時代。そこにあるのは無知なるものの純粋さ。
その純粋さがほのかな手肌の温度となって仏像を守っているように想像する。
近くから見れば厳しい顔つきなのかもしれないが、全体を見るとふんわりした優しさがある。
細部は暗くて遠くて見えない!金堂再現壁画も金網の隙間を狙って、ああ、何か描いてあるとわかるだけ。
あの古い金網、味と言えば味だけど、何となく自分が虫になったような気分になるので、
何とかしてもらえませんか。遠いんだよなー。
五重の塔は、地中から生えた建築。薬師寺東塔はフェノロサに「凍れる音楽」と称えられたそうだが、
わたしは法隆寺五重の塔を「大樹の塔」と名付ける。大木が一本、自らの地に安住して、天へと伸びる。
塔の真上にある空が本当の天。大地と空を結ぶ宇宙樹のイメージ。
ストゥーパが塔に変化していくのは、NHKのドキュメンタリーとかでやっていそうなテーマだが
やってないかね?ストゥーパに高さが加わって行く過程なんかをもし探せたら、相当面白い番組が出来そうだ。
金堂と五重の塔を囲む回廊も美しいもの。
敷地も定かならぬただっぴろい場所に金堂・講堂・五重塔・中門があってもいまいち統一性を感じない。
特に金堂と塔は、いわば非対称だからね。
回廊でまとめることでその建築群が一つになると思う。
夢殿は逆に、回廊があまりにも小さくあることで残念な結果になっている。
あの建物はもう少し遠くから見たい。回廊をもっと大きくとってくれたら良かったのに。
前に来た時はなかった大宝蔵院。仏像がいろいろ集められている。有名どころのみ印象に残った。
小品もそれなりに良かったけれどね。たしか十二神将とかあって、なかなか良かったけれど。
ここは、何と言っても「百済観音」。
以前は若干荒れ果てたような、温湿度管理もしてないような建物だったと記憶する。
でも今の建物もガラスケースもなく、直接見られるようになっていて(だよね?)大変ありがたい。
だが百済観音は彩色がまだらになっていて、顔の表情があまりわからないんだよなー。
表情を見るには照明が少し暗い。……と思ったら、同じく仏像をみていた観仏人が、こっそり光を当てた。
当然これはマナー違反だし、小さいけれども強いその光が塵も積もって仏像を傷めるのだから、
絶対にやるべきではないと思うが、しかしそのおかげで見たいと思っていたものを見られたので、
アリガタイと思ったことも否めない。懺悔合掌。
飛鳥仏なのに飛鳥仏の造型をしていない。その独自な雰囲気を考えると、どこか工房で修業をした人ではなく、
そして自分の工房も残さなかった人であることを想像する。
海を越えて来た渡来人が見知らぬ異国で、その異国になじむ前にたった一体彫った仏像。
薄い笑みははるか高みにいるよりは、むしろ身近な存在として感じさせる。
翻った天衣(?)が剣の印象になるほど薄くて鋭い。
横から見たなで肩の優しいライン。
優しいのか、実は醒めているのか、どちらとも取れるまなざし。
その細身すぎるほどの体は、仏像の円満ではなく、むしろ霊魂の姿を表したものというように思える。
衆生を救うための造型ではなく、後に残すものとして、形見としての像。
「橘夫人念持仏」
これは可愛い。いかにも女性が日々眺めて愛玩(ではないが)しそうなブツ。装飾性が高い。
尚、厨子は三尊の両側も吹き抜けになっている。普通は両脇はふさぐ気がする。
横からも眺めて楽しんだということか?
「玉虫厨子」
現在東京に出品中のため模刻品の展示。
玉虫厨子は前に地元の博物館に来た時にじっくり見たことがあって、それなりに強い印象があった気がするが、
それは造型としてよりも、「写真師来ず」……もとい、「捨身飼虎図」のテーマに打たれたせいかもしれない。
玉虫厨子は玉虫の羽を貼りつけていることによってそう呼ばれるわけだが、
……その制作のために何千匹の玉虫の殺生をしたのかを考えると、いいのか仏教のスタンス的に。
造型的にはだいぶ塗りがはげており、何が描いてあるのかわからない。
※※※※※※※※※※※※
中宮寺の「如意輪観音」は大好きな仏。広隆寺の弥勒菩薩と姉妹。
……前に来た時は堪能した記憶があったんだがなあ。
本堂の建物は当時からコンクリート作りだったし、それ自体は変わってないと思うのだが、
内陣の大きさを変えたりしたのかなあ。
満足のいく距離で見ることが出来ない。
これも光が奥まで届かなくて、ちゃんと表情が見られない。
そもそも黒い像だから、陰になっていると溶け込んでしまって……
頭の上のかわいいミヅラ?さえよく見えない。
存在として感じることは出来るけど、細部まで見られない。
気配を感じるだけでも、嬉しいことは嬉しいけれどもね。
でもせっかく行ったら、ちゃんと見ることが出来るとアリガタイ。
季節や時間や天気によって光の量は違うだろうから、見える時もあるのかもしれないが。
もう少し近くて見せてくれないか。
だが、ここは非常に鳥の声が多かった。
仏に正対するより、仏と同じ方角を向き、ここで鳥の声に耳を傾け、池の水面の揺らぎを見つめる日々は
どんなだろう、と想像することの方が楽しかった。それはそれで収穫。
※※※※※※※※※※※※
意外なところで、全く期待をしていなかった斑鳩文化財センターでいいものを見た。
すぐそばの藤ノ木古墳から出土したものを展示している。といっても、主要展示物は模作らしい。
が、こんな小さな円墳から、こんなにすごいものが出てきたの!?と思う金製品のすごさ。
正直言ってどんなんかは忘れたけど、鞍だの馬具だのアクセサリーだの、デザイン性の高い、相当なもの。
しかも金ですから見栄えがする。
模作だったらもしかして写真撮影出来たかな。今さくっとネット上を漁っても出土品の画像がないので少し惜しい。
せっかくですから斑鳩文化財センターはホームページを作って、写真を挙げて置いて欲しい。
検索で出てくるけっこう後の方で、歴史倶楽部というところのサイトでいくつか収蔵品の写真が見られる。
被葬者の結論は出ておらず、穴穂部皇子・宅部皇子・崇峻天皇などの名前が挙がっているそうだが、
暗殺されたような皇子たちにすらこんな副葬品があるのなら、天皇の墓には一体どんなお宝が、と驚いた。
わたしの大和時代の認識はもっとずっと貧相な(……)感じだった。
※※※※※※※※※※※※
最後に法輪寺と法起寺にさくっと行って斑鳩散策は終り。
法起寺なんて、いい季節に行けばいつまででものんびりしたいようないいところなのに、
……何しろ寒かった。
春の斑鳩なんてのはいいでしょうねえ。
この二つのお寺の三重塔は双子のようにそっくり。
意図してではなかったが、写真を2つの塔を続けて撮ることになったので、
自分で後で見返すと「あ!こっちは法輪寺の方か!」「あ!こっちは法起寺か!」と驚いた。
どっちにも仏像もちょこちょこあったけど、こちらの印象は散漫。
幸せな斑鳩でした。










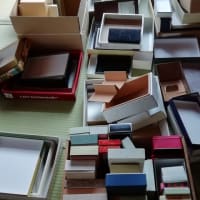















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます