この間、奈良に行きました。
実に久々。おそらく4回目だけど、前回行ったのは20年近く前。
4泊5日でじっくりブツを見て来て、大変いい思いをしました。せっかくなので感想を。
興福寺。今まで行ったことがない筈はないのだが、妙に印象が薄い寺だった。
今回は寒い時期で人が少なくて(まあ修学旅行生はいたけれども)、国宝館なんか独り占めの時間帯があった。
まず東金堂の仏たち。
ここの白眉は中尊を差し置いて、脇侍の「日光菩薩・月光菩薩」。
飛鳥のいい仏。だいぶ洗練されてきている。光背は補作だろうね。
山田寺のために造られたらしいではないですか。といったら「あの仏頭」の脇侍だろう!と思うよ。
あの頭、薬師如来らしいし。大きさもいけるんちゃう?
だが、説明によると技法や表現方法が異なるので作られたのはもっと後だろうとのことだった。
後だってええんや!あの3体がいつの時代かに3体並んだことがあったのではないかと想像することが愉しい。
完成度からして、わたしもやはりセットで作られたとは思わないけれど。
線がシンプルで柔らかいよね。飛鳥大仏と血縁関係はあるけど、そこまで近くはない、姪孫という感じ。
白鳳仏はとろりとして可愛らしい。童子の姿。
「銅造薬師如来坐像」。
これは室町時代に制作されたもの。
室町の仏についての具体的なイメージはないな。何か有名な仏像あったっけ?
でも言われなければ室町という感じはしない。おおどかさもある気がする。むしろ個性的じゃないということなのか?
写真よりは良く見えたけどねー。撮る方向のせいか。この写真では頭がでかすぎて、体が貧弱で、
相当残念な造型になっている。
「木造四天王立像」は9世紀の作と書いてあったようだ。
体に力感があるので、平安初期な感じがしない。むしろ後期ならば。
これもそうだし、「木造十二神将立像」もそうなんだけど、見ることが出来る位置が、
仏像の大きさに比べてだいぶ遠いんだよね。この二組はむしろ博物館ででもじっくり見たいところ。
「維摩居士」「文殊」は鎌倉時代。だいぶこまっかくなって、他のもっと古い仏像群と一緒に見ると、
こせこせとして見える。写実的なのはプラスに働く場合もあろうが、説明的でちょっとうるさくもある。
これも小さ目のブツなので、見る場所としては少し遠い。
彫刻は本来、あるべき場所に置いてこそだとは思っているが、せっかく三次元なのに、
一方向から見られない、ある距離からしか見られない、というのは残念なんだよな。
※※※※※※※※※※※※
国宝館の仏たち。
「乾漆八部衆立像」。
これは言わずと知れた阿修羅像を含む一揃いだが、今回わたしが一番長く見たのは五部浄像。
これは写真で見るのとは大変に違っていて。国宝館では照明を上から当てて、眼が見えないようにしているの。
つまり現地で見ると目は虚空。ただ真っ黒い穴が開いている状態。
写真のように正面から光を当てて、くまなく表情が見えるようだとそれはそれだけの話だが、
眼がないとね。これは相当に謎めきます。
ガラスケースの中の像と対面で向き合う。
表情が……読めない。眉根を寄せて、悔しげな顔にも見えれば笑っているようにも見える。
訴える顔。語る顔。そしてその思いに身を寄せられないのがわたしは悔しい。
語る顔に出会えて、そして意思の疎通が出来たように思えるのは幸福なことだが、
意思の疎通が出来なくてもそれも幸福なことだ。
修行と言ったら大げさに過ぎるだろうが、見る時は真剣に見たいと思っている。マジ見。
もちろん語らない仏像(及び数々の美)はわたしに語るものより数多くあって、
そういう中で語る顔、語る美に出会えるのは僥倖である。
五部浄像は、竜王という説もあるらしい。竜王という名で定着した方が人気は出るだろうなあ……。
上半身だけではなくて破損がなかったら、阿修羅像と美少年ぶりでは双璧だと思いますよ。
そしてその「阿修羅像」あまりにも有名な。
初めて見たわけではないと思うし、いい加減テレビ番組なんかで見慣れてるから、若干食傷気味。
と思いながら見に行ったのだが、やはり現物の阿修羅像は一味違いました。
ドキュメンタリー番組でブツ好きのタレントが確か言ってたのだが、
「ずっと見てられる」これは本当だと思いましたね。見飽きない、清涼な魅力がある。
わたしは常々、なんでコノヒト、こんなに腕が細いんだろう?と思っていた。
他の八部衆は、まあ腕むき出しではなく服を着てるとはいえこんなにか細い造型ではないのに。
いくら少年の若々しさを出すとはいえ、まるで棒のようではありませんか。
現地で見たところ、この疑問には仮説が立った。
この六本の腕は、額縁なのではないかと。
顔の周りを取り囲む額縁。腕のラインをたどると、自然に顔に視線が行くようになってる。
その場合、額縁があまりにも存在感がありすぎてはダメだろう。袖があってもウルサイ。
ただの棒のような腕で中心の三面の顔に集中させる。
やっぱりずっと顔を見てたな。他のところはほぼ見ていない。
そこに在るという存在感が生々しい。だからといってこちらを見ている気はしない。
まなざしは、やはりずっと遠くを見てるね。はるかな過去か。未来か。
少年が。その遠くをみようとしているまなざしが、魅力なのかもしれない。
八部衆では他に「畢婆迦羅(ひばから。……読めませんが)像」も気になった。
いる!いる!西域にはこういうおっさん!
まあ現代の西域にも当時のシルクロードにも行ったことはないんだけど。
でも唐の長安を歩いていた西域人そのままという気がするな。モデルがいたに違いないと思わせる。
「天燈鬼・龍燈鬼」がカワイくてね。
これがもっとデカイならカワイさよりも迫力を感じるのかもしれないが、ちっちゃいから(78センチ)。
天燈鬼なんか、ポーズ的にどう見ても蕎麦屋の出前である。
「へい、お待ちぃぃぃぃ!」こんなのがド迫力で蕎麦を届けに来たら腰抜かすわ。
龍燈鬼の方は、これもいつも思うのだが、なぜ作者はこんなポーズでこれを作ろうと思ったのか……
大道芸人じゃないなんだからさ。なぜ頭の上でバランスを取る必要がある?
しかもこの表情が。この上目遣いは……一体何を狙ってるんだ!と笑っちゃうよ。
「銅造梵鐘」
梵鐘について語れることなど何もないが、西暦727年の段階でこんなに完成・洗練された形が
もう作れたということに一驚を禁じ得ない。梵鐘もかなり奥が深いものらしいんですけどね。
「板彫十二神将像」
これはレリーフ。平安時代の板彫なんて珍しいでしょう。しかも十二神将の板彫なんてきっと相当珍しいでしょう。
そのせいか、どうも時代が平安に見えない。むしろ江戸の寺辺りに今もあってもおかしくない気がするよ。
このユーモラスぶり。平安時代に仏教がここまで自由な表現をされていたか……
そう思って見ると、サイズといいポーズといい、江戸時代の浮世絵に近いでしょう。
もう浮世絵の役者絵にしか見えない。
あと大物は二点。どっちも仏頭。
運慶作「木造釈迦如来頭部」
色が美味しそうなチョコレート色。写真で見るのと違って、もっと愛嬌のある、いたずら盛りの少年の風貌。
たしかこれはどこかで見たような気がする。
平行で長い細い目、眉毛のラインがきれい。
「山田寺仏頭」
通った鼻筋とかラインとか、全体的にとても洗練されているので、全身像が残っていたら
どれだけ美しかっただろうと残念に思う。
しかし今正面からの写真を見ると意外に左右の眉のラインが違いますな。
向かって右の方が完璧。
奈良時代とは思えないほど力感がある。頬の盛り上がり、微妙な肉付きはリアル。
これも好きな仏だ。
他にもいろいろいろいろ仏像はあったのだが、とりあえずこんなところで。
白眉はといえばなんといっても五部浄像。次点で阿修羅像、山田寺仏頭、運慶作釈迦仏頭。
ここらへんをウロウロしていた。まあ結局興福寺で2時間くらいいて、
行くつもりだった東大寺にはその日行けなかったという……。
まあ良い。予定をこなすよりじっくり付き合う方が大事。
実に久々。おそらく4回目だけど、前回行ったのは20年近く前。
4泊5日でじっくりブツを見て来て、大変いい思いをしました。せっかくなので感想を。
興福寺。今まで行ったことがない筈はないのだが、妙に印象が薄い寺だった。
今回は寒い時期で人が少なくて(まあ修学旅行生はいたけれども)、国宝館なんか独り占めの時間帯があった。
まず東金堂の仏たち。
ここの白眉は中尊を差し置いて、脇侍の「日光菩薩・月光菩薩」。
飛鳥のいい仏。だいぶ洗練されてきている。光背は補作だろうね。
山田寺のために造られたらしいではないですか。といったら「あの仏頭」の脇侍だろう!と思うよ。
あの頭、薬師如来らしいし。大きさもいけるんちゃう?
だが、説明によると技法や表現方法が異なるので作られたのはもっと後だろうとのことだった。
後だってええんや!あの3体がいつの時代かに3体並んだことがあったのではないかと想像することが愉しい。
完成度からして、わたしもやはりセットで作られたとは思わないけれど。
線がシンプルで柔らかいよね。飛鳥大仏と血縁関係はあるけど、そこまで近くはない、姪孫という感じ。
白鳳仏はとろりとして可愛らしい。童子の姿。
「銅造薬師如来坐像」。
これは室町時代に制作されたもの。
室町の仏についての具体的なイメージはないな。何か有名な仏像あったっけ?
でも言われなければ室町という感じはしない。おおどかさもある気がする。むしろ個性的じゃないということなのか?
写真よりは良く見えたけどねー。撮る方向のせいか。この写真では頭がでかすぎて、体が貧弱で、
相当残念な造型になっている。
「木造四天王立像」は9世紀の作と書いてあったようだ。
体に力感があるので、平安初期な感じがしない。むしろ後期ならば。
これもそうだし、「木造十二神将立像」もそうなんだけど、見ることが出来る位置が、
仏像の大きさに比べてだいぶ遠いんだよね。この二組はむしろ博物館ででもじっくり見たいところ。
「維摩居士」「文殊」は鎌倉時代。だいぶこまっかくなって、他のもっと古い仏像群と一緒に見ると、
こせこせとして見える。写実的なのはプラスに働く場合もあろうが、説明的でちょっとうるさくもある。
これも小さ目のブツなので、見る場所としては少し遠い。
彫刻は本来、あるべき場所に置いてこそだとは思っているが、せっかく三次元なのに、
一方向から見られない、ある距離からしか見られない、というのは残念なんだよな。
※※※※※※※※※※※※
国宝館の仏たち。
「乾漆八部衆立像」。
これは言わずと知れた阿修羅像を含む一揃いだが、今回わたしが一番長く見たのは五部浄像。
これは写真で見るのとは大変に違っていて。国宝館では照明を上から当てて、眼が見えないようにしているの。
つまり現地で見ると目は虚空。ただ真っ黒い穴が開いている状態。
写真のように正面から光を当てて、くまなく表情が見えるようだとそれはそれだけの話だが、
眼がないとね。これは相当に謎めきます。
ガラスケースの中の像と対面で向き合う。
表情が……読めない。眉根を寄せて、悔しげな顔にも見えれば笑っているようにも見える。
訴える顔。語る顔。そしてその思いに身を寄せられないのがわたしは悔しい。
語る顔に出会えて、そして意思の疎通が出来たように思えるのは幸福なことだが、
意思の疎通が出来なくてもそれも幸福なことだ。
修行と言ったら大げさに過ぎるだろうが、見る時は真剣に見たいと思っている。マジ見。
もちろん語らない仏像(及び数々の美)はわたしに語るものより数多くあって、
そういう中で語る顔、語る美に出会えるのは僥倖である。
五部浄像は、竜王という説もあるらしい。竜王という名で定着した方が人気は出るだろうなあ……。
上半身だけではなくて破損がなかったら、阿修羅像と美少年ぶりでは双璧だと思いますよ。
そしてその「阿修羅像」あまりにも有名な。
初めて見たわけではないと思うし、いい加減テレビ番組なんかで見慣れてるから、若干食傷気味。
と思いながら見に行ったのだが、やはり現物の阿修羅像は一味違いました。
ドキュメンタリー番組でブツ好きのタレントが確か言ってたのだが、
「ずっと見てられる」これは本当だと思いましたね。見飽きない、清涼な魅力がある。
わたしは常々、なんでコノヒト、こんなに腕が細いんだろう?と思っていた。
他の八部衆は、まあ腕むき出しではなく服を着てるとはいえこんなにか細い造型ではないのに。
いくら少年の若々しさを出すとはいえ、まるで棒のようではありませんか。
現地で見たところ、この疑問には仮説が立った。
この六本の腕は、額縁なのではないかと。
顔の周りを取り囲む額縁。腕のラインをたどると、自然に顔に視線が行くようになってる。
その場合、額縁があまりにも存在感がありすぎてはダメだろう。袖があってもウルサイ。
ただの棒のような腕で中心の三面の顔に集中させる。
やっぱりずっと顔を見てたな。他のところはほぼ見ていない。
そこに在るという存在感が生々しい。だからといってこちらを見ている気はしない。
まなざしは、やはりずっと遠くを見てるね。はるかな過去か。未来か。
少年が。その遠くをみようとしているまなざしが、魅力なのかもしれない。
八部衆では他に「畢婆迦羅(ひばから。……読めませんが)像」も気になった。
いる!いる!西域にはこういうおっさん!
まあ現代の西域にも当時のシルクロードにも行ったことはないんだけど。
でも唐の長安を歩いていた西域人そのままという気がするな。モデルがいたに違いないと思わせる。
「天燈鬼・龍燈鬼」がカワイくてね。
これがもっとデカイならカワイさよりも迫力を感じるのかもしれないが、ちっちゃいから(78センチ)。
天燈鬼なんか、ポーズ的にどう見ても蕎麦屋の出前である。
「へい、お待ちぃぃぃぃ!」こんなのがド迫力で蕎麦を届けに来たら腰抜かすわ。
龍燈鬼の方は、これもいつも思うのだが、なぜ作者はこんなポーズでこれを作ろうと思ったのか……
大道芸人じゃないなんだからさ。なぜ頭の上でバランスを取る必要がある?
しかもこの表情が。この上目遣いは……一体何を狙ってるんだ!と笑っちゃうよ。
「銅造梵鐘」
梵鐘について語れることなど何もないが、西暦727年の段階でこんなに完成・洗練された形が
もう作れたということに一驚を禁じ得ない。梵鐘もかなり奥が深いものらしいんですけどね。
「板彫十二神将像」
これはレリーフ。平安時代の板彫なんて珍しいでしょう。しかも十二神将の板彫なんてきっと相当珍しいでしょう。
そのせいか、どうも時代が平安に見えない。むしろ江戸の寺辺りに今もあってもおかしくない気がするよ。
このユーモラスぶり。平安時代に仏教がここまで自由な表現をされていたか……
そう思って見ると、サイズといいポーズといい、江戸時代の浮世絵に近いでしょう。
もう浮世絵の役者絵にしか見えない。
あと大物は二点。どっちも仏頭。
運慶作「木造釈迦如来頭部」
色が美味しそうなチョコレート色。写真で見るのと違って、もっと愛嬌のある、いたずら盛りの少年の風貌。
たしかこれはどこかで見たような気がする。
平行で長い細い目、眉毛のラインがきれい。
「山田寺仏頭」
通った鼻筋とかラインとか、全体的にとても洗練されているので、全身像が残っていたら
どれだけ美しかっただろうと残念に思う。
しかし今正面からの写真を見ると意外に左右の眉のラインが違いますな。
向かって右の方が完璧。
奈良時代とは思えないほど力感がある。頬の盛り上がり、微妙な肉付きはリアル。
これも好きな仏だ。
他にもいろいろいろいろ仏像はあったのだが、とりあえずこんなところで。
白眉はといえばなんといっても五部浄像。次点で阿修羅像、山田寺仏頭、運慶作釈迦仏頭。
ここらへんをウロウロしていた。まあ結局興福寺で2時間くらいいて、
行くつもりだった東大寺にはその日行けなかったという……。
まあ良い。予定をこなすよりじっくり付き合う方が大事。










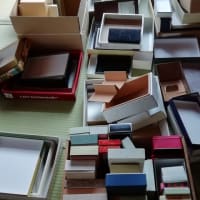














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます