安倍文殊院。
ここは渡海文殊菩薩騎獅像がお宝。
鎌倉時代の彫刻、しかも運慶・快慶というと浮かんで来るのが東大寺南大門の仁王像なわけで、
もっとマッスル系の、力感メインのイメージがあるが、実は繊細、端整な作風だったんですね。
ただ工房作品なので、慶派はあまり個人の名前にこだわらない方がいいのかな。
それとも運慶プロデュース、快慶プロデュースで明確な特徴があるのだろうか。
というより、多分明確な特徴はあるのだろうが、実際に誰がどのくらいどこまで仕事をしたかというのが
仔細にわからない以上、単なる伝承に従ってその特徴を決めていく事に意味があるのだろうか。
というのも、ちょっと話は変わるが、興福寺の北円堂に「無著・世親像」というのがあってですね。
無著像
世親像
今回、見られるのだろうかどうだろうかと思って行ったら、出会わなかったので
大変悲しかったのですけどね。
この彫刻は、仙台市博物館に来たことがあって、そこで見た時は息を呑んだ。すごい。迫力。
写真とは印象が違う。
写真では、無著は若々しささえ感じさせる、これから何事かチャレンジしていこうというような明朗な
人柄っぽいが、実際に見ると、――これは大変ワルイ感じですよー。
すごく性格が悪そう。他人を蹴落としても出世してやる!というような凄味を感じる。狷介。
それがこっちも見据えて目を光らせているんだから、震え上がります。
世親像は、そんな兄に対して「兄やん、何もそないえぐいことせんでも……」とおろおろしているように見える。
世親さんは気は優しくて力持ち、タイプの大柄なわりには穏和な人柄。
興福寺のホームページには「運慶の指導のもとに無著像は運助、世親像は運賀が担当したことが知られます」とあるが、
wikiによると判読が困難な墨書を元にして推定されているそうで、確実なところではないようだ。
でもとりあえず無著像は運助、世親像は運賀ということに“してしまう”と、
逆にそこを基準にして運助、運賀の作風を決めて行く、というようになってしまわないかと……
何が言いたいかというと、快慶作とされているけど、どの程度が快慶部分なの?と言いたいだけ。
まあルネサンスの画家たちもだいたい工房作品だし、その辺りはあまり気にするなってことなのかもしれないが。
とにかく、意外に繊細な快慶作の渡海文殊菩薩騎獅像。
しかし菩薩は端正なのだが……なにしろ獅子のインパクトが強くて。
獅子はユーモラスを狙い過ぎやろ!あのぶっといラインの造型が中央にあるせいで、文殊菩薩に今一つ目がいかない。
獅子が何で左を向いているのか気になって気になって……
あれは善財童子をとって食おうとしてるんじゃないですよね?
その善財童子は東京に出張中で不在。なかなか小さい像なので、あの距離ではほとんど見られますまい。
博物館で見て吉な気がする。
聖林寺。
十一面観音像は大層有名な観音様だが、わたしは今回あまりピンとこなかった。
あまりに有名どころが褒めすぎたせいかもしれない。フェロノサが褒め、和辻哲郎が褒め、
白洲正子が褒めてるのなら良くないわけがない!写真では今一つ良さが伝わってこないけど、
きっと実際に見れば何か信じられないものが感じられるに違いない!
……と、大層な期待をして行ったら……。多分期待が大きすぎたのだろう。
ふっくらとした体のラインや全体的な細身のバランスはいいと思うんだけど、なんか立派過ぎる?
心に染み入る造型にはならない。どこが悪いということもないが、どこかちぐはぐ感が。
主に顔の厳しさと体型のふくよかさが合わない気がする。
顔ももう少し大らかであるべきじゃないのかね。
でも十一面観音を独り占めして向き合う時間はぜいたくなものでした。
聖林寺付近はその佇まいがとても素敵で。
段々田んぼと、近くまで迫った山に囲まれた里の風情に、
(勤め人じゃなかったら)こういうところに住みたいと思った。
寺川という小さな川がまた良かった。
ここは渡海文殊菩薩騎獅像がお宝。
鎌倉時代の彫刻、しかも運慶・快慶というと浮かんで来るのが東大寺南大門の仁王像なわけで、
もっとマッスル系の、力感メインのイメージがあるが、実は繊細、端整な作風だったんですね。
ただ工房作品なので、慶派はあまり個人の名前にこだわらない方がいいのかな。
それとも運慶プロデュース、快慶プロデュースで明確な特徴があるのだろうか。
というより、多分明確な特徴はあるのだろうが、実際に誰がどのくらいどこまで仕事をしたかというのが
仔細にわからない以上、単なる伝承に従ってその特徴を決めていく事に意味があるのだろうか。
というのも、ちょっと話は変わるが、興福寺の北円堂に「無著・世親像」というのがあってですね。
無著像
世親像
今回、見られるのだろうかどうだろうかと思って行ったら、出会わなかったので
大変悲しかったのですけどね。
この彫刻は、仙台市博物館に来たことがあって、そこで見た時は息を呑んだ。すごい。迫力。
写真とは印象が違う。
写真では、無著は若々しささえ感じさせる、これから何事かチャレンジしていこうというような明朗な
人柄っぽいが、実際に見ると、――これは大変ワルイ感じですよー。
すごく性格が悪そう。他人を蹴落としても出世してやる!というような凄味を感じる。狷介。
それがこっちも見据えて目を光らせているんだから、震え上がります。
世親像は、そんな兄に対して「兄やん、何もそないえぐいことせんでも……」とおろおろしているように見える。
世親さんは気は優しくて力持ち、タイプの大柄なわりには穏和な人柄。
興福寺のホームページには「運慶の指導のもとに無著像は運助、世親像は運賀が担当したことが知られます」とあるが、
wikiによると判読が困難な墨書を元にして推定されているそうで、確実なところではないようだ。
でもとりあえず無著像は運助、世親像は運賀ということに“してしまう”と、
逆にそこを基準にして運助、運賀の作風を決めて行く、というようになってしまわないかと……
何が言いたいかというと、快慶作とされているけど、どの程度が快慶部分なの?と言いたいだけ。
まあルネサンスの画家たちもだいたい工房作品だし、その辺りはあまり気にするなってことなのかもしれないが。
とにかく、意外に繊細な快慶作の渡海文殊菩薩騎獅像。
しかし菩薩は端正なのだが……なにしろ獅子のインパクトが強くて。
獅子はユーモラスを狙い過ぎやろ!あのぶっといラインの造型が中央にあるせいで、文殊菩薩に今一つ目がいかない。
獅子が何で左を向いているのか気になって気になって……
あれは善財童子をとって食おうとしてるんじゃないですよね?
その善財童子は東京に出張中で不在。なかなか小さい像なので、あの距離ではほとんど見られますまい。
博物館で見て吉な気がする。
聖林寺。
十一面観音像は大層有名な観音様だが、わたしは今回あまりピンとこなかった。
あまりに有名どころが褒めすぎたせいかもしれない。フェロノサが褒め、和辻哲郎が褒め、
白洲正子が褒めてるのなら良くないわけがない!写真では今一つ良さが伝わってこないけど、
きっと実際に見れば何か信じられないものが感じられるに違いない!
……と、大層な期待をして行ったら……。多分期待が大きすぎたのだろう。
ふっくらとした体のラインや全体的な細身のバランスはいいと思うんだけど、なんか立派過ぎる?
心に染み入る造型にはならない。どこが悪いということもないが、どこかちぐはぐ感が。
主に顔の厳しさと体型のふくよかさが合わない気がする。
顔ももう少し大らかであるべきじゃないのかね。
でも十一面観音を独り占めして向き合う時間はぜいたくなものでした。
聖林寺付近はその佇まいがとても素敵で。
段々田んぼと、近くまで迫った山に囲まれた里の風情に、
(勤め人じゃなかったら)こういうところに住みたいと思った。
寺川という小さな川がまた良かった。










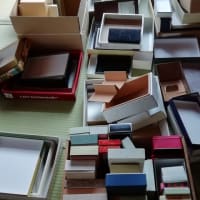














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます