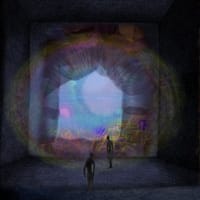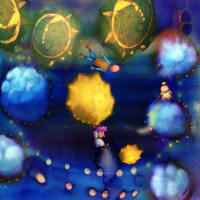私の中の彼へー青き騎士ー第5回
作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所
第5回
●シーン5
私、沙織か始めて「青き騎士の伝説」を聞いたのは。小学校の時だった。
話をしてくれたのは、同級生の移動商人の娘パウエだった。
移動商人とは、戦場地帯コロニーと平和地帯を結ぶ隊商を商売としている。
「沙織ってさ、「青き騎士の伝説」って聞いた事がある?」
「いいえ、何の話なの、それって」
「人類の守護神のごとく「青き騎士」は困難な時にあらわれ、人類を助けてくれるのよ。戦争の伝説よ、何人かの人がそれを聞いた事かあるわ」
「それは、個人ではなく、人類全員を助けるの?。それに、パウエあなた、その青き騎士とやらを見た事はあるの?」私は尋ねた。
「ええ、あるわ、私が別のコロ一てにいた時にね」目を輝かせていた。
パウエは、それを見た時のことを、まるで映画を見ているように話してくれた。パウエにとり、青き騎士を見たことは、人生最大の出来事なのだろう。
私はたづねる。
「その人は、本当に青き色をしているの?」
私は目を輝かして尋ねた。
「その青はね、地球光の青なのよ。宇宙から地球を見た時の、あの青色なの。そして皆、私たちを幸せにしてくれるわ」
「しあわせにしてくれるって、それじゃこの地球を款ってくれるわけなの」
「そう、私たち地球人類をね」
「それじや、私みたいな「アイスブレッドーニューオーハン」かも知れない人間は無理なのね」
「そうじゃないわ、沙織、全ての人類を救ってくれる」
「ふうん」
この時も、私は、私がその「青き騎士」に出会うとは夢にも思っていなかった。
私は幼い頃から、親、育ての親だが、厳しく育てられていた。
それが、何故なのかわけもわからずにいた。
「早く、沙織、この綱をわたるんだ」
アイスフイールドに吹きわたる寒風の中、その私がわたれと命令されたローブは、、地上3mの位置にぴんとはなれていた。
が、子供の頃の私にとって、それは超高層ビルのいただきにいる、に等しかった。
それでも。それは、日々の日課にすぎなかりたのだが。
とうとう、ある日、私は呟き叫んでいた、
「やめてよママ、死んでしまう」
母(まま母だが)は言った。
「ふつ、ああ、そうだね。死んでしまった方が、お前は楽かもしれないね」
そして付け加えた
「ふうう、これから、お前はね、もっともっと地獄を見るに違いないのだから」
その地獄が、どれ程の地獄か、私はまだ気づいていなかった、
また、ある日、母は言った
「ほれ、沙織、あの大をつかまえるんだ」
「えー、だって、あれは私のロボット犬花梨だよ、つかまえてどうするの」
「わかっているじゃないか。だから、つかまえて分解をするのだ。IC部品が高く売れるだろうが。おまんまが食べられるじやないか。食事をしたくなけれぼ、いいけれどね。おまえ、おまんまをたらふく食べたいだろう」
ロボット犬花梨は、私が、とても愛していた犬だった。子供の孤児になった時からの愛犬だった。
だから、できるだけ苦しまないように、カリンを殺そうと思った。
ロボット犬「花梨」との格闘は、骨がおれた。
彼は、私がじゃれていると、冗談だと考えてていたようだ。
彼は、意思を私に送っていた。私は機械生命の言葉が読めるのだった。
それも私の能力の一つだった。
「私、カリンが死ねば、あなた、沙織が助かるわけですね」
そう、彼はいった。
彼の目は、悲しみをたたえて私をみていた。
「許して、カリン。私は生き延びねばならないの」
「どうぞ、私は逆らいません」
人工脳神経があつまつている部分を、私は一折りにした。
涙は、でなかつた。
「私は、花梨を殺してまで、なぜ、生き残らねばならないの?それはだれがきめたの」
私は自問自答した。答えはかえってこない。
心は空虚だった。
まま母からいわれた通り、カリンの体をバラバラにして、冷静に使える部分をよりわけた。
私たち両親ともアイスにおそわれた時、キャラバンに生き残つていた犬だった。その犬を、人工犬コードから、私は後から何とか見つけだし、大事に育ててきたのだ、
ロボット犬、花梨の首が折れた、
「キューン」
人工生命が消え去る音。
そのカリンのうめき声は、、いつも私の耳朶によみがえる。
記憶の音は、こころにこびりついていた。
そのときは、泣けなかったが。思い出すたびに、涙がこぼれ落ちた。
なぜ、私だけが、こんな目に、会うの。
まま母と父親がいう。地球連邦は、アイスブレッドと思われる子供たちを、養父母をつけて監視させていた。
「それはお前がアイスブレッドだからさ」
「ちがうわよ、私はアイスなんかじやない、人間よ」
コロニーに住む同じ年頃の子供たちは、もっと残酷だった。
「それじゃ、沙織よ。お前の体温はなぜそんなに冷たいのだ」
そうだった。
私の体温は、普通の子供より低かった。
異常体貿なのだろうか
「やあい、冷血動物やい、あっちへいけやい」
私は泣きながら、家にたどりつく、
泣いてははいたが、けっして涙を人に見せなかった。
学校は、養父母のいる家庭よりまだ、ましだったからだ。
しかし、やがて、そんな私に、、転機が、、訪れた。
(続く)
作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所