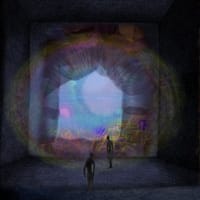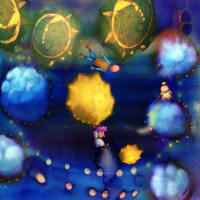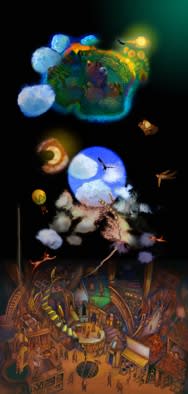
石の民「君は星星の船」第7回
作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所
http://www.yamada-kikaku.com/
『私は石の男だ』
驚きがミニヨンの心に走った。
「えっ、石の男ですって、信じられない」
『事実、君に話し掛けているだろう。君はなんという名前なのだ』
「私はミニヨンよ」ミニヨンは思わず自分の名前を答えていた。なぜなんだろう。この気
持ちは。
『そうか、ミニヨンよ、私の心底にこい』
心底ですって、ばかなことはいわないで、何故、あなたの心底に。大体、石の男に心底な
んてあるのかしら。
ここ樹里の人々は訓練すれば、他人の心底にいく事ができる。もぐりこんだ本人の心は
「分心」となり、その場所、「心底」にいる。その場所で、分心は本人と同じようにものを
見、言葉を発するのだ。しかし、その分心が、他人の心底にいっている間、分心の本体は
何も見えず。考えずその場所にいる。この体は幽体と呼ばれる。
『君はアルナににているな』
「アルナって」
『私の古い知り合いだ。君が私の心底にくるのがいやなら、私からいこう』
「何ですって」
■宗教の中心地樹里には、この「石の壁」と「石の男」を管理する祭司委員会が存在する。
祭司は代々世襲され、祭司職はこの樹里の里ではハイクラスを意味する。
樹里の町中からも、巡礼たちの騒ぎを聞き付けて、多くの人々が走り出てきて、石の男
を見あげていた。
「たいへんなことになったなあ、アルク」
知り合いの、ガントが汗をふきふき話しかけてきた。ガントはあせっかきだ、
たぶん、店のほうから、騒ぎを聞き付けて駆けてきたのだろう。
ガントの姿をみれば、心配性のようにはみえない。
この里の者には珍しくまるまる太っている。
アルクと同じくらいの身長だ
が、体重は2倍はあるだろう。ほおひげとあごひげが、チュニックとよくマッチしていた。
「しかし、ガント。この事件で、樹里にくる人々が増えるとすれば、お前の店の収入があ
がるではないか」
アルクはいやみをいった。ガントは妻のモリに巡礼向けのスーベニアショップをやらせ
ている。
この店の売上が、たいした金額になると、アルクはきいていた。ガントのチュニックは
特別じたてといううわさだ。その生地は遠くの商工業都市ヌーンからとりよせているとも
いわれていた。
「我々では手がでない。マニさまに報告しょう」アルクが言った。
「そうだ。マニさまがどうするか決めてくださるだろう」ガントが言う。
「さあ帰るぞ。ミニヨン」
が、ミニヨンは答えない。ミニヨンの様子がおかしい。彼女の目は「石の男」に向けら
れている。瞬きひとつしない。
「ミニヨン、どうした」ガントものぞきこむ。
■先刻から、ミニヨンの心に言葉がみちあふれていた。
ミニヨンの分心は石の男の心底に呼び寄せられていた。こんな体験はミニ
ヨンにとって初めてだった。どうしていいのかわからない。
『助けて、おとうさん』ミニヨンは心の中でさけんでいた。石の男の分心がミニヨンの心
底に侵入していた。
『さてミニヨン。私の話を聞け。
私はずーっと昔から、涙をながしていたのだ。私は世
界を憂えている。私の話をきけば、君も涙を流すはずだ。なにしろ、君はアルナに似てい
るのだからな』
アルクはミニヨンが、涙を流しはじめているのにきずく。
「ミニヨン、どうしたんだ」アルクの声はミニヨンの心まではとどかない。
ミニヨンの目は石の男に釘ずけになっている。
アルクはまさかとおもう。まさか、石の男がめざめたのか、そんなことはありえない。が、涙が流れているとすれば、石の男の感情が蘇ったのかもしれない。
「いかん、もしかしたら、石の男がミニヨンをとらえたのかもしれない」
アルクは叫んでいた。
「そ、そんなバカな」ガントが汗をふきだしていた。
アルクの分心は、ミニヨンの心の中に沈みこむ。ミニヨンの心理バリアーが働いていな
い。人の分心が入り込む時のあの痛みに似た感覚がないのだ。アルクの分心はずぼっとミ
ニヨンの心に入っていった。心の中はどんよりしていた。
アルクは、ミニヨンが子供のころ、心理バリアーの教育、練習のため、ミニヨンの心に
はいったことがあるのだが、空色だった。その空色がこんな色に。いったいなにが。ミニ
ヨンの中に、だれかの分心がいた。
「なんということだ。私の娘だぞ」アルクは、叫んだ。
石の民第7回
作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所
http://www.yamada-kikaku.com/