ドラマでも、
「絶対に失敗しない」
外科医の女性
や、
貸し剥がしの苦い記憶を
原動力に
やられっぱなしどころか
やられた分は
「倍にしてやり返して」
しまうタフな志高き銀行員、
そして、
自分の子どもでなくとも育てると決めたら、
子どものためならエリート街道を捨てて、
どんな
「ブルースな人生」
にも立ち向かってしまう
義母、など
、が、ドラマで流行った歴史が最近の日本にはあり、
映画では
最低の総理大臣が
政治家になった頃からの
「記憶をなくす」
ことで勧善懲悪に燃える政治家に生まれ変わり、
周囲もその影響で変わり
問題の根本に立ち帰る内閣となる。
......しかし、現実は、「失敗する」医者に怯えるからこそ、
失敗しない大学病院ランキングが途切れ暇もなく売れ、
相変わらず、
日本では外科は未だに男性社会だ。
銀行が合併しすぎて
「貸し剥がし」
た相手どころか、
銀行の名前の名残を探すにもひと苦労だろう。
それに
高齢化社会なのに
個別に訪問して
傘をさして帰って行く
銀行員の後ろ姿どころか、
窓口閉鎖をしまくるが、
システム不具合頻発問題があり、
最近のマイナ保険証問題の中の紙の保険証問題対応に
根本は似ている気がする。
自分の親や子どもですら虐待するというおぞましいニュースを視たばかりだが、
もうすぐ裁判かな?
(→私も女性なのでしみじみ思うが)
エリートで退職しても
経済力やスキルがあり、
多くを子どもにかけられる女性が多い世の中とはお世辞にも言えないと思う。
ドラマは
「あって欲しい姿」
を描くから
(特に話題や人気の)ドラマたり得ているのだろうし、
続きを想像して楽しく、
結末に感動するのだろうけれど、
なんだか、
いつも、
一抹のさみしさや不安な気持そして問題提起をそっと残してゆくように私は思う。
先に挙げた映画はテレビで放送しており、
これまた、
(あり得)ない世界が映画の中にだけはあることを見せつけられた気がしている。
まだまだ、学ぶことが多い。
ここまで読んでくださりありがとうございます。Re:シリーズでした。
昨日ニュースを見ていてがっくりした。
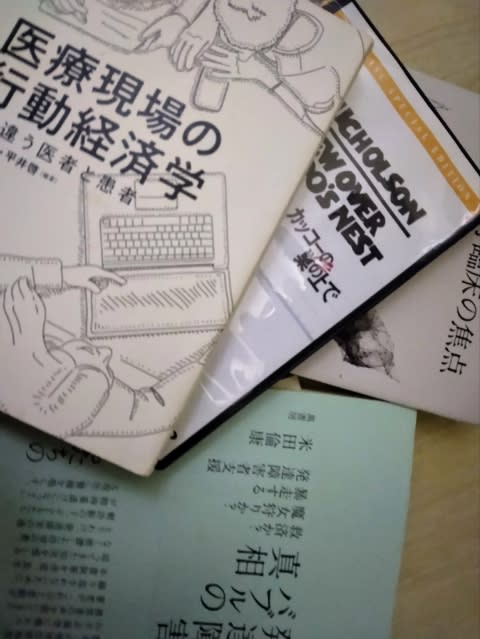 。
。
まず、社会的地位に拠って、
加害者でありながら、
背景を考えてもらえるのに、
被害者でありながらあまり背景を鑑みられないケースが在ると感じたから。
つぎに、
日本人の欧米に対する憧憬の念と劣等感のすごさ、
それに基づくスポーツニュースの報道の仕方に
衝撃を受けたから。
そして、いまだに
適切とは思えない場面で「障がい者」ではなく「障害者」
と未だに表記していることに
ショックを禁じ得なかったから。
テレビには学ぶことが多い。
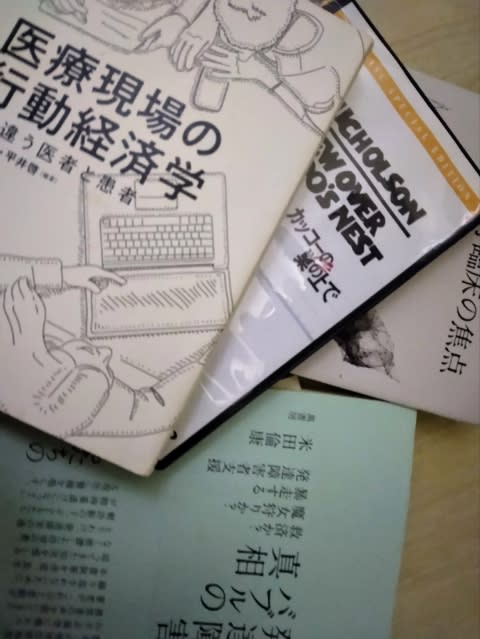 。
。
DSM-5(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersの略、以下DSM)
の「正しい」目標は
診断の抑制と診断のデフレ
にあったようだ。
DSM-4では、
精神の「正常」と「異常」あいだに線を引こうとするとき、
功利主義を最善の、もしくは唯一の哲学的指針とするアプローチを用いていた。
(かばうようだが、DSM-4、DSM-5の作成者は、功利主義の、「最大多数の最大幸福」の過ちを確実に作成者の一部は十分理解していた、と、私は考える。)
前に描いたように、
「正常」と「異常」を厳密に定義など出来ないし、
普遍的な意味など求めようがない。
「正常」と「異常」は、
視座次第で、その視座のおかれた、ときところそれらに基づく文化により変わる。
ゆえに、「正常」と「異常」の境界線は、
異なる選択をしたときに、どのような正負の影響があるかといったバランスに基づくべきであり、何が最善の結果を生み出すことが可能かを考えつつ決断すべきである。
したがって
(ベンサム的に)「最大多数の最大幸福」をつねに追求(希求)しなければならない
、と、なる。
しかし、現実的な功利主義を貫こうとも、それが当てにならないケースが存在することは否定しがたい上に、
「大小をどのように測定し、幸福をどのように定めればよいのか」という「最大多数の最大幸福」の曖昧さに立脚した構造を直視しなくてはならないと私は、思う。
功利主義が、現代ドイツにおいて、いまだ不人気であることは、偶然などではなく、ヒトラーのせいである根深い嫌悪感と悪評が消えないことに起因する。
ドイツが、第二次世界大戦中に、
その戦前戦後ならまちがいなく
「異常」
と見なされる蛮行をおこなったのは、
支配人種の最大幸福のためには必要だと、
功利主義の立場から、当時はことごとく正当化したからである。
歪められた統計的な「正常」が、あるべき世界や慣習に則った世界そして人間の尊厳がある世界の「正常」をあるいっとき圧倒してしまったのである。
邪な手に落ちれば、功利主義は、善き価値観から目を背け、悪しき価値観に歪められてしまうことは悲惨な歴史が証明している。
功利主義、とくにそれを象徴する「最大多数の最大幸福」の扱いには眼を光らせるべきであろう。
ここまで読んでくださりありがとうございます。
G20に習近平国家主席が不参加のようです。
日本を取り巻く国際情勢も暗雲が垂れ込めているような……。
とはいえ、とりあえずでも、まず目先のやれることをやろうと思います。
今日も頑張りすぎず頑張りたいですね。
では、また、次回。
ここ数日
かつての病気になったことと
リハビリの関連性について考える。
まあ、ここ数回
「正常」や「健康」
の定義は曖昧であり、
それらの状況を断定することは困難であり、
私たちの生きるこの世界で問題を整理、解決することに役立つような
「普遍的」であり「超越的」な定義は存在しない
ということ。
と、
(夜の闇に乗じるように)曖昧さに乗じて、
「いくらか病気」と「おおむね健康」
の間に在る曖昧さを利用して、主に精神医療において
病気の領域を広げる製薬業界のビジネスモデル
同様の手法をとり、薬の購買数を増やそうとするマーケティング
そして、その両者の線上にある、診断インフレ
について描いてきた。
今回は、
「思い込み」や上記で描いてきた意味での「曖昧さ」、そしてそれらに基づく「主観的判断」を利用した、
ある意味での市場の操作
が可能になってしまう理由
について考えたいと思う。
まず、
精神医学の特徴として、
「正常」と「病気」の境界線の操作に対して、生物学的なデータや明確な数値が存在しない、
ために、
巧妙なマーケティングに影響されやすい主観的判断に大きく依存する構造をとりやすいから。
つぎに、
どのような病気や企業にかかわらず、
収益性は市場規模と商品の利鞘を大きく出来るか、に依存する、ことは言うまでもない。
診断インフレを推進することが、製薬企業成功の最善手だ。
もはや、市場浸透のため、
幅広い人口層の取り込みに奔走する。
その結果老若男女が取り込まれてしまうから。
そして、
製薬企業は自身に隣接する、処方箋を書く医師たち、それを求める患者たち、さらなる治療を求める消費者団体たち、精神医学の研究者たち、彼ら/彼女らすべてをつなぐメディアや(インター)ネット、を、先の二つのとともにうまく利用し、
強固で広範で、長期的なキャンペーンをはることが、出来るから。
あまりに哀しい理由だが、どんな企業であれ、最終的には、何より大事なのは、株主と企業自身の生き残りであって、公共の福祉ではない、ということなのだろうか。
ここまで読んでくださりありがとうございます。
雨だからと湿度を伴う、残暑がまだまだ厳しいですね。
日の出日の入りは変化しているのに、あまり気温と連動しないのがかなしいですが、頑張りすぎず頑張りたいですね。
では、また、次回。
















