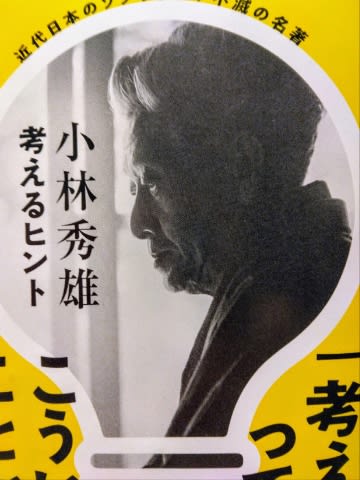小林秀雄のベルクソン論である『感想』の第1回目は、ベルクソンの遺書の紹介で終わっている。
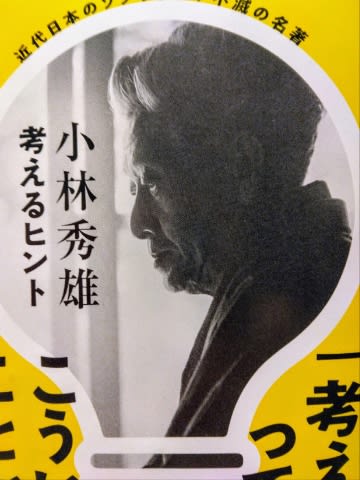
遺書というと、『感想』のあとに書かれた『本居宣長』の遺言書が想い起こされもするが、小林秀雄が、ベルクソン論と本居宣長論のいずれにおいても、遺書の分析から、その論をはじめたことは、興味深い。
このことは、言ってしまえば、小林秀雄が遺書を認めるかのようにベルクソン論である『感想』を書きはじめ、ベルクソン論を未完のままで終わらせてしまったあとに、本居宣長論である『本居宣長』においても遺言書の分析からはじめたことは注目に値することであろう。
小林秀雄のベルクソン論である『感想』は、母の死の記述からはじまっている。
「終戦の翌々年、母が死んだ。
母の死は、非常に私の心にこたえた。
それに比べると、戦争という大事件は、言わば、私の肉体を右往左往させただけで、私の精神を少しも動かさなかった様に思う」
勿論、これは小林秀雄固有のレトリックであり、小林秀雄もまた戦争という大事件によって精神を動かされ、相当、心にこたえたのであるが、
戦争という大事件よりも母の死の方が、心にこたえた、と述べることによって、精神が動かされ、心にこたえるというのは、母の死が心にこたえるような、そのような次元から、物事を考えるべきだと言っているのだろう。
つまり、喩えば、母の死については、私たちは、単純素朴にその死を哀しむのだが、戦争というような大事件になってしまうと、途端にその悲劇を悲しむというよりは、それを分析し、反省し、解釈してしまうのである。
小林秀雄が、あえて戦争より、母の死の方が精神にこたえたというのは、一種の認識の問題を言っているのであり、戦争と母の死を単純比較するのではなく、母の死に直面した時のような、直観的で単純・素朴な認識法と、戦争というような社会的大事件に直面したときのような、いわゆる分析的で、反省的な認識法とを対比しているということであろう。
小林秀雄は、『感想』の第1回目のなかで、
「以上が私の童話だが、この童話は、ありのままの事実に基づいていて、曲筆はないのである。
妙な気持ちになったのは後の事だ。
妙な気持は、事後の徒な反省によって生じたのであって、事実の直接な経験から発したのではない。
では、今、この出来事をどう解釈しているのかと聞かれれば、てんで解釈などしていないと答えるより仕方がない」
と述べている。
ここに小林秀雄が対置するふたつの認識法が書かれている。
ひとつは、事後の徒な反省によって生じる反省的認識であり、もうひとつは、事実の直接な経験から発した経験的認識である。
小林秀雄は、反省的認識を斥け、経験的認識を重視しているのであるが、小林がこのふたつの認識について、とりわけその直接的な経験に基づく経験的認識について、小林秀雄の母の死後の奇妙ともいえる経験を通じて説明している 。
その奇妙ともいえる経験を、小林秀雄は、「或る童話的経験」と呼んでいる。
「或る童話的体験」を簡単にまとめると、以下のような体験であったようである。
小林秀雄は、母が死んだ数日後のある日、仏様にあげる蝋燭を切らしてしまっていることに気付き、蝋燭買いに出かけた。
もうそのときは夕暮れであったため、門をでたところで、蛍が1匹、飛んでいるのを見つけた。
その蛍は、今までに見たことのないような大きな蛍あり、見事に光ってもいた。
小林秀雄は、母が蛍になっている、と思った。
そう考えると、もうその考えから逃れることが出来なくなった。
しばらく歩くと、曲がり角で蛍は見えなくなったのだが、小林が、Sさんの家の前を通り過ぎようとすると、1度も吠えかかったこともない犬に吠えかかられ、横須賀線の踏切の近くでは子供たちが騒ぎながら走り去った。
踏切のところについたとき、子供たちが踏切番と「火の玉が飛んでいったんだ」と大声で言い合っていた。
小林はそれを見て、
何だそうだったのか、と思い、驚きもしなかった。
簡単なまとめのつもりが随分長くなったが、小林秀雄は、このような奇妙な体験を、すこしも奇妙だとか、感傷的だとか思いはしなかった。
しかし、小林が妙な心持ちになったのは、このような事実を後から反省し、分析し、解釈した結果であろう。
事実を渦中においてではなくて、暫くしたあとで奇妙だと思える経験は、私たちも持っているかもしれないのだが、ただ、それを語ることが出来ないし、それを他人にもわかるようにせつめいすることが出来ないだけなのである。
しかし、私たちは、それを語ろうとし、また説明しようとする。
そこに矛盾が起こってくるのである。
小林秀雄は、ベルクソン論である『感想』の第1回目のなかで、死んだ母の話に続けて、その2カ月後に、水道橋のプラットフォームから転落したときのことも書いている。
転落しても、酷い場所のなかの一間ほどの隙間に落ちたため傷ひとつなかった小林秀雄は、
「母親が助けてくれたことがはっきりとした」
と述べている。
さらに、小林は、後から反省し、考えた上で、母親が助けてくれた、と思ったのではない、と言うのである。
小林はこの例を以て、反省的思考と経験とは必ずしも一致しないということを言いたかったのではないだろうか。
言い換えるならば、私たちは、現実という直接的経験を、理論によって正確に説明することも、表現することもできないのではないか、と言いたかったのではないだろうか。
確かに、アシルは、亀の子に追いつき、追い越して行くのに、私たちが、それを理論的に説明し、表現しようとすると、アシルは亀の子に追いつくことができない、という結論に、達する他はないのである。
小林秀雄は、
「この時も、私は、いろいろと反省してみたが、反省は、決して経験の核心には近付かぬ事を確かめただけであった」
と言っている。
このような考え方は、ベルクソンの、いわゆる「分析と直観」に基づいているようである。
ベルクソンは、認識をふたつに分けている。
ひとつは、「科学」的思考において用いられる分析的認識であり、もうひとつは、「哲学」的思考において用いられる直観的認識である。
ベルクソンは、分析的認識は、真の実在としての持続を認識することはできないと考えているようである。
分析的認識は、対象を既知の要素へ還元する操作である。
つまり、分析することは、ある物を、その物ではない別の物に置換することであるため、分析をいくら繰り返しても、その物の実在に触れることはできない。
その物の実在は、他の何ものにも置き換えられない物だからである。
だからこそ、分析的認識は、あくまでも相対的認識に留まるのであろう。
これに対して、直観的認識は、その対象を外側から分析するのではなくて、その対象そのものの持続のなかに一体化することである。
言ってみれば、記号や言語によらず、直接的に知ることが直観である。
ベルクソンのいう直観とは、対象を、持続の相においてとらえるということのようである。
つまり、それは、持続する実在を時間のなかでとらえるということではないだろうか。
そして、ベルクソンは、『形而上学入門』のなかで、
「直観から分析へ移ることはできるが、分析から直観へ移ることはできない」
と述べている。
冒頭で、小林秀雄のベルクソン論である『感想』の第1回目は、ベルクソンの遺書の紹介で終わっていることについて触れた。
小林秀雄の『感想』の第1回目で紹介されているベルクソン遺書は、次のようなものである。
「他人に読んで貰いたいと思った凡てのものは、今日までに出版したことを声明とする。
将来、私の書類其の他のうちに発見される、あらゆる原稿、断片、の公表をここに、はっきりと禁止しておく。
私の凡ての講義、授業、講演にして、聴講者のノート、或は私自身のノートの存するかぎり、その公表を禁ずる。
私の書簡の公表も禁止する。
J・ラシュリエの場合には、彼の書簡の公表が禁止されていたにも係わらず、学士院図書館の閲覧者の間では、自由な閲覧が許されていた。
私の禁止がそういう風に解される事にも反対する」
これが、ベルクソンが残した遺書であるが、小林秀雄は、この遺書を書き写したあとに、
「ベルクソンは、自分の沈黙についてとやかく言ったり、自分の死後、遺稿集の出るのを期待したりする愛読者や、自分の断簡零墨まで漁りたがる考証家に、君達には何もわかっていない、と言っておきたかったのである」
と付け加えているが、このことばは、小林秀雄自身のことをも含んでいるように私には思われる。
そして、小林秀雄のベルクソン論である『感想』は、ベルクソン哲学の助けを借りて、後世のベルクソンの、小林秀雄の読者や研究者たちに、
「君達は何もわかっていない」
と言い残そうとした作品であるのかもしれない。
だからこそ、小林秀雄はベルクソン論である『感想』の冒頭から、反省的、分析的な認識によっては、直観的な体験の実相に迫ることはできないと何回も繰り返したのであろう。
それは、小林秀雄の批評を、伝記的事実、あるいは外国文学からの影響という観点から分析しようとするような、後世の読者や研究者たちへの警告でもあったのかもしれない。
小林秀雄は、ベルクソン論を通じて、批評という体験は、小林秀雄個人の単純な経験であって、それは、他の何ものにも置き換えることのできないものだ、と言いたかったのかもしれない、と、私は、思う。
ここまで、読んで下さり、ありがとうございます。
明日から、また、数日間、不定期更新となりますが、また、よろしくお願いいたします😊
今日も、頑張り過ぎず、頑張りたいですね。
では、また、次回。