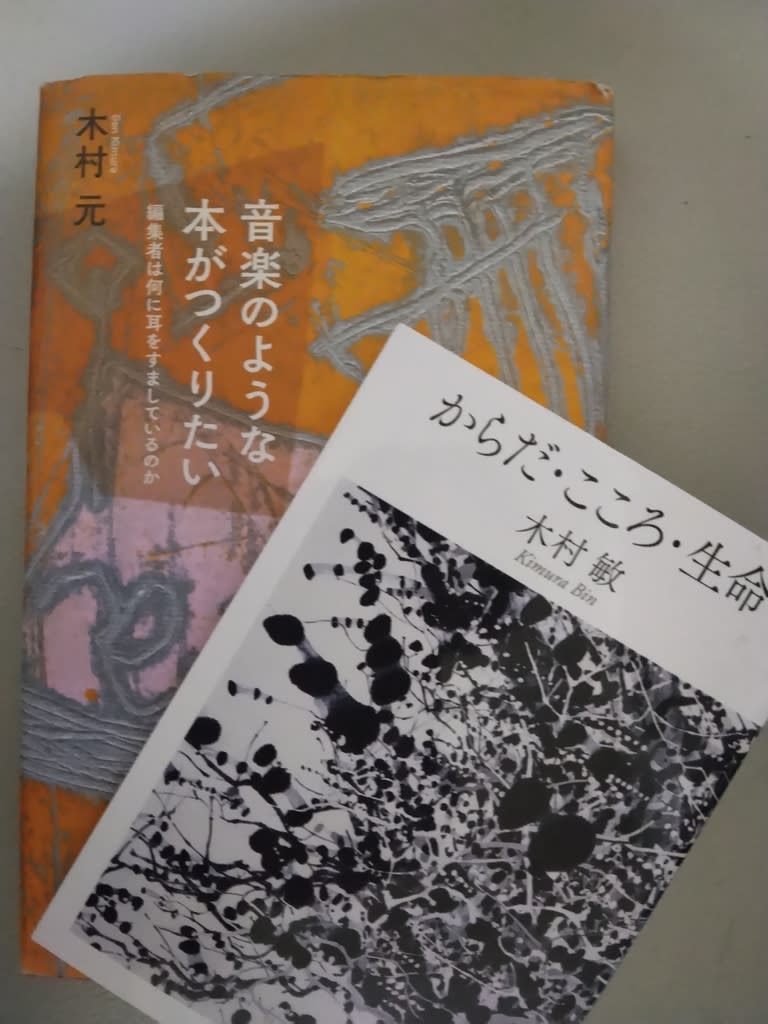
ここに音楽に対する、ふたつの考え方がある。
ひとつは、
「音楽というものは、人種、国境を超えて普遍的なものである」
というもので、
もうひとつは、
「音楽が普遍的だというのは能天気な戯言だ」
だというものである。
前者は、音楽の持つ抽象的な機能に注目した考え方である。
確かに、喜びや悲しみと言ったものは個別具体的なものであり、例えば、シューベルトが抱いた悲しみはシューベルトだけのものであろう。
だが、それがひとたび音楽となれば、抽象化された悲しみの表現に、私たちは、自分の心の中にも共鳴する響きを聞きつけて、共感するのである。
また、後者は、抽象化する作業の過程に注目した考え方である。
それぞれの音楽には文化的コードがあって、その文化コードをまず学習しないことには理解など不可能だというわけである。
確かに、シタールの一弦の響きがどのような心の動きを表したものなのか、それなりの学習を経なければなかなか理解は難しいのかもしれない。
どちらも両極端な考え方であるが、共通する、あるいは類似した体験が無ければ共感など、無いであろうし、体験を共有していても、それを理解するための文化コードが共有されていなければ、表された音は理解が難しいだろう。
現在、世界では、幸か不幸か、西洋音楽が発展をさせ、かつ洗練させてきた音楽語法が覇権を握っているので、文化コードについてはおおよそ共有されていると見て良いだろう。
ごく大雑把に言えば、上昇してゆく音型は気分の高まりを表し、不協和音は何かよろしくないことが表されているのである。
では、作曲家が抽象化された感情などではなく、完全に個別具体的な、例えば、恐怖や苦しみを表したいときはどうすればよいのであろうか。
アルノルト・シェーンベルクは、晩年に心筋梗塞を起こした時、心臓に直接注射を打ち込まれてしまった。
シェーンベルクは、その時の感覚を弦楽3重奏曲で激しいえぐり込むような不協和音で表したというが、そのような説明を受けなければ
「なるほどこれが心臓への注射の感覚か」
などとは誰もわからないし、そもそもシェーンベルクは、たぶんそんなものを表し、人に伝えるために音符を描いたのではないだろう。
彼は、ただ、その時の体験を、作曲に活用してみたというだけのことである。
そんな迂遠な方法を採らずとも、簡単な方法が在る。
「転んだから痛い」と言いたいならば、
「転んだから痛い」と言えばよいのである。
それは、音楽でも同じことなのかもしれない。
マラン・マレ(1656~1728年)という人も、当時の人生最大の病苦に挙げられる膀胱結石に苦しんだようである。
しかも、痛みの割には命には別状が無いので、他人の同情を買えないという点もつらいそうである。
現在では、超音波で粉砕するという洗練された手術法があるのだが、マレの時代にはもちろんそのような手術法はない。
それどころか、マレの時代はこの手術自体がさらなる苦痛を強いるものであった。
おそらく、そのあまりのつらさのためだったのであろう。
なんとしてでも、マレはこれを楽譜に書き残そうとしたのである。
音では足りないと感じた彼は、その手術の恐怖やそのものを音楽と共に語らせたのである。
まさに、ヴィオール曲集第5巻に収められた『膀胱結石切開手術図(Le tableau de l’operation de la taille)』こそ、その記録である。
音楽は激しい不協和音に慣れた現代人には物足りないものの、それでも、手足を縛り付けられ、手術を受ける患者マレの不安と恐怖を表すのには余りある。
そこに
「ああ、あの器具が近づいてくる!
いよいよ切開するのだ!
もはや声も出ない!
血が流れる!」
と台詞が加わったあと、しばらく台詞が途切れるが、その間のヴィオールの音楽こそが、言葉にならない苦痛と絶望と、そして諦めとを余すことなく描写しつくしている。
そして
「取れた!」
という声と共に、音楽は明るい調子へと変化する。
それだけを聴けば、何の変哲もない中世音楽らしいロンドであるが、前半の苦悶を知っている人には、天上の音楽だと認識出来るであろう。
YouTubeで検索可能である。
暑い気候にぴったりかもしれない、ぜひ、ご視聴あれ。
ここまで、読んで下さり、ありがとうございます。
今日も、頑張りすぎず、頑張りたいですね。
では、次回。
*見出し画像はいつも通り内容は特に関係ありません( ^_^)



















