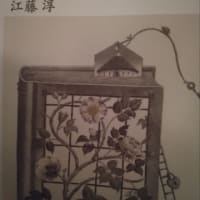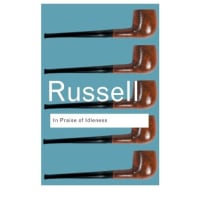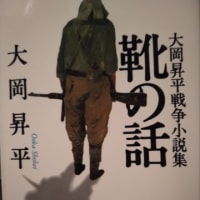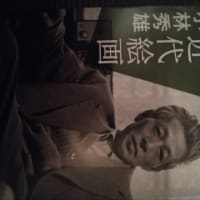何が「正常」で、何が「正常」でないのか、を考えるにあたって、まず「正常」とは、どんなものであろうか、という問いに突き当たる。
「正常(normal)」ということばは、大工の矩尺を指すラテン語として生を受け、今も、幾何学で、直角や垂直を表すときに用いられている。
その成り行きとして、「normal」はいくつもの「正しい」という含みを持つようになったのである。
通常、標準、ふつう、日常、平均、典型、平凡、予想通り、習慣、普遍、共通、適合、慣例、妥当、通例などである。
そこからさらに、normalは、
「生物学的にも、心理学的にも良好に機能している状態」を、
つまり「心身の病気にかかっていない状態」を表すようになったのである。
しかし、「normal(正常)」が何かを知るためには、何が「異常」かを知らなければならないのだが、辞書によると「異常」は、正常でないもの、自然でないもの、典型でないもの、ふつうでないもの、や、基準に適合しないもの、となる。
まさに、堂々巡りである。
辞書は、一方のことばを他方のことばの反対語として提起するだけであり、どちらについてもまともな定義はなく、両者の間に有意義な線引きはされていないのである。
私たちは「正常」と「異常」という相反するふたつのことばを、よく知っているようで、知らないのである。
確かに、私たちは、両者の大体の意味は、直感的にはわかっているが、具体的にどのようなものか断定することは困難であるようである。
なぜなら、私たちが、現実世界で問題を整理するのに役立つような、普遍的で超越的な定義など存在しないからである。
では、哲学は「正常」についてどう語っているかを考えたとき、あまりに僅かしか語っていないことに、気が付く。
哲学は、私たちの認識の仕組み、人間の本質や、真実、道徳や正義、愛、美、善や悪、死と不死とか、自然法とか、といった仰々しい概念の意味を深く理解すべく、たゆまぬ努力を重ねてはきたが、「正常」はこの哲学の混沌の中に紛れて見落とされて「放置」されていたのである。
この「放置」が長くつづいたあと、日常のもっと身近な問題に哲学を用いようとする新たな動きが現れたのである。
先駆けとなった功利主義は、「正常」と「精神疾患」をどこでどう線引きするかについて、今も、現実的、哲学的な唯一の指針となっている。
基本前提は、「正常」に普遍的な意味などないということであり、必死になって演繹法を働かせても厳密に定義するのは不可能だということである。
つまり、美と同じく、まさにそれはみる人次第であり、時代や土地や文化によって変わってくるため、「正常」と「精神疾患」の境界線は空理空論に基づくべきではなく、異なる選択をしたときに、どのようなプラスとマイナスの影響があるかというバランスに基づくべきであり、「最大多数の最大幸福」常に追求せねばならず、何が最善の結果を出せそうかを考えて決断しなければならないのである。
しかし、現実的な功利主義を貫こうとしても、それがあてにならないどころか、価値観にまつわる危険な地雷が潜んですらいる。
「最大多数の最大幸福」は字面こそ立派であるが、大小をどのように測定し、幸福をどのように定めれば良いのかあまりに曖昧なのである。
功利主義が現代のドイツでひどく不人気であるのは、偶然などではなく、ヒトラーによる「最大多数の最大幸福」の乱用のせいで根深い悪評があるからである。
ドイツが第二次世界大戦中、戦前や戦後なら間違いなく異常と見なされたような蛮行を行ったのことは、支配人種の最大幸福のためには必要だ、と、功利主義の立場から、当時はことごとく正当化された。
統計的な(頻度に基づく)「正常」が、命令的な「正常」(あるべき世界や慣例に則った世界)を一時圧倒したのである。
邪悪な手に落ちてしまえば、功利主義は、善き価値観から目を背け、悪しき価値観によって歪められるのは、確かではある。
しかし、それでも、精神の「正常」と「異常」の間に私たちが、線を引くとき、功利主義が最善、もしくは唯一の哲学的な指針であることには、変わりはないのである。
現に、功利主義は、日々使われているDSM(-5)で用いられているアプローチであるのである。
「正常(normal)」を定義するのは難しいことである。
今回は、辞書は納得のいく定義など示せず、哲学者は長い時間をかけながら、いまだにその意味を巡って言い争っていることについて少し考えてみた。
次回は、統計学者や心理学者、社会学者たちについても、少し考えてみようと思う。
ここまで、読んで下さり、ありがとうございます。
私は、「ふつう」≒「正常」とは都合のよい言葉ですが、曖昧にすぎる言葉であると思っています。
また、「正常」についてよく考えず、アタリマエに使っている人ほど簡単に「おかしい」≒「異常」意味を振り回すのかもしれない、とも思います。
最近、ある知人から、
「それはおかしい、ふつうはそうしない、だからこうすべきだ」
という内容の話をされた際に、なんだかもやもやとしたのです^_^;
「おかしい」は、(正常を前提とした)「正常ではない」と言い換えられるし、「ふつう」も、「正常」と言い換えられる文脈だなあ、と感じたのです。
そんなきっかけもあって、これまでいろいろと考えてきたことを、長い話にはなりますが「闘病生活を経て考えたこと」、というシリーズの中で描いてみたいと思います( ^_^)
良かったら、お時間のあるときに読んでやって下さいね(*^^*)
何だか最近、急激に温かくなったように思います。
体調管理に気をつけたいですね。
今日も、頑張りすぎず、頑張りたいですね。
では、また、次回。