まさにそうです QT @yosh0316:“@yone_oki5 厚生労働省が児童精神科を充実させたいらしく着々と児童精神科が増え、子どもを診てなかった精神科が子どもを診るようになっている。…学校が提供する情報を元に診断。…””その陰に製薬会社。教育と児童精神医療連携の危うさ
“@yone_oki5 専門家と言われる人が間違った情報をせっせと流しているのが現状 QT @takoyakinyanko: 第3の専門家が”専門家は時の流行に流される付和雷同の存在です。自閉症が母親の養育に原因と言われた3、40年前から行動療法主流の今でも変わりません!
“@yone_oki5 QT @takoyakinyanko: 「本人や家族から発信される課題を正しく受け取ろうとしない姿勢」の専門家"専門領域の知見を精査して各々の当事者の現在に活かすことが使命なのにマニュアルに従うだけの仕事しかしていません!独自性の有る専門家が望まれます!
“@takoyakinyanko マニュアルって、誰が作っているんでしょうね”精神科の診断ではアメリカ精神医学会のDSMが診断マニュアルとして有名です。学校、専門支援機関にもそれなりの機関の指導者作成のマニュアルが有ります。初任者研修受講からマニュアル化が始まります。
@yone_oki5 @takoyakinyanko 初任者はマニュアル的な問題解決、対応を好む傾向が強いようです。困難を抱える当事者の立場ではなくて自分の所属する組織、機関の〇〇指導員とか〇〇ワーカーとして職務上この様に振る舞えば無難と言う典型例を探すのは広義のマニュアルです。
@takoyakinyanko @yone_oki5 当事者、子ども達は大人の無難な職務的、マニュアル的な支援に困難さを更に募らせているのが現状です!本来の当事者の支援に未だ至らずです!それは私が知っている四十数年前からの構造ですが…最近は更に状況が酷くなっている様に思います。
@yone_oki5 @takoyakinyanko 当事者の困難に寄り添わない現状維持の無難な形式的・自己満足な支援ではなくて当事者の立場・視点から望まれる支援の在り方が必要だと二人の当事者の保護者として考えています。勿論、自分の子育ての立位置が最優先ですが…今はその途上です。
@yone_oki5 @takoyakinyanko 障害当事者の保護者として有り体に辛辣な言葉を言えば、広義のマニュアル的な支援では子どもの障害が障害として更に温存、深刻化する迷惑に何度も遭遇してのTWです!自閉症の障害を当事者から学ばないマニュアル支援は傍迷惑な支援なのです!
@yone_oki5 @takoyakinyanko 医者も含めて自閉症の当事者に良かれと支援したとしても本当に当事者の支援に繋がるのでしょうか?パニック症状を薬剤で抑制するのは当事者の子どもよりも周囲社会への配慮だとすれば最悪です!岐阜のワクチン急死事件は支援の本質を問う事件!
@yone_oki5 @takoyakinyanko パニック症状に誰が耐えられないのか?誰の為の薬剤投与?パニック症状は他の方法で乗り越えられないのか?それこそ支援の真価が問われる問題です!何故パニック症状に為るのかを問わずに薬剤投与に頼る現状ではまともな支援は望めません(続
薬剤投与の対応は更なる薬剤投与を呼びます。症状を唯一の方法で抑制する連鎖がその当事者の子育てに許容されます。支援とは以前の実績に胡座をかく性質が有ります。以前偶々有効でも次回からは禁忌の方法が多々有ります。支援側の視野、知見の寛さが問われます!支援の結果の死亡・重篤化は言語道断!
@yone_oki5 @takoyakinyanko 薬は状況を間違えると毒に働きます。同じことが支援にも有ります。誰かに有効な支援でも、誰にでも有効だと思い込んでマニュアル的な支援をすれば障害を温存・固定・重篤化することも有ります。オールマイティーな支援法は有り得ないのです!
ダウン症の娘がきっかけで障害者福祉に40年。植村満子さんが旭日単光章。「この子らに世の光を」ではなく「この子らを世の光に」の言葉を支えに。 bit.ly/SmwSwR
“@takoyakinyanko 【社会学を解析する専門員が必要】@yosh0316:”その視点は示唆的ですね!障害は当事者の精神・身体の内部の問題であると同時に当事者の置かれた社会的な構造の問題ですから!
どんなに専門的にやっていても、これで終わりではないですよね。常に発展途上であって新しい発見があるから進歩できる。個々がその発見や良いアイデアを出し会える環境であれば連携も意味が出て来ると思います。 QT @yosh0316: @yone_oki5 @takoyakinyanko
【社会学を解析する専門員が必要】社会福祉士・心理士・保健師・特別支援専門員・精神保健福祉士など個人の支援を目的とする職業はありますが「なぜに二次障害が起こるか」背景や課題を解析し専門員をサポートする・社会と広域に連携する職業が存在しない。@yosh0316:
本来なら専門員が社会学を学んでいるのですから個人を取り巻く環境背景をリサーチし課題を抽出し、本人と周囲の関わりをサポートしていくのが本来の在り方かと思いますが、当事者を指導する手法だったり他人ごととして向き合わなかったりするので、悪循環が起きていると思います。@yosh0316
@takoyakinyanko イワン・イリイチの様な幅広い分野に知見の有る人間が日本には存在し難いですね!現状では社会的な批判精神、問題意識を持った支援者は少数派ですね!
病理ーーどうやって病気になったか、どんなときにどうなるか。これも、医者だけに委ねてはいけない。医者が正しく判断するとは限らない。もちろん当事者が正しく判断する保証はない。重要なのはどれだけ納得が行くか、という説得力である。それを問い続けるプロセスは、当人が持つ必要がある。
重要なのは主体性である。極端なことを言えば、結果的に自分のためにならなかったとしても、自分でするという実感こそが大事なのである。障がいを持つ者が最も奪われる権利は、失敗する権利である。
当事者は自らの病気を巡るあらゆるものーー病名、病理、治療法、処方、処遇、生活、人生までーーを、専門家という他人に委ね、舵を取られてきた。だが専門家は、そのいずれについても(処方でさえ)、常に合理的にさえ判断してきたとは言いがたい。だが重要なのは合理性以前の、主体性と所属であろう。
当事者研究の方法で有名なのは自己病名。医者の付ける病名は、取っ付きづらく、冷たくて、侮蔑的だ。それはある日突然降ってくる。告知されるか秘匿されるかも医者次第で、その不名誉な名前は当人の知らぬところで業界人にやりとりされる。自己病名は、まずその名前を取り戻す作業である。
“@yosh0316 “@I_Yoichi 重要なのは主体性である。極端なことを言えば結果的に自分のためにならなかったとしても自分でするという実感こそが大事なのである。障がいを持つ者が最も奪われる権利は失敗する権利である””障害支援の一番の要諦、私の自閉症児子育ての原点です!
石川陽一さんのTWは秀逸です! “@I_Yoichi 【重要なのは主体性である。極端なことを言えば結果的に自分のためにならなかったとしても自分でするという実感こそが大事なのである。障がいを持つ者が最も奪われる権利は失敗する権利である】障害者支援の要諦、障害児子育ての原点です!










 yonemaru @yone_oki5
yonemaru @yone_oki5 YOSH @yosh0316
YOSH @yosh0316 五藤博義 @gotoledex
五藤博義 @gotoledex tanno takako @takoyakinyanko
tanno takako @takoyakinyanko 石川陽一 @I_Yoichi
石川陽一 @I_Yoichi 伊藤絵美 @emiemi14
伊藤絵美 @emiemi14



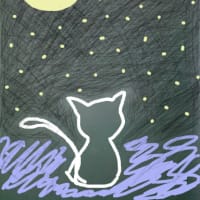
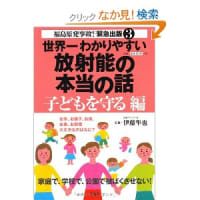
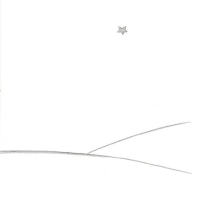
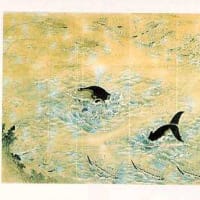

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます