56、63、65、75
81、83、94、99
の平均を求める
56+63+65+75+81+83+94+99=616
616÷8=77
しかし解法は多様にある!
画一的な解法を訓練することが教育なのだろうか?思考の刷り込み操作ではなく柔軟な思考の育みが教育の役割なのでは?
?
56、63、65、75、81、83、94、99
の平均を求める問題
順に足すのではなくて
順を工夫
56、94 65、75
81、99 63、83
とすると和が求め易い!
150 + 140 +180+ 146=616
求め方の発想を変える生徒も居る。
?
56、63、65、75、81、83、94、99
?発想転換生徒の解法
75を基準に各々
-19、-12、-10
0、6、8、19、24
すると
この総和は
24-10-12+6+8
=16【19-19はラッキー】
16÷8=2
平均は75+2=77
?
?
56、63、65、75、81、83、94、99
?発想転換生徒の総和の求め方は次の通り
75を基準にした時の総和は16なので
56+63+65+75+81+83+94+99=75×8+16=616
56、63、65、75、81、83、94、99
基準を70にする
-14 -7 -5
5 11 13 24 29
計算し易すさに留意
(29+11)+(24-14)+(13-7)=56
総和は70×8+56=616
平均は70+56÷8=77
計算は工夫次第で劇的に簡単で美しい計算が可能になるのに、多様な思考を否定する機械的な画一計算指導による訓練で退屈な上に空虚な苦役になる。しかし工夫次第ではこの上なく楽しいゲームになり得ると私は考えている(^_-)
数式を眼で追い過ぎると数式に支配されます!数字の並び順を手と鉛筆で捌きます。一目見て手で捌き解体すると混乱は有得ません!食材を見詰め過ぎて気分が悪くなるよりも包丁で捌いて花の様なお造りに仕上げるのが数式捌きの醍醐味です。数学は眼と手(筆記具)のアンサンブルです!










 【Muttsu66】=YOSH @yosh0316
【Muttsu66】=YOSH @yosh0316



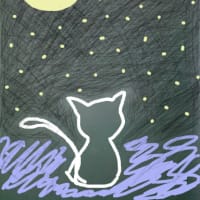
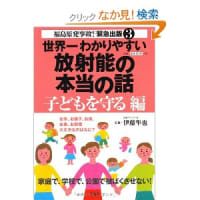
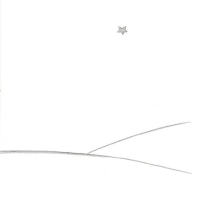
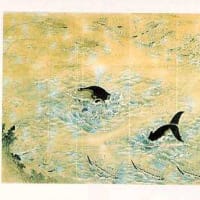

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます